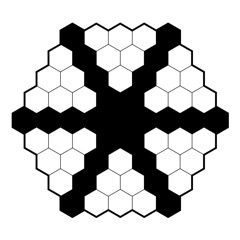「ああ、幼い頃に助けてくれた探偵のようになりたいな」
それは遠い日の思い出。僕は身代金目的に誘拐されていた。幼稚園から帰宅した後、ちょっと外に出て、お花摘みでもしようかと気まぐれに動いたのが不運の始まりだったのだ。そこに目を付けた男達がバイクでやってきて。「お菓子でもあげるよ」と言われるのかと思っていた。それなら、幼稚園でも習っていた「知らない人に甘いものをあげると言われても、ついていっちゃいけないよ」との言葉通り、用心しようとしていたのだが。「君みたいな若者に公的年金やら、重圧ないじめやら、この世界の中で恐ろしいことが起きようとしている。それを君から守ろうと思うんだけど、一緒に来てくれないか?」と真剣な顔で煽られてしまったので、たぶん行くしかないと思ったのだろう。僕はそのバイクの男の後ろにしがみついて、一緒についていってしまった。バイクで風を感じている僕は心地よかったせいか、君の名前は、親の名前は何かなどなど、答えてしまった。今考えたら、あまりにも愚かな言動である。
ただその中で一つおかしなところと言えば、その誘拐犯が何故か僕を連れてコンビニに入ったところだ。中で何回か僕に訳の分からない質疑応答をさせて、少々目立つようなことではあった。まだその誘拐犯が正しい人だと思い込んでいた僕は、その言葉に従ってしまったのだが。後から考えても、不思議な行動だった。何故、誘拐してる本人がわざわざコンビニに行って、顔を晒すようなことをしたのか。犯罪心理学上あり得ない話。あっ、僕が変な文言で誘われたり、ぺちゃくちゃ犯人に情報を伝えてしまったりした点についてはおかしい点に含まれないからね。そこ、注意。
その後は、その男と共に屈強な男達のいる場所、鉄臭い工場の中に連れてこられてしまった。僕はその男達にベタベタ触られるものだから、そこで感じることができた。僕は今、変な事をされようとしている、と。だから、叫んでしまった。それが男達にとって一番避けたい状況だったのであろう。だって、それを聞いた人が助けに来てしまったら捕まってしまうんだから。
「こいつを黙らせろ」
「じゃ、俺が。誰か、こいつの親に電話はしたか?」
「じゃ、オレ、身代金を請求しとくわな」
慌ててその男達は僕の口を塞ごうと殴るわ縛るわの状況。僕は声を出さずに泣いていた。もうこれで命が終わってしまうのではないかと五歳ながらに酷い恐怖を感じた程だ。ただ、ただ、救世主がいた。
工場の入口に立った男が一人。響き渡る声で、こう叫ぶ。
「君達はもう包囲されている! 尋常にお縄に付け」
それから後ろにいた青い恰好の人達が「ちょっと、警察の言葉を取らないでくださいよー」となよなよした声でその男に伝える。
僕には何が何だか分からなかった。
ただ、その髭面の男が真っ先に僕の方へと走ってくる。それがまた恐怖を感じて涙を流しそうになるも。彼に抱きしめられた。その優しい抱擁がその時の僕にどれだけ安らぎを与えてくれたか。常人には想像もつかないだろう。本当に、これ以上自分が傷付けられないと分かって。優しい人がいることが分かって。もうわんわん泣いた。それを見て、手が空いていた近くの人が探偵に一言。
「あああ……泣かせちまったな」
「え、その……いや、ああ、すまんかった。悪い悪い。もう安心だよー」
探偵が言葉で僕をひたすら泣き止ませようと頑張っていた。ただ、僕はその涙と鼻水を止められず、彼の服を汚れでぐちゃぐちゃにしてしまった。それでも笑っていてくれた、その男には感謝の言葉がしきれない。
それから後日、身代金目当てで近所の高校生が誘拐計画を企んでいたことが分かった。後日、お礼をするために母親と一緒に訪れた探偵事務所。
母親が玄関でお菓子を持って何度も頭を下げている中、僕は一人の少女と出逢った。猫目の少女は手招きで僕を呼んでいるものだから、勝手に靴を脱いで上がってしまう。母親は感謝に夢中で気が付いていない。
仕事場と思える応接間の前を通り過ぎ、リビングだろう部屋にまで来ると、少女はすぐさまソファーに座り、こう告げた。
「お父さんに助けてもらった子って君なんだね?」
「う、うん。お父さんって……あの探偵さんの子供?」
「そうよ。私は作花って言うの。よろしくね」
「うん」
「で、何で君が連れ去られたのか、そして、お父さんが君のいる場所を見つけちゃったか、知りたい?」
そう言われると、不思議だった。僕が何故かとその少女に問い掛けたいところではあったが、その前に探偵自身が飛んできた。彼はすぐさま僕へと一つの話をする。
「探偵としてのまっとうな勤めを起こしたからだ。探偵として。人として。それを全力でやったから、君が見つかっただけだよ」
取り敢えず、気合で探し求めることができた。そういうことで納得していたのだけれども。どうしても気になっていた、作花がポカンとして親の話を聞いていた、と言うこともある。何故そこまでひた隠しに真実を隠すのか。まさか、とんでもない計画に僕が巻き込まれていたのではないか。
僕は彼、探偵のおかげで誘拐事件のことがトラウマにならずに済んだ。探偵の姿が鮮明に記憶へ残って離れない。彼のおかげで平常な生活を送ることができた。
だからこそ気になった。あの探偵が必死に僕の秘密にしようとしていたことが。
あれから十数年。高校生になった僕は推理小説を読んで、そんなことを思い起こしていた。
学校の帰り道、僕はもう一度呟いた。「助けてくれた探偵のようになりたいな」と。彼と同じ推理ができるのであれば分かるはず。
幼き日、どうして僕は見つかったのか。
何故、探偵はその真実を僕に隠そうとしていたのか。あれ以来、作花はこの話題について口にはしない。お父さんからしっかりお口にチャックをするよう言われたのであろう。
「でも、いいさ。あの探偵の隠した謎を解き明かすことこそ、僕の今の勤め! 探偵になるための修行だ……きっと、見つかる。大丈夫」
そう走り、僕は過去を巡るための小さな旅を始めていた。町内を駆けまわるなんて、ちゃちな、旅を、ね。
その行動が。溢れんばかりの勢いが、とんでもない真実を呼び起こすとは露知ることもなく。ただただ、馬鹿みたいに張り切って。
だけれども、これが始まりだった。僕が探偵として、人間として。成長するための最初の一歩だった。それでも、僕はそんなことを思いもせず、好奇心を持って動き始めていた。
僕が最初に訪れたのは誘拐された場所。小さい道だけれど、バイクが入れる位の広さはある。それでいて近くにいる林や家のせいで影になっている場所。人目を気にせず、犯罪を行える場所としては最適だ。
犯人がたまたまそこを通りがかって、誘拐をしたとは考えにくい。何故かって、彼らは集合場所に集まってすぐさま身代金を請求する準備が整っていた。きっと、この辺りを歩く幼児を犯人が捜しまわっていたに違いない。
そこで良い鴨となるであろう僕がやってきた。そんな僕は馬鹿なことに情報という葱まで渡してしまう。犯人は一度は美味しい鴨葱鍋をいただいたことだと思う。
そんな犯人達の完璧な団らんは何故に壊れたのか?
一つ考えられる理由としては、誰かがミスを犯したから。何か付け狙える証拠を落としていたのだ。だけれども、思い付かない。僕が犯人が何か落とした様子を見ていない。
それとも誰か裏切者がいて、もう警察や探偵に相談していたか。いや、その可能性も低い。僕が叫びそうになるのを抑える手は本気だった。電話をしている人もしっかり身代金を口座だか何処かに払ってもらうよう、必死に伝えていたし。犯行に困惑の色を見せる人は誰一人としていなかった。彼等は本気だった。
一番、考えられる証拠としては、コンビニで起こした行動だ。あれで僕の姿が防犯カメラと犯人が映っていて。犯人の正体を知ることができた。そう考えることも可能だが、と思いつつ、僕はコンビニへと向かっていた。
ちょうどそこに少々厄介な人が現れた。彼女は私服姿で僕に手を振ってくる。それから僕の制服姿に関して、質問を入れてきた。
「あれ? 公? 制服をまだ着てるの? もしかして居残り勉強でもさせられてたの?」
今も猫目を光らせ、爆発したような髪とたった今買ってきたコーラのペットボトルを揺らしている彼女。探偵の娘であり、幼馴染と言えるかよく分からないクラスメイト、作花だ。
少々嫌味な彼女の発言に僕は返答する。
「違う違う。ちょっと思い出の調べものを、ね」
「思い出の調べもの? 何それ?」
「作花、お前が隠してる重要な過去の秘密を、ね」
「ははーん。お父さんから言っちゃダメって言われてるから。でも、自分で調べるってのなら、ヒントを」
「ん、くれるの?」
「あげないわよ。自分で考えなさい」
うう、と僕は断念する。そんな彼女は飲もうとした炭酸飲料を顔に吹いて大変なことになっている。あれだけ持ってたペットボトルを揺らしたら、そうなるわなと思った後で、僕はコンビニへと入店する。
彼女もそれに追ってきた。
「あれ? 作花は何か買い忘れたものでもあったのか?」
「ないわよ。ただこのまま家帰っても暇だし、見てるだけ」
彼女は後ろに手を組んで、じっと観察している。何だか緊張するが、調査に支障をきたすものではない。直接的な邪魔さえされなければ良いと考えて、コンビニの奥へと歩いていく。
そこで見上げながら、考える。ずっと前からあるはずの防犯カメラを確かめてみるのだ。そこから考えると不自然な犯人の行動が見えてくる。ここの防犯カメラの位置から考えると、そちらに顔を見せなければ、そうそう顔は分からない。だから意識して防犯カメラから避けようとすれば、完全に姿を見せず買い物もできる。
あの時の店員の態度に関係があるかとも考えるが、その可能性もカメラのことと共々に否定される。
「なぁ、作花。もし誰か犯人のことを知っている人がいて、伝えたんなら、別にそうやって見つけたって言えばいいだろ? カメラもそう……」
「そうね。でもまぁ、お父さんがどうやって調べたかって言うとね……たまたま来店したお父さんが、お店の人に怪しい人の情報を聞いてパッとあるところに目を付けたそうよ」
「ん、となると、偶然僕が誘拐されてる事実を知ったってこと?」
「そりゃ、そうよ。だって助けに来たのは身代金を請求されてからすぐって聞いてたわよ。たまたま聞く機会があったのよ。たまたま」
やけにたまたまを主張してくる作花。まあ、偶然でも探偵として能力を発揮して助けてくれたのだから、問題ない。
そのパッと思い付いた論理とは何なのだろう。と思ったところでちょいと作花が僕に情報をくれたことに気が付いた。
「って、見てるだけじゃなかったのか?」
何て言うと、彼女は猫みたいに髪の毛を逆立て、爪を剥き出してみせる。怒っているのか、頬が真っ赤に染まっている。
「う、うるさいわねぇ! き、気にしなくていいのよ!」
「うるさいのは作花、お前の方だよ」
「うっ……ううっ……知らないわよ。アンタなんか」
ぷいっと顔を背ける彼女。少々、騒がせたようだし、考えついでに何か買っていこうかと考える。メロンソーダを買おうかと冷凍庫を開いたところで、頭に何かが突き刺さったような不思議な感じを覚えてしまった。
横を見る。きっと、この感覚はエジソンが発明した時に味わったものと同じで違いない。これなら、誘拐した僕をわざわざコンビニまで連れてきた理由も説明できる。
答えを知っているであろう作花に早速、説明だ。
「ふふふ……謎が解けたよ、ワトソン君」
「ワタシ、ワトソンじゃないんだけど……えっ、何ホームズになりきってるの?」
「いや、そこは乗って。ちょっと自分が調子に乗ってるところなんだから。一人で何か、推理ショーやるの寂しいじゃん」
「やるんなら家の中で一人勝手にやってれば? って言いたいところだけど、ワタシに答え合わせをしてもらいたいのね。いいわよ。やってあげる。で?」
僕は胸を張って、探偵が僕を見つけた理由を告げる。
「君のお父さんはパッと考えたんだろう。何故、わざわざ目撃者になる子供をコンビニまで連れてきたのか。トイレって訳でもないし、僕を誘拐した後でも来れるはず……でも、どうしても犯人は僕を連れて入らなきゃ、いけなかったんだよ」
「いけなかった?」
そう、いけない理由はただ一つ。僕がいなければ、買えなかったから。
「そこにあるお酒だよ。お酒! アルコホールだよ! 二十歳未満は買えないもの。犯人としたら、困ったんだ。お酒を買いたいけど、身分証の提示を求められたらどうしようもない、って」
「だから?」
「僕の存在で誤魔化したんだよ。僕に父親のような言葉を掛けることで店員はこの人は父親。ちょっと子供には見えるけど、たぶん二十歳は超えるって判断できるんだよ。もし、それで求められたとしても子供がいたら、一人の時とは違う」
「一人の時? 一人だと何が?」
「言い訳ができないんだ。二人、僕みたいな子供がいる時は違う。身分証を求められた時、子供がぐずっただったり、急に調子が悪くなったように見せかけることで、会計を後にしてもらったりの配慮ができる。後は店員が保留している中、隙を見てトイレから出て。戻らないって言う選択をすれば、いいんだ」
「なるほどなるほど……」
「で、探偵はその情報を思い付き、犯人がバイクに乗れる年齢からお酒が買えない年齢だって考え、後はこの辺りを見張れる位に近所にいる人物から特定して、そのまま犯人のことを、ね」
彼女はうんうん頷いて、僕の推理に納得してくれたようだった。ただ、それが何故探偵が隠さなかったか。その理由も説明しておかなくては。
「で、探偵はきっと僕がそう言った犯罪に利用されていることを気付かせないように。僕が犯罪の片棒を担いでしまったと言う真実を気付かせないように。本当、ありがたい」
彼は最後の最後まで僕を守ろうとしていた。男達から、罪の責任から。自分が意識せずとも犯罪の片棒を担いでいたという事実は消えないが。それよりもあの探偵の気持ちが伝わって、とても暖かった。
なんて話で終わらせようとしたところで、彼女が手を前に出して一言。
「んな、幻想お疲れ様ね」
「え」
「アンタよりお父さんのこと知ってるワタシだから言わせてもらうけどね。そんなこと考えてないわよ」
「あ、あれ……? あれ、でも、合ってるよな? お酒のくだりは」
「違うわよ。お酒じゃないわ。お酒とバイクの年齢から考えると、容疑者はこの町内にいる十五歳から十九歳ってことになるわ……となると、どうなるか知ってる? 大学生も考慮しないといけないし……結構範囲が広いのよ。で、たまたま聞いて、たまたま誘拐のことを知ったお父さんがたまたま、高校生か大学生か特定できると思う? たまたま、行動範囲の広い大学生の秘密基地をたまたま、見つけられると思う? 隣の駅にあるかもしれない秘密基地をたまたま?」
たまたまがやけに大きくなっているのだけれども。彼女は少々吊り目で僕の方へと近寄って、真実を言おうとしている。
たまたま……!
「たまたま……たまたまさか!?」
「ええ。もっと範囲は狭くできるわ。たまたま……たまたまのエロ本でね! これなら十八歳未満の高校生だって、推測ができるのよ!」
僕はまた叫びたくなった。十数年越しにとんでもない助けを求むべく、コンビニの中で奇声を上げたくなったのだ。
「まさかまさかまさか、お父さんはエロ本を……まさか、さっき、言ってたけど、たまたま知った理由って?」
「店員さんに言われたらしいわ。貴方と同じお父さんらしき人が、エロ本を買ってた。だけど、一緒に子供もいるなんて珍しいって。それでこの辺りで高校生が秘密基地にできそうな場所を学校やら、いろんな人やらに聞いて、特定したそうよ」
「ええ、あの探偵、買おうとしてたの!? えっ!? じゃあ、あの人の性欲強くなかったら、僕が誘拐されてたことも知らなかったの?」
「ええ。アンタはお父さんに助けられた訳じゃないわ。エロ本によって、助けられたのよ」
僕は頭を抱え、蹲る。そしてすぐさま購入したメロンソーダを勢いよく振りながら、外に出る。
「嘘だ嘘だ嘘だ嘘だっ!」
「ほんとよほんとよほんとよ。そしてこれは夢じゃないわ」
「夢だぁ! 覚めろ覚めろ覚めろ!」
パッとペットボトルの蓋を開ける僕。顔全体をメロンソーダの泡に覆われたのは言うまでもない。
それでも諦めない。きっとこの事件には裏があるんだと信じ続けて歩いていく。その裏を証明できるように、僕は自分の推理力を鍛えていくのだ。
僕が尊敬していた人の正体がエロ本好き言うのは、高校生にとってあまりに残酷で過激すぎる!
名探偵になろう

目次