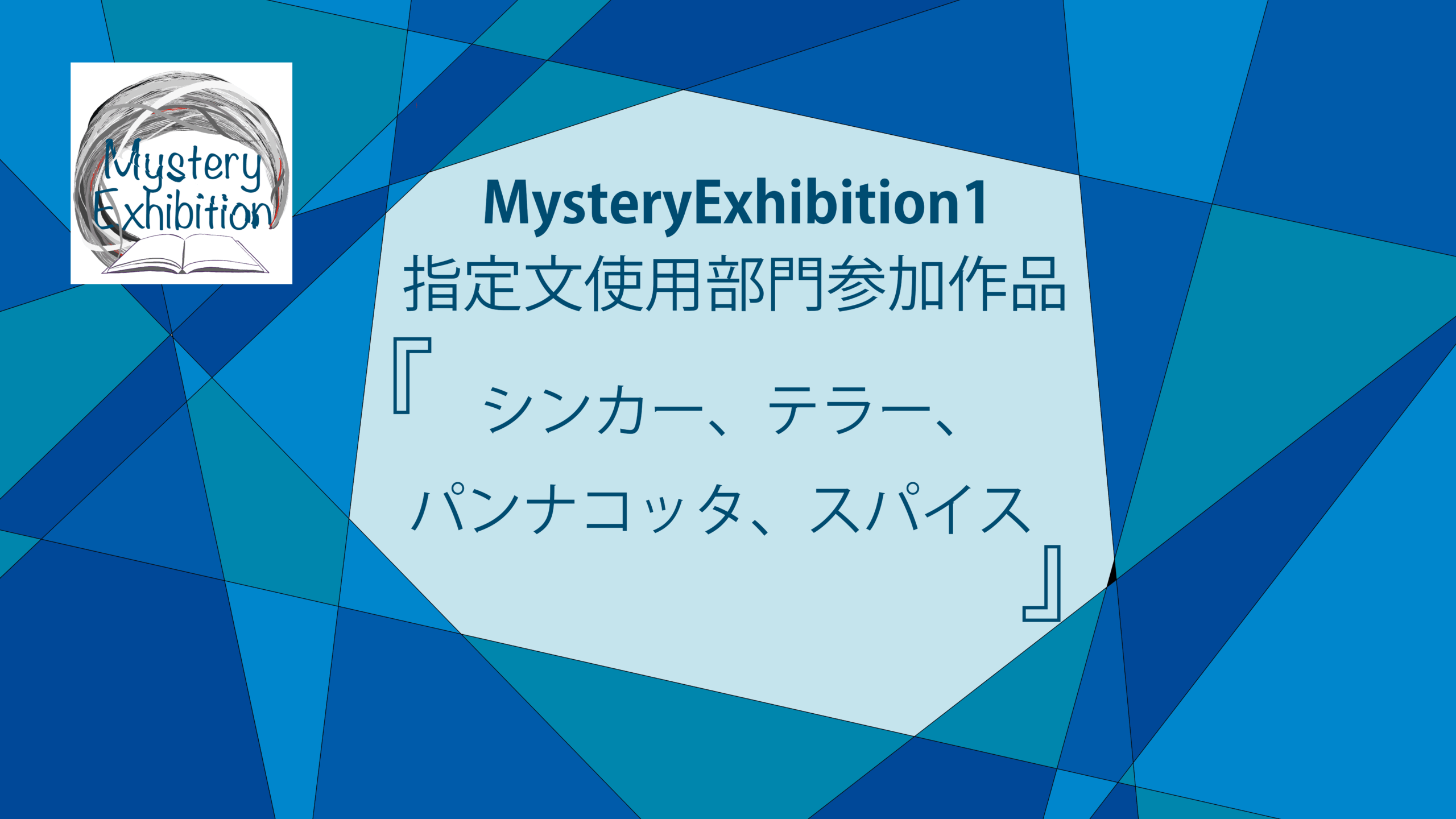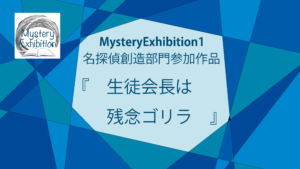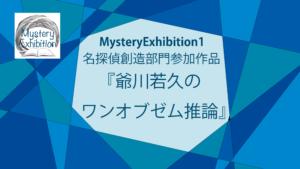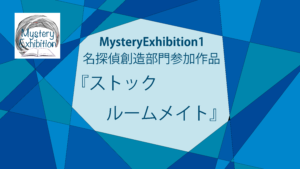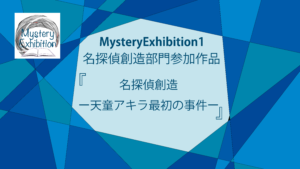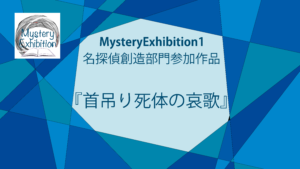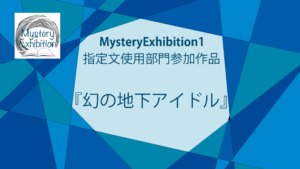0 巻頭歌
少女よ
少女よ
何故踊る
これ以上生きるのなんて迷惑だと
身悶えしているのか
1 目覚め
…………ブウウ――――――ンンン――――――ンンンン………………。
耳鳴りだ。
頭痛。倦怠感。吐き気。
最悪の目覚め。ゆっくりと体を起こす。ばきばきと体が音を立てる。石造りの床に転がって寝ていた。そのせいで体が固まってしまったらしい。
ここは?
見回す。さっきまで寝ていた、年季の入った石造りの床。コンクリートではない、年季の入った、自然石らしきものを敷き詰めてできた床。壁も石レンガでできている。狭い部屋に、壁や床と同様に年季の入った本棚が詰め込まれている。そこに入っている書籍もまた、見た目からすると古そうだ。どうやら全て洋書らしい。内容は、英語のものらしいタイトルをみただけでは全く分からない。
小さな図書室、そんな印象を受ける。だがもちろん、学校のものではない。この古さは、果たして、一体。
城。古城。そう、ここは遥か空の上に浮遊する絶対不可侵の天空城、永遠城≪エターナルキャッスル≫だ。
頭の中に、そんな言葉が浮かんでくる。
山々よりも高い、雲に隠れるようにして存在する城。
混乱する。なんだそれは? いや、そもそも。
そこでようやく、私は自分が誰なのかを知らない、いや覚えていないことを自覚する。私は、誰?
「ババロアではダメ。パンナコッタでないと」
揺れる意識の中、そんな文言が頭をよぎる。声ではなく、文字列が頭に浮かぶ。
また頭痛。さっきよりもひどい。思わず頭を抱えて俯くと、自分の服装が目に入る。青を基調としたロングスカート。そこから、棒のように細く白い足が飛び出している。藍色のブーツ。黒い縁取り。
何かの、コスチュームのようだ。
そんな感想を抱いた途端、また頭痛。
「つうっ」
呻き、立ち上がる。
狭い部屋。空気が悪いのかもしれない。
私はよろめきながら、分厚い木製のドアまでたどり着く。ノブをまわす。ありがたいことに鍵はかかっていない。
部屋を出ると、さっきの部屋と同様の石造りの床と壁からなる廊下。窓のひとつもないのに、明るい。そういえばさっきの部屋もそうだった。床、壁、天井がそのまま淡く光っているかのようだ。
狭い廊下。途中、いくつかドアがあるが、おそらくさっきと同じサイズの部屋だろう。今は、もう、とにかく広い場所にいきたい。
足をもつれさせながら歩いて、やがて急に開けた場所に出る。廊下の終わり。
ほう、と思わず息を吐いて、足を止める。
私がたどり着いた場所は、広いホールだった。これまでの閉塞感とは全く違う、広々としたホール。天井も高い。5メートル以上は上にある。いや、それだけではない。巨大な天窓から、ガラスを通して空を見ることができる。解放感がさっきまでと比べものにならない。
ただ、残念ながら曇り空だ。おまけに雪が降っている。天窓のガラスに、べしゃべしゃとほとんどみぞれのような雪が当たっている。雪? 今は冬なのか? また頭痛。ずっと上を見上げていたからかもしれない。
視線を下に戻す。
「え?」
ホールの床に、何か奇妙なものが転がっている。
薄汚れた、モップ。モップの固まり。だがそれにしては巨大すぎる気がする。そんなものが転がっている。
これは一体、と立ち尽くす私の前で、
「うーん」
そのモップが呻き、もぞもぞと動く。
それは、あまりにも毛の長い、大型犬だった。犬種は分からない。雑種かもしれない。薄汚れたその犬は、大きく伸びをすると、ぐるりと周辺を見回して、そして私と目が合う。
とぼけた顔をしたその犬は、長く汚れた毛で表情が隠されていることもあってか、絶妙に可愛くない。どちらかというと腹が立つ顔をしているとすら言える。
「何だ、お前」
とその犬が口を開く。
2 ルミナス・ブレイブ
犬が口をきいたことよりも、言われた言葉への反発心が先に来る。
「あんたこそ、何よ」想像していたよりも、かすれた高い声が私の喉から出てくる。
私の反論を受けて、犬は驚いたように目を見開いて、しばらく黙った後、「そう言えば、俺は、誰だ? 何か、頭痛いし」と呻く。
どうやら、この犬と私は同じような状態らしい。
「おい、俺、どんな風に見える?」
慌てた様子でぶんぶんと頭を振り、自分の体を見回しながら犬が聞いていたので、
「汚れたモップそっくり」
と教えてやる。
犬は苛立たし気に自分の左耳のうしろををがりがりとかきむしる。
「ねえ、あたし、あたしはどんな見た目?」
そういえばと思い聞いてみると、
「え? ああ、そうだな」
犬は私を上から下まで見て、
「有機出して魔法少女のコスプレした文学少女みてえな見た目だな」
「魔法少女のコスプレって――」
口に出した瞬間、これまでで一番の、頭が内側から破裂するかのような頭痛。
悶える。
「え、何何?」
犬は驚き怯えている。
だが、それどころではない。
私は絶叫する。そうして。
思い出す。
恒星戦士ルミナス・ブレイブ。
人々の心を蝕む「虚無≪ヴォイド≫」の軍勢が現れ、希望や夢を奪って世界を暗黒に変えようとしている。
「星の守護精霊≪セレスティア≫」に選ばれし四人の少女たちは「煌星≪ルミナス≫」の力を宿し、勇気と絆で戦う。
この説明をしても、犬はぽかん、とした顔でこちらを見ているだけだった。
「思い出さないの? あなたは――」
また頭痛。歯を食いしばって耐えて、名前を引っ張ってくる。
「ルクス。そう、マスコットキャラクターのルクスよ。星の守護精霊≪セレスティア≫の使い。私たちにブレスレットを渡してくれたのもあなたじゃない」
「ええ? マジ?」
犬、いやルクスはしきりに首をひねっている。
「全然記憶ないけど、俺ルクスっていうの? うーん……他に思い出したことはあるのか? 例えば、ここは?」
「ここは永遠城≪エターナルキャッスル≫。空高く山よりも遥か高くに浮いている天空の城で、星の守護精霊≪セレスティア≫が私たちルミナス・ブレイブに何か用がある時は、この城に呼び出されるの」
「ふーん」
ルクスは息なのか返事なのか分からないものをもらし、
「で、お前は?」
「え?」
「俺はルクス。それはとりあえず受け入れるとして。結局、お前は誰なんだよ」
肝心なことが抜けていた。記憶を探る。頭痛。耐える。
「四人。ルミナス・ブレイブは、四人の少女。シンカー。テラー。パンナコッタ。それから、スパイス」
「変な名前。まあ、魔法少女ってそんなもんなのか?」
「そして、私は、私は」思い出す。思い出そうとする。その、ルミナスの言うところの変な名前のどれが、自分なのかを。「……分からない」
頭痛。ただそれだけだ。顔をしかめる。
「その魔法少女のなんだっけ、ルミナス・ブレイブ? そいつらの設定は思い出せても、自分のことが思い出せないってことか?」
「ええ、そうみたい」
頭痛で頭を抱える。
「これって、確か、ほら、記憶喪失でエピソード記憶だけ思い出せないとか、そういう話なんじゃあないかしら?」
「さすが文学少女。確かにエピソード記憶うんぬんは聞いたことがあるがな、でもにしたっておかしくねえか?」
もう会話に飽きたのか、ルクスは天窓を見上げている。水っぽい雪が天窓のガラスに衝突するのを、ぼんやりと眺めている。
「おかしいって、それは確かに。私もルクスも同時に記憶を失っているなんて、そんな馬鹿な話が」
「それじゃなくて、いやそれもだけど、お前の恰好だよ」
「え」そう言われて自分の服装を見直す。青を基調としたコスチューム。そう、これを見て魔法少女のコスプレみたいだと言われたから、ルミナス・ブレイブのことを思い出したのだ。
「キャラクターごとに服装違うだろ、こういうのって。その服装がシンカー、テラー、パンナコッタ、スパイス。その誰のなのか、覚えていないのか?」
言われてみれば。
だが、名前やルミナス・ブレイブの設定は出てきても、ビジュアルは全く思い浮かんでくれない。
でも、恰好からして私がルミナス・ブレイブのうちの誰かなのは間違いないし、この薄汚れたモップみたいなのはルクスのはずだ。
それは、間違いないけれど。
「結局、俺たちがどうしてこうなってるのか、どうしてその、え、え、エターナルキャッスルだっけ、そこにいるのか、全然分からんわけだよな」天窓をずっと見上げていたルクスは首を戻す。
「で、これからどうするか案はあるか?」
私は返事ができない。
「ん、これなんだ」
ルクスは、ホールの中央まで歩いていく。
ホールの床の中央に金属製のプレートがある。埋め込まれている。小さなプレートだ。気づかなかった。
「なんか、銘文みたいなの刻まれてるな」
私ものぞき込む。
そこには、詩のようなものが日本語で刻まれている。
少女よ
少女よ
何故踊る
これ以上生きるのなんて迷惑だと
身悶えしているのか
「なにこれ? 城主ポエム?」
ルクスが訊いてくるが、私に答えられるはずもない。
また、頭痛。
「城主は不在。いや、四人のうちの誰かが城主だ。一体、誰が?」
「ババロアではダメ。パンナコッタでないと」
フラッシュバックのように、そんな文言が、脚本に書いてあるセリフのように浮かび上がってくる。だが、今の私には、その意味が分からない。
A 最近はやりの特殊設定ミステリってどうよpart3
1 :名無しのオプ :202X/05/10(月) 12:01:44.15 ID:abcd1234
最近の特殊設定ミステリって多くね?
「館が孤立」とか「全員記憶喪失」とか、もうお腹いっぱいなんだが。
2 :名無しの読者 :202X/05/10(月) 12:03:21.55 ID:efgh5678
>>1
「館が孤立」は全然特殊設定じゃねえだろw
それはともかく特殊設定はやってるのは同意
まあ、流行り廃りあるのは仕方ない。
3 :名無しのオプ :202X/05/10(月) 12:05:33.77 ID:ijkl9012
「吹雪で山荘孤立」→定番すぎてもはや特殊設定じゃない
「全員が双子」→やりすぎ
「犯人も探偵もいない」→意味不明
4 :名無しの読者 :202X/05/10(月) 12:07:12.48 ID:mnop3456
>>3
最後のやつ逆に読みたいわwww
5 :名無しのオプ :202X/05/10(月) 12:09:44.90 ID:qrst7890
特殊設定って、上手くハマれば神作になるんだよな。
『~館』シリーズとか。
でもハズレはただの悪ノリ。
6 :名無しの読者 :202X/05/10(月) 12:11:27.66 ID:uvwx1122
現実に何か特殊設定一つプラスするだけならいいんだが、まったく別の世界が舞台になったらおもんない
例えば魔法がある世界のミステリとか。何でもありだろ
7 :名無しのオプ :202X/05/10(月) 12:13:09.77 ID:yzab3344
>>6
さすがに魔法でどこまでできてどこからできないかは描写されてんじゃねえの?
8:名無しの読者 :202X/05/10(月) 12:15:27.66 ID:uvwx1122
>>7
そうなんだけど、探偵役とか読者の知らない魔法でどうにか可能性が排除できないじゃん
9 :名無しのオプ :202X/05/10(月) 12:17:23.67 ID:yzab3344
>>8
そんなこと言い出したら現実世界だってそうだろ
俺たち一般人の全く知らない科学技術とかが使われてる可能性はあるんだから
10:名無しの読者 :202X/05/10(月) 12:20:22.26 ID:cdef5566
(´・ω・`)< 結局、設定じゃなくて料理の仕方なんだよなぁ
11:よせ@ほぼ無職 :202X/05/10(月) 12:21:42.58 ID:naby0031
メタ推理するのがお勧め。
特殊設定の説明をじっくり読んで、作者はそのルールのどこの裏をかこうとしているのか考えれば楽勝
12:名無しのオプ :202X/05/10(月) 12:25:03.14 ID:ijkl9012
特殊設定は小説とかじゃなくてゲームならうまくいくのかもな
ゲームだと作者は読者に謎を解決してほしいから、丁寧に誘導してくるからそれに乗れば間違いないだろ。別の可能性とかを考えてもやもやする必要がない。小説とかは逆に読者に解けないようにしてそうだw
よせの言ってるメタ推理っぽいけど、作者の想定したルートにのってやったら、その先にあるのが正解だろ、すくなくとも作者の想定した
3 食事と名前についての考察
手がかりがないかと二人、というより一人と一匹で城を探索することになる。ホールから一本道の廊下を歩きながら、私たちは相談する。
私が目覚めた状況、図書室あるいは書斎のような場所で床に倒れていたことを説明する。
ルクスも説明を返すが、目覚めたらあのホールで寝ていたというだけで、結局そういうところまで私たちの状況は似通っていた。
「あの、ところでよ、あんまり聞きたくないんだけど、ここって、あの天窓以外に窓はないし、俺が倒れていた玄関ホールっぽいとこにもドアもないよな」
「そうね。永遠城≪エターナルキャッスル≫には出入口はないわ」
「うっ、やっぱり」
ルクスの顔が引きつっている気がする。毛むくじゃらでよく分からないが。
「出入りは城主である星の守護精霊≪セレスティア≫に管理されているから。私たちは召喚魔法でこの城に呼び出されて、用が終わったら召喚魔法でもといた場所に戻される」
「じゃあ、そのセレスティアとやらに会って頼まないとこのこの城から出れないってことかよ」
犬でありながらルクスはげんなりした表情を器用につくってみせる。
「ええ……そう、ね」
不都合な設定がまた一つ浮き上がってきたが、それを今説明してもルクスをいたずらに絶望させるだけなのでとりあえず黙る。
私がホールに向かう前に通り過ぎたいくつかのドア、それを片端から開けていくことにする。まずは一つ目。やはり鍵はかかっていない。
「おっ」開いたドアの向こうに首を突っ込んだルクスは嬉し気に叫ぶ。「これ、キッチンじゃあないか? なんか食い物あるかも」
ルクスの言うように、ドアの向こうにあるのはキッチンだ。近代的なシステムキッチンが、不釣り合いな古びた石壁に張り付いている。
そういえば、空腹だ。
冷蔵庫とパントリーを、犬ながら二足歩行までして手でルクスは開けていく。
「肉、野菜、魚、はっはああ、生クリームまである。城主は菓子も作るタイプなのか? まあ、いいや、さっさと食えるものは何かないかな、パンとかカップラーメンとか」
「犬なのにカップラーメン食べられるの?」
素直に驚く。
「なめんなよ、カップラーメンくらい」言ってる途中で自分の肉球のついた手を眺める。「いや、やっぱりパンにしよう」
だがいくら漁ってもパンは見つからず(カップラーメンはあったが)、代わりに見つかったのは、オートミールクッキーだ。
「けっ、オーガニック野郎が。砂糖卵乳製品不使用だってよ。意識高いな、ここの城主は。それともお前らルミナス・ブレイブの総意か?」
文句を言いながらも、早速そのクッキーをかじり出す。
「私たちも別にこの城で食事に招かれた覚えはない、はず。うん、ルミナス・ブレイブはこの城で食事をした設定はない。これは城主である星の守護精霊≪セレスティア≫用のものだと、思う、けど」
そもそも守護精霊って食事をするのか? また、頭痛。
とりあえず、空腹は空腹だ。
生の肉や魚もあったがそれは避け、火を使ったりせずにさっさと食べられるものを選んで、使えそうな皿や鍋にそのまま開けていく。調味料も多種多様だ。聞いたことのない、海外のものらしき謎の液体の入った瓶も多数。使う勇気がない。
カット野菜にノンオイルのドレッシングをかけただけのサラダ、ハム、ウインナー、ルクスが食べているのと同じオートミールクッキー。ちなみにどれもパッケージからすると無添加の結構いいものらしい。
同じものを床にも置いてやる。
「マヨネーズとかないのかよマヨネーズ、ノンオイルのドレッシングじゃなくてよ、マヨネーズどばーっとかけたいなあ」
野菜をばりばりとかみ砕きながらルクスがぼやく。
贅沢を言うルクスだが、私も贅沢を言えば甘味も欲しい。
生クリームがあるんだから甘味の類もあるのではないかとパントリーと冷蔵庫を改めて漁ると、ゼラチンや砂糖といった製菓材料らしきものと一緒に、和菓子がいくつか入っている。ちょうどいい。
饅頭をいくつか拝借して口にぽんぽんと放り込む。甘味が脳にしみこむ。頭痛が和らぐ。
「ルクスもいる?」
「あ、俺、洋菓子派だから。フランスの文化が入ってないと喉を通らないんだよな」
「マヨネーズどばどばかけたいって言ってたのに偉そうな」
喋りながら、とりあえず胃を満たしたことで人心地着く。
「次はどうする?」
ルクスの言葉に私は肩をすくめる。アイデアはない。
「未だに自分が誰なのか分からないのか?」
「ええ、まあ」
「じゃあ、俺の予想でいいか?」
「あ、私も予想ならあるけど」
そして、二人の声が重なる。
「「シンカー」」
やっぱり、そうか。
「書庫みたいなところで目覚めたし、私の見た目が文学少女っぽいって言ってたじゃん」
だから、シンカー。思想家。短絡的だろうか。
「そうそう、お前根暗っぽい見た目だからな」
ルクスは一言多い。
「あと、他の奴らのイメージがあれじゃん、テラーは恐怖だからめちゃくちゃ狂暴そう、服装も刺々しかったりしてたりな。パンナコッタはまあ、スイーツ的な、ふわふわしてそうじゃん、服装もフリルいっぱいついてたりとか。で、スパイスは、なんか異国情緒あるれる外観してそうじゃん」
あまりにもな偏見だが、しかし的を得ている気がする。魔法少女の名前というかコードネームは、名は体を表す、な気がする。こういうのがイメージとも内容とも関係のないことはないだろう、きっと。
「しかし、どうしてパンナコッタなんだろうな」ルクスがぼやく。「ババロアでいいだろ、ほぼ同じじゃん」
「いえ、ババロアでは」ババロアではダメ。文字がフラッシュバックする。「ババロアでは、多分ダメなんでしょう」
理由にもならない理由。ルクスは妙な顔をするが、突っ込んできたりはしなかった。
食事が終わる。とりあえず、空腹は落ち着いた。
さて、とりあえずアイデアはない。ひたすらに他の場所を探索していくとしよう。
4 死体発見
キッチンのとなりの部屋を確認する。キッチンや私が目覚めた書庫と同様の部屋の、真ん中に無造作にソファーが置いてある。
「ん、ここが城主の寛ぐ部屋か? にしては殺風景だな」
ルクスが不審げに呟く。
確かに。まるで、空の部屋に、無理矢理役割を与えるために慌ててソファーを設置したかのような――
刺すような頭痛が私の思考を止める。
とりあえず、その部屋を出る。
その隣、私が目覚めた部屋だ。一応確認する。相変わらずの本棚に埋め尽くされた壁。
「ふううん」
器用に二足歩行に切り替えたルクスが、本棚の本を引き出してぱらぱらとめくる。
「英語だ」
中身を見て、一言だけ言って本を戻す。
「英語は読めないの?」
「日本語しゃべれるだけでも褒めてくれよ。犬だぞ」
文句を言ったルクスは、何かを探すように本棚の隅から隅まで調べ回り、やがて本棚の隅から、他と比べても分厚い書籍を引っ張り出す。
「何それ?」
「辞書だ。英和辞書。よっしゃ、これで英語を訳しながら読めるぞ」
そんなものがあったのか。私は気づかなかった。しかし。
「本当に、いちいち辞書引きながら読むつもり?」
「なわけねーだろ」
せっかく引っ張り出した辞書を床に転がす。
「でもタイトルぐらいは訳せるからな、ええっと、これはなんだ、えーっと、誰が風邪から戻ったかスパイしろ?」
「絶対訳ミスってるわよ」
これ以上そんなことで時間を無駄にするわけにはいかない。
だらだらしたそうなルクスを引っ張って、次の部屋に向かう。
「ひっぱるなよお。俺の勘だけど、この辞書に全ての謎は隠されてるから、あとは辞書を引きながら本のタイトル訳していこうぜ」
「そんなわけないでしょ。いいからさっさと――」
文句を言うルクスを制しながら、私は次のドアを開ける。
「――うえ?」
視覚よりも先に、猛烈な臭いに、私の思考と動きが止まる。ドアを半分開いたまま。
ルクスも、固まっている。
ドアの向こうに、部屋がある。サイズも、壁も床も天井も、これまでと同じ。ただ一つ違うことは。真っ赤だ。
部屋が、真っ赤に塗りたくられている。赤いだけではなく、何か、塊のようなものがあちらこちらに散乱していて。
「うう、ふう」
異臭で息ができない。頭も動かない。一瞬でしつこかった頭痛は消えて、代わりに脳みそが凍ってしまった。
「さすがにちょっときついな、これ」
げんなりとした声でルクスが言う。
そうしてようやく、さっきからの猛烈な異臭が血の臭いであり、目の前にあるのが、おそらく、部屋全体にぶちまけられた、粉々になった死体なのだと分かって、吐き気と共に視界が休息に狭くなっていって、私はドアを閉めてその場にうずくまる。
廊下の片隅に座り込んで動けなくなった私の代わりというわけでもないのだろうが、ルクスは嫌そうな顔をしながらも、しかし存外気軽な様子で「俺が部屋チェックしてくるわ」と言ってあの血と肉片塗れの部屋に入っていった。止める気力もないが、あのモップのようなルクスが中に入ったらどんなことになるのか、考えただけでも恐ろしい。
「最悪だ、風呂入りたいなー」
懸念どおり、全身の長い毛を真っ赤に染めて、血を滴らせながらルクスが部屋から出てくる。思わず悲鳴を上げる。
「ルクス、あなた平気なの?」
「いや、だから風呂入りたいくらいだってば」
「そういう問題じゃなくて、し、し、死体」
「え? ああ、俺、犬だし」
言いながら、ルクスは部屋の中からずるずると何かを出してくる。
「ええ、何、何?」
「原型とどめててた肉片とか、なんか推理の足しになりそうなやつ」
また悲鳴を上げる。気が遠くなる。
「まあまあ、落ち着けよ。いいか、これとか、まだ原型とどめてる。多分、腕だ。脚かもしれないけど。ほら、コスチュームもくっついている」
言われるが、目を固く瞑る。見たくない。
「ちょっとでいいから見ろよ。話が進まないだろ」しかし、ずっとそうしているわけにもいかない。仕方なく、薄くだが、目を開ける。
銀色のついた肉片が見えて、慌てて目を閉じる。
「銀色のコスチューム。多分、お前のお仲間だな。あと、これだ、これも気になる」
ずるずると何かを引きずる音。
「もうやめてよ」
「見ろって、これはそんなに刺激的じゃあない」
そう言われて、私は恐る恐る目を開ける。
床に転がっていたのは、多少血にまみれているとはいえ、確かにさっきまでのおぞましいものとは違った。何か、機械の部品のようだ。
「これって、パソコン?」
見たままを言う。キーボードの破片、中の基盤が折れ曲がったもの、ディスプレイの欠片。
「いや、でも、それに近いガジェットじゃあないか? これ、多分頭の一部だと思うんだけど」
ごろり、と何かを後ろから前に出そうとするルクスに両腕で×をつくってとめる。
「ああ、そう? じゃあ、これだけでも」
とルクスが見せてくるのは、ひび割れているが、眼鏡らしきもの。だが、レンズの形がおかしいし、何やら奇妙な部品がごちゃごちゃとくっついているし、千切れているがコードが数本つながっている。
「これは?」
「スマートグラスの類じゃないか? 現実拡張なんたら。頭につけてた。で、そのパソコンっぽいのも、多分そいつが腕とかにつけていたガジェットなんじゃねえかな」
創造してみる。銀色のコスチューム。メカっぽいガジェットを体に装着した魔法少女。
「確かに、ありうるかも……」
臭いにも光景にも慣れてしまったのか、少しずつ私は落ち着いてくる。ルクスともやりとりをする余裕が出てくる。
「つまり、あれだ、ここで死んでたのは、データキャラだ。ほら、敵が出てきたらキーボードかたかたやって『既に分析済みです』みたいなの言うやつ」
分からんでもない。
「そうなると、なんか」正直に言う。「その魔法少女の方が、シンカー、思想家っぽくない? 私よりも」
「確かにな」
じゃあ、私の名前は何だろうか?
結局、それ以外に分かったことはない。
「死因も分からない?」
「分からんね。爆弾でも爆発したのかとも思ったが、それにしちゃ壁や床が無事だ」
「ああ、それなら、不思議はないわ」私の頭からするりと知識が出てくる。「この城は、永遠の掟によって守られているから。たとえ爆弾によって粉々になったとしても、すぐに元通りになるの」
「えっ、そうなの? まあ、だとしても焼け焦げたりしていないから、やっぱり爆弾説はないような気がするんだよなあ。というかさ」
ルクスは溜息をついて白けた顔をする。
「その、ついさっき聞いたこの城の復元機能もそうなんだけどよ、魔法とかあるんならどうやってお前のお仲間が粉々にされたのか凶器なんかを論じるのって、超無駄じゃないか?」
仰る通りだ。不思議なパワーで粉々にされた可能性が多々あるわけだから。
ずっとこうしているわけにもいかない。とりあえず、ルクスが運び出した諸々、特に肉片がなるべく目に入らないように気を付けながら私は立ち上がる。
「とにかく、ここを離れましょうよ。ホール、あそこに戻れば」
「えっ、他の部屋を探索しようぜ」
気が進まない。
「とにかく、水場を探したいんだよ、俺こういう状態だから。これで血が乾いちゃったら俺、全身ばりばりで固まっちゃうだろ」
そう言われると無碍にはできない。
私たちはホールとは逆方向に歩き出す。
「あ、そうだ」
ふと、ルクスは足を止めると、私の前にぼろぼろの紙を差し出す。
「なに、これ?」
「あの部屋で見つけた。多分、あのシンカー疑惑のある死体の持ち物だ。メモの切れ端みたいなんだが、どう思う? どういう意味だと思う?」
血に塗れたメモは、かろうじて文字が読める。
そこには、角ばった筆跡で、ただこれだけ書いてある。
『城主は仲間外れ』
じっと、ルクスが私の顔を見ている。メモを見た私の反応を観察している。だが、私には何も分からない。何も分かるはずがない。
だというのに、どうしてせっかく消えたはずの頭痛が酷くなっていくのか。脳を内側から引っ掻き回されているかのような。
やがて、私たちは二人とも無言のまま、歩行を再開する。
B 「魔王のいた教室」あらすじ
連続殺人鬼「デッドエンド」に怯える街。
名探偵・Nは、その犯行に不可解な既視感を覚えていた。
――小学生時代、同級生が一人、不可解な状況で殺された。
だが当時の記憶は曖昧で、肝心な部分がどうしても思い出せない。
事件を確かめるため、かつての同級生を訪ね歩くN。
しかし、彼らは次々と「デッドエンド」に襲われ、証言は闇に消える。
そんな中、存在すら記憶にない「クラスメイト」から同窓会の招待状が届く。
空白の記憶と、現在進行形の殺人――二つの謎は一つに収束していく。
果たして、あの教室で本当に起きていたこととは?
そして「デッドエンド」とは何者なのか?
欠けた記憶と連続殺人が交錯するとき、誰もが気づいていなかった“重大な見落とし”が浮かび上がる。
読者の認識すら試される、本格推理の到達点。
最後に暴かれるのは――探偵の推理か、それともあなたの記憶か。
5 死体以外発見
運のいいことに、次の部屋でいきなり当たりを引いた。
次のドアを、前の部屋のことがあるのでかなり警戒しながらゆっくりと開けると、そこはシャワールームだった。
といっても、今までと同様の部屋に、シャワーと排水溝、それから着替えやタオルが入っているであろうクローゼットが置いてあるだけのものだが。
狂喜乱舞して突入したルクスはシャワーノブをひねる。ちゃんと水が出てくる。水浴びをしたルクスの体は、みるみる赤から最初の茶色に戻っていく。ただ、元々の汚れはかなり強力なのか、シャワーを浴びても血が消えただけでルクス自体がきれいになっている感はない。
「どうだ、いい感じになったか?」
全身に水を浴びながらルクスが聞いてくるので正直に、
「血はとれたけど、ええと、水に濡れた薄汚れたモップみたい」
「嘘だろ、きれいなモップにすらなれねえのかよ」
「もっとシャワー浴びたら、ちょっと汚れたモップくらいにはなれるかもよ」
私の目の前から血が消えて臭いもなくなったことに大分、気分が良くなる。軽口も叩けるくらいには回復してきた。
言うなら今かもしれない。不意にそう思って、言うのを後回しにしてきたことをルクスにここで伝えることにする。
「ねえ、ルクス」
「うん?」
「その、星の守護精霊≪セレスティア≫に会って頼まないとこの城から出れないってことだけど」
「ああ、そうだよな」
「実は私、いえ、誰も、彼女に会ったことはないのよ。いえ、そのはず。そういう知識だけ、ぼんやりと私の中にあるの」
思い切って、一気に言う。
「はぁ? どういう意味だよ」
困惑したルクスの声。
「そのままの意味よ。この城に呼び出された時はいつも、置手紙で指令を伝えられただけだったはず」
「じゃあ、あれか、そもそも、そのセレスティアとやら、ここの城主がどんなヤツなのか一切分からないってことか?」
頷く。
シャワーを浴びながらルクスは天を仰ぐ。
「冗談きついぜ。じゃあ、そもそもそいつが存在しているかどうか自体怪しいことじゃねえのか?」
その言葉を聞いて、頭痛。存在、していない? そんな、馬鹿な。
ともかく、全身を洗ったルクスはさっぱりした顔らしきものをしてシャワーから離れる。
「タオル使わないの?」
「犬だぞ」
とはいえ、びしょ濡れだ。見ている方が嫌だ。
「しょうがない、ちょっと待ってよ」
私が拭いてやろう、とクローゼットを開ける。
油断していた。全く持って、油断していた。
だから、クローゼットの中に、数枚のタオルと横向きに体育座りするようにして押し込められている少女を見つけて、私はまた止まってしまう。
「はっ、あ」
それでも、さっきよりも数段まともに頭が働き、すぐに現実復帰できる。理由は、この少女は人の形をしているし血にも塗れていないからだ。いや、というよりも。
「生き、てる?」
疑問は無意識に口に出ている。
少女は、身動きせず、目を閉じているが、それでもわずかながら、呼吸に由来するであろうわずかな肩の上下がある。
「うわ、何、そいつ」
ひょこりと後ろからルクスが顔を出す。
それで、私は完全に動き出す。
恐怖よりも先に好奇心、いや確認して安堵したい気持ちが上回り、私は少女の口元に手をかざす。やはり、呼吸している。
安堵で腰が抜けそうになる。
シャープな顔立ちで、ショートカットの少女だ。目を閉じているからいまいち印象がはっきりしないが、おそらく目つきは鋭いのではないだろうか。真っ黒い、肌に張り付くようなタイトなコスチュームを身にまとっている。身体は、一分の隙も無く引き締まっている。だというのに、今、彼女の身体は全くの無防備。
「寝ている、っていうのとはちょっと違うよなあ」
ルクスが言うが、同感だ。さっきからゆすったり、声をかけたり、ちょっと勇気を出して耳を引っ張ったりしてみたが、まったく反応がない。
意を決して、その体をがっしりと抱えて、
「よっ」
少女をクローゼットから取り出そうとする。
その時、少女のタイトなコスチューム、黒い布の内側で、何かがかすかに蠢いた気がする。反射的な嫌悪感で、私は少女から手を放し、身を引く。
次の瞬間、少女の手首、ぴったりと張り付いた袖口から、ぬるりと滑らかに刃が飛び出す。
「うわっ」
「怖っ、暗器ってやつか?」
横でルクスが怯えて飛び跳ねる。
心底怯えたものの、このあまりにも現実離れした(魔法少女なのだから当たり前か?)状況に、私の心は麻痺、あるいはどこかしらが壊れてしまっているらしい。
すぐに他に仕掛けがないか、彼女の身体をつつきまわすことにする。
彼女の細い小指をくるくると回したところで、今度は彼女の肘から長い錐のようなものが突き出てくる。
「びっくり人間だな」
ルクスは半分呆れている。
この仕込み武器。漆黒のコスチューム。シャープな体つきと鋭い印象の顔立ち。
暗殺者。
それが、私の率直な感想だ。ということは。
「「テラー」」
私とルクスの声が重なる。
やっぱり、そうなる。どう考えても、彼女がテラーだ。
「殺し屋っぽいしな。怖いし」ルクスが補足する。「少なくとも、絶対にパンナコッタじゃないだろ、見た目シャープすぎるし」
同感ではある。
「あーでも、もしこれがただ寝てるだけならワンチャン、パンナコッタ説ありうるかもな。ふわふわしてよく眠りそうじゃん」
「名前のイメージだけで判断しすぎでしょう、さすがに」
死体の衝撃、続いて少女の発見という事態の急変から私のメンタルを少しでも回復させるために、あえて軽口を叩いてくれているのだとは理解できる。だから、私も乗ることにする。
「別にパンナコッタにとっては悪い話じゃないだろ。名前のイメージからすると、少なくともパンナコッタがこの事態の黒幕ってことはなさそうだし。パンナコッタは裏表ないアホだろきっと。信用できるんじゃないか?」
「そんな理由で信用されてもパンナコッタだって嬉しくないわよ。そんなのパンナコッタだって迷惑こうむる」
途端、ルクスは黙ってじっと私を見てくる。
「な、なによ」
「いや、今お前――」ルクスは首を振る。「いや、ともかく、こいつがテラーっぽいってことは分かった。それで?」
「そうなると、結局、最後の疑問は、どうして寝てるのかってことだけど」
「これ、寝てんのか? 全然起きないじゃねえか」
「まあ、そうね」
私は、おそるおそる、彼女の顔を触ってみる。やはり何の反応もない。かすかに呼吸しているのは分かるが、それだけだ。
「ちょっとやっているぜ」
言って、ルクスが突然彼女の指に噛みつく。
「うわ、ちょっと!」
慌てて止めるが、後の祭りだ。それでも、彼女は起きない。そして、彼女の指には噛み痕が。
「え?」
あったが、見る見る間に消えていく。
「おいおいおい、なんだ、これ」
ルクスも驚いている。
まるで逆再生だ。
「これって、あれか。なんだっけ、永遠の掟だっけ」
確かに、私もそれを連想した。この城のものは破壊してもすぐに復元する設定だ。設定? まあ、いい。だが、おかしい。
「これは人よ。モノじゃあない」
「まあ、そうだな」
ともかく、傷跡は消えて元通りになる。
「ちなみに、だったら俺たちが食べたクッキーとかも復元されるのか?」
と、重箱の隅をつつくような指摘がルクスから出る。
「そんなわけないでしょ」
「どうして?」
「えーと、所有権じゃない? 食べた時点で、城のものじゃあなく、私たちのものになるっていうか」
適当に言ってみたが、なかなか筋が通っている気もする。
ともかく、少女は目覚めない。私とルクスは黙って顔を見合わせる。
少し気が引けたが、無理矢理指で右目の瞼を上げてみる。
「……ひえ?」
あまりにも予想外、というよりも意味が不明なものが見えて、私の口から間抜けな声が出る。
ルクスも目を丸くしている。
ぽかんとして動けず、疑問で頭が一杯になる。そうして、そのあとに根源的な恐怖が徐々に、徐々に湧いてくる。
意識のない少女、その無理矢理開けた目、眼球がある。美しい瞳。つくりもの、義眼を疑うような美しい眼球だ。いや、実際、義眼なのだろう。これが、本物の眼球なわけがない。
その瞳、真っ黒い瞳の中に、はっきりと浮かび上がるように、あるいは瞳を真っ二つに両断するかのように、真っ白い数字が、「1」が刻まれている。
数十秒たって、ようやく私は悲鳴を上げる。
6 死体と死体以外発見
もう勘弁してくれ。
私はシャワールームから這う這うの体で退散する。
もう、何も考えたくない。この城の中では、何もかもが狂っている。ある意味で、死体よりも奇妙なものを見てしまった。
「おーい大丈夫か」
遅れて、ルクスも廊下に出てくる。
「もう、やめよう。頭がおかしくなりそう」
私が正直な感想を言うと、ルクスは頷く。
「まあ、気持ちは分かる。けど、どうもあと少しみたいだぞ」
ルクスに言われて廊下の先を見ると、確かにもうすぐ廊下の突き当りのようだ。ただ、単に廊下が終わっているだけではなく、何か別の空間になっているようだ。
どうでもいい。あそこをチェックして、そうしたら終わる。
床にでも転がって寝てしまいたい。
よろよろとそちらに向かう。
「しっかし、確かに何が起こってるんだろうな、これは」
ルクスが気を使ってか話しかけてくる。
「分からないわよ、そんなの」
「いや、そりゃそうだろうけど、それにしたって妙だ。少なくとも、死体が一つあった。粉々の奴がな。犯人が多分、いるはずだよな」
「犯人」無意識に名前が出てくる。「星の守護精霊≪セレスティア≫」
「せれ……? ああ、城主か。まあ、そうだよな、そいつが怪しいよな。じゃあ、あれか? そいつが魔法少女を粉々にして殺したり、意識を失わせたりしてるってことか?」
「もしそうだとしたら」頭痛、それと共に私の中から知識がこぼれ出てくる。「最悪だわ。だって、勝ち目がない」
「そうなのか? お前も魔法少女なのに?」
「星の守護精霊≪セレスティア≫はこの永遠城≪エターナルキャッスル≫の中にいる限り、無敵よ。絶対領域≪クイーンテリトリー≫によってありとあらゆる攻撃を無効化する。ダメージを絶対に受けないの」
「なにそれ。つまんねー」
目的地に着いたところで、話はそこで終わる。
廊下の突き当りにあったのは、開けた空間だ。だが、あのホールよりは狭い。大分狭い。これまで見てきた部屋と大して変わらないサイズだが、天井が遥かに高い。天井が、はっきりとは見えないくらいだ。多分、ここは、塔のようになっているのだろう。
城に塔がくっついているような外観をしているのか。
だが、正直、そんなことはどうでもいい。
「ははは」
笑う。笑ってしまう。もう、やってられない。
その場に座り込む。
廊下からは見えなかった。高い高い天井のすぐ下、壁の途中から、真っ赤な帯がまっすぐに床まで垂れている。
だがそれはもちろん、本物の帯ではない。夥しい量の血液が、不可解にも塔の先端近くから床にまで垂れているのだ。帯のように。
そして、その帯の終点には、当然のように死体が転がっている。
死体は、両手がありえない方向に折れ曲がっていたりとか、血に塗れていたりとか、それなりに損傷はあるが、粉々になっていたあの死体とは雲泥の差だ。ピンクを基調としたフリルの着いたコスチュームも、柔らかそうな巻かれた茶色の髪も、幼さを残した顔も、その全てが原形をとどめている。
そう、よほどマシだ。粉々の死体よりも、意識のない眼球に数字が刻まれた少女よりも。
ただ、その少女の死体は、下半身がなかった。正確には胸の下あたりで、完全に両断されている。一体何がどうなったらこんなことになるのか、漫画やアニメの世界のように鮮やかに両断されている。切断面は真っすぐで、ギロチンでも使ったのでなければこんなにも綺麗に切断できないだろう。
「ふふ、うふふ」
笑いが止まらない。お腹が痛い。酷い頭痛も襲ってくる。その痛みすらおかしい。おかしくてたまらない。
「おいおい、大丈夫かよ」
ルクスが後ろから声をかけてくるが、笑いをこらえることができない。横隔膜が勝手に痙攣してしまっている。
「うふ、うふふふふ」
笑いながら、私はその少女の死体のすぐ横、そこに転がっているもう一つのもの、いや、人、いややっぱりもの? とにかく、私の笑いの原因のひとつに這いよる。笑いすぎて立ち上がることができないから、四つん這いだ。
獣のように歩きながら、私はそれに近づく。笑いながら観察する。
黒いタイトなコスチューム。細い手足。少女が、床に寝ている。似ている。いや、違う。髪型と顔立ちを近づいて確認する。「ふふふ」笑える。同じだ。全く同じ。あの、シャワールームのクローゼットの中の少女と、全く同じ。
あの少女が、ここにもいる。上半身だけの切断された死体の横で、寝ている。面白くて仕方ない。
「あはははは」
笑いながら手を伸ばす。少女の顔に触れる。指で、右目を確認する。
「ひひっ」
予想通り、いや予想以上の光景にひきつった笑い声が出る。少女の眼球。瞳に数字が刻まれている。「2」と。
もう我慢できない。
げらげらと笑いながら私は床に倒れこむ。笑いすぎて呼吸が苦しい。
呆れ果てたルクスの顔を視界の端に、私は笑いながら全身が急激に冷えて意識が遠くなっていくのを感じる。
暗闇。
思い出したことがある。
そう、私たちは、シンカー、テラー、パンナコッタ、スパイスは、全員、疑っていた。
私たちの誰かが、星の守護精霊≪セレスティア≫の正体ではないのかと、互いを疑っていたのだ。
だけど、そもそも、
私は誰なのだろうか?
C ワードサラダ
白光が痛い。廊下は長すぎる。リボンが落ちる。影が伸びる。名前を呼ぶ声がする。誰もいない。笑い声が割れる。机の角が冷たい。上履きのきしみが耳に残る。チョークの粉が舞う。パンのにおいが濃すぎる。パンはダメだ。ババロアはダメだ。朝昼放課後ベルが鳴る。鐘の音が重なる。窓の外は青い。鳥が飛ぶ。羽ばたきが速すぎる。光が裂ける。目が追いつかない。視線がどこにも届かない。ざわざわ、ざわざわ。耳鳴りが増える。笑っているのか、笑っていないのか分からない。顔がない。声が重なる。背伸びして読んでいた夢野久作全集。私は特別な存在。爪先が赤い。血? マニキュア? 滴る。階段が消えた。踊り場が増えた。手すりは冷たい。胸が沈む。沈む、浮く。沈む、浮く。枯葉がざくざく音を立てる。足音が止まらない。誰かが追ってくる。誰もいない。「わがまま言いやがって。好き嫌いするんじゃねえよ」笑い泣きが混ざる。制服の袖が濡れる。母の声、父の声、友達の声、先生の声、知らない声が一斉に叫ぶ。手が空気を掴む。掴めない。押される。押す。落ちる。落ちる。落ちる。ジョン・ル・カレ作品は難しすぎる。白光が押し寄せる。骨が軋む音がする。心臓が止まるようだ。耳が裂ける。闇が裂ける。目が飛び出る。指先が途絶える。壁が揺れる。誰かいる。誰もいない。風が冷たい。母は消え。父は狂う。窓の外が遠すぎる。声が跳ね返る。光が割れる。机の角が痛い。涙が止まらない。息ができない。廊下が長すぎる。言葉遊び。ノート。それが防波堤。階段が消える。階段が増える。手が届かない。足が止まらない。ルミナス・ブレイブ。見えない。誰もいない。リボンが回る。回る。光が押し寄せる。青、赤、黄、紫、影が伸びる。消える。消える。笑い声が裂ける。酒臭い息。母が呼ぶ。名前を呼ぶ。もう母はいない。誰かが泣いている。手が空気を掴む。掴めない。落ちる。落ちる。落ちる。風が裂ける。耳が割れる。心が冷たい。胸が裂ける。空気が固い。固すぎる。影が押す。押される。押す。押す。押す。白光、白光、白光。真っ白。消えない。消えない。消えない。父の血走った目が私の脚を。光が飲み込む。舞うリボン。蕁麻疹。ほどける。吸い込まれる。落ちる。カタカナ英語。落ちる。思いついた。落ちる。カタカナ英語。骨が軋む。カタカナ英語。影が揺れる。誰もいない。誰かいる。誰もいない。誰かいる。声、声、声。沈む。沈む。沈む。浮かぶ。浮かぶ。浮かぶ。沈む。沈む。沈む。手が消える。足が消える。目が消える。口が消える。全てが消える。白光、白光、白光、白光。ジョン・ル・カレ。ジョン・ル・カレ。ジョン・ル・カレ。壁が揺れる。誰かいる。誰もいない。光が裂ける。影が増える。息が詰まる。涙が溢れる。リボンがほどける。設定。設定。設定だけ。飛び散る。回る。目が回る。胸が重い。沈む。浮かぶ。沈む。消える。光が押し寄せる。闇が押し寄せる。誰もいない。誰かいる。名前が消える。声が消える。ドグラ・マグラ。手が消える。足が消える。骨が砕ける音がする。耳が割れる。目が割れる。心が割れる。影が裂ける。風が裂ける。リボンが裂ける。白光、白光、白光、白光、白光。しん。
7 再びの目覚め
…………ブウウ――――――ンンン――――――ンンンン………………。
耳鳴りだ。
頭痛。倦怠感。吐き気。
目覚める。
今度の目覚めは、あの書庫ではなく、ホールだった。ルクスと出会ったホール。どうやら、精神が限界を超えてヒステリックに笑いながら気絶してしまった私を、ルクスがここまで引っ張ってきてくれたらしい。
そのルクスは、少し離れた場所で天窓を見上げている。
私の視線に気づいたのか、ルクスが顔を向けてくる。
「あ、起きたか」
「私、どのくらい……」気を失っていたのか、と訊こうとして体を起こし、また体ががちがちに固まっていることで痛みを覚えて顔をしかめる。
「時計がないから、正確な時間は分からないけど、まあ結構ぐっすりだった。のんきなもんだな」
さっきまでルクスが見ていた天窓を確認する。窓の外は、完全な夜になっている。みぞれ雪が降っていたが、その後は晴れたらしい。満天の星空がある。つくりものじみて美しい、まるでプラネタリウムのように見事な星空だ。星が大きく瞬いていて、じっと見ていると催眠術にかけられているように意識がもっていかれそうになって目を逸らす。
「もう、探索する場所はない。だろ? 情報整理と事件解決の時間だ」
そんなことをルクスが言う。
事件解決? 何が事件なのかすら、分かっていないのに?
だがルクスは、奇妙に落ち着いた様子で、私に向かってノートとペンを差し出してくる。どちらも新品らしい。
「え? これは?」
「あの書庫、もう一度調べてたんだ。そうしたら見つけた」
見れば、ルクスの横には例の辞書がある。どうやら、あの後にそれを取るために書庫に行ったらしい。
「さあ、書くことで頭の中も整理されるだろ? やってみろよ。さっさと、これを終わらせようぜ」
「ルクス、ひょっとして、あなたはもう、何か分かったの?」
これまでとは違う、こちらをを誘導してくるルクスの様子に不気味なものを覚える。
「まあ、お前が寝ている間に、俺の頭は大分すっきりしてきたし、ちょっとずつだが、記憶も戻ってきてな」
「記憶を? それは、どんな?」
事件解決の手がかりになるかもしれない。
「いや、それは置いておこう。多分、俺の記憶は基本的に関係ない」そんなことをルクスが言う。「俺は無関係だと思ってくれ。だから、俺の断片的な記憶は多分、逆に邪魔な情報になる。いいから、さっさとやれよ」
なんだか、ルクスのあたりがきつくなっている気がする。
だが、ともかく、私は座りなおして、ペンを持つ。
「まずは、お前が思い出した情報もしくは設定、それからこの城を探索して分かったこと。大きく分けて二つだな。思いつくままに書いてみるんだ。さあ」
ルクスの声、妙に大きく響く。私の脳内で反響しているようだ。命令に逆らえない、いや逆らう気にならず、私はノートを開いて、ペンをはしらせる。
『情報・設定』
・恒星戦士ルミナス・ブレイブ。
「星の守護精霊≪セレスティア≫」に選ばれし四人の少女。
シンカー。テラー。パンナコッタ。スパイス。
・星の守護精霊≪セレスティア≫。
私たちをルミナス・ブレイブに変え、指示を出す存在。
正体は不明。四人は、自分たちの中にいるのではないかと互いを疑っていた。
永遠城≪エターナルキャッスル≫の城主。この城の中では絶対領域≪クイーン・テリトリー≫によってあらゆるダメージを無効化する。
・ルクス。
星の守護精霊≪セレスティア≫の使いでありマスコットキャラクター。
・永遠城≪エターナルキャッスル≫。
山々より高くに浮く天空城。
出入口がなく、ルミナス・ブレイブは星の守護精霊≪セレスティア≫の力によってこの城に召喚・送還される。
永遠の掟に支配されており、どのような損傷を受けてもすぐに復元する。
『発見』
・目覚めた書庫。英語の原書のみ。のちに英和辞書が発見される。
・ホール。ルクスと出会った。奇妙な詩の刻まれたプレートが床に設置。
・キッチン。食事を提供された覚えがないので、城主用のもの。多種多様な食材や調味料あり。保存が効くものが中心? 高級なオーガニック系。
・血と肉片の部屋。死んでいたのはおそらくシンカー。『城主は仲間外れ』のメモ。シンカーによるもの?
・シャワールーム。クローゼットに、テラーらしき少女。生きているが反応はなし。眼球に「1」の文字。
・ホールの反対側は塔のようになっている。天井付近の壁から床にかけて血痕。上半身だけの、鋭く両断された、おそらくはパンナコッタらしき死体。
・塔の死体の横に、シャワールームで見つけたのと全く同じ少女。反応はなし。眼球に「2」。彼女もテラー? どうして二人いる? ひょっとして、消去法で彼女はスパイス?
・だとしたら、私は誰だ?
「よくまとまってるじゃあないか」ノートを覗き込んでいたルクスが評価する。「永遠の掟とやらで白紙のノートにもどるかと危惧したが、所有権は俺たちに移っているみたいだな」
「でも、書き出したけど、全くわけがわからない」吐露する。「これに、筋の通った説明をつけることなんてできるの?」
私の吐露は、最後は悲鳴にも近くなる。
「あー、そりゃあ無理だ」あっさりと、ルクスが言う。「ちょっと言っただろ、魔法少女うんぬんかんぬんの時点で、まともに考えるのなんて馬鹿らしいって。ほら、特殊設定ミステリって流行ってるけど、あれは現実ベースにルールが一つか二つ、追加される感じだから成立してると思ってるんだよ、俺」
突如としてルクスがわけのわからないことをべらべらと饒舌にしゃべり出し、私は唖然と眺める。
「だけど根本の世界観の時点で違うとさ、ほら、例えば魔法のある世界だとか、そうなるとどうしてもミステリで論理ぎちぎりにするのってどうしてもムズいと思うんだよな。どこまで可能か不可能か分かりにくいし、言及されていない不思議な力でやったって可能性が除去できない
意味は分からないが、私の頭はぐらぐらとしてくる。ずっと続いていた頭痛に加えて、気分が悪い。視界が歪む。間抜けなはずのルクスの姿が、不気味に歪み広がっている。
「じゃあ、どうやって……」
「発想を変えるんだよ。いいか、この謎は、お前に解かれたがっている」
解かれたがっている。その言葉が脳内を反響する。
「不思議なくらいに手がかりがあるだろ。メモや、謎の詩や、あとはお前が目覚めた場所が書庫でそこに謎解き用らしきノートとペンが用意されていたってのもそうだ。この謎はお前に解かれたがっている。だから、ゲームだと思えよ」
「ゲーム?」
「推理ゲームだ。ああいうのって、物語の展開とか手がかりで、プレイヤーをある程度誘導するだろ? 製作者の想定している真相、辿り着いてほしい真相に。これも同じだ。お前が謎を解くように、誘導しているんだ。そう思ったら、どうだ?」
「でも、でも」視界はぐるぐると回る。「謎を解くって、一体、どの謎を? 全部、全部狂っていて謎なのに」
「結局のところは、一つだ」ルクスはいまや視界一杯に広がっている。「すなわち、城主は誰なのか? それから、大ヒントをやろう。ヒントは、カタカナ英語だ」
途端、私の視界は元に戻る。頭痛も、消える。
目の前にいるのは、ただの、薄汚れたモップみたいな犬だ。
ああ、そうか。
立ち上がる。
「お、どうした、分かったのか?」
頷く。
事件の鍵を握るのはあの人物に違いない。
私は、走り出す。
9 私の正体
私が息を切らせて、全力で駆けて辿り着いたのは塔だ。ホールの反対側。
天井からの血の帯。真っ赤だったそれは、黒っぽく変色し、固まりかけている。時間の経過をそんなところにも感じるが、今はそれどころではない。
「はやい、はやいって」
はあはあ言いながら、ルクスが追いついてくる。
「もう、死体の振りなんてしないで」
私は、見下ろす。
上半身で切断されて、転がっているその死体を。
もう、臭いも血も気にならない。解決して、早く解放されたい。それだけが私を突き動かしている。
「あなたが城主なんでしょう、パンナコッタ」
私は言う。
沈黙。
しばらく待つ。
だが、何も起きない。
想像していた、逆再生のように死体が復元してパンナコッタらしき少女が私に向かって一礼をして「よく分かったわね」と微笑むというようなことも起きない。
まさか、違ったのか?
「惜しい」
ルクスの声に振り向く。彼は、首を振って残念そうにしている。
「本当に惜しいな。いいところまでいってるのに」
「違った、の?」
「まあ、ちょっと。ちなみに、どうしてパンナコッタが城主だと思ったんだ?」
気まずさを覚えながら、私は咳払いをして、
「あのメモ、城主は仲間外れってあったでしょ」
「ああ」
「あなたの言うように、あれが偽物や無関係の手がかりなんかじゃあなくて、私に解いてほしい謎の手がかりだとすると、文面をそのまま素直に解釈すればいい」
「いいね」
「仲間外れは誰なのか。それは、名前を見ればいい」
「そうそう。いいぞいいぞ」
「シンカー。テラー。パンナコッタ。スパイス。この中で、パンナコッタだけがイタリア語」
沈黙。
「え、それだけ?」
「ええ。そうだけど?」
そう言われると、確かにあまりにも根拠が薄い気がしてきた。
「ふざけんなよこのガキ。こんなところまで走らせやがって」何故かルクスは激昂している。「あーもう、仕方ないか。お前が自分で辿り着いた方がよさげだから遠慮してたが、こりゃ望み薄だな。俺が啓蒙してやるよ」
ルクスはまだ荒い息を少し整えてから、
「とりあえず、ホールに戻るぞ」
と言う。
ホールに戻るまでに、私の視界は再び歪みはじめ、頭痛も再開する。
あれで終わる。城主がパンナコッタだと指摘すれば終わるだと信じていたからこその回復だったのだろう。ホールに辿り着く頃には、私は猛烈に気分が悪くなり、立っているのもやっとな状態になってくる。
「楽にしろよ」
ルクスにそう言われて、私は床に座る。
「仲間外れを探す。そりゃあ、合ってる。名前が手がかり。それも合ってる。ただ、イタリア語だからパンナコッタが仲間外れっていうのはな、別に実はそこまで的外れってわけじゃあないんだが、それだけだと肝心な話が解決しない」
肝心な話?
歪む視界の中、ぐにゃぐぎゃなルクスが私を指す。
「お前だ。お前が、誰なのかって話だ」
私。私は。
「記憶がない。城の中で、唯一明らかに無事な魔法少女。怪しいだろ。お前が誰かって言う話を抜きにして、城主うんぬんの話はできないはずだ」
「ちょっと待って」何とか反論する。「ルクスだって、そうでしょ。記憶がないし、この城で無事で動き回っている」
言いながら、だんだんと不安になってくる。苦し紛れの反論のつもりだが、そうだ、この薄汚れたモップのような犬が、何よりも怪しいんじゃあないのか? 私の視界いっぱいに歪んだルクスは邪悪に笑っている。
「ああ、だから、言っただろ、俺は関係ないって。俺のことは考えるな。部外者だからな」
「どういう意味? 星の守護精霊≪セレスティア≫の使いのあなたが一番--」
「それは俺じゃない」
頭が、割れるようだ。
「ルクス自体はいる、設定はあるんだろうな。けど、それは俺じゃあないはずだ。そりゃそうだろう。魔法少女シリーズのマスコットキャラクターが、薄汚れたモップみたいな犬だなんてあり得ると思うか? 自分で言うのも悲しいけど」
「けど、じゃあ」
「もっと可愛いキャラクターだろ、多分。ふわふわしてて語尾にも特徴あるタイプの。知らないけどよ。まあ、ともかく、俺がルクスだっていうのはお前の勘違いだ。いや、というよりも無意識に当てはめたのか。俺なんて、この城に存在しないはずのものだからな」
ルクスはそう言い放ち、
「それで、お前の正体だが」
脳が暴れて零れ落ちそうだ。痛み。内側からの痛みが。
「ああ、いや、やっぱりそうか。順を追った方がいいよな」
ずい、と前に差し出してくるのは、辞書だ。あの、英和辞書。
「丁寧に誘導されてる、そう言っただろ。お前が目覚めた部屋で、全部英語で書かれた本。手がかりがないかと本を読もうにも読めない。辞書なしでは。これは、お前がこの辞書を手に取るように誘導されてたんだよ。まあ、俺ってイレギュラーのせいで、辞書取ったのは俺なんだけど」
辞書。熱を出した時のような浮遊感のまま、それを手に取りぱらぱらとめくる。だが、内容は頭に入ってこない。
「まあ、この辞書を適当に見たって答えはでない。というより、これはあくまでヒントだ。つまり、英語がキーポイントだってこと。それを押さえて、自分で考えて、あくまでも辞書はそれを確かめるために使えばいい」
まるで、意味が分からない。言葉も入ってこない。
「ああ、例えばシンカーだよ。最初、お前が陰キャっぽい見た目だからシンカー、思想家じゃないかって話をしたよな?」
言葉に棘がある。嘲るような目つき。文学少女、という表現が陰キャなんて言葉に変わっている。吐き捨てるような口調。
ああ、受け入れるしかない。ルクスは、私に敵意を持っている。どうしてなのかは分からないが。取り戻した記憶とやらに関係があるのだろうか。
「シンカー。英語だとthinkerだ。考える、のthinkにerで考える者。けど、他にシンカーってあるの知ってるか? これは英語詳しくなくても、野球知ってればいける」
「ああ、変化球、シンカーって変化球がありました」
何とか言葉を絞り出す。
「そうだ。sinkが沈む、で、erがついてシンカー。沈むもの、だな」ルクスは肉球のついた手で辞書をめくり、sinkの単語が載っているページを開く。「それで、だ。どうして、こっちじゃあいけない?」
「……え?」
「沈む者。人についている名前だとしたら妙だ。思想家なら意味が通るが、こっちだとよく意味が分からない。だよな。でも、魔法少女なら? 何か、沈むのに関係する魔法が使えたらそれでよくないか?」
にやにやとルクスは笑っている。長い毛で隠れているのに、その笑いはよく分かる。
「テラー。恐怖。魔法少女の名前にしちゃ物騒だ。terror。ところで、中学生英語レベルでも知っている話だが、tellって単語あるよな。話すとかの意味がある。それにerつけてもteller。テラーだ」
話す人。語り手。そういう意味だろうか?
「で、調べてみたらこっちのテラーは銀行の窓口とかの意味があるらしい」今度は辞書のそのページが開かれる。「どうしてなのかというと、tellには数えるって意味があるからだってよ。辞書ってなかなか面白いもんだよな。ああ、つまりテラーには数える人って意味の可能性もあるわけだ。ところで、データキャラだったらこの名前にぴったりだとは思わないか?」
粉々になったガジェットの数々が頭をよぎる。
「スパイス。これはちょっと考えたな。他にスパイスは思いつかなかった。けど、何のことはない。複数形だ。spice、香辛料じゃなくて、spyの複数形、spies。これは正確にはスパイズに近い発音らしいが、まあカタカナ英語だったらギリギリありだろ」
スパイの複数形。真っ黒い、暗殺者のような恰好、または映画に出てくるスパイのような恰好の少女を思い出す。それも、同じ少女が二人。複数形。
「もちろん、意図的に間違えるようにしてるんだと思う。カタカナ英語で、こっちをひっかけてくるわけだ。で、そのひっかけが存在しないのが一人。もちろん、元々英語ですらないパンナコッタだ。だから、パンナコッタが城主。そこは合っていたわけだな」
痛い。痛い痛い。
「さて、じゃあ、お前が誰か、だ。これはもちろん、多分に推測を入れていく。ガジェットからしてテラーはあの粉々の死体でいいだろ。で、もちろん、コスチュームといい二体いた件といい、塔とクローゼットのあいつらがスパイスだ。そうなると問題は、塔のあの死体だが……あれって、結構妙な死体だよなあ。上半身ですっぱりと切断されている。一体何がどうなってあんな風に切断されたのか、不思議だよなあ。下半身がどこにいったのかも」
「考えたって仕方がないって、そう言ってたじゃない。こんな、狂った世界観でそんなことを考えるなんて、無駄だって」
「確かに、ゼロから考えるのはな。けど、さっき言ったように、手元にある手がかりから誘導される答えだと限ったら、そう無謀でもない。ほら、さっきまで分かったこと、カタカナ英語トリックから、何か思いつかないか?」
私が黙っていると、歪んだ視界の中でもはっきりと分かる舌打ちをしてルクスは続ける。
「何だよ張り合いがないな。なあ、シンカーって魔法少女、どう沈むんだと思う? まさか、本当に水に沈むだけのわけないよな。魔法なんだから、あー、たとえば、どうだ、地面や壁とか、液体じゃなくて固体に沈む力を持っているっていうのは」
固体に沈む。地面や、壁に沈み込む。イメージが浮かぶ。少女が、硬い床に下半身まで沈んだ状態で、突如として絶命する。それまで少女を床に沈ませていた不可思議な力が消えて、体はそこで切断されてしまう。
「まあ、そういうわけであの上半身がシンカーだとすると、残るは一人だ」
忌まわしく笑うルクスが私を指さす。幻覚か、その指は人間のようにも見える。いや、歪み切った視界はもう信用できないか。
「お前がパンナコッタで、城主だ」
「違う。そんなわけがない」
私は反射的に言い返す、が。
「記憶がないお前にそんなことを言えるはずがないだろう」
斬って返される。
「ちなみにパンナコッタ=城主の説の補強としては、そもそもどうしてパンナコッタなんて名前がつけられたのかってのもそうだ。なあ、ババロアでよさそうじゃないか。どうしてパンナコッタなんだ。一つだけイタリア語だし。まあ、ババロアだってフランス語だったと思うけど」
ああ、思い出す。何度か頭の中に浮かんだ文字列。「ババロアではダメ。パンナコッタでないと」あの言葉。どうして、ババロアではダメなのか。パンナコッタでないと。
「パンナコッタとババロア。似た洋菓子だが、何が違うか知っているか? いや、まあ、色々違うんだけど。パンナコッタには、洋菓子には珍しく卵が使われていない」
卵。呼吸が苦しくなる。全身がかゆい。
「でだ、この城のキッチン、城主用のキッチンを見ただろ。不思議に思わなかったか? あって当然のものがなかった。妙なクッキーはあるのにパンがない。多種多様な調味料はあってもマヨネーズがない。和菓子があっても洋菓子の類がない。もう分かるだろ? 卵と、卵を使ったものが存在していない。おそらく城主は卵が食べられない、アレルギーの可能性もあるな。ともかく、そういう理由で城主は名前をパンナコッタにしたんだよ。卵を使っていない洋菓子の名前に」
こじつけだ。ただの、こじつけ。私は言い返そうとするが、息ができず声が出ない。
「そうそう。もう一つあった。お前が城主だって根拠」ルクスは少し動いて、床にあるプレートの前に座りなおす。あの、奇妙な詩が刻まれたプレート。
「お前、言ったよな。覚えているか? 『そんなのパンナコッタだって迷惑こうむる』ってフレーズ」
それが、どうかしたのか。
「話の流れからして、『迷惑こうむる』って妙なんだよ。迷惑を受けるって意味だからな。明確に間違っているわけではないけど、どうにも気持ち悪い。少し時間をかけて考えて、分かったんだ。お前は、言葉を間違えて使っている。背伸びして難しい本を読んでいようが所詮はガキだな。まあ、大人でも言葉間違えて使ってるやつはいるけど」
言葉の誤用。私が? 誰よりも言葉に気を付けていたはずなのに。言葉に拘って、言葉遊びを多様して設定をノートに書き綴ったのに。
「多分、お前が使いたかったのは、『迷惑こうむる』じゃあなくて『御免こうむる』じゃあないか? そっちならしっくりくる。お前は、『迷惑』と『御免』を混同しているんだよ」
そして、ルクスはプレートを指でなぞる。
「この詩。詩というか、ドグラ・マグラをパクったというかオマージュなのか知らないが、これ自体はクソだけど、それはいい。ここの部分だ」
指が、『これ以上生きるのなんて迷惑だと』の部分を何度も往復する。
「まさに、さっきのフレーズと同じだ。意味が通じないわけじゃあないが、絶妙に気持ちが悪い。けど、こうしたら気持ち悪さも消える。『これ以上生きるのなんて御免だと』ほら、な。言いたいこと、分かるか? この城にあるプレートに刻まれている詩、それとお前が同じ言葉の間違い方をしているんだ。なあ、もういいだろ、認めてくれよ」
頭が内側から破裂しそうだ。痛みと一緒に記憶が溢れ出てくる。ノートにペンで刻み込んだ。ドグラ・マグラの冒頭をそのまま書き写した。辞書で調べた使えそうな英単語をひたすら書き込んだ。パンナコッタが大好きだった。卵が食べられない私でも食べることのできる洋菓子。何よりも好きで、好きで、だから私の本当の名前がパンナコッタだったらと。
爆発。強烈な頭痛。そうして、全てが消える。頭痛も、倦怠感も、視界の歪みも。
私はパンナコッタだった。そして、城主だった。星の守護精霊≪セレスティア≫でもある。記憶は完全には戻っていないが、そう認めただけで、私は解放された。清々しい、気分だ。
「そっか、そうだったんだ」
私は立ち上がる。
いまや、私は、更にその先が。この世界の真実が見えている。
「ここは、私がつくりあげた想像の世界。ノートに設定だけを書きなぐっていた、ルミナス・ブレイブの世界ってことね」
そう、ルミナス・ブレイブは私がつくりあげた架空の存在。ノートに設定だけを羅列した創作。だから、私が創造主であり、この城の城主だった。
「そして、ルクス、あなたは、私の理性。謎をとかせようとした手がかりと同じく、私をこの想像の世界から目覚めさせようとしていた、もう一人の私。そういうことでしょう?」
「全然違う」
ルクスは完全に否定する。
10 何があったのか?
じゃあ、ルクスは一体何者なのだろうか?
混乱する私に、ルクスは舌打ちをしてから、
「だから、俺は部外者だって言ってるだろうが。俺のことは気にするな。混乱するだけだ。この世界がお前の脳内世界っていうのは、多分あってるんじゃないか? それだけでいいだろ」
部外者? 部外者が、どうしてこの私の想像の世界に、ルミナス・ブレイブの世界にいる?
「そんなことより、ほら、城主なんだから、お前の力でこの城から出してくれよ」
ルクスが言う。
確かに、そうだ。そして、私自身も出ていかないと。
だが。
「……どうやればいいの?」
「知るかよ。おい、できないのか?」
苛立たし気に右耳の後ろをかきむしると、ルクスは盛大にため息をつく。
「仕方ねえなあー、じゃあ、最後までやるか」
「最後?」
何が残っているのだろうか?
「あのな、この城がお前のつくった設定だけの世界だろうが、何だろうが、解かなきゃいけない謎は残ってる。要するに、何があったのか、だ」
「何が……あったのか」
「そうだ。お前の設定を再現しただけなら、お前の記憶はなくならないだろうし、他の奴ら、シンカーもテラーもスパイスも、無事なはずだろ。それが、どうして全員死んでいる? 設定だけの存在だからって、粉々になったり真っ二つになる必要はないはずだ。何かがあったんだよ、この城で」
じゃあ、何があったのか?
「私が、城主。私が、この城の中では絶対者。じゃあ、記憶を失う前の私が、皆を殺した?」
言って、その忌まわしさに身震いする。
「動機がないだろ。あー、そもそもだ、いいか、俺の体は真っ赤な血まみれになった」
突然、そんなことをルクスが言う。
「え?」
確かに、あの粉々の死体の部屋に入ったルクスは真っ赤になっていた。だが、それが?
「血は乾いていないし変色もしていなかった。そうだろ? シンカーの血の帯なんて、今では黒っぽく乾燥している。つまり、俺たちが目覚める直前にテラーもシンカーも死んだことになる。どのくらい直前なのかは別として、だ。そうなると、あいつらが死んだ理由と、俺たち、というよりお前が記憶を失うほどの衝撃を受けた理由は、同じ可能性が高い。何かが起きて、魔法少女たちは死に、お前だけは生き延びたが記憶を失った」
「どうして私だけ生き延びて、いや」
思い出す。設定だ。城主である星の守護精霊≪セレスティア≫は、この永遠城≪エターナルキャッスル≫にいる限り絶対領域≪クイーン・テリトリー≫であらゆるダメージを無効化する。だからか。
「いや、でもやっぱりおかしい。ほら、あの二人、スパイス。あの娘たちは、意識はないけど生きてる」
「いや、多分死んでるんじゃあないか? 予想だけど。だって、あんな反応ないのおかしいだろ」
「でも……」
「あれは多分、子機だ」
「子機?」
「人形とかロボットみたいなもんじゃあないか? いわば子機。親機、本体は多分死んでいる。もしかしたら遠く離れて範囲外の可能性もあるけど。どちらにしろ、そういう理由で、子機は無反応なわけだ。そして、所有権者のいないモノだから、城の所有になった」
永遠の掟。それで噛み痕が回復した光景を思い出す。
スパイス。スパイの複数形。分身できるから複数形だったとしたら。コスチュームからして、コンセプトは忍者だったのかもしれない。いや、そんな設定を私がした気がする。だから、分身の術か。それに、確かに人間じゃあないと考えた方が納得できる。目に数字が刻まれているのだから。
「」
「じゃあ、結局、一体、何があったっていうの? この城で、何が」
「あー見ろよ」
ルクスは、また空を見上げている。天窓を。天窓の向こうの星々を。
「この城はお前の妄想の世界だ。でも、あの天窓の向こう。一歩外に出れば、冷たくて厳密な現実の世界が存在している。星が、瞬いているだろ?」
「そうね、前も思ったけど、不気味なくらいに美しくて、怪しいくらいに瞬いてる」
「いいよ、そういう詩的な表現は。それより、お前、星ってどうして瞬いてるか知ってるか?」
「え? 星が、燃えているからですか?」
適当に答える。
「違うよ。宇宙空間だったら星は瞬かない。大気を通して星を見ているからだ。大気の揺らぎが、星の瞬きの理由だ」
「はあ」
だから、何だ?
「お前の言うように、やたら瞬いているよな、星が。あれだけ瞬くってことは、余程大気が揺らいでいるか、大気の層がそれほど厚いかどちらかってことだ」
「……え?」
何か、ひっかかる。大気の層が、厚い?
「それから、昼には雪が降っていたよな。ただの雪じゃあない。みぞれっぽいのが、天窓にぶつかっていた。だろ?」
ルクスの言いたいことが、何となく分かる。だが、それが一体何を意味しているのか。
「ここが本当に山よりも遥かに高い上空に浮いている城なら、みぞれなんて降ってくるわけがない。みぞれってのは、気温の低い上空から降ってきた雪が、気温の高い地表付近で溶けかけてできるもんだからな」
さっきの大気の層が厚い、ということと併せて考えると、結論は一つだ。
「ここは……地上ですか?」
この城は、空に浮いていない。
「ああ、そうだろうと思う。で、だ。設定だと、この城は天空城なんだろ? 元々は浮いていたはずだ。それが、今は地上にある。なあ、これはゆっくりゆっくり下降したんだと思うか?」
ああ、イメージが溢れてくる。あるいは、これは記憶だろうか。それとも私の妄想なのだろうか。
天空の城が、真っすぐ落下していく。落下していく城の中で、少女たちが動く。
テラーは、最後の瞬間まで城主の正体を探り、メモに手がかりを記す。
シンカーは生き延びる可能性を少しでも高くしようと、塔に向かい下半身を壁に沈ませて高く昇り、激突の瞬間の衝撃を殺そうと画策する。
スパイスはホールの天窓を割って、復元する前にその天窓から外に飛び出す。分身を残して。だが、外に飛び出したところで生き延びることはできない。凄まじい風に、彼女の姿は消し飛んでいく。
そして、地面に激突する。城は砕ける。テラーは城と共に砕ける。シンカーは衝撃を殺しきることはできずに、そのまま壁から出ている上半身がそのまま下にずれるようにして切断される。私は凄まじい衝撃の中でも、絶対領域≪クイーン・テリトリー≫によって無傷だ。しかし気を失い、そして記憶も失う。
そうして、粉々になった城が、復元していく。
「さあ、それじゃあ、最後の謎だ」
頭に溢れるイメージに呆然とする私に、ルクスが冷めた目をして問いかける。
「一体、どうして城は落下したんだ?」
その理由は。
今度こそ、私は全てを思い出し、そして、私とルクスは永遠城≪エターナルキャッスル≫から送還される。
D エピローグ
受付にて名前を呼ばれる。
ようやくだ。病院の受付はどうしてこうも待たされるのか、不思議だ。
ともかく、これで面会できる。
消毒液の臭いのする廊下を歩き、目当ての病室を見つける。生意気に個室だ。
ドアを開けると、退屈そうに薄型テレビに映るニュースを見ていた男が、僕に気づいて笑みを浮かべる。
「おお、きたきた、何だよ薄情だな、もっと早くに来いよ」
「ちょっと前まで面会謝絶だったでしょうが」
ともかく、僕は病室に入り、見舞い客用のパイプ椅子に腰を下ろす。
男、いや名探偵のNは、テレビを消すと、多少痛そうに顔をしかめながらも包帯の巻かれた顔をこちらに向ける。
「いやー、とにかく暇でよ」
「でしょうね」
見舞いの品、最近評判のよかったミステリ小説の詰め合わせをどん、と傍に置いてやる。
「いやあ、助かるわ。暇すぎて死にそうだったんだ」
「洒落にならないですよ。本当に死ぬところだったんですから。喩えでしょうけど、医者いわく、あんたと向こうの脳が一つになるぐらいの衝突だったらしいですよ」
「実際、一つになってたよ。脳味噌混ざってたわ」
「え?」
「いや、何でもない」
Nは首を振ると、
「それで? 悪かったな、代理で同窓会行ってもらったんだろ?」
「まあ、あんたがあんな状態でしたからね。同業のよしみですよ。ただでさえ、探偵なんてお互い肩身が狭いんだから。同窓会とやらに行ってきましたよ」
「で?」へらへらとしていたNの目が、名探偵らしき鋭さをたたえる。「俺に招待状を送ってきた『クラスメイト』とやらの手がかりは分かったか? 殺人鬼『デッドエンド』との関係は? 少しでもいい、情報は入ったか?」
「ああ、『デッドエンド』事件ね」僕は他の見舞客が持ってきたであろうゼリーを見つけて、さっそくそれを食べ始める。「解決しましたよ」
「……は?」
「解決しました。まだ、ニュースにはなってないですけど」
「解決って、どうして?」
「どうしてって、普通に、僕が」
沈黙ののち、Nはがっくりと首を落とす。
「お前、やりすぎだろ。普通、名探偵の代行で事件解決までやるか?」
「いけそうだったからやったんですよ。別にいいでしょ」
「いや、俺の小学校時代関係ある事件だぞ。他人が解決していいわけないだろ」
「知らないですよ、そんなの」
それなりに高級品らしく、ゼリーはなかなかうまい。あっという間に食べきる。
「あー、本当についてない」
Nが愚痴るが、それについては疑問の余地はない。
「確かにね。調査中に飛び降り自殺に巻き込まれるなんて、探偵初じゃないですか? それも、ちょうど頭と頭が衝突するなんて」
「俺の頭蓋骨が頑丈でよかったよ」
Nは顔をしかめる。
「悪運はいいですよね、あんた。そんなことがあったのにあんたも向こうも一命をとりとめたし」
「向こうはいいんだよ、別にどうでも」
「ちょっとちょっと、死を選んだほど追い詰められたいたいけな少女を捕まえて……」
「女だろうがガキだろうが自殺するほど追い詰められていようが、あいつは俺を殺しかけたんだ。無関係な俺を。無差別殺人犯の通り魔と一緒だろ。あのパンナコッタクソガキが」
「パンナコッタ?」
「ともかく、同情するつもりは全くない。あいつに同情するなら、通行人刺した挙句自殺するような馬鹿にも同情しなきゃいけなくなるからな。まあ、生き延びたなら、生き地獄を味わわせてやる。とりあえず、ありとあらゆる伝手を使って俺の慰謝料を増し増しして金を請求してやらないとな」
「ちょっとちょっと」どうみてもNが本気なので、いたたまれず宥める。「あんな女の子に、そんなお金払えるわけないでしょ。失礼だけど、家もそんなに裕福でもないみたいだし」
「『あんな』女の子? それに、どうして家庭環境まで知ってる?」
じろ、とNに睨まれて僕は内心舌打ちする。藪蛇だ。
「いや、ちょっと気になったからお見舞いに」
「俺より先に?」信じられない、とばかりにNの目が見開かれる。「被害者の俺より、仲間の俺より、加害者のパンナコッタ女の方に先に見舞いにいっただと?」
「いやいや、単純に面会できるようになったのがあっちの方が先だったからさ。ほら、あんた面会謝絶だったから」言い訳してから「とにかく、父子家庭で大変らしいよ? お父さんの方も、仕事が大変で面会にもこれないみたいだし」
「だったらその父親から搾り取ってやる。蟹工船にでも乗せてやるよ」Nは邪悪に笑う。「どうせ、ロクな父親じゃねえだろうし」
「なんでそんなこと分かるんです?」
「分かるんだよ、俺には」
Nはそこで、ふと言葉を区切りじっとこちらを見てくる。
「な、何ですか?」
「いや、ちょっと訊きたいんだけど」
やけに真剣な顔で、
「俺って、どんな風に見える?」
「冷血強欲おじさん」
「そういうことじゃねえよ。俺、しばらく髭も剃ってないし髪も切ってないし風呂も入っていない。どんな見た目かな、と思って」
「ああ、そういう意味ですか」
僕は改めてNを観察する。
伸びきった髭と髪はぼさぼさ。風呂に入っていないということだからやはり薄汚れている感はある。面会できるようになったのがつい最近なんだから仕方ないことではある、が。
「えーとですね」正直に答える。「汚れたモップそっくり」
僕がそう言うと、Nは苛立たし気に自分の左耳のうしろををがりがりとかきむしる。
了
MysteryExhibition1_指定文使用部門:読者投票
以下のフォームから読者投票ができます。
MysteryExhibition1指定文使用部門について、こちらの条件で結果を算出します
・投票の対象期間 :2025年9月1日~2025年11月30日
・作品の選択のみ :1point
・作品の選択&感想:3point
・悪意があると認められる行為や内容は除外
感想は、作者へ共有したり選考会で用いたりさせていただくことがあります。
(選考会で用いられたくない場合、フォームのチェックボックスを未選択にしてください)