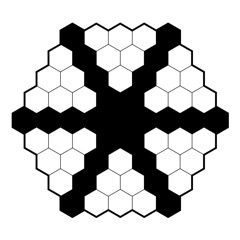01
白河由弦は困惑した。年齢の半分以上はスイス暮らしとはいえ、幼い頃から母親の使う日本語によく親しんでおり移住してからは専ら日本語とともに生活してきた。その甲斐あって電話の内容は問題なく日本語として一言一句すべて聞き取れていた。
相手の声が小さく早口だったわけでもない。むしろ気遣うような慰労と申し訳なさが込められていた。ゆっくり、はっきりとした女の声に聞き覚えは皆無だった。しかし間違い電話として切れなかったのは最初に「白河六花さんの御親族ですか?」と尋ねられたためだ。
それは、満月が役割を終えて太陽に空から追い出されたころの非常識な電話だった。妹からの電話でなければ舌打ちでもしていたが、ため息に留める。着信を承諾する黄緑色の受話器アイコンをタップかスライドかよくわからない触れかたをしてスマートフォンを耳に押し当てた。「なんだ、どうした?」だったか「もう寝ろよ、何時だと思ってんの?」だったか、あくび交じりに何かを言った。
直後、右耳の鼓膜を振動させている声が自分よりも数回りほど年齢を重ねた女性のものだと認識して、ようやく相手が妹では無いのだと把握する。
途端に、頭上から冷水を浴びせられたごとく目が覚めた。しかし回りかけの思考では、最後の「――と申します」だけまともに聞き取るのが精一杯だった。相手はただ名乗っただけだろうか、意味もわからず「はい」と答えてしまう。
何拍か間をおいてから聞き逃したものを聞き返せばよかったと思い至り、口を開こうとした。すると、相手は「シラカワリッカサンノゴシンゾクデスカ?」そう続けた……シラカワリッカ、サン、ノゴシンゾク、デスカ……白河六花、さん、の御親族、ですか……ゴシンゾクが御親族であると理解する。
同時に、なぜ尋ねられたのか考える。兄だから御親族に含まれるとはいえ、なぜ知り合いや友人ではいけないのだろうか。理由がわからなかった。
今すぐにでも通話を切ってしまいたかった。
切ってはならない理由もわからなかった。
しかしながら由弦の声帯は震えて「はい」と返事をしてしまった。唇を引き結ぶ代わりにただ相手の言葉を待つ――続けられたその言葉が何を意味しているのかよくわからなかったが、再び「はい」と返してしまった。数秒後、我に返り、改めてもう一度繰り返してもらわねばならない気がした。
「……みません、もう一度……あの……すみません」
どうにか言葉にできる単語の羅列を試みる。
何を伝えたいのか、何を知りたいのかすらわからない。
さりとて、もう一度同じ文言を聞かせてほしかった。無意識下の働きだろうか、聞き間違いではないことだけでも確かめずにはいられなかった。それ以上に、聞き間違いであってほしかった。
電話先の女性は再び似たような口調で同じ内容を由弦に突きつける。
「白河六花さんの御親族ですよね?」
「はい、六花は妹です」
「本日未明、白河六花さんと思われるご遺体が発見されました。御親族にご確認いただきたく思うのですが――」
その先は意識に引っかからなかった。
わからない。
最初に自覚したのは、わからないという事実だけだった。あくまでも可能性の提示をされているのか、確率を確定させるための確認なのか……否。前提として六花からの電話だ。内容以前に六花のスマホが用いられて連絡が寄越されているのだ。すでに限りなく信じたくない可能性を突きつけられている。
しかしながら奇妙なほど感情は鎮まっている。
何も感じていないと錯覚するほど、由弦は自らに困惑していた。取り乱せていない心配すら抱いている反面、電話先に何度か肯定を返しながら、かろうじて困惑しているなら心が壊れたわけではないのだろうと推察して安堵している奇妙さには気づいていた。
不意に妹とのやり取りを思いだす――
つい先日だ。ノックに気がついて視線を向けると、小さく開けられた扉の影から顔だけ見せる六花の姿があった。
「兄上ぇ、リュックサック貸してくださいませぬか?」
普段は「兄上」などと呼ぶことはない。古文のような奇妙な語尾も使わない。あくまでも彼女なりのおねだり作法である。
「なんで? 持ってるだろ?」
わざと冷たくあしらう。すると、扉が緩やかに開け放たれる。
その奥にある廊下の薄暗がりにて。六花はスポットライトをひとり占めにする舞台俳優ごとく気障に壁に寄りかかっていた。
「ああ、兄は利口だ。うぬぼれているが良い。私はちゃんと借りる覚悟でいるのに。自分のリュックは決して壊していない。ただ……ただ、私に情を掛けたいつもりなら…………何だっけ?」
愛想笑いでは誤魔化しきれないトチリだが、畑違いの由弦からすると指摘する優先度は低い。構わず「いつ、誰と、どこへ?」と、端的に知りたい情報を求める。
「終業式の後、我は友とともに新幹線へ参るのでございます。二泊三日ゆえに大きめのリュックサックが求められるのです」
「それで?」
「返却までに三日間の日限を与えてください。たったひとりの妹は、友とともに二泊三日旅行へ参りたいのです。三日のうちに、私は旅行を全力で楽しみ、必ず、ここへ帰ってきます」
調子を取り戻しつつある六花の口上を聞き流しながら、彼女が愛用するリュックサックの大きさや意匠を思い出す。
なるほど、彼女が中学生のころから外出時よく背負っている桃色のリュックサックには、一泊ですら入りきらないだろう。一方、由弦のリュックサックは大学進学を期に買い替えて数か月ほど。ほぼ新品同様であり容量は相応だ。唯一、懸念としては、十六歳の女の子が持つには少々無骨なことくらいだ。それでも、見たことがあったうえで頼んでいるのだから気にしないことにした。
演劇部でもないくせにそれらしい所作を見せる妹の、次のセリフを待つ。
「私は約束を守ります。私を三日間だけ外出させてください。友が、旅行に誘っているのだ。そんなに私を信じられないならば、よろしい、私の部屋のベッドの上にテディベアのシオンがいます。私の無二の友人だ。あれを、人質としてここに置いていこう――ちょっと取ってくるね、待ってて」
すべての仕込みを済ませたから件の作品になぞらえた演技を交えて要求を提示しているのだろうと思っていたが、どうやら違ったらしい。急展開についていけず、廊下に響く軽快な足音を効果音にしてぽっかりと開いたステージを呆然と眺めた。
曖昧な笑みが零れて、机に向きなおり、ノートパソコンを開いて起動させておく。案の定、妹は白いテディベアを抱えてすぐ戻ってきた。
「アドリブだったの?」
「瞬発力で生きてるから!」
「はいはい……いつ帰ってくるんだっけ?」
「三日目の日暮までに」
「だとさ、セリヌンティウス」
「変な名前つけないでよ」
引き渡された人質を机に乗せ、六花にパソコンのスクリーンを向けた。リュックサック、レディース、使いやすい――それらしい言葉を検索欄に並べた通販サイトの結果を見せながら由弦は言葉を続ける。
「好きなデザイン、あるよね? 終業式前には余裕で届くよ」
「それは、そのー……お小遣い、足りなくて、えへへ」
「いらないの?」
「今回はいいや」
「誕プレでもいいのに」
「だったらコスメ欲しいな。あのね、今欲しいのが」
「はーい、じゃあまた今度」
スマホをいじりだした妹をあからさまに遮ると不満が込められた声で抗議される。構わず進行方向にいる彼女を数歩ほど右に動かした。由弦は、クローゼットからリュックサックを取りだす。念のため、すべてのポケットが空であることを確かめて、
「楽しんでこいよ」差しだしながら告げた。
「うん、ありがとう!」
受けとるとともに六花はとびきりの笑顔を残して退室した。
が、直後、再び顔を見せた。
「ねえ、お土産どうする?」
「思い出話」
「了解、ディオニス!」
片手を頭の高さに掲げて了承を示すと、今度こそ足音は廊下に溶けていった。
由弦は、眼鏡のアーチを親指で押し上げる。首を傾げるまではしないものの、何が引っかかったのか思考を精査しながら、ぼんやりとした足取りで机まで戻った。開いたままのパソコンのスリープを解除すると、なり青空文庫で『走れメロス』を確認した。本文を画面いっぱいに表示させるとスクロールするまでもなく目に入ったその名前を認識した途端、頬が緩んでしまう。が、すぐに誤魔化すように舌打ちした。
せっかく要求を飲んでやったのにその名で呼ぶなら暴君のように行くなと手のひらを返してやろうかと思い浮かんだが――やめた。早生まれの十六歳だったら宿題や勉強を優先するよう言い含めてでも止める必要性が生じていたかもしれないが、まだ高校一年生の夏だ。幸い心配にかられるほどの成績を取っているわけでは無く、何より由弦は六花が自分から友人と旅行へ行きたいのだと言ってくれたことに安堵していた。
我慢を避けられない環境もそれを変えられない事情も、きっと理解している。理解した上で、お互い半年前とは比べ物にならないほど晴れやかな余裕がある今、このタイミングを狙ったのだろう。
無邪気さに欠ける配慮は気に入らないが、何もかも内に蓄積させて元気にふるまわれるよりはよほど健全だ。
由弦は机に落書きされた黒鉛のうさぎに目を細めた。助けを求めて兄の部屋を訪れたくせに持参した冊子を開くなり勝手に自己解決して、お礼にと残して去ったのが数か月前のこと。摩擦で容易に跡形もなくなるだろうが、邪魔になるわけでは無いから積極的に消すつもりは無かった。
六花が絵を描くのが好きであると知っている。それこそ幼いころは色鉛筆やクレパスなど筆記用具に強くこだわっていたが、いつの間にか紙とペンさえあれば絵を描くようになっていた。趣味と呼ぶにはどこか描くことに固執しているようにも見えたが、ゲンにとっての読書と同じだよ、と指摘されて納得した。だから高校進学のお祝いには、ボールペンとトラベラーズノートと画用紙のリフィルを贈った。
以来、絵を見せながらその日あったことを教えてくれるようになった。口先では軽くあしらう由弦だが、妹の報告を心待ちにしていた。内容もさることながら少しずつ上達していくイラストを見るのが楽しみだった。道端のタンポポも放課後の教室もインク一色で描かれた。旅行のお土産話を求めれば二泊三日分のイラストはどれほどの数に上るのか……想像するだけで待ち遠しかった。三日目の日暮れを心待ちにしていた。
――由弦は壁に背を預けると、滑らせてしゃがみこむ。
その拍子に手の甲をフローリングに打ちつけたらしく、じんわりと熱が集まっていくのを自覚する。昨夜から開けたままだったカーテンが柔らかく風に揺れる。
遠慮なく入ってくる陽光は視界を白くするほど眩しかった。
02
未明、若い女性の遺体が発見された。熱海の美しい浜辺へと続く何の変哲もない歩道の外れ。そこに横たわっていた。鑑識が臨場したときには、彼女が生きていた証拠は頭部付近から零れると降水に薄められながらアスファルトに広がっていた。
小雨に降られて湿った衣類が華奢な身体に張りつき、生気に欠けた滑らかな白い肌に水滴がすべる。端正な顔立ちと相俟って彫刻か絵画を前にしている心地に陥った――静岡県警捜査第一課強行犯捜査二係班長を務める鷲見は臨場するなり被害者に黙とうを捧げた。生憎、芸術方面には昏いと自覚している。いつかの何かで偶然どこかの類似する彫刻か絵画でも見たのかもしれないと終止符を打ち、事件解明へ向けた思考に切り替えた。
腕時計の針は諸手を上げている。仕事中毒上等だ。鷲見はひとまず、馴染みの検視官から死後硬直や遺体の様子をあるていど確認した。頭を打ったことによる出血のほか、首筋にはアイスピックのような細く鋭利な道具による外的受傷が見られたという。ふたりは無言で視線を交わらせる。
被害者の両手には何も無く、海は近いが日没後の断続的な雨により陸風の影響が限りなく抑えられて何らかの物品を遠くへ運んでしまうような気象条件ではない。頭部の出血はさておき、頸部の出血は、被害者自らの意思に基づくとは考えにくい。何者かによる受傷だと考えるのが自然だ。要するに、他殺である可能性が高い。
鷲見はあらためて被害者を見遣る。
最近の少年少女は大人びているとよく耳にする。少年課に配属されている同期と宅飲みした際には、終わらない愚痴を聞かされ続けて雑に相槌を打って構わず酒を流しこんでいたが……成人か、直前か、あるいは中学生か……鷲見はさらに眉根を顰めた。
ふと付近の柵に視線が留まる。錆とは異なる異質の赤黒い物体だ。すると目敏い検視官は鑑識が既に確認して採取も撮影も済ませたと告げる。採取された試料が被害者のものと一致すれば、被害者が当該箇所に頭を打ちつけた証左のひとつになるだろう。
鷲見は立ち上がり、深く息を吸う。頭を打った後に首を刺されたのか、刺されたことに驚いて体勢を崩して頭を打ったのか、あるいは他の状況下にあったのか……いずれにしろ単なる事故死ではない。
死因となり得る損傷を正確に判定するには、検視だけでは不十分だろう。
鷲見は、検視官に軽く礼を告げてブルーシートから出た。
現場に持ちこまれた白昼の太陽代理に目が眩む。腕で目元を庇う一方、鑑識課員たちが熱心に仕事を進めている様子を確認する。降水に焦らされているのか真摯なのか、それぞれ無言だった。彼らから視線を外して、規制線の向こう側を眺める。わずかながら人が集まっていた。何がおもしくて集うのか、甚だ疑問を抱く。同時に、見渡したかぎり姿がない部下にも疑問を抱く。ため息をつく価値すら無い。険しい表情とともに現場に未到着らしい髙橋に電話を掛けた。
数コールで応答した髙橋いわく、車で移動中らしい。現場を通り過ぎて司法解剖要請を準備するよう端的に言いつけると鷲見は一方的に通話を切りあげた。
少し離れたところでは鷲見よりわずかに早く臨場していた望月と大城が第一発見者の少年を聴取している。人間か自信が無くて遺体に触れてしまったという彼は、恐縮を通り越して怯えていた。
鑑識作業のため照明が周囲を昼間のように照らしているが普段の照明といえば街灯のみ。遺体が発見された場所から最も近い街灯ですら五メートルは離れている。人の形をしていると認識できてもそれがマネキンなどの人工物ではないと判断する根拠には欠けていただろう。行動に悪意は見えず、ましてや撮影した映像を拡散するような娯楽の錯誤をやらかしていない。メンタルケアは手配するものの、注意内容は夜間にひとりで外出した事実に対してのみに留めるのが筋だろう……思考をまとめたが、鷲見から指示するつもりは無かった。それがわからない部下たちではないと認識している。
望月はまだ捜査一課に配属されて二年目である一方、大城は現場一筋の叩き上げだ。聴取の技術は圧倒的に大城へ軍配が上がるものの、大切な試合が近いから雨が上がったのを知って軽く走りたかったという野球少年に手早く親へ連絡させるような気配りは望月のほうが上手である。再び降りだした雨から車内へ避難させたのは大城だが、水気を拭くようハンカチを少年へ渡して促したのは望月だった。
降水のおかげで規制線付近から野次馬が散った直後、五人ほどの人影が戻って来た――否、さきほどまで陣取っていた野次馬よりも若い男女だ。傘もささずに駆けてきた彼らのひとりが規制任務にあたる制服警官に話しかけている。
鷲見はその集団に歩み寄ると「何があった?」端的に尋ねた。顔がよく見える距離に立つと、彼らのあどけない顔立ちが哀れなほど不安に染まっていると認識させられた。
「あのっ、け、警察の、方、ですよね……?」
三人いる男子のうちひとりが、制服警官から鷲見へと質問相手を変えた。硬質らしい頭髪から水滴がぽろぽろ肩へ落ちた。彼は答えを待たずに言葉を続ける。
「六人で旅行してて、でも、友達がひとりいなくなってしまったので探してるんですけど」
「話は聞く。ただ、雨も降っているし時間が遅い。君ら、高校生くらいだろう? 親御さんは」
そのとき。
遺体がブルーシート外へ運び出された。遠目からは担架に乗せられた遺体は非透過性納体袋越しでは曖昧な形に見えるはずだった。
「女の子ですか、黒髪の」
つぶやかれた言葉に誘われ、女子のひとりへ視線が集まった。額に張りついた前髪から垣間見える、との茶ごとく瞳。その双眸はまっすぐ遺体を見据えていた。曖昧なふくらみが網膜に確かな像を結んだ瞬間、両手で頭を庇うようにひとつにまとめた髪を乱して悲鳴を上げた。その場に崩れるように膝を曲げた彼女を、背後の男子が咄嗟に抱きとめた。
鷲見は答えず、努めて無表情を通した。確かに遺体は黒髪の若い女性だった。しかし警察官の矜持としてむやみに動揺を見せるわけにはいかない。
鉄面皮から何かを読み取ろうとしているのか見上げてくる少年少女たちの双眸を、ただ受け止めた。
幸い、異変を感じ取った現場の班員が応援に来た。宿泊先に協力要請して話を聞くよう指示を出す。少なくとも聴取は保護者が到着してからだと伝えるのも忘れなかった。
第一発見者とは事情が異なるものの、依然として未成年への対応にはひどく気を使わねばならない。二十三時を過ぎているため補導の建前で最寄りの警察施設へ連れていき話を聞く方法も可能だが、遺体と面識があるなら後日にでも任意聴取を要請することになる。ならば、なるべく心労を軽くする努力を優先すべきだ。それが後に篤厚として扱われる。
現場から遺体が運び去られてしばらくしたころ、第一発見者の両親が車で迎えに来た。我が子を抱きしめる彼らの感情を必要以上に刺激しないよう心掛けながら丁寧に、指紋採取は容疑をかけるためでは無く事件の容疑者から外すための手順のひとつだと説明する。必要な個人情報の提供に応じてもらい、鷲見は親子に深く頭を下げた。誠実が伝われば、大抵は大事には至らないと信じている。良心の所在を信じなければ神経をひたすら擦り減らす仕事は続けられるわけがない。
息抜きか溜息か曖昧な何かを吐き出してまもなく、着信があった。髙橋からのそれは、県警の要請が適って当該遺体が司法解剖に回される手筈が整った旨だった。
「早かったな」
「たまには迅速っぽいです、有り難いことに」
軽口に思わず冷笑を浮かべた。
答えはわかっていたが「解剖、立ち会うか?」尋ねてみた。
「あー、いえ。班長にお譲りします。終了までに、いろいろ、ガイシャについて確認しておきます」
「任せた」
「はい」
どれほど軟派な言葉と口調だろうと最後の返答だけは間違えない――鷲見が髙橋を気に入っている理由のひとつだった。場や条件を弁えて使い分ける器用さは分け与えてほしいほどだ。
遺体がどこに運び込まれたのか端的に確認して通話を切った。
それから一時間も経過しないうちに鷲見は代表して解剖に立ち会った。
不自然な照明の配置をした二十畳もない小さな部屋。
解剖台に乗せられた遺体には異様なほど光量が集められている。
すでにふたりの助手が解剖の準備を整えていた。自らを棚に上げて就業時間外によく働くものだと呆れ混じりの感心を抱いた鷲見が光源から逃げるよう壁際に陣取った直後、ここの主人が入室した。
「では始める」
助手らが静かに雰囲気を切り替える。
張り詰めた集中だけが室内に満ちている。
「十代女性、痩身傾向あり。手の甲に擦過傷および皮下出血、手首に打撲傷あり。左頸椎付近にダイズ大の類円形開放性損傷あり。右側頭部から後頭部にかけて皮下血腫および頭部裂傷あり。……顎関節、上半身に広く硬直が見られる」
監察医の冷たい声色が滔々と事実を告げていく。
冷徹かつ滞ることなく進められる確認作業だ。
観るのを完了すると、続いて首筋の小さな傷に細い器具を差しこみ、抜いた。
「開放性損傷。鋭器損傷、刺創と思われる。深さ十ミリメートル。創口から深さ五ミリメートルについて創洞およそ七ミリメートル、そこから創底までは創洞一ミリメートル前後。頸椎には未達」
持ち替えられたメスが雪よりも蒼白い肌に触れる。Y字切開すると躊躇なく胸部が開かれた。視覚が赤に慣れているからか、室内の誰ひとり動揺する素振りはない。安心だが底知れない恐ろしさもある。鷲見がひとつ瞬きした隙に手際よく肋骨が切除されていた。露わになった内臓が検められている。
哀しいかな、鷲見は生物の死の匂いにはもう慣れてしまったと自覚している。
スクリーン越しならば思わず目を逸らしたくなるような光景だ。しかし、認知が歪んでしまったのか感覚が麻痺しているだけなのか、目の前であれば凝視できる。髙橋や望月には怯えられ大城にすら曖昧な表情をされるが、それもこれも、この監察医による規則――見ないなら出ていけ――ゆえである。
次々とサンプルが採取されて助手が渡されたそれを顕微鏡や試料を用いて即興で分析したり保管したりしていく。血液の色や胃の内容物の確認を終えると
「開頭する」
監察医は無感情に告げた。
本来は剃毛して開頭部位を露わにする過程を飛ばし、頭皮にメスを入れる。両耳を繋ぐような切開線は惚れ惚れする精緻な曲線だった。
「裂傷部位付近、生活反応あり。硬膜外血腫、硬膜内血種いずれも軽度」
頭蓋骨を開いている監察医の背に「死因になりますか」尋ねると「いいや、頭蓋骨骨折はしていない。頭部陥没は無く脳挫傷が生じるほどのエネルギーは加えられていない。硬膜内の出血は脳を圧迫するほどではない、自然治癒の可能性もある範囲だ。なお、コントラクー外傷も無い。外傷による影響は脳震盪程度だろう。頭部を打ちつけたり殴打されたりした可能性は示唆される。ただし、裂傷に伴う出血は相応だが、死に至る直接の怪我とは言いきれない」
やがて観察を完了すると「解剖終了。縫合する」端的に告げて、その言葉どおり、すばやく切開した箇所を縫い合わせていく。あらためて機械のような早さと正確さに感心していると
「脳溢血に失血性ショックを併発した。検案書はすぐ用意する」
この監察医と鷲見はすでに何度か仕事をした仲だ――さっさと着替えろ、お前がモタモタ着替え終わったころにはこちらは整理した情報を渡せる――言外の意図を受けとり解剖室をあとにした。
実際、解剖着を脱いで法医学教室で待機しているとまもなく白衣姿の監察医が悠然と現れた。
「頭ですか、首ですか」
「強いて言えば両方だ。放置されて息絶えた。どちらの傷にも生活反応が見られた」
「そうですか。推定時刻は?」
「髪と頭皮が湿っていた。この断続的な雨に濡れたんだろう? 期待しないでもらいたい」
「わかってます、参考に」
「死後硬直は当てにならない。軽微な角膜混濁と胃の内容物からの推定だ」
「何か問題ですか」
「根拠の希薄に問題無いとでも?」
「そういうことですか。あくまでも念のためです」
監察医は小さく唸るように声を零すと
「死後六時間は経過していない。食後二時間から五時間程度だろう。ただ、頭と首、どちらが先か判断できない。息絶えたのが、その時間だろうという話だ。受傷後しばらくは息が合った」
「しばらくというのは?」
「数十分から数時間……個人差の幅はあるが、遺体の年齢を考慮すると短くなかっただろう」
「申し分ありませんよ、先生。ありがとうございます」
鷲見は監察医に頭を下げてから暇を告げた。
03
ぼんやりと虚空を眺めていた。
風に揺られた前髪がわずかに額を撫でる。電話先の女性から尋ねられた「こちらへ来れますか?」に対して「はい」と応えたのだと思い出す。応えてしまった以上、行くしかない。右手だけを動かして、スマートフォンのホームボタンに親指を触れさせる。ロック画面からすぐにホーム画面が表示された。気怠い動作で腕を膝に乗せるとしばらく画面を前にして、なんとなく電源ボタンを押した。
真っ暗なスクリーンに反射する何かを眺めていると、次第に肺と胃の中間あたりが白けてくる感覚に襲われた。それを自覚すると、脳髄のあたりからしびれていく感覚も知覚する。指先から体温が消えていく代わりに耳朶に熱が集まってきた。
なぜスマートフォンを起動させたのか――調べようとしたのだ。どうすれば警察署へ行けるのか。
瞬間、認識する――座っている場合ではない。
由弦は椅子から飛び上がってスマートフォンと財布を掴んでポケットに押しこんだ。玄関へ駆けて室内履きを脱ぎ捨てて爪先に外靴をひっかける。
階段を使うか迷ったが、エレベーターのボタンを連打した。
エレベーターの駆動音が鼓動のリズムを巻きこむ。ほんのわずかに思考できる余白が生じて、昨晩は何をしていたか思い出そうとする。首筋に触れると予想外の温度差に驚いて一瞬だけ手を離す。しかし、構わず再び押しつける。沸騰しそうな脳への血液の熱を少しでも下げたかった。
昨日は、六花が出発した翌日――二泊三日の折り返しだ。
「An nescis,mi fili,quantilla sapientia mundus regatur?
(私の息子よ、お前は、叡智がいかに世界をほとんど支配していないことを知っているか?)」
ふと由弦の脳裏には父親の言葉が過ぎった――あの事件について考えていたと思い出す。
父親がラテン語の格言を持ち出すのは滔々と語りたいときだった。妻に関する自慢にはじまり古本の良さや魅力が延々と語られる前に逃げ出した。当時から読書に苦手意識は持っていなかったが、運動のほうが圧倒的に好きだった。
今は、聞けるときに聞いておけば良かったと後悔している。
前代未聞のスイス国内における銃乱射事件によって父親が命を落としたのは六年前の冬。
由弦はKnabenschiessen(青少年射撃大会)に初参加して準優勝を飾り、六花は父方の祖父母の支援を受けて名門校のサマースクールに参加した年……白河兄妹はまだ幼かった。
スイスの銃所有率は世界屈指だが、長年、乱射事件は発生しないと信じられてきた。
欠乏と蹂躙の歴史が歩ませた永世中立国への道だ。国家のための武器の保有である以上、個人のために武器を取る意識は薄い。
しかし、あの日、事件は起きた。
件の犯人による自殺を終結とする三分にも満たない襲撃は明らかに国家のためではない。犯人自身の怜悧な憎悪を顕現するためだけに百発以上の銃弾とともに命が散らされたとされている。国民が衝撃と恐怖に陥れられたのは想像に易しい。殊、由弦にとっては疑問も同時に押しつけられた。
乱射事件からまもなく、ニュースに流れる事件に関する情報や犯罪学の専門誌に載せられた専門家による考察がことごとく腑に落ちなかった。
映像然り文字然り、記録するという行為は認識の共有の一助となる。このように認識することが正しいのだと広く伝えるための行為は、正気とともに在るはずだ。
当事者にとって、殺人は唯一にして最善の解決策になり得るのかもしれない……それは理解できた。納得はできないが、ここまでは理解できた。
前提として、罪の成否や罰の存在は問題の発生条件には関係なく、問題を落着する手段として凶行が存在しており凶行は狂気によって成し得る。
発生したときには問題の原点には狂気が宿っている――原点と狂気は運命をともにする――原点が熱量を失えば凶器は消える。原点が熾火のように長く熱量を持ち続ければ狂気は燻ぶる。
原点の熱量が閾値に達することは滅多に無い。滅多に無いからこそ狂気が激しく燃え盛るごとく機会は無く、罪や罰を論じる余裕や正しいことを認識するための思考が保障される。平穏が保たれるかぎり、狂気を測る唯一の定規として正気が存在を許される。ならば狂気のすべてを計測した果て、何もかもが明らかにされたとき、理屈の上では納得すら可能となる。
にもかかわらず、由弦は納得できなかった。
犯人が直接的に憎悪を抱いていたと思われる人物を殺害するため引き金に指を掛けたと考えられているにもかかわらず、同じ空間に居合わせた件の標的を殺害する前に犯人は自殺したのだから。
そのために無関係な人々を死傷させていながら当初の目的であり動機の根幹を成す憎悪を解消しないまま犯人は自ら頭を撃ち抜いたのだから。
自らの正気を疑った時期もあったが、
「An nescis,mi fili,quantilla sapientia mundus regatur?
(私の息子よ、お前は、叡智がいかに世界をほとんど支配していないことを知っているか?)」
その度に父親の言葉を思い出した。
納得できる答え――まだ誰もその叡智をもってしても理解していないことならば――わからないことを分解して叡智で名前をつける作業を理解だとすれば、それが適わない事象が存在すると知っていることこそ正気である証明にできる。どれほど語彙が豊かであろうと博識だろうと、理解の範疇を超えていれば伝えられる内容が無いのだと納得できる。
正気は狂気の度合いを測れるが動機をはかることには向かない単位が用いられている定規なのだとようやく理解して納得したとき、由弦は自らの興味関心が人間心理にあるのだと確信した。
その後。事件から一年も経過しないうちに母親の身体を蝕む病魔が見つかり遺された家族で母方の故郷である日本へ移り住んだ。
以降、由弦は適当に入手した犯罪学や心理学の専門誌や論文を読み漁って犯人の思考を考え続けた。いつか事件についてすべてを明らかにできる日がくると信じていた。正気とともに思考をやめなければたどりつけると信じていた。昨今の世界的に流行する感染症の影響と大学進学による受講カリキュラムの融通を最大限に利用してでも時間を費やしたい内容だった。
たまに六花から妨害を受けたが、自宅が最も集中しやすい環境だった。だからこそ、二泊三日旅行で彼女が家を空ける期間にちょうど大学の期末試験後の夏季休暇が重なったことは由弦にとって絶好の機会だった。この得難い機会に、降りてきた思考はまさに天恵だと信じられた。
――もし、当初から標的を殺すつもりではなかったとしたら?
犯人は当初から標的を生かしておくつもりで引き金を絞ったのだと仮定してみると……事件は就業時間内に起こった、標的に関する下調べをしていたから襲撃時に同じ空間に居合わせた、事前の調査で標的の居場所を正確に知ることはできたのか、正確とはいえ座標で小数点以下までは不要だ、少なくともどの建物にいるのか分かれば十分だ、標的の仕事や立場から特定の時間に特定の順路を用いる可能性も考慮できる、待ち伏せすることは出来ただろうか、待ち伏せしたなら警備や警察が到着するまでに標的を殺せた、けれど殺さなかったのは何故だろう、殺すつもりが無かったのに銃は乱射されて死傷者が……今までとは全く異なる方向で考察が進んだ。
ノートパソコンを起動してドキュメントアプリを開いて半日以上はキーボードを叩き続けた。新視点の推察に由弦はすっかり魅せられていた。
だから、最中、傍らに置いていたスマートフォンが告げた着信を放置した。区切りをつけるには早過ぎた。休憩するには思考が速過ぎた。身体の疲労やあらゆる些事が魅力を凌駕するにはあまりにも無力だった。
到着したエレベーターに乗りこんで駐車場へと急ぐ。
上手い具合に落下していく箱の中で財布を確認する――財布のキーチェーンには、自宅の鍵とバイクの鍵が並んで引っかかっていた。
ふと鼻歌とともにリビングを散らかしていた妹の姿を思い出す。
その背に「どこ行くの?」と問いかけると軽く振り向きながら
「んーとねぇ、何だっけ、熱帯雨林みたいなカンジ」
「赤道近く? え、旅行って日本国内だよね?」
「違う違う、カンジは熱帯っぽいけど読むのは三文字」
しかたなく出来の悪いなぞなぞらしい言葉遊びに応じる。キッチンの棚からグラスをふたつ取りだして適当に氷を入れた。冷蔵庫のペットボトルを取りだすと同時に「熱海?」思いつきをそのまま解答してみると
「ああ、そうっ、アタミ! アタミ行こうって」
お気に入りの花柄のワンピースをリュックサックの底で整えると、六花は一旦パッキングを中断してキッチンに駆けて行った。氷入りのグラスに飲料を注ぐ兄の顔を覗きこむように見上げながら「海だよ、海! 見たことある?」楽しそうに尋ねる。
「こっち来るとき飛行機からなら」
「例外でしょ、それは」
頬を膨らませる六花だったが、グラスをひとつ受け取って礼を告げるなり表情から不満は消えていた。
「なんで熱海?」
「海の日近いから、海行こうって」
「山の日が近かったら山だったんだ?」
「そうなるねー。山もいいよね」
「スイス以上に山ではないでしょ、この国」
リビングは六花の所持品が広げられていた。テーブルや椅子の背までも侵食されている。少々困惑したが、由弦は器用に椅子を引いて腰かけた。
「国土の三分の二には勝てないけどさ、それでも7割だよ? 気候も違うし面白いと……待って、負けてるよ? 三十分の一、負けてない?」
「どうしてアルプス単体で一国と戦おうとするの。平均標高でしょ、広さも高さも違うんだし。それよりさ、熱海、七月下旬に花火大会あるよ。時期合わせなくていいの?」
六花は、スマートフォンを掲げて見せている兄を碌に確認せず「えー、絶対混むよ。だったら隅田川のほう行きたい」ラグに並べた自分の荷物を踏まないよう気をつけながら消極的な答えを返した。
「どうせそっちも混んでるでしょ」
「距離に因るってこと! それに今回の旅行のハイライトは海なのっ!」
「へぇ?」
「アタミはね、目の前がもう海なんだってさ。決めるとき写真見せてもらったんだけどね、すっごくきれいなんだよ!」
兄妹が長く暮らしていたスイスは内陸国であり、移住先の日本は海洋国だが今の自宅は決して海沿いではない。中学生時代の修学旅行では京都や奈良の文化や歴史に触れることが主題とされて、海には行っていない。正真正銘の初めての経験を前にする妹の興奮は想像するまでもなく由弦は理解できた。
「晴れると良いね」
「そう、それ! 空がきれいなら海も綺麗だもんね! ええっと、おてんと……違うね、テルテルボウズだっけ? そう、テルテルボウズ、テルボウズ♪ ねぇ、晴れにしてもらうにはいくつ作ればいいと思う? どんな顔がいいかなっ?」
「いくつ作ってもいいけど、顔まだ描くなよ」
「なんで? 欠いてない? 画竜点睛」
「欠いてていいんだよ、晴れてほしいってお願いが叶ってから描くんだから」
「そういうもの?」
「歴史に倣うなら。顔無しが嫌なら蝋人形作って玄関置いとけば?」
「比べるまでもなく労力違い過ぎるんだよなぁ、さすがに」
苦笑しながらラグを避けてグラスを置き、パッキングを再開する。
「全部入るか?」
「吟味した結果この量だから。押しこむ」
六花の瞳が、この前テレビで見た、詰め放題セールに精を出す一般人のそれに重なった。ビニール袋のように破けるような素材ではないが、万が一、破壊されそうになったら止めねばならないだろう。これから窮屈に苛まれる荷物たちが哀れだった。ふと、二回りほど大きなジップロックに乗せられたノートに視線が留まる。
「絵、見ていい?」
「ラナパーまだ乾いてないと思う。ちょい待ち」
そっとノート表面に手の甲を触れさせ、逡巡する。桃色の花が踊るジップロックからハンカチを取りだすと、円を描くようにノート全体を軽く拭う。よく手入れしているらしく、ハンカチにはノートの深緑が移っていた。パスポートサイズのノートは五分もかからず拭き終わり、腕を伸ばして差し出された。
由弦は椅子から立ち上がりノートを受けとった。
しっとりしたカバーが手に馴染む感覚が心地良い反面、手入れの効果を下げるのは悪い気がした。
ノートの端を持ちながらゆっくりページをめくっていく……向きも絵の大きさも統一されていないが、誰かの製図用シャーペンのグリップの凹凸まで精密に再現していたり教室の窓の奥に広がる青空を広げてみたり……四冊目のリフィルにもなると、ひとつひとつの筆致について、素人目にも迷いが見えない。由弦の頬は緩んだ。
「もういいかーい?」
再び伸ばされた妹の手にノートを乗せる。いつの間にか荷物は無事にリュックサックに収められていた。想定よりもリュックサックが無理をさせられていない様子に安心した。
六花はノートを入れて軽く空気を抜くとジッパーを閉めた。よく見ると、中にはハンカチと、一緒にプレゼントしたペンも仲間入りしている。
「なんでこれに入れてるの」
「前ね、持ち運んでるときに爪ひっかけちゃったことあって……ほら、ここ」
掲げたジップロックを翻し、指さした。目を細めると線状に若干色が薄くなっている箇所が把握できる。ただ、言われなければ気づけない程度だ。
「一緒についてきた布ケースは出し入れちょっと大変だし。こうしてハンカチとペンも入れておけば拭きたいときに拭けるし描きたいときに描ける」
「なるほど」
「そうだ! 私、海行きたくなるような絵、描いてくる! そしたらバイク乗せてよ。一緒に海行こ?」
「二人乗り無理。行くなら電車」
「わかった! 待っててね!」
先ほどの通話では、一度でも熱海だと言っていただろうか――たいして傾聴していなかったのだからまともに思い出せるわけがない。だが、六花は熱海にいるはずだ――彼女に何かあったと仮定すると、車もバイクも免許を持っていない十六歳なのだから移動距離はたかが知れている。
地図アプリを起動して、現在地から熱海駅の道のりを検索した。おおよその経路を頭に叩きこむなり、エレベーターから飛び出して駐車場へ駆けこむ。
高校在学中に免許取得するなり間もなく友人と乗り回して以来、感染症流行によってほとんど休ませていたバイクを久しぶりに走らせた。
目指すは熱海駅、そこからは駅から最寄りの交番か警察署を見つければ良い。
今年五月に免許を更新してから大学にも乗って行っていないが、安全運転を心掛けられるほどの余裕はない。辛うじて交通違反を避けたい良心はあった。警察に呼ばれて急いでいるのに警察によって阻害されるような事態を避けたくもあった。
頭痛や吐き気がひどくなってくる。
徹夜に近い不摂生だけが原因ではない。カフェイン不足だろうと予想した。
ひとりきりを満喫している最中に降ってきたような新視点に魅了されてから一切飲食をしていない。もちろん、コーヒーも飲んでいない。最後にカフェインを摂取したときから十二時間は経過している。離脱症状が出たのだろう。体調不良が解消されないまま運転する危険は承知している。どこかコンビニや自販機でコーヒーを買って一気飲みすれば解消されるだろうと認識する。いずれもバイクを走らせながら何度か選択肢に上がった。
しかし由弦は頑なに熱海駅へ最速最短で向かう優先順位を下げなかった。
04
法医学教室から離れて鷲見はそっと一息つく。五感が死の匂いに慣れたとて、その雰囲気からは解放されたくて辛抱ならない。さすがに仕事だと割りきっているため頑是ない子どものような真似はしないが、生存本能のひとつなのか単に心の底で仕事に関する何かを嫌悪しているのか、答えが出ても仕方のないことだと予想はついているがふとした拍子に考えてしまう。
大学の駐車場に停めた車の鍵をポケットに探っているとき、車両の影から人影が現れた。
「どうも」暗がりの中で軽く手を上げているのは髙橋だった。
「車は?」
「望月が近くまで乗せてくれました。俺、運転しますよ」
鍵を渡すと代わりに缶コーヒーが差しだされた。
「間違えて買っちゃいました。飲みます?」
「ガキか」
憎まれ口を叩きながら受けとり、腕にかけたスーツのポケットに缶を滑りこませた。スーツの襟を引いて均衡を整える。
髙橋は運転席側から乗りこみ、鷲見は助手席に腰を下ろした。エンジンをかけながら「冷めますよ」と指摘する。
「冷めてまずくなる飲料にアイスは存在しない。だいたい、こんなクソ暑い日にホットを買うな」
「胃腸は冷やさないほうが健康にいいんですって。ご存じありません?」
「こんな時間からコーヒーを飲ませようとするやつが健康志向か?」
腕時計を一瞥して冷笑すると髙橋は軽く肩をすくませる。
「こんな時間から仕事だと呼び出されたんですから時間なんてどうだっていいでしょう? それとも、ビールをお求めですか?」
鷲見が「勘弁してくれ」というのが早いか否か、アクセルが踏みこまれる。捜査本部が置かれることになった現場から最寄りの署へ走り出した。
鷲見と髙橋が当該会議室に到着したときにはほとんど会議の用意が整っているように見えた。最初の捜査会議だ。情報共有とおおよその方針が共有される。大きなホワイトボードにはすでに文字や写真が配置されていた。そこには、瞼を閉じたまま小雨に降られていた少女が満面の笑みを浮かべている写真も、含まれている。
鷲見の到着に気がついたらしい大城が厳めしい表情のまま近づいてきた。
「ガイシャの身元、判明ったらしいな」
「白河六花さん、修桜大学付属高校一年生。生年月日から察するに十六歳――所持品の財布の中に学生証がありました。まあ、本人でしょう」
「今どきの学生は夏休みに学生証を持ち歩くものなのか?」
「クラスメイト五名で旅行中だったそうで、学割目的じゃないですかね」斜め後ろから髙橋が補足する。
「彼らの友人だったか」
誰に伝えるでもなく言葉が零れた。鷲見は誤魔化すように「被害者の両親に連絡は?」大城に質問をぶつけた。すると、聞かれると予想していたらしい、タブレット端末を差しだした。慣れない手つきでスクロールする上司に構わず大城は続ける。
「所持品の中にガイシャのものと思われるスマホはありましたが、碌に連絡先を登録していないようで。まあ、最近は電話帳なんて使いませんから。ひとまず、被害者支援の担当者は、お兄ちゃん、に電話してこっちに呼んだそうです」
「メッセージアプリやSNSにも?」
「お兄ちゃんと登録されているデータのほかには友人と思われるものだけです。いくつか並んでいるこの……レ、ロゼイ? このほかオマ・アンド・オパについては、確認中です」
現場から証拠品として取得された被害者のものと思われるスマートフォンから抽出された情報を列挙したもののうち、鷲見はようやく登録された連絡先に辿りつき、目を通した。大城のカタコトどおりのローマ字読みであってもそうでなくても、鷲見は心当たりが無かった。
「父、母、白河……確かにひとつもないな。それで? お兄ちゃんとやらは来れるのか? 旅行中ってことは、こっちは地元ではないんだろう?」
「担当者いわく取り乱した様子は無かったそうです。落ち着いていた、と。関東からなので会議が終わるころには到着するでしょう」
「そうか」
会議室の前の扉から管理職が次々と入室する。会議開始の頃合いだった。
被害者は白河六花だと断定されたのは、遺体発見まもなく現場まで姿を現した五人の少年少女の話からも間違いないらしい。ところが、任意で宿泊していた部屋を確認したところ、被害者が滞在していた部屋からリュックサック含めて被害者本人の荷物がすっかり消えていた。
詳細を聞いてみると、同室の女子ふたりが被害者の荷物が無いと気がついた時点では最後に被害者本人を見てから二時間以上は経過していたという。すぐに男子三人にも声をかけて相談するまでもなく、彼ら五人は被害者が何処へ行ったのか捜索を始めたらしい。
雨が降ってきたとはいえ宿泊先から決して遠くない場所での事件を知り、希望か不安か、よくわからないものに突き動かされるように駆けてきたのだろう……鷲見は腕を組んで資料を睨みつける。
ホテルの一室を借りて聴取未満の聞き取りをしてきた班員によって、被害者の最後の飲食は、姿が見えなくなった当日の夕食および直後のデザートだと確認された。朝から海水浴をして疲れたためその日はホテル内で食事したという彼らの証言は、ホテルに設置された防犯カメラ映像が裏付けた。十七時五十七分ごろ六人で食堂に赴き、十九時二十三分には揃って出ていく姿、宿泊階のエレベーターホールに到着したのは十九時二十七分だと確認できた。なお、デザートは男子三人の宿泊部屋に集まって日中に購入した熱海プリンを食べた。その後、若い身体とはいえ朝から海を楽しんで疲労は蓄積していたようで、誰が主張するでもなく二十時を目途に被害者を含む女子三人は部屋に戻ったと口を揃えていた。
監察医の話では被害者の死亡推定時刻は食後二時間から五時間程度、つまり当日二十二時から翌一時に該当する。
また、女子側は部屋に戻ると順番にシャワーを浴びつつ就寝準備を進めたと言った。被害者が二番目に浴室を使用している間にひとりは疲れてベッドで眠ってしまったが、もうひとりは被害者の次に入れ替わるように浴室へ入った。最後に浴室を使うことになった彼女はそれが最後に被害者を見たときだと言い、おそらく二十時四十分前後ではないかと推しはかった。なお、これを補強するようにホテルが提供したルームキーの解錠施錠時刻は、男子部屋が十九時五十九分に内側から解錠され、女子部屋が二十時二分に外側からカードキーで解錠されると、ともに二十時六分に自動施錠された記録がある。次に女子部屋が内側から解錠されたのは二十時四十三分であり、この三十七分間は一度も解錠されていない。
要するに、最後にシャワーを使用した少女の話について時間的な違和感は見受けられない。
実際、被害者は発見時の服装に加えてリュックサックを背に桃色のマスクで顔のほとんどを覆った姿を宿泊階のエレベーターホールでは二十時四十五分ごろ、ホテルのエントランスではその数分後。それぞれ防犯カメラに捉えられていた。
欲を言えば男子部屋と女子部屋を取っておいて欲しかったものだが、宿泊者のプライバシーを考慮すれば無理な話だ。死角はあるが、及第点の範囲を記録している。
それぞれを考慮すると、現時点における被害者の死亡推定時刻は当日二十二時から二十三時だと考えられる。他方、これはあくまでも被害者が息を引き取ったと考えられる時刻だ。
受傷後しばらく息があったというから前者を引き延ばして――二十時四十五分から二十三時――被害者の身に何かあったと思われるのは、この二時間十五分だろう。
鷲見はなんとなく腕時計に視線を降ろした。目敏い髙橋の視線を無視して再び会議に聞き入る。
現場からは被害者のものと思われるスマートフォン、財布、ホテルのルームキーは回収されたがマスクやリュックサックは見つかっていないため捜索が続行されること。
被害者が通っていた学校関係者や一緒に旅行していた友人らに任意聴取をするため少数が関東へ送られること。
被害者の保護者への連絡を急ぐこと。
第一発見者の少年への対応を丁寧に進めること。
初回の捜査会議における決定事項はこの四点だった。粒立って目を引くものではないが、鷲見の班から大城および望月の両名が関東へ向かうよう決定が下された。
会議室を出ると、鷲見の後ろから「いいんですか、望月で」髙橋が尋ねる。
「不満か?」
経験の浅い望月に大役を任せる不安はあるが、彼女の性格上、活かせる経験になると考えた。大城が同席するなら多少のミスがあったとしてもフォローできるだろう。髙橋にしても、ベテランと呼ぶにはだいぶ早いが現場周辺の捜査を進めるにあたり十分な技量がある。人選には問題ないと判断した。
「いえ。そういうわけでは……」
珍しく歯切れの悪い彼に疑問を抱く前に、廊下の先にいる別の人物が気になった。
二十代前半だろうか、青年は廊下に設置されたベンチに腰かけて、署員を見上げながら話している。白い半袖ティーシャツに黒い細身のパンツ姿、膝にフルフェイスのヘルメットを乗せている。刑事ではないだろう。纏う雰囲気だけが判断理由ではなかった。キャンディケインのような赤と白のストライプのフレームをした眼鏡があまりにも場にそぐわない。ただし、彼の口調はひどく平坦だ。
「大丈夫です、母が亡くなったときの手順なら覚えています。でも、今、印鑑持ってないです。電話でおっしゃってくださっていましたら、失礼しました。正直あんまり覚えてない感覚で」
「急ぐ必要はありません。書類が整い次第、こちらから改めてご連絡します」
「でしたら、番号どうなりますか? 妹のからじゃないと思うんですけど」
「はい。さきほどお渡しした名刺の裏に書いてあります」
青年は手にしていた紙片へ視線を落とし「ああ、本当ですね。すみません。見てませんでした」謝意を込めきれていない声色とともに軽く頭を下げた。
ちょうど話していた署員が鷲見たちに気がつく。彼女は青年に断りを入れてからこちらへ足を運んだ。
「シラカワユヅルさん……被害者のお兄さんです」
端的に告げた。その言葉だけで彼女の所属が犯罪被害者支援課の所属だと理解した。被害者へ連絡したのも彼女だろう。
「両親は? 兄だけで来たのか?」
「ふたりとも亡くなっているそうです。父親の死がきっかけで六年前に母親の故郷である日本へ移住することになったそうですが、その母親も三年前に病死しています」
「……祖父母は?」
「母方に関しては疎遠で会ったことがなく連絡の取りかたは知らないそうです。父方には連絡がとれるそうです。ただ、時差のため今は控えたいと」
「時差?」
「スイス在住の方だそうです」
「北米か」
「いや、あの雲はなぜー、ってとこですよね?」
髙橋の絶妙に空気の読めない質問に遺族担当は曖昧な苦笑を返した。
直後、
「ヨーロッパの内陸国です。フランス、ドイツ、イタリアとか、そのあたりです」
三人は同時に振り向いた。件の青年は足音もなく一メートルほど距離をおいて立っていた。髙橋と目が合って「ハイジで合ってますよ、山しかない国です」淡々と続けた。彼は遺族担当に水のペットボトルを差し出して
「それと、すみません。やっぱりいらないです」
「持っているだけでも」
「別に空気乾燥してないですから。大丈夫です」
口調は先ほどと比べて柔らかいが、有無を言わせない圧を帯びている。
遺族担当はペットボトルを受け取って「すみません」小さく頭を下げた。
「あ、いえ。ご厚意なのはわかってます」
担当者いわく取り乱した様子は無かったそうです。落ち着いていた、と。関東からなので会議が終わるころには到着するでしょう――大城の言葉が脳裏を過ぎる。取り乱していないどころか、むしろ感心するほどの冷静さである。
何を思ったのか、髙橋が一歩前に出る。
「修桜大学付属高校、横浜の学校ですよね? 関東からここまで?」
「あ、はい」
「始発?」
「あ……いえ、バイクで来ました」
「遠かっただろう? 大変じゃなかったか?」
「ですね。始発……電車、確かに電車のほうが楽ですね」
「仕事は?」
「えっと……大学生で、たまに知り合いの手伝いみたいな感じでウェブライターしてます」
「大学生?」
「はい……財布、今ちょっと学生証持ってないんですけど、あ、大学のポータルサイトでも良いですか。たしか学生情報が見れたはず――あ」
「どうした?」
「充電切れました」
呆然としながらも青年は真っ暗なスクリーンを見せてくれる。髙橋が言葉を探している傍らで「……帰りかた、わかりますか?」遺族担当が尋ねた。
「来た道戻れば、一応」
「初めてこちらへ来られたと思うのですが」
ヘルメットを小脇に抱えなおす青年に、遺族担当よりも積極的に髙橋が提案する。
「バイク乗ってきたんですよね、電車ではなく。車で送りますよ。それか、充電しませんか? 少し休んだほうが」
「でも、私がここいたら邪魔になりますよね? ほかに用はありませんし、できることないですし」
「急ぎの用事でも?」
「いえ、それはとくには」
「それなら、少し話を聞かせてもらえないかな」
なるほど、それが目的だったか――鷲見は髙橋の横顔を睨んだ。大学生ならば少なくとも十八歳以上だろう。任意聴取に親権者の同席は必須ではない。青年もなんとなく察したような声を漏らした。
「事情聴取ってやつですか、構いませんけど……仕事、大丈夫ですか?」
「あいにく、これが仕事だよ」
青年は遺族担当と髙橋を交互に見比べると、困惑したように鷲見へ視線を向けた。部署や職務内容の違いまでは把握していないのだろう。鷲見は自己紹介したうえで、遺族担当は捜査とは別の大切な仕事を担っており、事件解明を担うのは自分たちだと教えた。
ひとまず納得してくれたらしい青年を連れて、小会議室へ移動した。
遺族担当が扉を背後にできる椅子を引いて青年に着席を促した。
「……被害者と雰囲気が近いですね」
鷲見は改めて青年の後ろ姿を見下ろした。髙橋の指摘どおり、眼鏡の印象を除けば、兄妹は十分似ている。廊下で話しているときははっきりしなかったが、明るい部屋に移動したことで眼鏡のレンズ越しでも空色鼠の双眸は確認できた。
「どうしました?」尋ねながら、部屋を見渡す青年の正面に髙橋が陣取った。鷲見はすぐ隣に座る。
「いえ……こういう部屋もあるのだと思って」
「取調室に入れるのは容疑者と刑事だけですよ」
青年から椅子ひとつ空けて座る遺族担当に睨まれた気がして、咳払いをする。
「捜査の初動ですから、今は情報が必要です」
「電話で妹が、死んだとは聞きましたけれど……事故ではなかったんですか? 何時くらいに」
「何があったか明らかにするため、捜査中です」
「……わかりました。何を答えれば良いですか」
「白河六花さんの交友関係についてはご存じですか?」
「今回友達と旅行するというのは聞いていました。でも、詳しくは知りません。高校進学から間もないので交友関係と言われても浅いものばかりでしょう。ああ、小旅行を計画して実行するのって、別に浅いわけではないですかね」
「学校の知り合いよりは親しい間柄と言えるかもしれませんね。ちなみに、その友達の名前や容姿は?」
「そこまで干渉してませんから、知りません」
「ひとりも?」膝を進めた髙橋が尋ねる。すると「刑事さん、御兄弟はいらっしゃいますか?」淡白に切り返した。
「ええ、まあ。弟がふたりほど」
「でしたら、どちらの弟さんでも構いませんが、彼の御友人の名前はいくつご存じですか?」
「……高校時代からのが、それなりにいるくらいですね」
「妹はまだ進学から三か月程度です。贔屓目に見て、友人は少なくありませんでしたが、どれほどの時間をかけていままで親しくなっていったのか知るすべはありません。年齢差ゆえに入学と卒業が重なって、同時期に同じ校舎には通っていませんから」
「失礼、ありがとうございます」
「いえ……正直、話すよりも絵を描くほうが性に合っている子でしたから、私からは妹に学校で何があったか聞いてきません。もし聞いたらいくつ名前を挙げてくれたでしょうね」
「一緒に旅行していた友人についても、聞いていませんか?」
「……そうですね。海に行こうと提案があり熱海に決まったとは言っていましたが、それ以上は何も」
「人数については」
「聞いていないです」
「男女比も?」
「女子旅じゃあ……男子もいたんですか?」
これが演技なら経験者だろう。本当に何も確認していなかった自らの不足に呆れ切っているらしい。
このご時世にかぎらず、観光地へ女子高校生だけの宿泊旅行を許可するのは日本の平和神話を信じすぎている。他方、年頃の男女旅行を許可するのもどうだろうか。
青年の言葉から察するに、彼が思い至ったのは後者だけなのだろう。しかし鷲見と髙橋は何も言わない代わりに一瞬だけお互いを見やると、改めて青年に意識を集中させた。
「現場から六花さんのスマートフォンが回収されました。白河さんはパスコードをご存じでしょうか?」
「スマホ、ロック解除できていないんですか? たしか、電話……」
遺族担当へ視線が集まる。彼女は、登録されていた緊急連絡先から電話をかけた、と言う。
「じゃあ、捜査は難航してるとか、そういう」
「いや。ロックを突破できなくても情報を抽出する方法があるんです。それで、心当たりはあるかな」
「いえ、わからないです。指紋とか顔の認証はできないんですか」
「どうだろう。試させてもらいたいね」
「あくまでも捜査のことですよね? 私に拒否権があるとは思わないのですが」
青年が眉を顰める。髙橋に代わって鷲見があからさまに「ところで」話題を変えた。
「これらは六花さんのスマートフォンに登録されていたんですが……レ、ロゼイ。オマ・アンド・オパ……聞き覚えや心当たりのほうはありますか?」
すると、青年は何度かゆっくり瞬きをした。知らないのだろうな、と諦念を誤魔化すように居住まいを正そうとしたとき、
「Le Roseyですか? レ、ロゼイというのは。それなら、オマ・アンド・オパは、おそらく祖父母のことです。あの……」
言いよどむと、困ったように何度か握りこぶしを宙で振り、青年の視線は机の端にある充電中のスマートフォンに流れ着いた。遺族担当がすかさず自らの手帳とペンを彼に差し出した。意図を察したらしく、筆記用具を受けとるなり、青年は流れるような筆致によってそれぞれ「Le Rosey」「Oma&Opa」と綴った。
「父方の祖母が通わせたがったんです、妹も新しい環境が苦手だったり勉強が嫌いだったりしたわけではなかったので。インターナショナルボーディングスクールです」
あいにくながら、所在はレマン湖の近くだと補足されても、そもそも鷲見だけでなくこの場において被害者の兄以外はスイスの地理についてあまりにも解像度が低い。
「もしかして、連絡先のいくつか、Le Roseyの後にアンダーバーか何かで人名が続けられていませんでしたか?」
「人名?」
「向こうでの妹の交友関係はよくわからないんですけど、何か、女の子の名前です……アルファベット、何が綴られて――すみません、こっちから聞いたらいけませんよね。ポストカードで見たことがあるのは……ミア、マリア、アンナ、パトリツィア、カタリナ、キアラ……そのくらいです。どうですか?」
音が指定されると、案外アルファベットと一致させるのは苦にならなかった。
鷲見は「アンダーバーに続けられているのはマリア、カタリナ、キアラ……ほかにもあるが、スイスで通っていた学校での友人だったのだろうね」独り言ちるように結論付けた。
「向こうにいたころは妹さんに学校のことを聞いていたのかい?」
「あ、いえ……母が聞いてたのを」
「すまない、無作法だった」
髙橋は素直に非礼を詫びた。
「……それでも、今の交友関係を知らないのは私の責任です。お力になれずすみません。他には何か、私が答えられることありますか?」
青年のまっすぐな視線を受け止めて、髙橋は居住まいを改める。
「昨晩、白河さんはどこにいましたかね?」
「おいっ」
思わず鷲見は部下を諫める。案の定、遺族担当も眼差しを険しくして、和らげた瞳で青年を見つめる。
「自宅にいました」
不安をよそに、青年は答えた。
「ずっとですか」
「はい。妹が終業式から荷物を取り換えに帰ってきて玄関まで見送りましたが、家からはでていません」
「たしか大学生でしたよね? 白河さん自身のご友人を自宅に招いたりなどは」
「ああ、在宅を証明してくれる人ですか。いませんね。無意味に騒ぐのは性に合わないですし、世間ではまだ在宅推奨されてますから。最近は大学の講義も無くてオンライン会議の予定も入れてませんでしたし。強いて言えば、マンションの防犯カメラでしょうか。あと、ここまでバイクで高速使ってきたので、何か記録に残ってる可能性はあると思います」
「ありがとうございます。それでは最後に――白河六花さんを恨んだり憎んだりしていた人物に心当たりはありますか?」
続けられた髙橋の質問は、あくまでも機械的な口調だった。どこか青年の纏う雰囲気に合わせるような淡白さがあった。鷲見は部下を凝視する。
「事故ではなかったんですね?」
負けず劣らず冷静な声が響く。
髙橋は平然と目の前の青年を見つめている。
「ただ死んだなら、恨まれていたかなんて気にしませんよね? 交友関係や家族構成も、書類も」
「何を想像されているかわかりませんが、手順ですから」
「……わかりません。あいにく交友関係もまともに知りませんから」
「恋人がいることも?」
「はい?」
「妹さんに御友人がいることは知っていても、名前まではわからないんですね? でしたら、仮に恋人がいても六花さんは貴方には話さなかったかもしれない、それなら、知らないでしょうね」
「……そうですね。可能性は否めません」
青年は天井を見上げると淡白に答えた。続けて、髙橋を見据えて尋ねる。
「誰に殺されたんですか?」
「繰り返しますが、目下、捜査中です」
「いつわかりますか?」
「最善を尽くします」
掴み切れない冷静な青年の探るような瞳を前に、髙橋は誠実そうな眼差しを返していた。
やがて疲れたから帰りたいという青年を見送るため小会議室を後にする。被害者の所持品は改めてこちらから連絡をした際に確認してほしいと告げ、了承を受けとった。
警察署のエントランスにて、彼は高校生前後の少年に話しかけられ、そのままヘルメット片手に会話をしている。
相手の少年に見覚えがあり、記憶をたどっていると、
「あの子、現場に来たひとりか?」
尋ねてから気づいたが、髙橋に確認しても無駄だ。彼は現場を経由しなかった。
ただ、鷲見はあの場にいた男子三人のうち話しかけてきた子でも悲鳴を上げた少女を抱きとめた子でもなく、もうひとりの男子だったと記憶している。見間違えだろうか、他方、ならば被害者の兄に話しかける理由も警察署にいる理由もない。事情を知る者に確認しようにも、せめて捜査本部へ戻らねばならないだろう。
ふと髙橋の表情を見る。まっすぐ青年の後ろ姿を見つめている。
「……たったひとりの家族が殺されたのに、って。そういう顔か?」
「いえ……」
「そういえば弟の友人、何人知ってるんだ?」
「それなりに社交的なやつらでしてね。今でも交友がある十五人なら住所まで知ってますよ」
「住所?」
「年賀状だってわざわざ送りあってるんですから。成人してからは生意気にも故郷納税の返礼品で遊んでますよ。まあ、俺の場合はどっちも男ですからね。妹いないんで、白河兄妹の関係性が普通なのかどうかすらわかりません。とはいえ……あまりにも落ち着き払ってませんか?」
「兄妹仲が良好だった保証は無い。幸いなのは、無関心ではなさそうだってことだな」
「そうでしたか? かなり淡白だったと思いますけど」
「どうでもいいやつの死にかたまで気にするか?」
「それは……そうだとしても、あそこまで冷静でいられるものですかね。班長だって、何か気になりませんでした?」
「まあ、そうだな。質問には丁寧に答えるが、多くを語ろうとしていないようには思う」
「ボロを出さないようにしてるってことですか?」
「先入観と私情で判断するな」
「……すみません」
自覚があるだけまだ良い。修正の余地がある。
青年が署を後にしてから「鍵を握るのは被害者だろうな」隣の髙橋にだけ聞こえるようつぶやいた。
「まあ、マスコミや世間様が飛びつきそうな被害者――痛っ」
手が出た後に「いい加減にしろ」と補足した。努力するつもりがあるのかないのか「へーい」と返された。注意を重ねようとしたが、その前に髙橋は「ねえ、君!」少年のもとへ駆け寄った。
「情報共有がなってなくて悪いんだけどさ、白河六花さんと一緒に旅行していた子であってるよね?」
警察手帳を見せながら気安く話しかけると、少年は首肯した。
「こんな時間までどうしたの? 他の子たちは姿見えないけど。まだ親御さんの迎え、来ない?」
「今、出張先から移動してるらしくて。連絡は取れてます」
「そっか、それなら良かった。送ったほうが良かったらそうするんだけど」
「いえ、大丈夫です。ほかの刑事さんにも提案してもらったんですけど、僕が断りました」
「そっか! そうだ、腹減ってる? そこにコンビにあるから何か買ってこようか?」
「え? いえ、大丈夫です」
少年は一瞬だけ視線を落とすと、再び髙橋を見上げた。何かを決意したようなまっすぐさだった。
「お兄さん、何か言ってましたか?」
「いいや、何も。君もさっき話してたの見えたけど、どうしたの?」
「いえ……別に」
髙橋がさらに質問しようとしたとき署内に男性が駆け込んできた。エントランスに話しかけようとした直前、髙橋と話す少年の姿を捉えて「ホタカ!」叫ぶように呼んだ。
「すみません、失礼します」少年は丁寧に頭を下げて暇を告げると、呼びかけてきた父親らしき男性のもとへ駆けて行った。親子そろってこちらへ頭を下げてきた。鷲見と髙橋も、礼には礼を返した。
05
空っぽ。
空虚な通夜だった。三年前の葬儀のときも頼れる大人は身近にいなかった。幼い妹に手伝わせるわけにもいかず、由弦が生前の母親にも協力してもらってあらゆる手配をした。あれから三年が経過した。再び同じ手順を踏むとは想像していなかった。
今、棺は六花の部屋にある。
幼いころから暗い部屋では眠れない子だった。いつものようにベッドの傍の間接照明はつけたままにしている。棺を部屋に静置するとき、どうしても室内の様子が気になった。高いところの掃除を手伝ったり勉強を教えたりする際に何度か出入りしたことはある。主人が戻ってきたはずなのに、部屋の様相がまったく異なって見えた。
白い本棚に並んだものを視線で追っていく……教科書やノート、スケッチブック、トラベラーズノートのリフィルいくつか、移住の際に彼女が唯一持ってきた書籍『雪のフィアンセたち』、中学時代に長期休みの課題図書だと話していたものが数冊、日記帳……厚い日記帳にはひとつだけ付箋がついていた。思わず手に取り、そのページを開く。数日前の――終業式の日付だった。付箋には「帰ってきたら書く!」 と、二行にわたり妹の字が綴られていた。
日記帳は五年分の記録を、一日一ページ書けるようになっているタイプだ。いつだったか、一緒に買いに行った覚えがある。
日記をつけたことがないのに最初から負担が重いものを選ぶのをなぜ止めなかったのか……
リビングで宿題をしていると、
「そういうかっこいい字書けるようになりたい!」
急に六花が宣言した。
「がんばれ」
「コツは?」
「知らない」
日本語は他言語のアルファベットとは一線を画す雰囲気がある。事実、由弦も母の書く字に憧れた。書道のように墨汁と筆で練習する機会は無かったが、はねやはらいを再現するには持っている筆記用具で十分だった。
「結局のところ慣れだよ。母さんの字、真似してみればわかってくると思う。そのうちかっこいい字になってくよ」
「うぅぅぃい……」
あからさまに乗り気では無かった。書く理由が無ければ練習も憂鬱だ。
数日後。
ふと思い立ったある日の午後、母親の診察中に、小学生だった六花の手を引いていくつか近くのバラエティショップを巡った。
何かを習得するとき必ず練習は欠かせない――由弦は、それは間違いないと信じていた。
初出場した射撃大会の準優勝という結果は、他者のコンディションによる差異は否定しないが、畢竟、自らの全力が出せたからだと認識している。
文字を書くことも例外ではない。練習しなければ「そういうかっこいい字」は書けない。とはいえ、十歳の妹にこの論理を押しつけても意味は無いとわかっていた。ならば、実際に練習するかどうかは任せるとして、その第一歩を手伝うくらいはしてやっても良いと思った。その程度なら、父親の死にまつわる考察の気晴らしになる気がした。
「日記って何書くの?」
「好きなことでしょ」
「好きなことって?」
「わかんないよ。クリスの好きなことを書くんだから」
「何が好き?」
「自分に聞いて。ほら、ここにもあった。良いなって思うの……」
有無を聞くまでもなかった。数秒ほど目を離した隙に、鮮緑は一冊の日記帳に惹きつけられていた。ただ、不安なのは
「それ、五年日記だよ。千八百日以上、毎日書かないといけないんだよ?」
「がんばる」
事前にがんばれと言った手前、否定できなかった。名前を呼ばれながら制服の裾を引かれる。
「これが良い!」
店内の照明を受けて、見上げてくる瞳が煌めいているように錯覚する――生前の父親の瞳と重なった。
見上げながら声をかけると、おだやかな眼差しが降ってくる。
「クリスには声かけなくていいの?」
「いやぁ、あのピオニーちゃんは読書にはそれほど興味ないでしょ。絵を描いたり自然の中でのびのび過ごしたり、そういうほうが合ってるよ」
射撃大会の成績を受けて、書斎のコレクションから自分で選んだ一冊をくれるという。ただ、古書ばかりでどれを選べば良いのか判断基準をもっていなかった。指南までは求めていなかったが助言は欲しかった。しかし、父親は「好きなのでいいよ」とだけ言って床に座りこみ近くの書籍を抜き取って読み始めてしまった。
改めて部屋を見渡す――壁一面はもちろん、部屋中が本棚であり書籍に満たされている。多量の紙が集められた特有の香りを深く吸いこんでみる――気合を入れて背表紙をひとつひとつ丁寧に確認していった。
いつの時代なのか、誰による著作なのか、そもそもどこの言語が用いられているのか。
知らない世界はとにかく新鮮でたまらなく惹かれた。
中でも、その書籍の古さは異質だった。なんとなく手に取った一冊……ポアンカレ著作・田邊元訳『科学の價値』に簡単に目を通した。
一九二七年に上梓された初版であったが、シミや損傷は穏やかだった。風化によって紙は変色していたものの、それ以上は何も気にせず読書できそうだ。父親が書籍を大切にする人だと知っているが、今までの持ち主からずっと大切にされ続けてきたと推察できる。
由弦はそれを片手に、読書もとい待機している父親のそばで膝を曲げた。気がついたのか、人差し指の関節で眼鏡のブリッジを押し上げながら上目遣いに視線が合わせられた。背の高い父親に見上げられる、この珍しい感覚を面白がっているのを悟られたくなくてぶっきらぼうに尋ねる。
「こういうのでも、本当にもらっていいの?」
「ああ、もちろん。何を気にしてるんだ?」
「いや……かなり古いから、本当は気に入っているのかなぁって」
「日本にいたころ、古本屋で買ったんだ。それは初版だったかな」
「へぇ」
「当時はとにかくミユキの気を引きたくてね。話を合わせようと、彼女が尊敬すると言っていた学者の著作を網羅しようとしていた」
隙あらば惚気てくる親を持つと苦労する。あからさまな父親だけで済めばいいが、母親は無自覚とくる。「はいはい。ほんと、健気な恋が実りましておめでとうございました」と突き返して他のを探そうとした、そのとき。書籍は押し返された。
「愛着がないといえば嘘になるが。それでも、関心を持ってくれたなら満足さ」
関心。
まあ一応、関心ではあるだろう。ただ、父親が望むものとは程遠いと自覚している。日本語で書かれた書籍だったから以上の理由はなかった。特にこういった古いものには画数が多い漢字もよく使われていてかっこいいと感じたくらいだ。少なくとも、内容への興味ではなかった。
「じゃあ……これが良い」
父親は優しく目を細めて頭を撫でてくれたが――同じ言葉で物を求めているのに、妹の関心の純粋さとは比べるまでもない。
妹と繋ぐ手が汗ばんでいないか、気が気ではなくなる。都合よく理由を思いついて、手を離す。その手で妹が選んだ日記帳を掴み、差しだした。
よこしまな思考が混ざっている。
正確には、一種の現実逃避。あの事件が、より没頭できる何かを求めさせているだけ。しかし、いつまでも見つけられずに縋り続けている。崇高な目的などなく、好奇心ですらない。
焦りたいのかもしれない。忘れるために好都合な焦りが欲しいのだ。焦れば焦らない自分に焦らずに済むから、一石二鳥とも言える。畢竟、パラドックスのような、ないものねだりに過ぎない。
それを知らない妹が……心の赴くまま好きを見つけられる彼女の感性が疎ましく、羨ましかった。
由弦は、本棚に背を預けて座って妹の日記帳の最初のページを開いた。
花瓶に生けられた花の絵が描かれているページの端には、闇夜に咲き誇れる日を待ち望む、と書かれていた――六花――自分の名前からの連想だろうか。描かれた花にはなんとなく見覚えがある。おそらく母親の見舞いで持って行ったいずれかだろうと予想した。
チーズ! Omaのチーズ食べたい 見つかるかな 今はパンでがまん
いちご大福 考えた人すごい みどりいろのお茶も、もっっっのすごくおいしい!
すれちがったわんちゃんかわいかった♡ 手ふったら、シッポふってくれた!
この花 名前なんだろう?
お水! そういえば!
やきそばパン考えた人、頭悪すぎて大好き
文字よりも絵のほうが大きく数も多い。一日一ページを守りながら、スケッチブックのような使いかたをしていたのだろうと想像する。やはり指定しなくても好きなものを描けたのだと眦が下がっていく。
しかし。
次のページをめくった瞬間、白河は全身を強張らせた。
銃乱射事件の日から二年――日記をつけ始めて一年目、この日だけ絵がない。十二歳の妹が文字で記録したものだ。文字だけで完結しているページだった。
今日も、リビングでやってた。
ひとつのことに集中しているゲンは知らない人みたい。
はなしかけるのも怖くて見ているのも怖い。
そのうち、パパみたいに本当にどこか知らないところへ行ってしまうのかな。
ママのようにごめんねと言ったきり動かなくなってしまう日がくるの?
わたしが声をあげて泣いていたら、だれか気づいてくれるのかな。
それとも、みんな知らないふりをするのかな。
この日になったから、わたしも考える。
考えないといけないと思う。
だれに言えばいいのかわからなかった。
何を言えば伝わるのかもわからなかった。
あのニュースの男の人、話したことがあること。
だれも聞いてくれなかった。
ううん、違う。聞いてもらっても、何を言えば良かったかわからない。聞かれてもこわくなって泣いてたと思う。
うまく言葉が見つけられなくて、聞いてくれる時間を守れなくて、だれにも伝えられなかった。
わたしが話したせいでパパはうたれたの?
そうだとしたら、あの日、わたしはママと泣いていてよかった?猫は好きだけど、被りたくなかった
わたしの仮面は猫なんかじゃなくて、いやなものがぜんぶ集められてはりつけられた呪いだった。
ぜんぶきらいだった。
だれにも言えないのはわたしの弱さだったかもしれない。今も言えないのはわたしの弱さだと思う。
楽になりたいのに、終わりにできない。
ゲンみたいにちゃんと向きあえるなら何か違ったのかな。何か変えられたのかな。
あの日のためにずっときらいなまちがってる道を進むしかなかった。
真実から遁走を続けた。だからこそ願ってる。
だれか私を終わらせて。
けれど、そうしたらひとりぼっちになる。
そうなったら、わたしはたえられる?
それとも、何か変えようとがんばれる?
もう何にもわからない。
由弦は、日記帳を閉じた。
早朝の電話に出たのは罪悪感だ。二十時五十七分の電話を、意図的に無視したからだ。ちょうど父親の事件に関する考察に熱が入っていたため、途切れさせたくなかった。
学問そのものは、人の好奇心から生じたというのは至言だろう。偏見は学問の敵だが、偏見は感情に由来し、好奇心という感情から生じた学問は、どうしても偏見と重なりうる。除外が困難である以上、つきあっていくしかないわけだが途方もない作業だ。失敗する可能性はあり、また、失敗すれば新たな無理解や偏見が際限なく生じていく。真実に寄り添うためには、そのような自らの不純物と向き合わねばならないのは承知のうえだった。それでもなお、あのとき、何かをつかめる気がしていた。
真実である保証はもちろん無い。
しかし、逃したくなかった。
「…………」
由弦はテーブルに突っ伏せた。
恋人がいるかどうか……刑事の推察どおり、由弦は知らなかった。しかし、肯定するのも否定するのも癪に障った。どうにか言葉を選んだ結果が「可能性は否めません」だった。
リビングのテーブルに教科書とノートを持ってくると、
「兄上ぇ、この問題の解きかたを教えてくれませぬかっ?」
コーヒーで朝食を食道へ流しこんでいる由弦の前に六花が陣取った。何も答えずただ眺めていたら、演劇の幕が上がる。
「定期考査を間近に控えつつ、解けない問題が立ちはだかりけり。何卒お力添えいただきたく存じまする!」
「古典? いつ?」
「……」
コーヒーを飲み干してから「いつ?」同じ質問を重ねた。
「今日の一限でございまするねぇ」
「……は?」
「およそ二時間後……」
リビングの時計の短針は今にも七を指そうとしている。
「諦めも大切だよ」
「あああっ、そこをどうにかぁ……!」
必修科目のテストのため早々に起きた日を狙ってきたかのような一幕から、まだ半月すら経過していない。六花が期末試験の結果を見せて由弦に自慢してきたのは、たった五日前だった。
兄なら絶対に断らないと信じて、若干身体を傾けながらおねだりする姿はもう見られないらしい。白い棺が目のまえにたしかに存在しているのに、どこか現実離れした感覚がはびこっている。
霊安室で目にした六花を思い出す。
表情豊かな少女は、殊にすぐ顔を真っ赤にしていた彼女は、生前の父親によく「ピオニーみたいだ」と揶揄われていたとは思えないほど、人工造形物のような不気味な蒼白に支配されていた。その反面、ただ眠っているだけのように見えて、リビングで寝落ちした彼女をみつけたときのようにそっと頬へ手を伸ばした。あと数センチメートル――怖くなって手を引っ込めた。
首に包帯が巻かれているのが目に留まった。
由弦は何かに誘われるまま包帯の端を見つけて慎重に解いた。
何を隠そうとしていたのか理解すると、可能なかぎり包帯を元に戻した。異様な蒼白にも納得した。六花に何があったのか、ほんのわずかながらわかった気がした。
終始付き添ってくれた警察官に、どこに倒れていたのか尋ねると、彼女は車に乗せてくれた。まもなく到着したのは海が見える道路から少し離れた場所だった。
「ここは?」
「宿泊していたホテルから親水公園のムーンテラスへ行く途中の道を、少し逸れたところです」
「ああ……献花、ありますね。あそこですか」
ホテルも海も見える場所だった。
「このあたりの夜って、暗いんですかね」
「ライトアップされると、けっこう明るいです。ここから歩いて二分くらいでムーンテラスです。ただ、当日は雨が降ったり止んだりしていたので人通りがほとんどありませんでした」
「ああ……そういえば、荷物、まだ見つかりませんか」
「……捜索中です。見つかり次第、ご連絡差し上げます」
「わかりました」
誰もいなかった。
息絶えるとき、妹は、ひとりぼっちだった。
両親が生きているころから、六花はひとりで過ごす機会は少なくなかった。しかし、積極的に誰かの視界から外れようとしているのではなく、好きなことをしようとすると自然とひとりのほうが環境として好ましいに過ぎない。
ひとりで過ごした時間以上に、両親や兄に甘えている時間のほうが長い。決してひとりぼっちが得意ではなかったのだ。
空っぽの拳を握りしめる由弦の掌には、爪が深く刺さった。
祖母からの電話を取るために病室から離れて、戻ってきたとき
「日本に行ったら、私、ママの名前もらえるの?」
六花の声が聞こえた。姿を見ずとも、由弦は母親の動揺を明確に察知した。咄嗟にフォローする方法に思考を割く――母親の言葉の代わりに、六花が続ける。
「クリステルって、オーマからもらったんでしょう? それなら、私、日本で使う日本語の名前、ママと一緒が良い」
「引っ越すのは、嫌……?」
「違う、ううん、えっとね、引っ越すのは関係ないよ。ミアたちと離れるのは寂しいし嫌だよ。けど、違うの。ママと一緒が良いの。一緒じゃないと嫌なの」
「帰化するわけじゃないから、クリスの名前を変えられるわけでは無いのよ。あなたが生まれて日本国籍は留保しているから、これから新しく名前を決められないの」
「じゃあキカする」
「クリス……」
これ以上は――わざと音を抑えずに扉を開けた。向けられる二種類の瞳をそしらぬ表情で受け止める。六花は「ジュース買ってくる」と病室を出た。
安堵のため息は掠れていた。様子を伺おうとすると、視線がかち合う。自分が先に何か意味のある建設的なことを言わなければならない――思考を回して言葉を探した。
「わかってるよ、クリスは。わかってて言ってるだけだよ」
母親の言葉を遮るように、軽く被りを振った。
「母さんの故郷でしょう? 興味あるよ。おもしろい国なんでしょう? それに、こっちよりも暖かいらしいから。僕、寒いのあまり好きじゃないし。友達とも、携帯あれば連絡取れるし」
そっと手を取られて、由弦は母親に誘われるままベッドに腰かける。気恥ずかしさはあったが、抵抗せずそのまま抱きしめられた。
「ごめんね。ありがとう。クリスをよろしくね」
「……うん」
なんとなく触れたシーツが湿っている気がして、母親の手を握るように包むことにした。
偶然手を置いた場所は、先ほどまでクリスが顔を押しつけている箇所だった。
由弦は日記帳を片手に、覚束ない足取りでリビングに向かう。椅子に体を預けて通話記録を確認した。
六花が死んだ夜。六花から電話があった。着信には気づいていた。しかし、父親の事件について知らない人に見えるような熱中とともに考えて、六花からの連絡を無視した。
母親の「よろしくね」という言葉はどのようにでも解釈できるが少なくとも、ひとりにしないであげてほしいというニュアンスは明確だった。にもかかわらず、約束を守れなかった。
二十時五十七分。
普段から兄が起きていると知っていたから掛けてきたのだろう。それは、わかる。
しかしこのとき彼女がどのような状況だったのか、わからない。
単純に暇だったから掛けてきたかもしれない。友人らに促されて掛けてみただけかもしれない。あるいは――だからこそ由弦は、妹が死んだ時間を知りたかった。しかしながら、警察は教えてくれなかった。最初の電話のときも未明としか言っていなかった。警察署での聴取をした刑事には捜査中だからと曖昧にされた。
なるべく正確な時間を知りたかった。そうすれば、本人には聞けなくても、六花が掛けてきた電話の用件に予想がつけられる気がした。
開いたままのスマートフォンで、ニュースを確認する。数時間単位でなら――期待を込めた。
妹のことを良く知っていると思っていた。明るく元気な、ぬけているところがあって少し勉強が苦手な少女のことを。生まれたときから見てきたはずだった。
由弦はスクリーンを見ていられなくなって、スマートフォンを力任せに壁へ投げつけた。
「割合でいったら、私のほうが妹として上手なんだよ? わかる? ゲンは私が生まれてからしか兄をしていないのに、私は生まれたときから……ううん、受精卵として着床した瞬間から妹をしてる。したがって、人生において私のほうが妹をしている割合が長いんだよ」
「何言ってるの?」
「私もわからなくなってきた」
由弦もわからなくなってきていた。
「………………」
否、わかるかもしれない――警察署で、一緒に旅行していた五人のうちひとりと連絡先を交換したと思い出す。
椅子を蹴るように立ち上がり、スマートフォンを拾い上げた。
06
第一発見者の少年をその両親立会いのもと聴取したが、特に有益な情報は得られなかった。深く息をついた鷲見の隣で髙橋は机に肘をついて両手に額を押しつけた。
「わかってたじゃないですか、どうせ何も知らないって言われるのは」
「念のためだ」
疲れが隠せないのは連勤だけが原因ではない。早くも捜査が暗礁に乗り上げようとしている感覚があるためだ。
完全に停滞しているわけでは無い。周辺への聞き込みにより、事件当日の二十一時ごろに女性が言い争うように声を荒げていたのを聞いたという証言が複数得られた。被害者と関係がある保証は無いが、無視はできない。だからこそ、断続的な小雨で流されてしまったかもしれない証拠の存在やまだ発見されない被害者の荷物など、積み重なる小休止が澱のように張りついて雰囲気に重さを加えている。
「顔見知りか通り魔か、どちらだと思います?」
「一般的には顔見知りだな」
「ほら」
「旅行先である必要はない」
「確かに心理的負担はホームに近いほうが軽いですけど、結局は人を殺すっていう負担は比べられないでしょう?」
髙橋は軽く椅子を引いて横座りしなおした。
「班長。仮の話です。あくまでも仮なので、予想です。先入観とか、そういうの無しでお願いします」
「予断は」
「認識した上であれば予断は推測の列挙です」
「……ガキか」
「じゃあガキの戯言遊びにつきあってください」
髙橋は嬉しそうに笑って、ひとつ手を叩いた。
鷲見は苦虫を噛んだようにその剛毛な眉を顰める。
「あの高校生たちを疑ってるのか?」
「旅行先の顔見知りですからね」そう言いながら手帳を開くと、
「二十時四十七分、ホテルのエントランスに設置された防犯カメラにリュックサックを背負って出ていく被害者の姿が捉えられています。この時点では被害者は生きていました。そして、およそ二時間十五分以内に殺された。自殺では無いのはいいですよね? 発見したとき被害者は自らの首をさせる鋭利な何かを持っていませんでしたから。それこそ氷の凶器が雨とか気温で融かされてウンヌンなんて机上の空論は無しです」
「被害者の荷物もまだ行方不明。誰かによって持ち去られた、か?」
「刺した人間と同一人物だってこともあり得ますし、違うかもしれません」
「だとしても、あの高校生たちには無理だ。ホテルのルームキーの記録は書き替えられた痕跡はない。おまけに、カードごとに埋め込まれた固有チップが何もかも記録している。遺留品のカードキーは確かに宿泊していた部屋のものだった。被害者が発見されるまでの二時間十五分間において、二十一時二十九分に内側から女子部屋の扉が開けられるまで五人は部屋から出ていない。その後もホテルと現場を往復できる時間は確保できていない。被害者をどうこうできる以前の問題だ」
「二十時四十三分に内側から解錠したのが被害者であることは疑いようもありません。ただ、このとき被害者ひとりだけが出たとは限らないでしょう?」
ようやく部下の言い分を理解した。「非常階段か」鷲見は電灯の眩しさに目を閉じた。髙橋は「ご明察です」若干、早口になりつつ続ける。
「被害者が解錠したついでに一緒に出たなら残る記録はひとつだけです。防犯カメラはエレベーターホールだけ。曲がった先の客室までは映せていない。だったら、客室のさらに奥にある非常階段も映せていません。幸い、あのホテルは非常階段関連に防犯カメラを設置していませんし内側からなら扉を開けられます。外からの侵入を防げれば良いだけだから内側からのセキュリティなんて設定されていないようでしたし。非常階段から出るときに何か噛ませておけば戻ってくるときにも使えます」
「仮に被害者の後を追って非常階段を使ったとする。じゃあ、帰りはどうするんだ? 非常階段で戻ったとしても部屋に入るにはルームキーで解錠する必要がある。残念ながら、次に女子部屋が開けられたのは二十一時二十九分、内側からだ」
髙橋の反駁を遮るごとく「それに」と続ける。
「一部屋に三枚のカードキーが割り振られていたわけだが、女子部屋に関しては、一枚は被害者が持っていたから残り二枚。三十分に外から解錠され施錠、三十二分に内から解錠され施錠。この記録は動かせない。三分間に三回開け閉めされたわけだが、同時にカードをセットして客室内の電気や換気のスイッチの役割を担うソケットからルームキーが抜かれた。これが三十分だ。三十二分時点、女子部屋にはルームキーが一枚もなかった。実際、事件発覚後に話を聞いたとき彼女たちは一枚ずつ持っていて、どちらも女子部屋のものだと確かめられた。被害者と同室に宿泊していた子たちがそれぞれエレベーターホールを経由して移動する姿が捉えられている。ひとりは一緒にいた男子のひとりと三十四分に宿泊階のエレベーターホール、三十六分には五階のエレベーターホールで捉えられ、もうひとりは三十二分の行きと三十六分にペットボトルジュース片手に戻る姿が捉えられている。後者の子に関してはその後、男子部屋に入れてもらったと話していただろう。女子部屋がしばらく解錠されなかったのは」
「彼らが共謀してたら?」
「何人で?」
腕を組んで挑戦的な眼差しを向ける。髙橋は教師に怒られる前の小学生のような面持ちで沈黙した。
「そりゃあ、お前。被害者を除いて五人いたんだ。部屋のカードキーだってひとり一枚ある。協力すればいくらでもやりようはあっただろう。だが、それこそ机上の空論だ」
鷲見は髙橋に倣って、椅子を引いて向かい合うように座りなおした。
「人を殺すってのは重労働だ。面白半分にチャレンジするようなものじゃない。スイカ割りとはわけが違う。やろうと誘ったからって何人がそれに乗る? ネットで集めてないんだ。同じ学校に通うようになって偶然同じクラスになった子たちの中に、たった数か月のつきあいで誰か殺そうと共謀するだって? 馬鹿言うな。推理作家だってもう少しマシなストーリーを作ろうと頭を捻る」
部下の表情をよく確認する。目は逸らされているが、反抗の色はすっかり薄れている。鷲見は心の底から安堵した。
髙橋の話を聞いた上で、高校生たちを擁護できる隙を見つけて彼らに反論の余地を残せたことに安心した。髙橋の言うように、鷲見も、なんらかの抜け道を考えなかったわけでは無い。だが、話を聞く前から推測を進めてしまうのは恐ろしかった。特に、それが子どもの話であれば尚更だった。
かつて鷲見が他の所轄で経験を積んでいるころ、地区内で殺人事件が発生した。この事件でも初動はそれほどの成果は上がらなかった。だからか、当時の先輩や上層部の焦りは、青い鷲見にも伝わるほどだった。何度も何度も周辺への聞き込みを重ねた。その際、まだ小学生くらいの少女が「お巡りさんですか」鷲見を呼び止めた。厳めしい刑事よりもひよっこのほうが話しかけやすかったのだろうと納得し、どうしたの――そう言おうとした。しかし、直後「鷲見!」鋭く呼ばれた。
「ごめんね。今は急いでいるんだ。これ、ここの番号に掛けてくれたら君の話を聞けるから」
それだけを早口で告げて先輩がハンドルを握る隣に乗りこんだ。
ちょうど容疑者が浮上したころだった。今は急がなければならないんだ――心の中で言い訳した。
数日ほど、少女に話しかけられたことなど忘れていた。
容疑者の自殺未遂と他の有力容疑者の急浮上、警察署前の道路を挟んだ向こう側の歩道で彼女と邂逅するまでは。
渡した名刺の番号に通報は無かった。それは鷲見が知っている。少女は電話を掛けてこなかった。しかし、勇気を出して声をかけたそのときに対面で話すほうが改めて電話をかけるよりずっとハードルが低かっただろう。相手は小学生だった。親類や友達、顔が見える範囲の交友関係の中でしか電話を掛けるという行為をする必要がない環境だった。知らない大人に話しかけるだけでも相当緊張しただろう。怖かっただろう。それでも、声をかけた――けれど、話は聞いてくれなかった。
あのとき少女が何を証言しようとしたか、今となってはわからない……重要な内容だったのか、最初に浮上した容疑者を守る内容だったのか、真犯人を告発する内容だったのか……邂逅した少女の表情は、絶望に染まっているように見えた。
悪意でも憎悪でもない。しかし、鷲見は生まれて初めて背筋が凍るというものを経験した。冷酷な殺人犯でもなく狡猾な知能犯でもない、年齢が二桁になるかどうかすら曖昧な少女の表情に怖気づいた。
二度目は御免だ。
恐怖の根源は再発、ならばもう繰り返すわけにはいかなかった。
「ヤケを起こすな。ガキじゃないんだ。まずは、彼らの証言を待つしかない。違和感があれば、お前の仮説だって採用する気になるかもしれない。関東からの報告を待とう」
「わかりました。すみません」
「馬鹿野郎、仮の話だったんだろ。謝るな」
「……はい。大城さんと望月のほうに期待ですね」
気を取りなおしたのだろうか、髙橋は両腕を持ち上げて思い切り伸びをした。
07
九時五十五分。
由弦が待機していると、五人は揃って約束五分前に指定したカフェに姿を現した。
「すみません、お待たせして」
軽く頭を下げたのは、久藤帆恭――熱海の警察署で由弦に話しかけてきた少年だ。彼に倣うように他の四人も頭を下げる。
「こちらこそ、急にすみません。なかなか動く気力が貯まらなかったもので……いそがしいところ集まってくれてありがとう」
軽く自己紹介を済ませ、飲みものの注文を完了する。
由弦が向かい合って左から、佐々木順也、久藤帆恭、園田彩結、古舘実幸、堀本理仁が席についている。いずれも表情は強張っていた。
「決して怒っているわけではないと言いますか……妹と一緒に旅行していた君らのことは少なくとも一切恨んでないです。六花が亡くなったのはあくまでも事故のようなもの、避けようがなかっただろうことは理解してます」
まず、由弦が口火を切った。それとなく敬語を和らげるのも忘れない。初対面でいきなり馴れ馴れしいと警戒される可能性はあるが、年長者がかしこまった対応を続けていては場の雰囲気が固まってしまいかねないだろう。
由弦の目的は、話を聞くこと――話せることを話せるような空間にするためには欠かせない配慮だと判断した。
「だから今日は、ただ、話を聞きたいんです。六花は海へ行くの初めてで、何よりも楽しみにしていたし、何より大好きな君らと行けるの嬉しそうにしてたから……学校では、同じクラスだったの?」
「はい。みんな同じクラスです」
佐々木が答える。ハリネズミを思わせる髪質だが、ジレンマなど知らないような純粋な明るさがある。
「出席番号で、自分が六花、さんの前の席に座ってます。彩結がその後ろです。んで、帆恭がその隣です。よく話すようになって、今回の旅行もその延長で一緒に行こうってなりました」
「前から佐々木くん、六花、園田さんの順だということかな。出席番号順なら、久藤くんは園田さんの右隣ですか?」
「はい」
「席が近いと話しやすいよね。あれ? だとすると、堀本くんと古舘さんは……同じ部活とか委員会とか、別のきっかけで話すようになったのかな?」
自然と堀本、古舘両名へ視線が集まる。恐縮が伝染したのか、古舘のポニーテールが小さく跳ねた。
「えっと……体育のとき……体育の時間に、六花さんから話しかけてくれました」
「あの子から?」
「やっぱり、珍しかったんですか?」
「いや、そういうわけじゃあないと思うけど……私とは違って明るい子だから、君には何て話しかけたんだろうって」
「それは……今思うと、よくわからないんですよね。古舘さん、名前なんて読むのって。体育で、しかも、シャトルランしてるときだったので、今? って、思いました」
「たしかにTPO弁えないこと多かったよね、ごめん」
「いえ、それが六花らしさでもあったと思います。理仁と私の席が近くて、それでいつの間にか六人でひとつのグループになって話したり勉強を教えあったりするようになりました」
正確に座席表を思い浮かべられたわけでは無かったが、仲良くなった経緯や垣間見える六花らしさが感慨深かかった。穏やかに「そうだったんだ」と言いながら瞳を閉じて一息ついた。
「休日もよく出かけてたんだけど、君たちと遊びに行ってたのかな?」
五人から肯定を返されて、由弦は「ところで、どうやって熱海旅行することになったの? 海の日が近いから海行くって言うのは妹から聞いたんだけれど」軽く首を傾げた。
「誰からともなく……ですかね。高校で初の夏休みだったので」久藤が言った。
「基本的に、行きたいところへ行こうって方針で決めました」園田が続ける。
「海に行くのがすんなりまとまって、交通を考えて熱海に決まりました。中日は海を満喫するとして、初日と最終日をどうするか相談しました。みんな行ったことない土地だったので、いくつか候補あげて、あとは多数決です」久藤が何度か頷きながら重ねて補足した。
「陶芸教室とか温泉とか体験するところも、美術館や起雲閣みたいな鑑賞する感じのところも、半々くらい候補挙がりました」自己紹介以来、はじめて堀本が声を発した。これに対して佐々木が「神社行こうって提案したら、伊勢神宮は却下されました」恨み節のようなものを吐く。
「伊勢は三重県だからね。熱海からは三百キロ以上離れてるよ?」
由弦が指摘すると、それみたことか、と言わんばかりに高校生たちの視線が佐々木に視線が集中した。旅行計画を立てるときも同じようなやり取りがあったのだろう。呆れた眼差しばかりだった。
「初日は終業式終わってから集合することになっていたのとチェックインが十五時だったので体力はあっても詰めこまないスケジュールにしようと決まりました。熱海に着いたらお昼にして荷物をホテルに置いたら起雲閣かトリックアート迷路館に行って、合流して夕食を外でとり、ホテルに戻り就寝。二日目は思いっきり海を楽しんで、最終日はホテルが十一時にチェックアウトだということもあり、前日の海水浴で疲れてると思ってのんびりしようということになって、来宮神社に参拝して熱海駅に戻って新幹線乗って帰ることになりました」
改めて代表するように久藤が二泊三日の旅程をまとめた。
「ちなみに、二日目の二十時五十七分は何かあったのかな?」
意を決して尋ねると、
「寝る準備してる頃だったんじゃあないでしょうか。その時間を気にされるのはどうしてですか?」
落胆を隠せない由弦を労わるような声色で久藤が問う。
当然、由弦は空振りの覚悟はしていた。想定以上に堪えてしまった手前、心なしか居心地が悪かった。
「……電話が、あったんだ。六花から。タイミングが悪くて取れなかったんだけれど何か知らないかと思って――それだけだよ。そうだ、せっかくだから最初から詳しく聞かせてほしいな。六花が楽しんでいたのか知りたい」
「終業式が終わったらすぐ帰って、十三時くらいの新幹線に乗って熱海駅行きました。たぶん、十四時前には着いてたと思います。ホテルのチェックインが十五時だったので、大きな荷物は駅のロッカーに預けてご飯食べに行きました」
「大きな荷物というと?」
「スーツケースとかリュックサックとかです。貴重品はショルダーバックやポーチにまとめたり、佐々木たちは手ぶらだったよね」
「うん、財布とスマホぽっけに入れてった。六花、さんも手ぶらだったっけ?」
「そう。白河さんも荷物リュックサックにまとめてきていたので手ぶらでした。そのとき二千円渡されて、足りなかったら後で追加で払うから持っててと言われました。でも、足りたので駅戻って荷物取りだしたタイミングでおつりは返しました。ちょうど十五時直後くらいだったのでホテルにチェックインしに行きました」
「理仁と実幸と自分が、迷路館ていうトリックアートのとこ行きました」
「私と白河さんと久藤くんは、起雲閣です」
「二手に分かれたんだ……六花、どうだったかな。理系科目のほうが得意だったけど、日本の文豪好きだったんだよね。たまに引用してた」
「そうだったんですね。起雲閣行きたいと提案したのも白河さんだったんです。入場してからずっと楽しそうでした。本当に、ずっと目キラキラさせてて」
「……旅館だったときに使われていた部屋もそれぞれの文豪をなぞらえて造られた部屋も、興味深く見てましたね。何度もすごいねって。本当、ずっとテンション高かったです」
「そっか、良かった。えっと、それで、合流の後は?」
「どっちも閉館が十七時だったので、十七時三十分に合流しました。そこの近くで海鮮が有名なお店があって、夕食を取りました。歩いてホテルに戻って……二十時くらいだったと思います。初日は、僕らは大浴場行って、すぐ寝ました」
「私たちも、三人で大浴場行きました」
「二日目は、九時半くらいにみんなでホテル出発して海行きました」
「親水公園のテラスで写真撮ったりして」
佐々木から由弦にスマホが差しだされる。表示されている写真では、六人とも満面の笑みだった。
そっと画面を操作して写真の撮影時刻を確かめる――九時四十三分だった。
「借りたグッズを設置して、海水浴しました。んで、十四時半くらいに近くのカフェで」
「待って? この写真、十時前だけど……ずっと海で遊んでたの?」
「はい。腹減ったら近くの売店とか自販機とかで買ってましたし。な?」
同意を求められ、ほかの四人も首肯する。
「ごめん、遮って……。十四時三十分に、カフェで?」
「食べたいモノ食べて、ホテル戻りました」
「四十五分くらいには着いたのか」
「たぶん、そうだと思います」
「十八時にホテルのレストランで夕食にしようってことだけ決めて、それまで自由時間でした。自由時間といっても、仮眠時間のようなものでしたけど」
「だな。理仁と帆恭に起こされるまでずっと寝てた」
「俺も直前まで寝てたよ。帆恭が帰ってくるときの扉の音でなんとなく目が覚めただけ」
「久藤くんもどこか行ってたの?」
「プリン買ってきてた。ホテル戻るとき、白河に会って一緒にエレベーター乗った」
「六花は何しに外出たか、わかる?」由弦は久藤に尋ねた。
「絵描いてたと言ってました。海の絵、見ながら描きたくなったからって」
「そっか。プリンって、どこか有名なところ?」
「熱海プリンです。かなり並んでいたので自由時間ほぼ使い切りました」
「暑い中、大変だったね」
「いえ。まあ、ご当地のお菓子、みんな食べたいだろうなって……。十八時に夕飯食べて、二十時前に部屋に戻って、みんなでプリン食べました」
「そうだね、二十時には私たち部屋に引き上げたから」
「男の子と女の子で分かれた後は、あとは寝ただけ?」
「いえ、その……いろいろあったので」古舘の視線が軽く泳いだ。由弦が軽く首をかしげると、園田がフォローするように「軽く汗ばんでいたのでシャワー浴びようってことになりました。古舘さんがダウン寸前だったので最初に、次が白河さん、最後に私の順です」と言った。
「古舘さん、大丈夫だったの? 熱中症か脱水症状とか?」
「いえ……眠かっただけ、です」
「あ、そっか。海で疲れたよね」
「はい。自由時間のときだけじゃあ足りなかったみたいで」
「この子が髪濡れたまま寝ようとしていたので、私と白河さんで協力して世話を焼いて、ベッドに寝かせました」
「そ、そうだったんだ……ありがとう」
「古舘さんが疲れてるのはわかってたから……。それで、たぶん四十分くらいに六花さんがシャワーを使って、私はその後だったので二十一時近かったと思います」
「五十五分とか?」
「正確には覚えてませんけど、まだ二十一時にはなってなかったと思います」
「その後は六花を見てない?」
「はい。シャワーを入れ替わりで使ったので」
「あの子、そのとき何かしてた?」
「え? 普通に、タオルドライしてたと思いますけど」
「そっか、そうだよね。えっと、その後はどうしたの?」
「私も自由時間はほとんど寝てたんですけど、夜あまり眠くなかったんです。でも、古舘さんはぐっすり寝てて六花もまた外に絵描きに行ってて、ちょっと手持ち無沙汰みたいな感覚でした」
「六花がそう言ったの? 絵を描きに行くって」
「いえ。私がシャワー使ってる間に出てたので、直接は……。自由時間のときも外に描きに行ってましたし。学校で、スイスにいたころ外で絵を描いてたら寝る時間過ぎても帰えらないまま描き続けてて怒られたことがあるって話を聞いたことあったので」
話ながら不安になってきたのだろうか、園田は視線を降ろして
「私があのとき探しに行っていたら」
「違うよ、大丈夫」
由弦は言葉を被せるようにごまかした。
「夜、眠くなかったんだよね? それで、どうしたの?」
「あ……えっと、久藤くんに電話しました。少し、話したいことあって」
「初日、ふたりは六花と起雲閣行ったんだよね? そのとき何かあったの?」
「あ、いえ、そういうわけでは」
「六花さん、旅行楽しみにしてたんですか?」
言いよどんだ園田に代わって、古舘が口を開いた。
「うん、そうだと思うけど」
「本当ですか?」
古舘は猜疑の瞳で由弦をみつめた。両隣の少年少女は労わるように不安そうに古舘を見つめる。
由弦は何も言わず、軽く首をかしげて先を促した。
「私……先月のはじめに、喧嘩したんです。いえ、喧嘩じゃなくて、私が一方的に怒鳴って……すごく悲しそうな顔、させました。悪いの、六花じゃないってわかってたのに」
「あの子がまた変なこと言ったのかな?」
古舘は強くかぶりをふってうつむく。その隣で堀本が「あの……」声を上げる。
「自分が、やらかしました」
この言葉について、体をよじらせて身を乗り出しながら友人らを見遣る佐々木を除いて、高校生たちは諦念のような息をついた。
「……恋路の、詫び寂び?」
「綺麗な言いかたをすれば、そうなるんですかね」
由弦の曖昧な予想に対して古舘は困ったように眦を下げた。
「高校生なら、思春期というか、そういう……ごめん、そのあたりの機微には疎くて。でもさ、なんだろう。ほら、愛は最良の教師だって言うし」
フォローにもならない何かを勢いで口走った。これ以上は経験の浅さを露呈させたくなくて「それに、どうにかするためだったんだよね、旅行は」乗った船を壊しかねない乱暴さで舵を切った。
幸いにも「余計なお世話だとは思ったんですけど、六花さんすごく落ち込んでいたので」園田が引き継いでくれた。
「初日に大浴場行ったとき、ふたり仲直り出来て……本当に安心して、久藤くんにも伝えておこうと思ったんです。廊下やロビーだとホテル側の迷惑になると思って、ふたりで五階のラウンジに行きました。他にも人はいましたが、騒ぐつもりはありませんでしたからそこで話してました」
「ずっと?」
「三十分くらいです。二十二時にホテルマンに叱られて、部屋に戻りましたから」
「二十一時三十二分です、電話。僕も部屋にいるだけで特にすること無かったのでエレベーターホールで合流しました」久藤が通話履歴を見せる。たしかに時刻は合っていた。
「それで、部屋に戻った後は?」
「あ、えっと」
「古舘さんがこっちの部屋いたので、園田さんも呼んで五人で話してました」
「あれ、寝ていたんじゃあなかった?」
「彩結のスマホのアラームが鳴って、目が覚めたんです。喉乾いていたんですけど備え付けの冷蔵庫には何もなかったので自販機に何か買いに行こうと思って……」
古舘は気恥ずかしそうに軽く身じろぎすると
「そしたら、あの……ほんとにバカなんですけど、ルームキーを持たずに出たのか何なのか、戻れなくなっちゃったんです」
「ああ、よくあるよね」
「本当ですか……?」
「うん。私も六花に何度か怒られたよ。家の鍵は閉めろ、って。今は財布にくっつけて忘れないようにしてる」
「なんだか、意外です。しっかりしてそうなのに」
「だらしなさが他のでカバーされているように見えるだけだと思うけど……。ああ、ごめんね。それが何時くらいだったの?」
「あ、はい! 彩結のアラームが、毎日掛けてるやつらしくて」古舘がそっと視線を向けると、園田は「二十一時二十五分です」丁寧にも、すぐにスマートフォンを起動させてスクリーンを見せてくれた。
「それで目が覚めて、三十分くらいに部屋出たんだと思います。あっ、そのとき彩結とすれ違ったよね?」
「うん。それで、ルームキー持ったか聞いたら首横に振ったから、私のカード持たせたんだよ」
「え、じゃあ、彩結はどうやって入ったの?」
「カードタッチしてから開けたままドアノブ離さなかっただけ」
「そうだっけ、あんま覚えてないけど……ああ、でも、そっか。みんなで集まったとき私が座った近くに一枚カードあったもんね」自分の言葉に納得するように頷くと「たぶん、そうですね。寝起きであまり覚えてないです。でも、私が座ってた近くにあったので、ポケット入れて忘れてたんだと思います」
「アラームを止めたのは古舘さんなんだよね?」
「はい」
「そのとき、園田さんは?」
「落ち着かなくて、廊下を行ったり来たりしてました」
「あっ。すれちがったとき、髪の毛まだ湿ってたよね。ドライヤー使ってなかったの?」
「寝てるのに起こしちゃうかなって、私髪短いからタオルでもちゃんと乾くと思って」
「全然使って良かったのに」
「だね。結局私のアラームで起こしちゃったし」
園田に何か言おうとしたが、やり取りを見守っていた由弦の視線に気がついて古舘は話を戻した。
「戻ってきたときは、カードキー持ってないと思ってて。一応探したんですけど見つけられなかったので、まず彩結に連絡しました。部屋にいると思ったんですぐ反応してくれると思ったんですけど」
由弦が「ラウンジに行ってたんだよね」確認すると園田が首肯する。
「古舘さんとすれ違ったとき、何か取りに戻ったの?」
「スマホを」と言う園田に対して「ああ、必要だね」由弦は同意を示して、再び古舘へ視線を向けた。
「なかなか出てくれなかったので、もういいやって思ってみんながいるほうにSOS出しました」
「グループラインに実幸が締め出されたって送ってきたので開けてみたら、本当にそっちの部屋の前でしゃがみこんでて」
「えーっと……二十一時三十七分です」
佐々木と堀本が答えた。「たしかにいろいろあったね」由弦は労わるように言った。
「その後……二人がラウンジから戻ってきた後は?」
「二十二時くらいに集まってからは部屋で話してました」
「誰か席立たなかったの?」
「お手洗いだけです。みんな五分以内には戻ってたと思います」
「グループにみんな男子の部屋のほういるよって流してたので、戻ってくるの待ってたんです」
誰が戻ってくるのか、聞く必要はなかった。
六人で旅行して五人が同じ部屋にいるのだから、足りないのはたった一人だけ。
簡単な計算だ。
残酷な事実だ。
静謐。
六人とも何も言いたくなかったために生まれた沈黙だった。由弦は年長者として、自らがこの集会を終わらせなければならないのは理解していた。
「警察から連絡を受けたのかな」
「いえ、違います。二十三時過ぎてると気づいたときにさすがに遅すぎるって心配になって探しに行きました。エントランス通ったら怒られると思ったので、みんなで非常階段から降りました。そしたら、近くでパトカーのサイレン聞こえて……」
久藤が弱弱しく言葉を切った。
「夜遅くだったのに探してくれたんだね。ありがとう」
由弦は静かに立ち上がった。
「今日はありがとう。私はもう行くけれど、みんな残ってて構わないから」
五千円札を置いて暇を告げた。
カフェを出ると、陽光に焼かれる。帽子を深くかぶり何度か瞬きをした。
同じかそれ以下の年齢層の男女が多かったが、上の年代は少ない。夏休みと平日が重なっているからだろう。それ以上深く考えるのはやめた。
目的もなくゆっくり歩く。まだカフェに戻るには早い。時間を確認せずともわかった。
「……」
ひとつずつ考えていく。
六花は殺された。明確な動機のもと、殺害された――これが前提だ。見知らぬ人間に偶然襲われたとは考えたくない。何のために死んだのかわからなくなるのは避けたかった……とにかく由弦は妹の死に納得できる原因が欲しかった。
一緒に旅行していた彼ら五人は、約束した五分前に一緒に姿を見せた。事前に集まっていたとしても、それほど猶予は無い。時間を守る力はある……二日目、言葉のとおり九時三十分にホテルを出発したのだろう。きりがいい時間だから誤差はともかく間違えることは無い。写真が撮影されたのは、親水公園ムーンテラスだった。九時四十三分には到着していた。熱海で対応してくれた担当者の話を考慮すると、ホテルから遺体発見場所までは十分前後で到着できる。
ここで問題になるのは、六花はどのように死んだのか……刑事は教えてくれそうもなかった。
他方、由弦は、ホテルで死んで現場まで運ばれた可能性は除外できると考察する。複数人が協力したとしても意識のない人間を運ぶのは骨が折れる。交通手段が徒歩しかないなら尚更だ。また、ホテルには防犯カメラが設置されており、観光シーズン真っ只中の海辺という立地のため宿泊者も多い。目撃される危険はあまりにも高い。そうなると現場付近で殺された可能性が大きい。ホテルから現場を往復して二十分、走れば十五分程度だろうか。
事件当日、二十時よりもあとに六花はひとりホテルを出た。
二十時以降に意識を向ける。
刑事は何も教えてくれなかった。ネットニュースにも、未明に遺体が発見されたとしか共有されていない。
六花からの電話があったのは二十時五十七分。六花のスマートフォンの緊急連絡を用いた警察からの電話があったのは四時四十一分。それぞれ履歴の残りかたが異なっている。
夜の電話は、ロックを解除した上で通話アプリから掛けられた六花本人によるものだろう。どのような状況下だったかまではわからないが、由弦は他者が掛けられるものでは無いと考えた。普通、パスコードは他人に教えるものでは無いのだから。
六花に何かがあったのは二十時五十七分より後だと信じた。
しかし、彼らの話を聞いてみて、どうだっただろう。
おそらく六花が由弦に電話を掛けたり部屋を出たりしたのは、園田がシャワーを使用している間だっただろう。湯船につかっているときならともかくシャワーを浴びながらでは電話を掛けられない。園田が最後に六花を見たのはシャワーを浴びる直前である二十一時前……電話はそれ以降に掛けられたのだとすれば、入れ替わったのは五十五分前後だと予想がつく。
タオルで髪の毛を乾かそうとしたりその他のケアをしたりした後で二十一時二十五分のときには園田はシャワーを終えて廊下を歩いていた。歩いていたとて、遠くへ離れたわけでは無かった。だから、部屋にもどってスマホを取り二十一時三十二分に久藤に電話をかけられた。二十一時三十七分に古舘が締め出されたと連絡したことも、時間的に無理はないだろう。
そこから二十二時くらいまで二人ないし三人で一緒におり、以降、五人はひとつの部屋にいた。誰かひとりの姿が見えなかったとしても五分ていど。
誰も十五分以上ひとりで行動していないらしい。強いて言えば部屋に戻った後の女子の行動は曖昧だが、三人のうちひとりが姿を消したのだから、論うのは無理がある。
古舘が眠りについて園田がシャワーを浴びているとき、六花には話し相手がいなかった。それで電話を掛けてきたのだと信じたかった。しかし、なぜひとりで部屋を出たのか理由がわからなかった。
そもそも、なぜ六花は夜遅くにホテルを出たのか。
近くのコンビニや自販機で軽食や飲みものを買うだけならスマートフォンか財布があれば十分だ。発見されたときスマートフォンと財布は持っていた。妹の遺体と一緒に確認した。しかし他の荷物は見つかっていない。荷物をまとめたリュックサックをもって出る必要は無い……六花もまた外に絵描きに行ってて……園田の言葉を思い出す。その日、外へ絵を描きに行くのは二度目だった。一度目のとき、海水浴を終えたあとの自由時間のときも六花はリュックサックを背負って絵を描きに行ったのだろうか。本当に?……こうしてハンカチとペンも入れておけば拭きたいときに拭けるし描きたいときに描ける……ジップロックに入れたトラベラーズノートとハンカチとペンがあれば絵は描けるのではなかったか。リュックサックまで持って外出する必要は無い。
仮に、あの五人全員あるいは一部が結託して六花を殺したのだとしたら……大した名優揃いだ……急に鼻で笑ってしまい、すれ違う数名の集団に睨まれた。
歩きながら勝手に考えているだけだが、急に居心地が悪くなった。
もう戻ろう――あの集団を追い越すのは気まずかった。引き返さない順路で件のカフェへ向かった。
入店しなおすと、高校生たちはまだ席にいた。
「あの」
「ごめん、スマホ忘れてってた! あっ、まだいて良いから。ごめんね」
すぐに立ち去ろうとして、足を止めてふり返った。
「また聞きたくなったら、連絡しても良いかな……?」
「でしたら、グループ作っておきます」
「本当? ありがとう!」
努めて明るい声で、再び暇を告げた。
今度こそ由弦は速足にカフェを離れた。信号の待ち時間で、ブルートゥースイヤホンを接続すると、両耳に押しこんで録音を再生する。
「行っちゃったね……優しそうな人で良かった」
「だな。ちょっと拍子抜けっつーか、なんか」
「わかる。私、正直、来るのめっちゃ怖かった」
「僕も。話聞かせてほしいって連絡来た夜、寝れなかった」
「俺も。何言われるんだろって」
「帆恭から連絡来たとき殺されるかと思った」
「とくに理仁はやらかしたからね」
「あれは、ほんとに……実幸、その目やめて。もう絶対やらないから!」
「六花にも言われたんでしょ? 大浴場で聞いた」
「マジでもうしません」
「ね。それ、俺、初耳なんだけど」
「佐々木くんは何も言わなくても来てくれたでしょ?」
「順也、余計なこと言いかねないし」
「じゃあさ、じゃあさ! もしかして初日に二手分かれたのも、そういう理由?!」
「それもあるけど……白河さんは起雲閣行きたいって言ってたし。佐々木くんはアクティブに体動かすアトラクションのほうが好きでしょう?」
「いや、否定はしないけどさぁ! 一言くらいあって良くない?」
「だから、言ってたらポロっと零してたでしょ。当事者には何も言ってないし」
「気づいてたよ、六花も。私ですらわかったんだもん…………ちゃんと謝れてよかった」
「ねー、待ってよ。どういうこと? 何があったの?」
「理仁がフタマタ掛けようとして失敗したの。そのしわ寄せが、私と六花に来たってだけ」
「おー……え、めっちゃしっかりやらかしてんじゃん、お前。もし六花が乗ってたらどうしてたん?」
「それは無いよ。六花、校外にいるし」
「いるって何が?」
「彼氏」
「そうなん?」
「名前呼び捨てにしていたから。誰って聞いたらお兄ちゃんのことって誤魔化してたけどさ。彩結も聞いたことあるでしょ?」
「ええ。何度か」
「お兄さんじゃないの?」
「そうかもしれないとは思ったけれど、ユヅルさんでしょう? だから、違うと思う」
「ピッピいるのに男女旅行オッケーだったってこと? それともスイスってそういう文化?」
「永世中立国から総攻撃受ける物言いやめたほうが良いと思う」
「前言撤回しまーす……でもさ、お兄さんに言わなくてよかったの?」
「学校外のことだもん。六花、ちゃんと教えてくれなかったし」
「まあ、そっか。曖昧なこと言わないほうが良いよなー。……んでさ、理仁はなんて断られたの?」
「その言葉は軽蔑する、って」
「おー。結構、辛辣なんねぇ」
「さすがに刺さった」
「純度百パーセントのまっすぐさだもんね、六花の言葉って」
「初会話がシャトルランだったのは初めて聞いた」
「ほんとだよ、もー。五十超えたくらいのタイミングだったからね? なんか近づいてくる人いるなーって思ってたら……ねぇっ、古舘さん! 名前なんて読むの?」
「ははっ、めっちゃ似てる!」
「もう一生忘れらんないよ、意味わかんなさすぎる!……もー、ごめん。なんか、やっぱダメだ」
「実幸」
「なんで六花だったの? 六花じゃなきゃいけなかったの?」
「……なんでっていうとさ、気になるよね」
「何が?」
「そうですね。お兄さん、どうして話聞きたくなったのでしょう?」
「どういうこと?」
「ライン交換して一日挟んでから、急に連絡きたんだよ」
「落ち着く時間欲しかったとか? 怒ってないって言ってたし、急には受け入れられなかったとか」
「でも、なんか無理してるように見えたよね。本当に怒ってなかったのかな」
「何言ってるの」
「通夜が行われるとしたら昨日か今日でしょう? 何もおっしゃいませんでしたよ」
「それは」
「家族だけで執り行うってこともあるよ」
「……そうだね、そういうことかな」
「あれ、お兄さんじゃない?」
「ほんとだ」
「どうしたんだろ」
「テレビドラマで見たことある。最後にもう一つってやつ」
「ドラマだろ?」
「ちょっと……!」
「あの」
「ごめん、スマホ忘れてってた! あっ、まだいて良いから。ごめんね。……また聞きたくなったら、連絡しても良いかな……?」
「でしたら、グループ作っておきます」
「本当? ありがとう!」
録音はここまでだった。ボイスレコーダーアプリを起動させたスマートフォンを椅子の上に置いていたから収音距離が不安だったが、問題なく聞き取れる音質だった。音声だけだが、声色や内容でなんとなく聞き分けられる。
卑怯な自覚はあったが、それを上回る成果だと思った。
話しているかぎり違和感は無かった。しかし、六花を取り囲む確執は存在していた。
今年の六月上旬。六花は、いきなり兄の部屋に入ると勝手にベッドを占領した。まだ就寝するつもりはなかったが、由弦は無視できなかった。それほど妹は明らかに様子がおかしかった。
「どうした?」
「……人間、好き?」
「何の問答?」
「私、人間好きじゃないかも」
ベッドに腰かけて、妹の身体を起こさせながら「学校の話?」確認がてら尋ねた。
「傷つくと思って……ううん、傷つけられると思って言葉を使った」
「どうして?」
「酷いことしたから」
「……」
「許すべきだった? ねえ、許せた?」
「事情がまったくわからないから結論は出せない。だけど……父さんを殺したやつを許せる保証は無い」
「……」
「クリスの感情と言動を否定できるほど大人じゃない。許したいなら許せばいいし、許したくないなら許さなければいい」
腕に預けられた頭部の重さは……
……温かさは今でも思い出せる。もう存在しないとは思えないほどの鮮明さは――不意に――刑事の質問を思い出す。無神経な問いに憤慨したが、思い出すきっかけになった。恨まれていたかどうか断言できるわけでは無い。妹の怒りも理解できる。同時に、逆恨みの原因にもなる。
あのとき許すよう諭していれば、殺される原因をひとつ解消できただろうか。
右腕に触れているだけの左手に力が入る。
六花の泣き声が聞こえていたのだと信じたかった。気づいたことに気づいてくれたと思いたかった。知らないふりをしてない、ちゃんと向きあってくれたのだとわかっていて欲しい。
すべて本人にはもう直接確かめられない以上、願うしかない。
「……」
知らないのだ、と。由弦は妹の本質を何も知らなかったのだと割り切ることにした。消去法をとるにしても解答群の中に正答が無ければならないのだ。
時間をかけて教科書を読み込めば自力で理解できる程度の読解力ならあるが、頭脳面における自身の平凡は痛感している。だからこそ、試行を重ねるしかない。非凡であれば瞬く間にすべてを解き明かしてしまうだろう。羨望は、ある。しかしながら、できないのだと自らの能力を理解している。考えるしかない。それが妹を理解するための最短距離に、自分なりの答えを見つける道標になると信じることにした。
何より――
「ねぇ、何見てるの?」背後からひっついてきた彼女に「眼鏡のフレーム」と答えた。
「壊れたの?」
「踏んだら戻んなくなった」
「寝ぼけてたの?」
「逆立ちしてたらバランス崩した」
「何してるの」
「眼鏡のフレーム探してる」
意味のない問答にすぐに飽きて、しばらくパソコンのスクリーンを一緒に見ていた。
すると「これ、良くない?」画面を指さした。
「赤って……なんか、なあ」
「大丈夫だよ、今までのも十分ダサいから!」
「……え?」
「え?」
「……」
「ごめん、あの……ごめんなさい」
「……」
「……ねぇ、なんで隠すの?」
「何が?」
「眼鏡」
「この国じゃ目立つから」
片方だけ頬を膨らませて、気の抜ける声を漏らす。頭を撫でながら言う。
「クリスには関係ないよ」
「無いの?」
「無いでしょ」
「たまに見たくなる」
そういうと、前に回りこんで膝に乗る。両手で顔を掴まれ、そのまま見つめ合う。
「おばあちゃんと同じ色でしょう? パパのこと思い出す」
「父さんと同じなのはクリスなのに?」
「鏡か自撮りじゃないと見えないもん。ゲンがいれば安あがり!」
華奢な妹の手を引きはがしながら「使いかた違うでしょ」文句をつけてみた。
「んー……便利?」
「はいはい、便利な下僕です」
「シモベ?」
「召使い」
「ふふっ――ワタクシ、空腹ですの。やきそばパンを用意なさい」
「あいにくパンが不足しております」
「あら。パンが無ければケーキを食べればよろしいのではなくて?」
「やきそばケーキはさすがに不味いでしょ」
「だね、頭悪いの次元が違う! だけどね、おなか空いたのは本当っ。作ろう!」
手を引かれてふたりでキッチンへ向かう。
「不思議だよね、おばあちゃんの名前もらったのは私なのにゲンのほうが似てるんでしょ? 先に生まれたから血が濃かったってこと?」
「さすがに現代科学に失礼だよ。減数分裂とか乗り換えとかで遺伝子の組み合わせの多様性が増すだけ。そのあたりの法則は未解明だけど……まだ生物でやってない?」
「細胞の話だけー、遺伝子はこれから!」
キッチンの電灯をつけて、ぱっと振り向く。
「さて。そんなゲンに中学生レベルの理科! 晴天はなぜ青く見えるか、説明できる?」
「太陽光がオゾン層で屈折したり散乱したりして、うまい具合に」
「そうだね、うまい具合に人間が見やすい波長の長い青の光が水晶体へ届き視神経が情報を脳へ運ぶからね。どれだけまっすぐ見つめようと、結局は曲げられた光を見るしかないの」
冷蔵庫から適当に食材を選んで取りだす六花を見つめる。
「ねえ、眼鏡はずしてよ。そうしたら、水晶体には何も干渉されていない純粋な光が届くよ」
由弦は何も答えず、フライパンを火にかけて油を引いた。作りたいものはなんとなく把握できた。必要な調味料を手身近なところに並べる。
「後は、網膜へ届くまでに光が屈折して、視神経が良い感じに帳尻を合わせて脳へ情報を送ってくれる。ただの透明なガラスを経ることないんじゃあない?」
「どうして」
「レンズに度が入っているなら、正面から見たとき屈折を確認できる。変なフレームに気を取られなければわかるよ。パパの真似っこでしょう?」
「……」
「違くても良いよ、どっちでもいい。私たちと一緒だよ、スイス人でも日本人でも、どっちでもいい。多様性が増すなら、はっきり分かれてるわけじゃないってことだよね? 気持ちだって考えてることだって同じだよ。わかってほしいわけじゃない、聞いて欲しかっただけ。まずはそれだけで良いんだよね!」
――どうやら妹のほうが妹として上手らしい。ならば、わからなくても仕方がない。
ふと『科学の價値』の著者を思う……水源は不明でも、やはり川は流れている……水が流れ始める場所やどうして流れるか説明できなかろうが、実際、川は流れている。ポアンカレは、論理より閃きに頼る節があった。行き詰った今、これに倣おう。偶然はそれを受け入れる準備ができた精神にのみ訪れる。
あの花が綻ぶ季節はもう二度と訪れない。
ならば、もう良い。
すべてを投げうってでもこの事件だけは、この手で必ず真相を解明する――そのためにもまずは――……帰宅するなり、由弦は必要だと思ったものをベッドに並べた。ただし、容れるものに困った。リュックサックは六花に課したまま戻ってきていない。警察署で見せてもらった持ち物はスマートフォンと財布のみ。リュックサックはまだ見つかっていない。
ふとシオンに視線が留まる。
首元のリボンが曲がっている気がして軽く整えた。それでも曲がっているように見えて、座りなおさせた。
満足してシオンの頭を撫でる。
結局、日常的に買い物に使っていたトートバックにベッドに乗せたものを押しこんで家を出た。
電車に揺られながら熱海駅行きの新幹線のチケットを購入する。待ち時間は生じるが、現状、持っている情報を整理するには有り難い。近くのカフェに入りコーヒー片手に、空いていた奥の席についた。
列挙するのはデジタルのほうが使いやすいが、整理したり考えたりするのはアナログのほうが好みだった。由弦は新幹線の時間の三十分前にアラームを掛けてから、クリップボードを開いてシャーペンを軽快にノックした。
クリップボードのポケットに詰めてきたルーズリーフ束の中に以前、六花に渡すために書いた歴史の解説が紛れ込んでいた。もう使わないだろうと、半分に折って一番下に入れなおした。
コーヒーを一気に嚥下してから――刑事からきいたこと、六花の友人らに聞いたこと、それぞれ比較しながら紙面を次々埋め尽くしていく――丁度良い頃合いでアラームが騒いだ。
ふと顔を上げた視線の先。
六花と同年代の子が目に留まった。夏休みの宿題なのか、問題集を進めている。歴史分野で苦戦を強いられているらしかった。
由弦は閉じかけたクリップボードを開きなおして、ルーズリーフを一枚セットする。六花もなかなか解けなかった問題の類題だ。すぐに解説をまとめられた。それを黙って当人に差し出し、何も告げずに立ち去った。
08
慣れない都会で人に酔いそうだった。誰も口を利かない息の詰まる車内にも酔いそうだった。望月は車外に打開策を探して――見つけた。
「あのっ、停められますか? すみません!」
「え、どうされました?」運転手を務める神奈川県警の長谷部は、意識だけ向けて尋ねる。
「今の人、彼!」
「見てませんでした、何です?」
「望月、何を見た。ちゃんと話せ」大城の低い声で指摘されてようやく自分の言葉を反芻した。幼い子どものような発言を恥じて、浮いた腰を助手席に戻しながら説明しなおした。
「たった今通りすぎたあのカフェから出てきたの、被害者のお兄さんです」
「夏休みが始まりだしてるのでその年代の人数多いんですけど、よくわかりましたね」
「特徴的な眼鏡をかけてるんです。それで、お兄さん。直前、何か渡してました」
「誰に?」
「店内の真ん中あたりに座っていた子です。私服なので何処の学校の生徒なのかまではわかりませんが、少なくとも被害者と同年代だと思います」
「関係者か?」
「わかりません。しかし、いつも班長から言われてます。気になること放置すんなよ、と……!」
後部座席の大城をバックミラー越しに見つめた。少しでも日和っていると思われたら静岡に送り返されない。決して視線を動かさないよう、ずっと頭で呪詛のように命令を唱え続けた。時代錯誤とも受け取れそうな頑固さに対抗するには、望月はこちらも頑固さを見せつけるしか方法を知らない。
「高校の場所、わかるな?」
「はいっ!」
「迷子なるなよ」
「っ、はい! ありがとうございます」
なんとなく察した長谷部は「次の信号、すぐそこです」とだけ言った。
その言葉どおり望月を降ろして、青信号を合図に車両は再び走り出した。
「良いんですか? 修桜高校、ここから結構キョリありますけど」
「走ってくるんだろーよ」
「はははっ、昭和ですか」
車内に沈黙が戻る。
不意に「ご不満そうですよね」長谷部がつぶやいた。バックミラー越しに一瞥されたのは気づいていた。大城は「元からです」とだけ言う。
「被害者の子、十六歳ですよ」
「……運転手役はさぞかしご不満でしょうね」
「とんでもない。事件待ちで暇していたところだったので」
「話し相手は関係者だけで十分でしょう?」
「他の県警と関わる機会、案外無いんですよ」
「望月を降ろしてからたぁ、さすがにあからさまです」
「震えてたので。可哀そうだと思ったんです。自分、人の親ですから」
「しょんないですな……。二十二と十九ですよ」
「やっぱり。ご不満の源はそこですよね。娘さんですか」
「いや、どっちも野郎です。そちらは」
「十五歳の男、十三歳の乙女です」
「それはまた難しい年頃で」
「後学に教えて欲しいですね、いろいろと」
「妻に任せきりだもんで。すみませんね」
「じゃあ、刑事視点なら良いですか」
「答えられますかね」
「……。被害者やその関係者に家族が重なるのって、もう避けようないんですか?」
「この年になっても無理だな、俺は」
「ははっ、そうきますか」
「特に同い年だと、な。長谷部さんの場合は、兄と妹ってのもクるだろう?」
「ええ。キますね。だから対処法聞いたんですけど」
「無い」
大城が即答すると長谷部の笑いが車内に響く。あまりにもはっきり逃げ道は無いと断言されればどうしようもない。むしろ悩むことそのものが面白可笑しくなってくる。
望月が合流したのは、担任教師に話を聞き終えた後だった。とはいえ、白河六花は部活動には未所属、学級内でも積極的に活動するほうでは無かった。加えて、担任は一学期のみでは生徒像を掴み切れていなかったらしい……誰にでも明るく平等に接する。試験勉強に真面目に取り組む……耳障りは良いが、なんとも当たり障りのない内容だった。
「すみません、遅くなりました」
「おう。お疲れさん」
「担任に話を聞き終わったところです。生徒さん、というか一緒に旅行してた子たちはこれからです。望月さんのほうは話、聞けましたか?」
「え……あっ、はい。被害者のお兄さんのほうはもう姿見えなかったんですけど、何か受け取っていた子はまだ店内にいたので」
「要点まとめろ」
「えっと、要点ないです」
「あ?」
「初めて会う人だから知らないそうです。受け取ったのは、なんか、歴史の年号推定のコツみたいなのをまとめた紙でした」
「初対面で渡すようなものか?」
「そもそも何なら初対面で渡す必要があるか想像つきませんが……問題の答えでは無くて、考えかたがまとめられてて、わかりやすかったです」
「それで。何年生だった?」大城が尋ねる。
「はい?」
「同年代に見えたが、私服だったからどこの学校かわからないんだろう?」
「あ……」
「顔はわかる。探せるから気にするな」
「……はい」
「おい」
「帰りません!」
「だったら切り替えろ。名前順で行く。久藤帆恭からだ」
「はいっ、翌朝まで父親が来るの待ってた子です。髙橋さんから聞きました」
「いつ?」
「さきほど、電話で」
「あいつ……」
「ひとまず移動しましょうか。三階だそうですよ、教室」
「ここじゃないんですか、聴取」
「学生相手だ。圧を掛けない配慮だ」
「圧を……」
望月の呟きに構わず、捜査陣一行は高校一年一組教室へ移動した。
09
「まったく、息子が御迷惑をおかけして申し訳ありません」
「こちらこそ情報が交錯してご不安にさせました。お詫び申し上げます」
父親の言葉に長谷部が労りをこめた人好きのする笑みとともに返す。当の久藤帆恭は教室の隅を見つめて動かない。
「緊張しなくていい。いくつか確認したいことがあるだけだ」
大城が言うと「はい」まだ声変わり間もないのか、低くなりきっていない声による返答だった。
「事件が発覚した後にホテルで聞かせてくれた内容と重複したらすまない。だが、なるべく正確に答えてもらえると助かる」
「わかりました」
「まずは……白河六花さんとはどのような関係だろう?」
「クラスメイトです。五月くらいに話すようになってから、仲良くなりました」
「仲良くなったから、旅行を計画したんだね」
「はい」
「旅行のこと、親御さんには」
「友達とは旅行すると聞いてましたが、異性がいるとは聞いていませんでした」
帆恭は答えようと口を開いていたが、先に父親が答えた。
「……。言いにくかったか?」
「別に。聞かれませんでしたから」
直後、反抗的な息子の名前を呼んで諫める。「お父さん、落ち着いてください」長谷部が言うと、父親は居住まいを正して両腕を組んだ。
「どうして旅行先を熱海にしたんだ?」
「みんなで遠出してみたいというのは中間試験くらいから……たぶん五月の半ばくらいから話していました。それで期末試験の最終日、海に行こうと方向性が定まりました。神奈川だと近過ぎて遠出した感じが薄いから、ほかのところを探しました。熱海なら観光地ですし、行ってみたいところも多かったのですんなり決まりました」
「光栄だね。じゃあ、初日から順に聞いていこうか。どこからなら話しやすいだろう?」
「初めからで大丈夫です。終業式の後、横浜駅集合しました。終業式自体は十時前に終わってたんですけど、ホテルのチェックインが十五時以降だったので、集合は十二時半でした。そこから新横浜駅で新幹線に乗り換えました。乗ったのは、これです」
帆恭はすらすら話しながらスマートフォンを操作し、画面を刑事たちに見せた。メール送受信アプリが表示され、オンラインで新幹線のチケットを購入した履歴が残っていた。望月は、よく確認して手帳の自分の文字と見比べる。新幹線の名前と発着駅、その時刻が一致している――事前に髙橋から、ホテルの男子部屋に新幹線の切符が二枚回収されたと聞かされていた。矛盾は無いらしい。
帆恭は望月からスマートフォンを回収して机の端に置くと、話を続けた。
「熱海駅ついたの、これ見たら十三時四十二分らしいです。正確には覚えてないですけど、十四時前だったのは覚えてます。新幹線でも飲食は軽くしましたがみんな空腹だったので、駅にスーツケースやリュックサックを預けて昼食にしました」店名と料理名を大城が尋ねると、店名はすぐに答えられたが料理名は「なんとかカツカレー」だと答えた。
「店を出たのが十五時前です。熱海駅に戻って荷物を回収したらチェックインしました。簡単に荷物整理を済ませたらホテルのエントランスで合流しました。そこから、僕と白河さんと園田さんで起雲閣へ行きました」
「あとの三人は?」
「トリックアート迷路館組です。体動かすほうが好きな三人に文化財のんびり見せるより良いと思いましたし、こっちの三人はゆっくりしたいのが集まったので賢明だと思いました。どちらの施設も十七時閉館だったのでそれにあわせてまた合流しました。近くの海鮮丼が有名なお店で夕食とって、歩いたのでホテルについたのは二十時くらいでした。初日で移動があったので、汗流してからすぐ寝ました」
「それが、一日目だね」
「はい。二日目は朝から十四時まで海で遊んでました。レジャーシートやパラソルを返却して、十四時半くらいに海が見えるカフェで遅めの昼食を取りました。名前は覚えてないんですけど、ナポリタン食べました。あとはホテル戻って、プリン買いに行きました」
「熱海プリンだね? ひとりで行った?」
「……。白河さんと行きました」
捜査陣は努めて父親を気にしないようにした。大城が「正直にありがとう」と告げて先を促す。
「初日のとき、ホテルへ移動しているときにちょうどお店の前を通りました。そのとき白河さんが気にしていたので……買いに行けるタイミング限られていましたし、僕から買いに行こうって約束しました」
「積極的だね」
「普通ですよ、これくらい。仲良くなかったら一緒に旅行しませんから」
「それもそうか。それから?」
「プリンが買えた後は、白河さんがお兄さんにお土産買いたいらしくて、平和通りを少し歩きました。気に入った栞を見つけられたみたいで、それを買ってからホテルに戻りました。鐘の音? チャイム、このあたりでも聞くようなタイプの音楽聞こえてきたので、プリンを買ったのが十七時過ぎ、ホテルに着いたのは三十分後くらいだったと思います。十八時くらいから夕食とって、部屋に戻ってからみんなでプリン食べました。僕らの部屋の冷蔵庫で冷やしていたので、そっちに集まってました。二十時には男女で分かれて、就寝準備進めました。シャワーを順に浴びてからは、しばらく男子三人で話してました。時計は見てませんでしたけど、隣の部屋からスマホのアラーム聞こえたりもしました。二十一時三十二分には園田さんから個人電話が掛かってきたので、髪の毛乾かしてスマホとカードキーだけ持って部屋を出ました」
ふたたびスマートフォンのスクリーンに通話履歴を映して、刑事らに見せた。何も指摘されなかったため納得してもらえたと判断したらしく話を再開する。
「エレベーターホールで合流してからはずっと園田さんと一緒でした。二十二時くらいまでラウンジで園田さんと話していたんですけどホテルの方に未成年は部屋に戻るようにと言われて部屋に戻ることにしました。もう寝ようかと思ってたんですけど、僕らの部屋に五人集まって話してました。二十三時くらいに、絵を描きに行ったきり戻らない白河さんを探しに非常階段を使って外へでてみたんですけど、そのときには通報があったみたいですね。公園近くに到着したときには、もう……」
言葉を失った息子に「大丈夫なのか」父親が不器用に尋ねる。
「……何が?」
「何がって……身近な子が死んだんだろう?」
「母さんが死んだときは無関心だったのに。息子が容疑者になったら急に家庭思いな父親面ですか?」
望月は内頬を噛んでやりすごそうと試み、大城と長谷部は似たような仕草で居住まいを正した。
「嫌なもの見せてすみませんでした。他に答えることってありますか?」
隣の父親を無視して、帆恭は刑事らに謝罪とともに頭を下げると逆に質問した。
大城は「いくつか、ね」と答えながら気を取りなおす。
「二十二時に部屋から戻ったときのことだ。五人ということは、その時点でもう六花さんの姿は無かったわけだね?」
「はい」
「二十三時になってから探し始めたそうだけれど、二十二時も結構遅いんじゃあないか?」
「遅いと思います」
「この時点ではまだ探そうとは思わなかったのかな」
「白河さんが絵を描くのが好きなのは知っていましたし、描いているときは邪魔されずひとりで描いていたいと聞いたことがありました。それに園田さんから、七歳のとき外で二十二時過ぎても描いていたら祖母に怒られたというエピソードを教えてもらって。それなら、ライン送っておいて戻ってきたら話すなり寝るなりしようということになったんです」
「探しに行くとき、非常階段を使った理由は?」
「二十二時のときに部屋に戻るよう言われたので、エントランスを通過したら同じようなこと言われて足止めされるかもしれないと思いました。なので、非常階段を使いました」
「ありがとう。最後にもう一つ。二十二時十五分ころ、五人で飲み物を買いに行ったね?」
「はい、エレベーターホールぬけた先に何台か自販機あったので」
「その後のことだ。六花さんを探しに行く前、誰か外に出なかったかい?」
「園田さんです。時間見てないので正確にはわかりませんけど、戻ってくるまで五分か十分くらいだったと思います。戻ってきたときに三回ノックするよう伝えていたので、また内側から開けました」
「忘れものをしたのかな」
「いえ、お手洗いだと言ってました。彼女、ラウンジ行ったときからカバンは持ってましたし、カードキーも持ってたとは思いますけど……」
「なるほど、親切だね。いまのところ、これでこちらからは以上だ。帆恭くんからは何かあるか?」
「……犯人、見つかりますか?」
大城は「最善を尽くしている」静かに答えた。
***
父親の到着を警察署で待っている間、帆恭はその青年を見て直感した。
会う機会はなかったが――白河六花の兄だ――雰囲気でわかった。「あのっ」何も考えず、声をかけた。ぼんやりと体を向けてくれたが、視線は定まっていない。ひとまず、一緒に旅行していたうちのひとりだと名乗った。青年は白河由弦だと名乗り返してくれた。
帆恭は栞を差し出した。
「これ……六花、さん。お兄さんにあげるって言ってたんで」
「六花が……?」
「二日目、一緒に熱海プリン買ったときに僕の荷物と混ざって渡しそびれて、それでそのままに」
「みんなで買いに行ったの?」
「あ、いえ……」
「プリンはみんなで食べたの?」
「はい、夕食後に部屋に集まったときに」
それまで曖昧だった視線が栞を捉える。
すると青年は「ありがとう」初めて目を合わせてくれた。長めの前髪ととんでもなくユニークなフレームの眼鏡でわかりにくかったが、青みがかった瞳は紛れもなく白河六花の兄だと証明してくれた。
自分のように他の子の荷物に妹さんのものが紛れていたら連絡取れなくなるから。
これを理由にして連絡先を交換する。
「何かあったら、連絡ください」
帆恭はしばらく会釈を残して立ち去るその背を眺めていた。
六花が久藤に持たせたのは、千円札一枚、百円玉二枚だった。
「六人分でしょう? 熱海プリン、ひとつ四百円だって。この服、ポケットなくてさ」
花柄のワンピース姿で腰辺りを軽く叩いて見せた。片手にはジップロックがある。他のメンバーに悪いから、絵を描いていたと言い訳するために持ってきたという。
「割り勘にしようよ。そうすれば楽しい時間も半分こで納得できるでしょ?」
買いに来たのは良いものの、想像以上に長蛇の列だった。炎天下の中では大変だからと近くの商店街へ避難しているよう伝えて、帆恭は並び続けた。まもなく戻ってきた六花はジップロックの他、コンビニで買ったアイス二つと、海が描かれた栞を持っていた。
「お兄さん、海好きなんだ?」
「ううん。これは絵が不発だったときのスペア」
「不発って、なにそれ。白河の絵、うまいじゃん」
「ありがとう」
笑いかたは兄妹でそっくりだった。
***
「心臓、止まるかと思いました」
望月が真剣につぶやくと、長谷部が軽快な笑い声をあげた。
知らない土地で初対面の刑事に協力してもらう運びに文句は無かったが、望月は緊張していた。しかし、車両移動の時点で、長谷部の人柄を知ってだいぶリラックスしていた。
「……大袈裟とは言わないんですね」
「実際、かなり耳は痛かったですから」
何のことか見当がつかない望月は大城を見遣るが、彼もまた気難しい表情をしていた。
首をかしげながら席を立つと「あの……次の子、呼んできます。佐々木順也くん」居心地の悪さを忘れようと、そそくさと退室した。
たおやかな女性が「よろしくお願いします」深く頭を下げた。その隣で、真似するように佐々木順也も頭を下げる。
「いえ、ご足労お掛けしました」
「主人の都合が合わず私のみなのですが、問題ございませんでしょうか?」
「もちろん、ありません。未成年者単独の聴取ができませんもんで、ご協力感謝します」
恐縮を言葉にする彼女に着席を促し、順也も座らせた。
どこか浮足立っている少年に対して「緊張しなくていい。いくつか確認したいことがあるだけだから」手順どおりに進めていく。
「わかりました!」快活な返事だった。無意識に長谷部は若干笑みを深めた。
「事件が発覚した後にホテルで聞かせてくれた内容と重複したらすまない。だが、なるべく正確に答えてもらえると助かる」
「はい、変なこと言ったらすみません」
「できるだけ正確であれば助かる。まず、白河六花さんとはどのような関係だろう」
「クラス同じで、前後の――僕があの席で、白河六花さんがすぐ後ろの席です。あっ、出席番号順のときだけです」
「よく話していたのかい?」
「はい。うるさくし過ぎて何回か先生に怒られました」
「ほどほどにね。ところで旅行のこと、親御さんには伝えたか?」
「はい、言いました。ホテル泊るのに同意書、書いてもらわなきゃいけなかったので」
「なるほどね。ホテル側に提出したのは確認済みだ」
「ほんとですか! 全員分ですか?」
「ああ。六人とも提出してあるのを確認した」
「へー、すっげーすね!」
「順也……」
「はーい」
「ちなみに、すんなり許してもらえたかい?」
「はい。変なことしないならって」
「変なこと?」
「わかんないです。何って聞いたら、わからないなら良いって言われたんで」
「……」
思わず捜査陣の視線が女性へと視線が流れる。彼女は小さく謝罪を口にした。
「他に同性が二人いればこの子が何かしても取り押さえてくれると思いまして」
「そうでしたか。ありがとうございます。――熱海に決めた理由は覚えているかい?」
「海ですね! 海の日近かったので! 刑事さん、山派ですか?」
「どちらかといえば、かな」
「ヤマハ、静岡ですもんね!」
「順也っ……すみません。落ち着きが無くて……ジュン、いい加減になさい!」女性の雰囲気が一瞬で極妻に近くなり叱りつけた。順也は「はいっ、ごめんなさい」姿勢を正した。
「よーし、本題に入ろう。終業式から帰って、まずどこへ何を持って行ったのかな?」長谷部が気を取りなおすように軽く手を叩き、尋ねた。
「横浜駅にリュックサック持って行きました」
「時間はわかるか?」大城が問いを重ねた。
「十二時二十五分です。俺が着いたの最後だったんで、そのままプラットホーム移動しました。新幹線乗り換えて、熱海着いたらハンバーグ食いました。おいしかったです!」
「それは良かったな。その後は?」
「ホテルで、部屋に荷物置きました。んで、俺と理仁と古舘で迷路館行ったんです! あれ、めっちゃすごかったです。やばかったです!」
「そしたら?」
「海鮮丼食って、ホテル戻って、風呂入って、寝ました!」
「その日、何か……驚いたことや怖かったことはあったか?」
「いえ、何にも」
「そうか。じゃあ、翌日は?」
「九時半くらいから海水浴してました。オムライス食ったら眠くなってきて、ホテル戻ってから爆睡してました」
「何時まで寝ていたか、わかるかな」
「十七時五十分くらいじゃないかと思います。帆恭と理仁が起こしてくれたんで。寝起きでホテルのレストランで飯食いました。戻ったらプリンあるってんで、めっちゃテンション上がりました! なんか、帆恭が六人分買ってきてくれてたんです! やばかったです、バカ美味かったっす!」
「その後はどうしたんだろう?」
「女子たちが一旦、部屋に戻って。男三人でいろいろ話したりしてました」
「話していただけかな?」
「え? あっ、寝る準備! 大浴場行くのダルかったんで、部屋のシャワー使いました。帆恭と理仁が一番譲ってくれました。あっ、そうだ。あとはもう寝るだけってなったとき、帆恭が部屋出てっちゃいましたね」
「時間はわかるかな?」
「えーっと……二十一時三十二分って言ったと思います!」
「誰が言っていたんだろう?」
「帆恭です。今日、六花の兄さんに呼び出されて色々話したんです、そのときに」
「……何時だ? 今日の」
「十時です。五人ともビビり散らかしてたんですけど、優しかったですよ」
「彼に何を話しだんだ?」
「刑事さんたちが聞いてきてるのとあんま変わんないです。妹は楽しそうだったか、とか。そういった感じで、怒ってないし恨んでないよって」
刑事たちが纏う雰囲気の変化を感じ取ったのか「あの……マズかったっすか?」肩身を狭くする。
「いや。君は気にする必要は無いよ」
「ですけど」
「そうだ、続きからいいかい?」
「わ、わかりました。あの、俺、あとは部屋で話してて……一回、二十二時過ぎにみんなで飲み物買いに行って、それで……」
「その後は?」
「……二十三時過ぎ、非常階段降りて、それで、あの…………パトランプ、光ってる場所まで行きました。お巡りさん立ってたんで、知らないか聞こうとしました。そしたら、いろいろあって、まあ、結局……六花かもしれないって」
「話してくれてありがとう。こちらから聞きたいことは以上だ。君のほうからは何かあるかい?」
「六花殺したやつ、捕まりますよね?」
「そのために最善を尽くしている」大城は似たような言葉を繰り返した。
***
「もう行っていいよ、いらない。邪魔」
しばらく走った車内、人通りが消えたところで佐々木順也は冷たく言い放った。隅に縮こまるように座っていた女性が大きく肩を震わせる。
「しかし」
「何? ああ、横領? 黙っといてやるよ。あと貸し九だな――ふははっ、おめでとう! ようやく一桁じゃん! 長かったねぇ、田中ぁ」
「ありがとうございます!」
「さっさと消えろよー。邪魔っつったよなぁ?」
女性が一目散に逃げだすと、再び車は走り出す。
しばらくして運転手が口を開いた。
「僭越ながら、あの女はイガラシです」
「で?」
「いえ、失礼いたしました」
「あー、そうだ。田中ぁ」
「はい」
「新しいおもちゃ、探しといた?」
「はい? 見つかったからもう探さなくていいとお話されていたと記憶しておりますが」
「あー。うん、言った言った」
「お気に召されませんでしたか?」
「違う違う」
「でしたら」
「なんか壊れた」
順也はあくびまじりに答えた。
***
望月は自分の両頬を強く叩いて「次の子、呼んできます。園田彩結さんです」駆け足で教室を後にした。佐々木順也のおかげで気が緩みそうになったらしい。
「若いっすね、彼女」
「経験が浅いだけですよ」
「同じようなものでしょう」
長谷部と大城の会話は廊下の先には届かなかった。
「園田彩結と申します。こちらは母です。よろしくお願いいたします」
母親よりも落ち着き払った少女が頭を下げた。
「こちらこそよろしく。緊張する必要は無いから、いくつか確認させてほしいだけだ」
「はい、善処します」
しっかりした子だと感心しながら、笑みを返した。
大城に代わって望月が質問役を担当する。
「いきなり本筋から逸れて悪いのですが……今朝、白河六花さんのお兄さんと落ち合って話をしたそうですね?」
傍らの母親がそっと彩結の腕にふれた。消え入りそうな声で娘の名を呼ぶ。
「心配なさらないでください。私は答えられますから」
彩結は労わるように母の手を取り、刑事をまっすぐ見据えた。
「はい、白河さんのお兄さん――ユヅルさんとお話しました。それが、私たちが示せる最大の誠意になると思いました」
「誠意というと?」
「六花さんが亡くなったのは、まぎれもなく私たちとの旅行中のことでした。どのような原因であれ、私たちの責任は免れません。もっと早く動き出すべきだったと悔やんでも悔やみきれません」
「どのような話をしましたか?」
「旅行の様子についてです」
「詳細は」
「本題へ移ろうか」大城が我慢しきれず遮った。望月が肩を跳ねさせた。
「彼に話した内容を我々にも教えてくれれば良い。さて、白河六花さんとはどのような関係だろう」
「友人です」
「仲が良かった?」
「……六花さんは明るくて素直だったので、誰とでも親しかったと思います。私は彼女の後ろの席だったので幸運に恵まれただけです」
「幸運か」
「おおげさな表現ではありません。心から幸運だと思っています」
「旅行のこと親御さんには伝えてあったのかい?」
「はい。男の子がいることも話して、説得しました。ホテル側に提出する親権者同意書を書いてもらわないと宿泊できませんでしたし、先に話しておいたほうが良いと思いました。熱海旅行、どうしても行きたかったので」
「何か思い入れがあるのかい?」
「いえ、そういった大層なものでは……高校生になったら、夏休みに友達と旅行したりお祭りに行ったりするのだと漠然と考えていて……ありきたりですけど、青春できると良いな、と。そう思ってました」
「そうだったんだね。じゃあ、さっそく初日から順に教えてくれるかな?」
「えっと、どこからですか? 熱海着いてからですか?」
「話しやすいところからで構わない」
「それなら……そうですね、終業式後からにします。白河さんのお兄さんに話した内容も、このあたりを含んでいたので。新横浜駅発の新幹線の時間に合わせて横浜駅に集合しました。六人とも定期が横浜駅を経由していたので……」
彩結は一度言葉を区切ると「あの、お兄さんにはここまで詳しく言ってないんですけど、どれくらい詳しいほうが良いですか?」不安そうに質問した。
「お兄さんが知っていることを不足なく知りたいのが大前提だ。余分な情報があるのは構わない。可能なかぎり正確かつ丁寧にお願いしたい」
少女は「わかりました」神妙にうなづき、言葉を続けた。
「新幹線で熱海駅に着いたのは十三時四十五分くらいだと思います。少し遅めの昼食をとってチェックインしました。荷物が多かったので、その前後で駅のコインロッカーに荷物を預けました。それで、あの、このとき白河さんは貴重品持ち運びようの鞄を持っていなかったので、会計用にと二千円をうけとり、チェックインしてからおつり分を彼女に返しました」店名と料理名を尋ねると、どちらもすんなり答えた。
「提案したの、私だったので」
「そうだったんだ。それで、チェックインしておつりを返した後は?」
「疲れて帰った後にやることが少なくて済むように、スーツケースから着替えやスキンケア用品を出しておきました。鞄に貴重品がちゃんとそろっているのを確認して、エントランスへ行きました。ほとんど待たずに男の子たちも来たので二手に分かれて出かけました。私は、白河さんと久藤くんと一緒に、路線バスに乗って起雲閣へ行きました。白河さんが行きたいといっていたところで、終始楽しそうにしていたと印象をお兄さんに伝えました」
彩結は曖昧に目を細め、閉じた。軽く息をつくと再び目を開けて大城を見つめながら話す。
「十七時の閉館まで楽しみ、迷路館へ行っていた三人と合流して夕食を食べました。バスに乗って戻ることも考えましたが、古舘さんが満腹だから乗り物あまり乗りたくないと早めに言ってくれたので歩いてホテルに戻りました。二十時ころに部屋に到着し、そこから大浴場へ行きました。少し疲れてましたけど、せっかくなら旅行しているって感覚が欲しかったので。白河さんと古舘さんと私の三人で行って、飲みものを買ってから部屋に戻りました」
「何を買ったか、覚えているか?」
「缶コーヒーです。白河さんと園田さんはテトラパックの飲み物だったと思います」
「起きているつもりだったのか?」
「いえ、明日用に。ホテルサービスで冷蔵庫に入っていたお水は三人で飲み切っていたので、朝から慌ただしくするより買っておいたほうがいいと思いました。私、お恥ずかしながら朝に弱いもので……」
「なるほど、懸命だ。その後、初日は何かあったかい?」
「それは、まあ、はい。次の日が朝から海の予定だったので早めに休もうとは話しましたけれど、夜の楽しみも欠かせないじゃないですか。私のスマホのアラームが鳴るまででしたけど、楽しかったです」
「アラームというのは? 時間制限を掛けていたのかな」
「普段は二十二時には電気を消してベッド入るので、目安として二十一時二十五分に毎日掛けてます」
「旅行中もずっと掛けていた?」
「初日に設定切ってないことに気がついた、というほうが正確です。結局そのままにしました。音量あまり大きくありませんし、スヌーズにしなければ一回止めれば済みますから」
「それもそうだね」
「これが一日目です」
一度言葉を切ると「二日目は」静かに続ける。
「九時三十分にホテルを出発して、海へ行きました。親水公園ムーンテラスで海を背景に何枚か写真を撮ってから、サンビーチへ……シートやパラソルを借りて、適宜軽食や飲み物を近くで買ってきて、そのまま十四時過ぎまで遊んでいました。そこから片付けをして、近くのカフェに行きました。店員さんが勧めてくれたナポリタンを食べました。白河さん、そういうとき物怖じせずはじめましての人とも話せて……彼女が聞いてくれたんです」 彩結は目を細めた。
担任教師いわく誰にでも明るく平等に接する――白河六花への評価は、あながち表層というわけではないのだろうか……ふと思考に浮かんだが、大城は軽く膝を進めて少女の言葉に耳を傾けた。
「そのあとは、ホテルに戻って自由時間でした。私と古舘さんはすぐに寝てしまったんですけど、このとき白河さんは外に絵を描きに行ってたみたいです。ジップロックに小さめの皮革カバーのノートを入れていて、それだけ持って行ったみたいです。何を描いたかきいたら、彼氏さんに見せてからって言われました」
「彼氏?」
「あっ、恋人のことです」
「それはわかる。白河六花さんには恋人がいたのか?」
「そう、だと思います。クラスとか学校内ではなくて、校外だと思います。だから、あまり積極的には……そもそも白河さんが自身のことで自慢したり尊大な対応をしたりすることが無いので、自然と隠しているようになってしまっていただけだとは思いますけど」
「実際に姿を見たり紹介してもらったわけでは無いのかな」
「はい。お兄ちゃんのことって誤魔化されることもあったので、あまり聞かないようにしてました」
「彼女のお兄さんとは今朝」
「初対面でした。どことなく妹さんに似ていると感じました。ただ、お兄さんの名前はユヅルさんだと伺いました。白河さんが彼氏さんに使っていた愛称にとはまったく違いました」
「彼氏について、お兄さんには聞いたかい?」
「いえ、無理です。聞いてません」
「そうか」
「恋人の他にも、その……周りが白河さんを放っておかないことは、何度かありました。強く言い争ってる姿は何度か見たことあります」
「相手は知っている生徒さん?」
「……言わないといけませんか?」
「いや。構わない。そうだなぁ、絵を描いてきたと言っていたんだね、戻ってきた六花さんは」
「あ、はい。そうです。十七時四十分前だったと思います。夕食行こうって約束が十八時だったので古舘さんを起こして、用意を整えてからホテルのレストランへ向かいました。食事を済ませてから男の子たちの部屋に集まって、熱海プリンを食べました。自由時間のとき、久藤くんがみんなの分を買ってきてくれたそうです」
わずかに望月の表情が引きつったところを目敏く大城が捉え、軽く足を蹴って注意を促した。望月は不自然なほど背筋を伸ばした。幸い、彩結は記憶をたどるように空中を眺めたまま話を続ける。
「そのあと、少し明日のことを話していたのですが、明らかに古舘さんの眠気が限界でした。私たちも疲労感はありましたから部屋に引き上げました。これが二十時ころです。時計は見ていませんでしたが……寝る子は育つよって、堀本くんが古舘さんを揶揄って。古舘さんは二十時じゃん、小学生だよこんなの……なんて、そういうやり取りをしていたので覚えています」
「部屋に引き上げた後は何をしていたのかな」
彩結は大城を見つめながら答えた。
「まずは古舘さんの対応ですね。ひとまずシャワーを最初に浴びてきてもらいました。そのまま寝ようとしてしまったので、私が彼女の髪を乾かしていました。せっかくの旅行で体調不良になるのは可哀そうだと思ったので。最後に、私がシャワーを使いました。ホテルで待機しているときにお話したとおり、二十時四十分くらいだと思います。十五分くらいで済ませたつもりなのですが、このときには白河さんはもう室内にいませんでした。彼女がぜんぶ荷物持って出ていたというのは、古舘さんが寝てたのでメインの照明とベッドのところの常夜灯は消していたので暗くて気がつきませんでした。リュックサックひとつに納まるくらいの荷物で少なかったから……すみません、言い訳です」
「いや。君も疲れていただろう? 気を使えと言うには無理がある」
「……。疲れてはいましたけど、私、古舘さんほどではなかったので」
「そうらしいね。シャワー後、君は外出している」
「はい。落ち着かなくて部屋の隅で足踏みしていたのですが、やはり、ちゃんと話さないといけないといいましょうか、話しておきたいと思って部屋の外へ出ました。出たのですが、スマートフォン持ってないことに気がついてカードをルームキーに翳した直後に古舘さんもドアを内側から開けてびっくりしました。飲み物買ってくると言っていましたが、手にはスマートフォンしか持ってなかったので指摘したら、空調とか電気とか使うための扉付近のポケットから抜き取ったので、それを見送りました」
「ポケットからカードを抜き取ったのは君ではないんだね?」
「私一枚持っていたので。カードキー、二枚も持ち歩く意味ありませんよ……?」
「その後はどうしたんだろう?」軽く笑みを見せて先を促した。
「暗くてもスマホ置いたところは覚えていたので、手探りで見つけてまた部屋の外でました。そのとき、久藤くんに電話かけながらエレベーターホールに歩いて行きました。ちゃんと話したくて……五階に宿泊者が自由に使っていい場所がありましたので、そこで話しました。二十二時にホテルの従業員の方から未成年者は部屋に戻るようお叱りを受けたので、ふたりで戻りました。古舘さんはやっぱり眠かったみたいで。カードをどこかにやってしまったらしくて部屋に入れなくなったということを私に直接連絡してくれていたみたいなのですが、気づかなくて……。堀本くんたちが彼女を引きとる形で部屋にいれてあげてました。三日目は来宮神社に行ってもう帰る予定でしたから、少しくらい夜更かししても良いかと思いました。五人で自販機に飲み物を買いに行きながら六花さんが戻ってきたときに気づけるようグループチャットのほうにもメッセージ送って、部屋で話しながら待ってました」
「何を買ったか、覚えているか?」
「缶コーヒーです。昨日の夜に買ったのと同じです。このときはすぐに飲むためでした」
「ちなみに、ほかに誰が触ったのか、わかるかい?」
「缶コーヒーですか? あの日は……白河さんが開けてくれました。お恥ずかしながらプルトップを開けるの苦手なので普段から回して蓋を開けるタイプにしているのですが寝起きだったからか、なかなか開けられなかったんです。それを見かねたのか、彼女が、かして、と言って開けてくれました。」
「ありがとう。ちなみに古舘さんのルームキーはどうなったんだろう?」
「ポケットに入れていたみたいで。ベッドの上に、彼女が座ってた近くにありました。カードに番号が振ってあったので、それで男の子たちの部屋のものではないとわかりました」
「なるほど。ホテルに待機してもらっているときふたりとも部屋のカードを持っていたから、探す時間が無いように思ってね。さて……その後のことを話せるか?」
「……。二十三時が過ぎていて、さすがに遅すぎるということで探しに行くことになりました。知らない土地で迷子になってしまっただけなら、連絡が無いのは変ですし……すぐに非常階段で一階まで降りました」
「非常階段よりもエレベーターを使うほうが楽だし早いのではないかな」
「それは、そうだと思いますけど……二十二時の時点で私と久藤くんがホテルの方に注意をうけていたものですから、二十三時過ぎていたら、外へ探しに行くのを止められてしまいかねないと思いました。十五、六歳なので、どうしてもまだ子どもに見えてしまうのは避けられないことですが、怒られるとしても、白河さんを見つけてからじゃないと……。結局、ちゃんと見つけてあげられませんでしたが」
彩結は力なく俯いた。
「話してくれてありがとう。こちらから確認したいことは以上だ。反対に、こちらに伝えておきたいことはあるかい?」
「伝えておきたいこと、ですか?」
「言っておきたいことでも、何でも構わない」
「……白河さんはなぜ殺されてしまったか、わかりますか?」
「それを解明するため、善処している」大城は言葉を選んで答えた。
***
「白河さん、絵を描くの上手ですよね」
「ほんと? ありがとう、嬉しいな。園田さんに褒められちゃった♡」
ルーズリーフの落書きを見せながら六花は紙面の端に新しいイラストを描いていた。休み時間が始まってたった数分だけではこれほど描ききれないだろう。
彩結はペン先を動かし続ける六花の緩やかな笑みを見つめていた。
「部活は入らないんですか? イラスト研究会や美術部に入ったらきっとたくさん褒められますよ」
「んー、褒められたくて描いているわけじゃあないんだよね。なんだっけ、横向きに側転していたら上手になったよ、みたいな。そういうやつだと思う。あっ、褒めてもらえるのはとっても嬉しい! けれどね、うーん、なんだろうなぁ……ごめんね、何て言ったら伝わるかわかんない」
「ゆっくりで構いません。私、知りたいです、白河さんのこと」
「そう? じゃあがんばっちゃおうかなー」
六花は、はにかみを見せる。彩結も嬉しくなり「はい、是非」笑みを浮かべた。
「絵を描くのは、文字よりも伝えられるから。そういう感覚がある。ほら、おひさまかいて。って言われたときを考えてみて。ひらがなでも、カタカナでも、漢字でも、もちろんほかの国の言葉でも書ける。けれど、その言葉を知らないと……共通認識が知識として持ってないとわからない」
寂しそうな笑みを改めて、彩結の瞳をまっすぐ見つめる。
「絵なら、わかりそうじゃない?」
「共通認識が必要なのは、絵も同じでは?」
「……ほんとだ。論理破綻しちゃった」
二人とも朗らかに笑う。
「もう少し考えてみて、わかりそうだったら言ってみるね!」
六花は彩結にそう伝えた。
***
「なんだか混乱しそうです。一気に情報量増えたような……」
「泣きごと言うな」
「はい……!」
「それから」
「はいっ」
「うだうだやろうとするな。相手の集中力を考えろ。いくらしっかりしているように見えても子どもだ。ストレスが多いと体調やその後に影響する」
「はい、すみませんでした!」
望月は「古舘実幸さん、呼んできます!」勢いよく教室を飛び出した。
空いたままの扉を眺めていると、長谷部からの視線を感じて「何です?」端的に問う。
「いやあ、父親の背が大きく見えるなぁと」
「茶化さんでください」
「本日はどうぞよろしくお願いいたします」美人だが、咽そうなほど強く香りを纏う女性が、どこか突き放すような口調で告げた。
「よろしくお願いします。お掛けになってください」
望月は怯えているのを隠しつつ、長い髪をハーフアップにまとめる少女に視線を向けて「緊張する必要はありません。捜査上の手順で、いくつか確認させてほしいだけです」と伝えた。
「はい」
「いきなり本筋から逸れて悪いのですが……今朝、白河六花さんのお兄さんと落ち合って話をしたそうですね?」
「っ……」
「なんですって?」
実幸は小さく肩を震わせただけだが、母親が強く反応した。
「どういうことかしら。そういえば、今日はずいぶん早く家を出ましたね?」
「……良いか悪いか、わからな」
「悪いに決まっているでしょう? もう嫌だ恥ずかしい、警察の方のご迷惑になっているじゃないの。高校生なんですからもう大人として考えなさい」
「ですが」
「言い訳はおよしなさい」
「……」
「実幸さん」うつむいてしまった少女に、優しく呼びかけた。「私たちは知りたいだけです。あなたの言葉で教えてください」
すると実幸は口を真一文字に引き結ぶ。望月はただ辛抱強く微笑む。
「断れると思いますか?」
「何をですか?」
「一緒に旅行してた女の子が死んじゃって……そのお兄さんが、私たちに話を聞きたいって言ってきたんですよ……? 何言われるかわからなくても、行くしかないじゃないですか」
「実幸」
「お母様は黙っててください! あの日、迎えにも来てくださらなかった! 今日も、いつものように私の付き添いなんてマツナガに任せればよかったじゃない!」
「何を言っているの、あなたを思って時間を作ったのに」
「刑事さん!」
実幸は母親に向けていた鋭い視線を捜査陣に投げる。
「ホテルに提出した同意書、私だけ親権者欄の名字と違うの見ましたよね? まだでしたら確認してください。この人、どうせ私のことちゃんと見てないんですから!」
そこまで言い切り、肩で息をする。気圧されたが、望月は居住まいを正して向き直った。
「……まだ落ち着いて話せますか? それとも、後日にしましょうか?」
「すみません。話せます」
「こちらこそすみません、話すの怖かったですよね。勇気出してくれてありがとうございます」
「いえ……はい」
「では、質問していくので、たくさん教えてください! まずは、白河六花さんとはどのような――お母様、手順です。実幸さんを疑っているわけでは無くて、もれなく五人に聞いています」
「今からでもマツナガに連絡しましょうか?」
娘のその一言が効いたらしく、ようやく母親は付き添いとしての役割を全うしてくれることになった。
実幸はあらためて望月を見つめると、
「白河さんは同じクラスの友達です。四月に体育の時間に話しかけてくれて、仲良くなりました」
「部活などが同じわけでは」
「違います。そもそも六花さん、どこにも所属してません。放課後、教室でノートやホワイトボードに絵を描いていましたけど、どこにも入るつもりは無かったみたいです」
「何か事情が?」
「わかりません。ただ自由が好きな感じはしたので、そういうことかもしれません」
「そういうこと、ですか?」
「部活に入ったら、大会とかあるじゃないですか。イラスト関係の部活動いくつかありますけど、文化祭のとき必ず合作本作っているので、そういう縛られるのが嫌だったのかなって、ことです」
「なるほど、ありがとうございます。そういうことですか。あ……の、旅行について親御さんはぁ」
「さっきのとおりです。男女一緒でもどうだっていいんですよ」
「実幸」
「違うの?」
「……あとで話しましょう。早くなさい」
急に照準を向けられ、蛇に睨まれたように望月が肩を跳ねさせる。
「はいっ、あの、なぜ熱海に?」
「海行こうというのは前から話していたんですけど、海水浴するなら距離的にもちょうどいいのかと思いました」
「でしたら、次は、初日からどうだったのか教えてください」
「こだま……? 新幹線なんですけど、それに乗って数駅でした。ホテルにチェックインするには早かったので荷物はコインロッカーに預けて、遅めのお昼ごはん食べました」
大城が料理名を尋ねると、実幸は小柄な体躯をさらに縮こまらせて
「すみません、私名前とか覚えるの苦手で……オムライス食べたのは覚えてます。理仁と久藤くんがカツカレー、佐々木くんがハンバーグ、女子はみんなオムライスでした」
「よく覚えていますね」
「ぜんぶおいしそうだったので。私が一番食べ終わるの遅かったんですけど、みんなのんびり待っててくれて。ホテル到着したときにはもうチェックインできました。あっ、駅に荷物取りに行ってから、ホテル行きました」
「それぞれ荷物の量は違ったんですか?」
「そうですね。佐々木くんと六花さんがリュックサックだけで、理仁と久藤くんはリュックサックとボディバッグ、私と園田さんは小さめのスーツケースと貴重品持ち運べる肩掛けバッグでした」
「そうなんですね。では、部屋についた後は?」
「六花さんと園田さんがすぐ用意終わらせてて、もういいやと思ってカバン整理しないまま、スマホと財布とメイクポーチを持ったのだけ確認して、一緒に部屋を出ました。エントランスでちょっと待ってたら男子も降りてきたのでそれぞれ分かれました。私は理仁と佐々木くんと一緒に路線バスで迷路館へ行きました」
「六花さんと園田さんは起雲閣へ行かれてます。女の子ひとりで大丈夫でしたか?」
「それは、はい、理仁も佐々木くんもいたので楽しかったです。そもそも、どこ行きたいか話しあってるときに六花さんが起雲閣を推してたので、もうひとつのほう選んだら迷路館だったんです」
「どうしてわざわざ違うほうを選んだのですか? 人数が偏ってしまったとかではなく……」
「あれ? 誰も話してなかったんですか?」
「実幸さんから聞かせてほしいです」
わずかに視線を彷徨わせたが、やがて机の端を見つめる。
「三角関係――とまではいかなかったらしいんですけど、私の彼氏が、何でしょう、不誠実? みたいな。六花さんにしたかもって聞いて。それで、私と六花さんの仲が変になっちゃったんです」
「……それは、白河六花さんのお兄さんにも」
「一応伝えました、かなりぼかしましたものを。お兄さんは恋路のワビサビって表現してくれましたけど、本当に残念ながらそんな綺麗な感情を発露したわけではありません。ぐちゃぐちゃで曖昧な、変な色をした気持ち悪いものです。あの子にも恋人いるんだからありえないのに」
自嘲するようなまなざしを望月に向けながら、実幸は言葉を続けた。
「ホテルで待機してるときに園田さんや佐々木くんが刑事さんたちに渡してた写真見てもらえばわかると思うんですけど……かわいいんですよ、六花さん。かわいくて頭も良くて明るくて。積極的に前へ出るタイプでは無くても注目を集めやすかったと思います。隣から見ていたので、よくわかります」
視線を落とすと
「コンプレックス刺激され続けると、だんだん心が重たくなるんです。当初は話しかけて嬉しかったり笑顔かわいいなって思ったり、それくらいの感情が少しずつ少しずつ汚れていくんです。そういうことじゃないって心のどこかではちゃんとわかってて――わかってても、実際に違うのだとしても、溢れたら人に見えるようになっちゃ、て……」
ハンカチで両目を押さえながら細く息をついた。
「すみません。えっと……そう、ですね。私が、六花さんを突き放すようなことをしちゃったんです。それを不憫に思った周りの子が旅行を計画してくれました。あれです、その……仲直り大作戦です!」
明るい声で取り繕うと、顔を上げた。
「佐々木くんがお手洗い行ってる間に、学校でのこと、理仁から話題にして謝ってきました。園田さんからもいろいろ聞いていたんですけれど、ああ、やっぱりなって思って。もう二度とやらないって約束してもらって許しました」
「予想はしていたの?」
「二択で起雲閣を選んでいたら愛想尽きましたけど、違ったので。おかげで私も六花に謝る覚悟できたので正直、有り難かったです。閉館と一緒に出て、久藤くんが調べてくれてたお店でご飯食べてホテル戻りました。そのあと、せっかくだから大浴場行こうってなって、そこで六花さんに謝りました。裸のつきあいっていうじゃないですか。一番素直になれると思ったんです」
「仲直りはどうなったの?」
「無事にできました。六花も、帰り道に理仁から謝られてたらしくて。次あいつが何かしたら一緒に埋めようって……すみません。えっと、お風呂終わって、自販機でジュース買って、部屋に戻りました。それで」
「あっ」
「はい?」
「遮ってごめんなさい、自販機で何買ったか、覚えてますか?」
「えっと……イチゴミルクです、六花さんはそれの黄緑のやつ、園田さんは缶コーヒーでした」
「ごめんね、ありがとうございます。続き、聞きます」
「はい。ベッドが二つしかなかったので、私と六花でひとつのベッド使いました。六花さんが明かり点けたままが良いって言ったので、普段は電気消して寝るんですけど点けたままにしてました。謝れたことでスッキリしてて、いつもよりずっと早くに寝たおかげで海水浴はずっと楽しかったです」
「それは良かった。その後のことは覚えてるかな」
「晴れててとても海がきれいだったので、近くのカフェでご飯食べました。お店の人におすすめをきいて、みんなナポリタン食べました。それからホテル行って、十八時にレストラン前って約束して部屋に戻りました。はしゃぎすぎちゃって、六花さんと園田さんに起こされるまで寝てました。軽くメイクできる時間を考えて起こしてくれたんですけど、もう寝ぼけてて、下地とパウダーだけで部屋を出ました」
「何を食べたか、覚えてる?」
「ビュッフェスタイルだったのでみんないろいろたくさんとってました。男子は何回かおかわり行ってたのであまりわかんないです。基本的に二、三色で彩りは三人とも考えてなさそうでした。そう、お昼が遅めだったので、私たちあまりお腹空いてなかったんです。だから、私はあまり食べなかったんです。園田さんは和食っぽい感じでお米とかお味噌汁とかお刺身を選んでて、六花さんは黄色っぽいスープとバターロールかな? パン食べてました。あっ、お寿司あるよって勧めたらいくつか選んでました」
「実幸さんは?」
「あまりみないで選んだんですけど、たぶんゼリーです。あと、アイスとオレンジジュース」
「眠かった?」
「かなり」
「じゃあ、その後のことって、どうだろう……?」
「プリンおいしかったのは覚えてるんですけど、ほんとに眠くて。みんな私に合わせてくれたみたいで、部屋に戻りました。メイクと汗流して、そのまま寝ようとしてたところふたりが髪の毛乾かしてくれたらしいです。ユヅルさんに聞かれたとき、園田さんが教えてくれました。ああ、そうです。寝ていたら園田さんのスマホのアラームが鳴って、目が覚めました。喉乾いてたんですけど、冷蔵庫の中は空っぽだったので飲み物買いに行こうとしました。ちょうど扉開けたら園田さんがいて、あまり覚えてないんですけどカードキー受け取ったみたいです」
「どこにあったんだ、カードキーは?」
「どこっていうのは?」
「園田さんのカードキーか、空調とかのソケットにあったカードキーか」
「すみません、わからないです。園田さんから受け取ったらしいんですけど、そこまで注意して見てなかったので……それに、受け取ったのにどこにしまったかわからなくなってしまって……園田さんの反応しばらくなくて六人のグループのほうに締め出されたって送ったら理仁たちが何してんのって言いながらも部屋入れてくれました。ゲーム持ってきてて、遊んでいるうちに眠くなくなりました。あっ、そうですよね、二十二時。未成年だから戻るよう言われたんだって、園田さんと久藤くんが部屋に来て、そのまま六花が戻ってくるの待っていたら二十三時をすぎちゃったので、探しに行きました。でも……」
「仲直り出来たばかりだったのに、辛かったですよね」
「……はい」
「こちらから聞きたいことは聞けたんだけど、実幸さんからは何かありますか?」
「捜査、進んでますか?」
「えっと」
「止まってはいない。最善を尽くしている」
言い淀んだ望月に代わり、大城が断言した。
「犯人必ず見つけてください! 絶対許さない!」
***
「私は六花の引き立て役じゃない!」
「古舘さん……?」
掴まれた手を振りほどいて、叫ぶように拒絶した。それを後悔させられるほど、見ていられないほど悲痛な顔。乱れた感情に任せて振り上げてしまった拳。
実幸は、下ろせなくなってしまった怒りの逃げ場を見つけられず、その場から逃げ出すしかなかった。
少なくとも、六花にすべてをぶつけるという選択肢は霧散した。
覚悟が決まってからは、もう怖くなかった。できると信じた。
「酷いこと言ってごめん。六花がそう思ってないこと、ちゃんとわかってる。本当にごめんなさい」
何も隠さない。それが正解の関わりかたになるそう信じて、頭を下げた。すると、六花は実幸を抱きしめてくれた。抱きしめ返しながら、彼女の温かさに涙が出てきた。
大浴場の湯船につかりながら尋ねる。
「なんで私なの?」
他にも親子ずれを含む女性たちが多くいたけれど、勇気を出して尋ねた。
「なんでって? 何が?」
「話しかけてくれたの、六花だったでしょ?」
「同じ幸せだって、そう思ったから!」
「……六花はすごいね」
「ついに気づいちゃったか、秘められた邪眼の」
「違うよ。簡単に笑顔にさせてくれる」
「一緒にいてくれるからだよ。ひとりじゃないって教えてくれるから」
***
「あ、の……大城さん」
「おう。次で最後だ」
「……。はい、呼んできます」
さっきとはうって変わって望月は肩を落として退室した。長谷部が小さくため息をついた。
「こういうとき、自分はちゃんと気をつけます」
「何をだ?」
「伯父の江角です。妹夫妻は海外で活動しているのですぐに戻ってくるのが難しく、代わりに同席させていただきます」
軽く背を押されて「よろしくおねがいします」堀本理仁は伯父とともに頭を下げた。
「おかか」
「お掛けください」
長谷部のフォローに謝意を示して、両手で首筋を冷やし終えた望月は、ひとつ咳払いをした。
「緊張する必要はありません。捜査上の手順で、いくつか確認させてほしいんです」
「はい」
「いきなり本筋から逸れて悪いのですが……今朝、白河六花さんのお兄さんと落ち合って話をしたそうですね?」
「あ、はい。何か、法に触れますか?」
「いえ。ただ、何を話されたのか確認が必要です」
「そうなんすね」
「そうなんです。どのようなことを話しましたか?」
「あんまり話してないです。旅行どうだったのかってのがメインだったんですけど、久藤くんたちが主に説明してくれたんで、話さないといけないところほとんどありませんでした」
「堀本くんは、何を話しましたか」
「いや……大したことじゃないです、あまり覚えてないので」
「わかりました。続いて、白河六花さんとはどのような関係ですか?」
「関係っていうのは?」
「そのままの意味です」
「クラスメイトですよ、普通に」
「旅行をするのは普通ですか」
「言葉の綾です。ややこしいこと言って失礼しました。仲のいい普通のクラスメイトです」
「こちらこそ揚げ足をとるような問いでした。すみません。質問を続けても良いですか?」
長谷部が穏やかに仲介する。望月は大城に睨まれていることには気づいていたが、あえて胸を張って怯えているようには見せなかった。
「……はい」
理仁が肩をすくめるようにうなずいたことで聴取は再開された。
「旅行のこと、親御さんに伝えましたか?」
「親権者同意書のことですか? 海外いるので、データ送って返信してもらいました」
「女の子も一緒でしたよね」
「そういうの気にしてたら一人息子残して海外いきませんって」
「……。熱海旅行にした理由はありますか?」
「旅行したいって話は、結構前からありました。佐々木くんが、海の日近いからって海行こうって言いだしたことで形になった感じです。あまり遠すぎたら移動大変過ぎるじゃないですか。車出せるわけじゃないんで。いや、まあ身近な大人に頼めば可能だったとは思いますけど、友達だけのほうが絶対楽しいものだと思うんで。関東圏でいくつか候補あがったんですけど、せっかくなら少し離れているけど行ける範囲ってことで熱海に決まりました」
「旅程と、実際にどうだったか教えてください。どこからが話しやすいですか?」
「重要なのって、二日目ですよね?」
「本題からですか」
「だって、もう他の四人から聞いてますよね? それなら必要なとこだけで良いと思うんですけど。新幹線乗った話からしたほうがいいならしますけど。どうしたほうがいいですか?」
望月は、視線を送る。大城は軽くうなづいた。
「では、二日目の話をお願いします」
「九時半にホテルから海行きました。十四時くらいに片付けして引き上げて、カフェで飯食ってホテル戻ったら寝ました。十七時半くらいに目が覚めて、その二十分後くらいですかね。レストラン行くために三人で部屋出ました」
「ルームキーは?」
堀本は一瞬だけ宙に答えを探すように虚空を眺めた。
「持ってってないです。久藤くんが持ってたので。佐々木くんと俺のは基本的にずっとサイドテーブルの上か部屋入ってすぐの、あれの名前わからないんですけど、あそこに入れてたかのどちらかでした。ホテルで別行動するとしても、基本部屋いたので持ち歩く必要なかったです。話戻していいっすか?」
「はい。レストランへ向かった後は?」
「飯食って、部屋戻ったらプリン食べました。久藤くんが昼間に買ってくれてたやつです。女子たちが二十時に一度引き上げていったので、その後は寝る準備進めながらしゃべったり遊んだりしてました。時間見てなかったので正確なのわかりませんけど、二十一時半くらいに部屋出ていきました。佐々木くんと俺で、続きしてたら園田さんがグループチャットでヘルプ求めてきたので扉開けてみるとほんとにジュースのペットボトル持って女子の部屋の扉の前いたのでこっちの部屋入れました。一応。もう一回ほんとにカード持ってないか探してもらったんですけどね」
「ありませんでしたか?」
「そのときは見つかりませんでした。でも、あとでちゃんと出てきたので、探したりなかったんじゃないですかね」
軽く頭をかいた。
「えっと、まあ、しばらくしたら五人集まって白河さん戻るの待ってました。けど、二十三時過ぎて返信もリアクションもなかったので、非常階段使って外探しました。近くを少し歩いてみて探していたら、騒がくなってるところがあって、すぐ近くにパトカーも止まっていたので、そっち行きました……旅行中は、こんな感じです。なんか他、ありますか?」
「白河さんが校内でトラブルを抱えているか、聞いたことはありますか?」
「校内はちょっとわからないです。駅前で男と言い争ってるのは見たことあります」
「いつのこと?」
「たぶん、五月下旬くらいです」
「相手の男性の特徴は覚えてる?」
「遠目だったので……若かったのはわかりました」
理仁は曖昧に被りを振った。
***
「白河っ」
理仁は走り去ろうとする少女の手を掴んだ。
「本気だよ、俺は。本気で白河のこと好きだ」
「バカなの? 古舘さんは」
「心許せるのは白河だけだよ。隣にいてほしいのは」
「私の気を引くためだけだとしても……上辺の言葉だとしても、そういうこと言えるんですね」
氷のような言葉に怖気づき、思わず手を離した。
「心より軽蔑申し上げます」
振り向いた少女の微笑みは、絵画のような美しさだった。
「古舘さんには謝ったの? 許してもらえた?」
謝罪するなり、六花は理仁に問う。
「二度目は無いって条件付きで」
「もー。ほんとだよ、二度目は熱海の海岸に埋めるから! いや、移動が大変だ。どこがいい?」
「埋められたくないからもうしない」
「ほんとに? いざとなったらアスファルトだよ?」
首をかしげる少女が生身だと安心して「仰せのとおりに」と返した。
***
「大したことないって、二股掛けようとしてたことですよね?」
明らかに憤慨する望月を長谷部が笑いながら窘める。
「望月、私情だ」
「大城さんには無いんですか?」
「あるよ。だが、捜査とは分けろ」
「……はい」
「今はそれよりも頭痛くなるくらいに考えなきゃならんことがある。気合入れなおせ」
「確認したいことは確認できましたよ? あ、久藤帆恭くんに白河由弦さんに何を話したか、まだ聞けてないですね」
「それもあるが……今は良い。署に戻ろう。細かいこと考えるのは鷲見さんらに共有してからだ」
「今日中に戻りますか?」
「じゃないと旅費がかさむからな」
大城の言葉どおり、二人の刑事は長谷部の運転で横浜駅まで送ってもらった。初めての関東に名残惜しさを隠せない望月を無視して、大城は軽く頭を下げる。
「どうも。世話になりました」
「いえ。聞きこみはこちらでも続けますから情報はお伝えします。今度は観光で、是非」
「隠居してからになりそうなもんです。では」
二人の刑事は横浜発熱海行の新幹線に乗りこんだ。
「あの、さっきの。考えないといけないことって何ですか?」
「公共の場だろ」
「考えてみたいんです」
「被害者の恋人はどこにいる?」
「え? でも、堀本くん、被害者が若い男と言い争っていたって。きっと園田さんや古舘さんの言ってた恋人のことですよ」
「あまり真に受けるなよ。裏取ってからだ」
「裏、ですか?」
「あったりめぇだ。長谷部警部補も行ってたろ、毎日数十件は男女のいざこざが駅前で開幕してるって。馬の耳か、お前のは」
「……じゃあ、すぐ見つからなさそうですね」
「あるいは、それを狙ったか」
「え?」
「ほら、考えるんだろ。考えろ」
何か言いたい望月だったが、目を閉じてしまった大城の隣で、必死に事件について思考を巡らせた。
10
良く晴れていた。
太陽は天上で煌煌と自らの役目をはたしている。このような日、決まって由弦は来日したばかりのころを思い出す。生国よりもずっと湿度も気温も高い。寒くないのは嬉しいがまったく別の憂鬱が与えられるとは想像していなかった。他方、おもしろいね、と知らない土地の楽しみかたを見つけて笑っている妹は――六花はもういない。
父親からの最後の誕生日プレゼントの、シオンと名付けられたテディベア。何を思って六花はあのくまに名前を与えたのか、なぜシオンと名付けたのか。新幹線に揺られながら考えてみた由弦だったが、納得できそうな答えは出なかった。
ふと彼か彼女を家にひとりきりにしてしまったのだと、不安に襲われて――何が悲しくてたかがくまのぬいぐるみにそこまで感情移入して心を乱されなければならないのか――途端に思考が冷えた。
なぜ六花は殺されたのか。
由弦が現時点で知りたいのはそれだけだ。どうするにしろ、すべてわかってから決めれば良い。それまではすべてどうなっても構わなかった。
深く帽子をかぶりなおした。眼鏡に干渉するうっとうしさはあったが、刺さるような日差しを少しでも緩和できるほうが嬉しい。妹に外して欲しいと言われても断って来た眼鏡を外す気はなかった。世界を間接的に目撃している感覚が消えるのは怖かった。
数日前、警察官の運手する車で移動したが、歩いてみると感覚として距離に実感が生じる。高揚感のような倦怠感とともに、六花の友人らの話をもとに彼女の足跡を追った。
熱海駅から、コインロッカー、昼食をとった店、コインロッカー、宿泊先のホテル、起雲閣、夕食を取った店、宿泊先のホテルに戻って一日目を終えた。
宿泊歳のホテルから――献花台が設置された遺体発見現場を横目に――親水公園ムーンテラス、熱海サンビーチ、海が見える近くのカフェ、宿泊先のホテル……どこかへ絵を描きに行って……宿泊先のホテル。ここから六花はどこへ行こうとしたのかわからず、献花台へ足を運んだ。
普段は率先して運動しない由弦にとって、季節柄もあいまって、想像以上に体力を奪われた。
とはいえ特に気になっていた三地点……宿泊先のホテル、遺体発見現場、親水公園ムーンテラス……それぞれの距離感覚は確かめられた。それぞれ徒歩十八分、二分といった所感だ。六花の友人らに聞いていたかぎりの内容と大きなずれは無い。あの日聞かせてくれた内容にも驚くような認識の相違は考え難かった。多少の差異については、高校一年生と大学一年生の体格差や知識量だと受け入れられる程度のものだ。受け入れられるから、小休止を取りたかった。
幸い熱海駅から離れていない、コンビニはかなり少ないが歩いて行きたくないほどの距離ではない。しかし店内飲食スペースはあるだろうか……足を休めるのが最優先であって、飲食は二の次三の次。座る場所を探すために歩き回るのは避けたかった。
いままで歩き回った経路を思い出して――海が見える近くのカフェ――適する場所に思い至った。
幸い、献花台前。親水公園ムーンテラスが近い。海は目の前にある。つまり、目的のカフェも近くにある。
お昼時を大きく過ぎていたが、店内は髪の毛が濡れた客が半分ほど埋めていた。海が見える距離だ。海水浴を楽しんでから腹ごしらえするには最適な場所。メニューを見るかぎり、食事の満足も適えられるらしいと思った。ひとまずコーヒーを頼んで待機する。
もし、当初から標的を殺すつもりではなかったとしたら?
不意に思考を過ぎった。父親が射殺された事件について考察がここに至ったとき、今まで見逃していた化石を発見した考古学者のような素晴らしい心地だった。これがカタルシスと呼ばれる経験に該当するならば、なるほど、人間は悲劇から離れられない宿命にあるのかと信じられた。
三分間でどれほどの金属が宙を舞い、いくつの命が散らされただろう。
明らかに狂気だと確信した。犯人の狂気に思考が至ったのだとすれば、由弦自身も狂気に苛まれているということになるだろうか。
拒絶。
抑えがたい好奇心。
相反する性質のふたつが由弦に巣食う。
狂気には陥りたくなかった。正気だと客観的に証明しうる範囲を逸脱してしまえば、狂気を測れなくなってしまう。あくまでも狂気を測るために狂気に触れていたに過ぎない。
由弦は正気を保ち続けていると自負し続けてきた。いまさら疑ってしまえば今までのすべてが疑わしく思えてしまう。人生の三分の一を費やしてきたもののために自らを疑えば遠くないうちに抑制が効かなくなる予感があった。だから、正気を証明するために記録した。
由弦はトートバッグのポケットからスマートフォンを取りだした。熱海に到着してからは使っていないが、それまでに目的地の経路を頭に叩きこもうと充電を消耗していた。足元にコンセントが無いか探して、諦めた。充電器系は持ってきたが、コンセントがなければいずれ尽きる。ようやく宿泊先すら決めていないと気がついた。
「宿泊先……」
調べてみると、六花たちが宿泊したホテルには部屋の空きがあった。事件の影響だろうか。由弦には幸運だった。一部屋に三人泊まれそうなところは二種類あるが、一方はファミリールーム仕様らしい。もう一方の部屋にしようと、クレジットカード情報を入力して予約を完了させた。狙ったわけでは無いものの相場より安かった。
充電はまだ半分程度ある。
由弦はドキュメントアプリを開いた。アカウントを同期させているため、六花からの電話を無視したとき必死になって文字に起こしていた思考の軌跡に触れられる。
――犯人は標的を生かしておくつもりで引き金を絞ったのだと仮定する――妙な感慨深さが心を包む。しかしこれは当日のカタルシスだと信じようとした感覚とはまったく異なっていた。
事件は就業時間内に起こった
標的に関する下調べをしていた
襲撃時に同じ空間に居合わせた
事前の調査で標的の居場所を正確に知ることはできたのか
正確とはいえ座標で小数点以下までは不要だ、
少なくともどの建物にいるのか分かれば十分だ、
標的の仕事や立場から特定の時間に特定の順路を用いる可能性も考慮できる、
待ち伏せすることは出来ただろうか、
待ち伏せしたなら警備や警察が到着するまでに標的を殺せた
けれど殺さなかったのは何故だろう、
殺すつもりが無かったのに銃は乱射されて死傷者が二十八名
標的の行動パターン推測可能
移動ルート出発点到着点わかれば推測可能
……
構造化しないまま全力で出力したそれらをスクロールしながら眺める。
魅せられたのは――自分は何に魅せられたのか、わからなかった。
半日以上かけた。文字数は十万を超えている。大学の、課題で出されるレポートや定期試験の論述の比ではない。圧倒的な熱量が保証している当時の興奮はなんとなく察せられる。何がここまで自分を突き動かしたのか……妹の次は、自分までわからなくなった……そんな馬鹿らしさが腹の底から嘲笑を誘う。
お前のせいで殺されたんだ――犯人が標的に刻みこみたかった悪意であり、目的。
二十四名が死亡、四名が重軽傷を負った――その責任は紛れもなくお前にある。お前が殺したも同然だ。
自らの憎悪を標的に思い知らせるためだけに、母国が永く悲惨な経験とともに培い守ってきた平和観念を揺るがした男がいた――いたから、何だ?
この思考にたどりついたとき満たしてくれたはずの、純粋な興奮は文字の奥に見つけられなかった。
何が違うのか。何が変わってしまったのか。
考えるまでもない、六花の生死だ。
六花が生きていると信じていたときに感じられた熱は、六花の死を知ってしまったことによって失われてしまった。見えなくなって、触れられなくなった。
答えが見つけられず苦しむより、どのような理由であれ、責任の所在が証明されてしまったほうが楽な気がした。
暗闇で立ちすくんでいる今だからこそわかった。
錯覚だったのだ。
幼い日に見た、流れてきた事件に関するニュースや専門家により綴られた考察のように。
解けるかどうかわからない何かに挑むのは、もはや自分自身への呪いのような決意は解ける方法を知らなかった。
不意に、自らの空腹に気がついた。やりたいことは、為すことはもはや明確だ。空っぽの間ままでは必要なときに全力を出せないだろう。それでは困る。
コーヒーを運んできた店員に、お勧めを聞いた。
「じゃあ、ナポリタンで」
店員は笑顔で承知を述べて足早に去って行った。
壁代わりの窓の奥。由弦は、青空を反射して悠々と広がる海から目を逸らしてカップを傾けた。
11
大城、望月両名から聴取内容が捜査本部に共有された。
「やっぱり非常階段イイ線行ってたじゃないですか」
「その代わり、ルームキーがボトルネックのままだ」
髙橋の主張を鷲見が断つ。
聴取内容もとに本来の計画を再現すると……
旅程・一日目
終業式
横浜駅集合 十二時三十分
新横浜駅発 十二時四十二分
熱海駅着 十三時四十二分
昼食
ホテルチェックイン 十五時
起雲閣/トリックアート迷路館 ~十七時
合流 十七時三十分
夕食
ホテル到着
就寝
旅程・二日目
ホテル出発 九時三十分
親水公園ムーンテラス
熱海サンビーチ 九時四十五分~十四時
カフェ 十四時三十分
ホテル到着/自由時間
夕食 十八時
就寝
旅程・三日目
ホテルチェックアウト 十一時
来宮神社 十一時三十分
熱海駅 十四時三十分
新横浜駅/解散 十五時十五分
……このようになる。
ホテル側の記録や聴取内容を踏まえた実際のそれぞれの行動は……
一日目
横浜駅集合 十二時二十四分
横浜駅―新横浜場駅 十二時三十五分―十二時四十八分
新横浜駅発―熱海駅着JR新幹線こだま号 十三時十五分―十三時四十二分
コインロッカー 十三時四十九分
昼食
コインロッカー 十五時十二分
ホテルチェックイン 十五時二十三分
エントランス防犯カメラ 十五時二十四分
女子部屋解錠(外:Ⅰ)十五時二十七分 /施錠十五時二十八分
男子部屋解錠(外:Ⅳ)十五時二十七分 /施錠十五時二十八分
男子部屋ソケットにカードをセット(Ⅴ) 十五時二十八分
女子部屋解錠(内) 十五時三十分 /施錠十五時三十分
エレベーターホール防犯カメラ 十五時三十二分
男子部屋解錠(内) 十五時三十二分 /施錠十五時三十四分
エレベーターホール防犯カメラ 十五時三十五分
エントランス防犯カメラ 十五時三十七分
起雲閣/迷路館 十五時五十一分/十五時四十七分
退館 十七時(十六時五十四分/十六時五十二分)
合流/夕食
エントランス防犯カメラ 十九時二十四分
エレベーターホール防犯カメラ 十九時三十五分
女子部屋解錠(外:Ⅱ)十九時五十六分 /施錠十九時五十六分
男子部屋解錠(外:Ⅳ)十九時五十六分 /施錠十九時五十六分
女子部屋ソケットにカードをセット(Ⅲ) 十九時五十九分
女子部屋解錠(内) 二十時八分 /施錠二十時八分
エレベーターホール防犯カメラ(女子三人) 二十時二十分
男子部屋解錠(内) 二十時十七分 /施錠二十時十七分
エレベーターホール防犯カメラ(男子三人)二十時十九分
エレベーターホール防犯カメラ(男子三人)二十時四十六分
男子部屋解錠(外:Ⅳ)二十時四十七分 /施錠二十時四十七分
エレベーターホール防犯カメラ(女子三人)二十時五十六分
女子部屋解錠(外:Ⅱ)二十時五十八分 /施錠二十時五十九分
就寝
二日目
女子部屋解錠(内) 九時二十三分 /施錠九時二十三分
男子部屋解錠(内) 九時二十三分 /施錠九時二十三分
エレベーターホール防犯カメラ 九時二十五分
エントランス防犯カメラ 九時二十七分
ムーンテラス
熱海サンビーチ(レジャーシート、パラソルの貸出あり)
カフェ 十四時二十八分―十六時二分
エントランス防犯カメラ 十六時二十六分
エレベーターホール防犯カメラ 十六時二十八分
男子部屋解錠(外:Ⅳ)十六時三十分 /施錠十六時三十分
女子部屋解錠(外:Ⅰ)十六時三十分 /施錠十六時三十一分
男子部屋解錠(内) 十六時三十五分 /施錠十六時三十五分
女子部屋解錠(内) 十六時三十七分 /施錠十六時三十八分
エレベーターホール防犯カメラ(白河、久藤)十六時三十九分
エントランス防犯カメラ(白河、久藤) 十六時四十一分
熱海プリン購入/散策(白河、久藤)
エントランス防犯カメラ(白河、久藤) 十七時三十四分
エレベーターホール防犯カメラ(白河、久藤)十七時三十六分
女子部屋解錠(外:Ⅰ)十七時三十八分 /施錠十七時三十八分
男子部屋解錠(外:Ⅳ)十七時三十八分 /施錠十七時三十九分
男子部屋解錠(内) 十七時四十八分 /施錠十七時四十八分
エレベーターホール防犯カメラ 十七時五十一分
女子部屋解錠(内) 十七時五十四分 /施錠十七時五十五分
エレベーターホール防犯カメラ 十七時五十六分
レストラン前防犯カメラ 十七時五十七分/十九時二十三分
エレベーターホール防犯カメラ 十九時二十七分
男子部屋解錠(外:Ⅳ)十九時二十九分 /施錠十九時二十九分
男子部屋解錠(内) 十九時五十九分 /施錠二十時六分
女子部屋解錠(内) 二十時二分 /施錠二十時六分
(白河六花 最終目撃:二十時四十分)
女子部屋解錠(内) 二十時四十三分 /施錠二十時四十五分
エレベーターホール防犯カメラ(白河) 二十時四十五分
エントランス防犯カメラ(白河) 二十時四十七分
(二十一時ころ、現場周辺で女性が声を荒げていた)
(二十時四十五分―二十三時)
女子部屋解錠(内) 二十一時二十九分 /施錠二十一時二十九分
女子部屋解錠(外:Ⅰ)二十一時三十分 /施錠二十一時三十分
女子部屋ソケットからカードを抜く 二十一時三十分
女子部屋解錠(内) 二十一時三十二分 /施錠二十一時三十二分
園田、久藤に電話 二十一時三十二分
エレベーターホール防犯カメラ(古舘) 二十時三十二分
男子部屋解錠(内) 二十一時三十三分 /施錠二十時六分
エレベーターホール防犯カメラ(久藤、園田) 二十時三十四分
ラウンジ前防犯カメラ(久藤、園田) 二十一時三十六分/二十一時五十四分
エレベーターホール防犯カメラ(古舘) 二十一時三十六分
男子部屋解錠(内) 二十一時三十七分 /施錠二十一時三十八分
男子部屋解錠(外:Ⅳ)二十二時六分 /施錠二十二時八分
男子部屋解錠(内) 二十二時十分 /施錠二十二時十分
グループチャット みんな男子部屋にいる旨(@白河)
エレベーターホール防犯カメラ(久藤、佐々木、園田、古舘、堀本)二十二時十三分
エレベーターホール防犯カメラ(久藤、佐々木、園田、古舘、堀本)二十二時十六分
男子部屋解錠(外:Ⅳ)二十二時十七分 /施錠二十二時十八分
男子部屋解錠(内) 二十二時二十九分 /施錠二十二時二十九分
女子部屋解錠(外:Ⅰ)二十二時三十分 /施錠二十二時三十分
女子部屋解錠(内) 二十二時三十七分 /施錠二十二時三十七分
男子部屋解錠(内) 二十二時三十八分 /施錠二十二時三十九分
男子部屋解錠(内) 二十二時五十九分 /施錠二十三時分
通報 二十三時四分
遺体発見現場到着(久藤、佐々木、園田、古舘、堀本)二十三時十五分
……遺体発見後、五人が現場に姿を現してからは刑事の立会いのもとホテルに待機することになった。
このとき、便宜上カードを判別するために数字を割り振ると、久藤帆恭はⅣ、園田彩結はⅡ、古舘実幸はⅢをそれぞれ所持していた。
「話によると……二十一時二十九分の内側、二十一時三十分の外側、二十一時三十二分の内側、女性陣が宿泊していた部屋において三つすべて園田彩結による解錠だと思われますよねぇ」
「二十一時二十九分に部屋の外へ、忘れ物に気がついて二十一時三十分にカードキーを翳してほぼ同時に部屋の前にいた古舘実幸とすれ違うときカードを渡し、二十一時三十二分にふたたび部屋の外へ。カードの固有チップも、ホテル待機時に確かめたら不審点ありませんもんね」
「そうだな。二十一時三十分の外側からの解錠は園田彩結が所持していたカードによるもの、直前まで女子部屋の空調関連ソケットにセットされていたカードを持っていたのは古舘実幸だ。三枚目は言わずもがな、発見されたとき白河六花が所持していた」
「通報は二十三時四分、最速で現着した警察官は二十三時九分、男子部屋の内側からの解錠は二十三時十五分。被害者の所持品にカードキーを紛れ込ませることは時間的に無理があります」
「となると、やはり被害者が外出時に持って行っていたということか」
「荷物まとめて出て、どこへ行こうとしてたんだ?」
「買い物バッグの感覚だったのではありませんか? 古舘さんの話では、六花さんは貴重品を別にまとめるためのバッグを持ってきていませんでした。近くのコンビニで買ったものを両手だけで運ぶのが大変だと思ったからリュックサックを背負った、とか」
「だったらむしろ中身は置いてくだろ。それに、防犯カメラを見るかぎり、ほかには何も入りそうにないね。両手のほうが荷物を持てる」
「でしたら、絵を描きに行った以外の理由はありますか? 一応、六花さんがよく絵を描いていたのは誰もが知ることだったようですけれど……」
「帰ろうとした」
「それこそ理由がありませんよ! 次の日は来宮にお参りして帰るだけだったんですから。このときに帰ろうとしなくても結局、高校生たちはすぐに帰りました。帰りの新幹線のチケットだって、発見された被害者の財布の中にありました」
「金銭面を考えなければ在来線で帰れた」
「ですから、どうしてそのタイミングで帰るんですか」
「さあね、乙女心には疎いんだ。だが、急に帰りたくなった可能性もある。二十時五十七分、被害者のスマホから自宅の兄へ電話が掛けられてる」
「古舘さんとの確執も初日には解消されてます。園田さんは、そもそもふたりが仲直りできるように動いているんですよ? 六花さんだって居心地悪いのはわかっていて旅行に参加したはずですが、それでも参加することを選びました。心のつかえがとれて二日目を楽しんだ後ならむしろ帰るのが惜しくなります!」
「わかんねえだろ、あの年頃の女子は」
「私にもあの年代はありました」
「こっちと都会じゃモノが違う。どうせ大した根拠ないだろ?」
「あります!」
望月に資料を突き出され、一歩下がってから受けとり改めて目を通す。
「二十一時三十六分に部屋へ戻る古舘さんはジュースのペットボトルを持っていました。二十二時十五分前後に五人で飲み物を買いに行ったときには、久藤くんと堀本くんはそれぞれスポーツ飲料、佐々木くんはカルピス、園田さんは缶コーヒー、そして古舘さんはテトラパックの抹茶オレを持ってます」
髙橋が「そうだな」端的に返す。続いて望月はもう一種類の資料を髙橋に渡した。
遺体発見直後、ホテル側と当事者らの協力のもと撮影された、それぞれの持ち物だった。着替えや海水浴用品は共通している。それでも個性は出ている。
三人とも何らかのゲームを持ってきた男性陣だが、久藤は磁石式チェス盤、佐々木は心理戦形式ボードゲーム、堀本はカード系をふたつ。
女性陣は洋服からバッグまで、スキンケアひとつ取りあげても――上質さが香る黒っぽい容器やシンプルなデザインが目立つ園田、ラグジュアリーや可愛らしさを優先した古舘――何もかも異なっている。
中でも望月が指定したのは、男子部屋のサイドテーブルを撮影したものだった。並ぶ六つの飲み物、古舘のジュースと二十二時代に買いに行った飲み物は、まだ誰も飲み切っていないらしかった。
「抹茶オレ、未開封です」
「……」
「古舘さん、初日に被害者と仲直りして……そのあと、女の子たち自販機で飲み物買ってるんです。古舘さんの話では、彼女がいちごみるく、六花さんが黄緑色のやつ、園田さんが缶コーヒー……黄緑色のやつって抹茶オレのことですよ。女子部屋のごみ箱にもありましたし」
髙橋は女子部屋のごみ箱に、ティッシュや汗拭きシートペットボトルや缶のほかに色違いのテトラパックが捨てられていたことを思い出しながら「それで?」抑えた声で尋ねた。
「二十一時二十五分のアラームで目が覚めてから古舘さんは飲み物を買いに行っています。ペットボトルの。それでも二十二時になってから五人で飲み物を買いに行くとき、抹茶オレを買ってます。未開封となっているのは、このとき彼女が買ったものです」
「だから?」
「六花さんの分だったんですよ。初日に買ってたのを覚えていたから。ちゃんと待ってたんです、帰ってくるの待ってたんですよ……!」
「それを信じられないんだよ。この仕事してるかぎり」
「……」
「もちろんお前の期待どおり、まったく無関係の第三者による犯行である可能性も否めない。事実、彼らのアリバイはホテル側の記録が動かせない現状、崩せていない。それでも、被害者がカードキー持ってなかったら、俺は帰宅に一票だった。いまでもこの可能性を捨ててない。持ったまま返し忘れていた可能性はある」
たった今しがたまで両手を強く握りしめて力説していた望月だったが、ふわと肩の力が抜けた。髙橋の言葉が持つ説得力に納得できてしまえたのが悔しくて唇を噛んだ。
「結局のところ被害者の感情は被害者にしかわからない。ガキみたいな馬鹿な言い争いはそこまでにして別のことに思考回せ」
鷲見の注意を受けて望月も髙橋も返事した。
「それでいうと、男子連中もなかなかの粒ぞろいが揃っていた。類が友を呼んだのかね。もちろん、被害者と同室だった女性陣のほうに注目するのは理解できるが」
大城が話題を引き継ぎつつ上手い具合に路線を変えた。
「たしかに、話を聞く限りそのようですね。堀本理仁の証言にある、若い男ってのがクセモノですが」
「恋人をすこしでも容疑者候補から外すためにあえて嘘をついた。目撃したことにして自分自身を候補から外そうとした。実際に目撃して相手の男は白河六花の恋人である。そして……被害者の兄である白河由弦は男子大学生。こちらも可能性を排除できない。もちろん、偶然知らない男に文句つけられて言い争いになったことも考えられるんでしょうね、関東は」
「偏見だろ、それは」
鷲見は指折り数えていた髙橋の言葉を否定しようとするが、
「神奈川県警さんによると駅前の喧嘩も日常茶飯事だそうです」
「酷いとこは酷いというのは伺いましたね」
望月、大城が擁護して適わなかった。
髙橋は冷笑しながら「いずれにしろ、被害者のスマホのロック突破できればわかることなんですけどね。イマジナリーでなけりゃ」机上にある、被害者のスマートフォンから抽出できた情報がまとめられた資料を指先で軽くはじいた。
「ソフトウェアのアップデートのタイミングが絶妙に悪かったんでしたっけ」
「連絡先を抽出できただけでも僥倖だ。期待していない」
「お? 鷲見さんがそうおっしゃるなら心強いですねぇ」
軽く睨みつけられて「止せ」と言われても髙橋は眦を下げたままだった。
「ところで鷲見さぁん。証拠品も証言も集まりましたよ、ひとまず」
「あいにく推理作家じゃない」
「嫌だなぁ、違和感を伺ってるんです。ストーリーテラーを求めているわけじゃありませんって」
「……関係者の証言には違和感と言えるほどの違和感は無い。ただ、個人的には、ルームキーとその指紋は気になる」
「まあ、指紋を確認するかぎり一人一枚っていうよりは三人三枚って感覚だったんでしょうね。どのカードにもそれぞれ複数人の指紋がたーくさんついてますから。まったく、スマホにアプリ入れてそっち使ってくれてりゃもう少し考えやすかったのに」
「私たちからしたらそうですし便利だとわかっているとしても、二、三日のためにそういう専用のアプリを入れるのが面倒だったり避けたいと思ったりするのは理解できます。Wi-Fiが使えなかったら結構ギガ減りますから月末まで二週間弱もあるのに制限速度かかるか気にするの嫌じゃないですか」
「それは一理どころか千里ある」
「若者にとっては不思議じゃないのか? こういうカード、財布に入れておかないと落ち着かなくならないか?」
その場にいた班員から曖昧な反応を返され、鷲見は潔く同意されるのを諦めた。足で情報を稼ぐため改めて聞きこみの指示を出す。ほとんどの面々が掃けたころ、本部にある一報が入った。海洋調査機器を扱う民間企業へ協力を要請して遺体発見の翌日から何らかの証拠品の捜索を進めていた班員からだ。
「被害者のものと思われるリュックサック、沖で発見されました!」
「回収場所は?」傍らにいた髙橋にホワイトボードマーカでおおよその場所をメモさせて「今どこにある?」質問を続けた。
「船上です、こちらに運んでいます」
「遺族への連絡は」
「まだです。黒のメンズリュックなので特徴は一致します。ただ、気休めになってしまうのは避けたいので、そちらで先に確認してもらえませんか」
「承知した。防犯カメラの映像と比較するから写真を送ってくれ。可能性が高いと判断したとき、こちらから遺族担当へ依頼する」
「ありがとうございます、すぐ送ります」
電話を切ったときには、すでに髙橋がタブレット端末を起動していた。
「この仕事をしているかぎり信じられない――だったか? なかなか厳しいこと言うじゃあないか」
「みーんな望月と同じ思考回路だったらマジで警察いりませんから」
珍しくふたりともそれぞれ寂しい笑みを浮かべた。
12
コーヒーも勧められたナポリタンも絶品だった。由弦は飲食の勘定を済ませると目が眩むような店内から足早にホテルへ向かい、チェックインした。機械を用いたチェックイン作業にてカードキーの枚数を選択するとき、由弦は二枚を選択する。エレベーターを経由して宿泊部屋の前に到着するまでに二か所の防犯カメラを見つけ、半球の位置をそれぞれ頭に叩き込んだ。
ルームキーに二つのうち片方のカードを翳そうとして、やめた。思いたち、財布を開く……学生証、保険証、マイナンバーカード、クレジットカード、自宅近くの図書館のカード、スーパーマーケットのポイントカード、紙幣、硬貨……すべてルームキーに翳したが、いずれも無反応だった。眼鏡や筆記用具も同様だ。他のあらゆる物品での代替は望めないらしい。
廊下の直線状に他の部屋の宿泊者の姿を認め、由弦は割り当てられたカードキーを翳す――短い電子音とともに扉は開いた。体を翻すように室内へ逃げ込んだ。
廊下での奇行を反省しつつ室内を見渡す。
右手にクローゼットの扉と鏡、左手にはシャワールームとお手洗い、その先には居室があり、さらに奥には小さな座敷がある。
中学生のころ緑茶が好きなことに気づいて以降、六花は炭酸の次には緑茶を好んで飲んでいた。間食に和菓子を選んでおいしそうに食べていた姿を思い出した。しばらく自力で再現しようと奮闘していたが、やがて買ったほうが楽かつ美味だと真理にたどりついていた。
由弦はトートバッグをベットの上に放ると、ふたたび部屋を出る。直前、手に持っていたカードキーを出入り口の扉のそばにあるソケットに差し込んで冷房を起動させた。
廊下の何とも言えない暖かさを気にせずスマートフォンのロック画面を確認してから歩き出した。エレベーターホールを通り過ぎて案内に従い自販機を目指し、到着すると再びロック画面を確認。再び宿泊部屋の前に戻って足を止めてからロック画面を確認した。
続いて、エントランス、大浴場、ラウンジスペースなど、部屋から防犯カメラやそれぞれの施設との距離と往復の所要時間を確認した。メモ帳アプリに記録を完了すると、廊下の先に非常口のランプが点いていると気がついた。歩み寄り、そっと握り手に力をこめると――重い金属音とともに扉は開いた。
生温い風が吹いた。半身を出して確認すると、踊り場の上下には階段続いている。非常口の外側には握り手が無い。由弦はロック画面で時間を確認して扉の下部にハンカチを挟むと階段を降りた。材質はわからなかったが、想像以上に足音は静かだった。一階に到着して、再び扉を押し開けながら時間を確認する。また、この扉も同様に外側には握り手が無かった。由弦は階段を駆け上って宿泊部屋へ戻り、トートバッグをひっくり返した。時間を気にしながら着替えに持ってきていたティーシャツ片手に部屋を出て非常階段を駆け下りる。ティーシャツを扉に噛ませて、海へ向かって走った。
献花台。
肩で息をしながらロック画面を確認する。なぜか笑いが込み上げてきて、その場にしゃがみこんだ。急いでも十分ていどは必要だった。往復なら二十分弱。由弦は、両手を組んで額を押しつけた。
海岸はこの調子で走れば一分もかからない距離にあるが、行く気にはなれなかった。所持品を回収しながら非常階段で宿泊部屋に戻った。
座敷の奥にあるカーテンを開けると、すでに日は傾き始めていた。夕映えが一本の道筋を茜色に染め上げる。長閑な風景の中、ぽっかりと開けた空間は茜色。
窓ガラスにそっと触れる。鋭い日差しとうるさい冷房を中和して、ほんのり温かい。
母親の腕に抱かれた妹を見上げていた。父親に手を伸ばされ両手を差しだし、抱き上げてもらう。見上げると父親は片眉と口角を上げ、見つめると母親は優しく微笑んだ。見下ろしながら、片手で父の服を掴み、もう一方の手を――思考を、着信音が遮った。
ポケットから携帯を取り出して確認すると、数日前に受け取った名刺に記された番号からだった。「はい、白河です」簡潔に名乗った。
向こうも名乗る。本人かどうか確認が完了すると彼女は、言った。
「白河六花さんが当日所持していたと思われるリュックサックが発見されました。彼女のものか、確認していただけますか?」
13
送られてきた写真とホテル側から提供された映像を見比べた結果、鷲見は遺族担当へ連絡を入れた。それから間もなく
「すみません、鷲見刑事、髙橋刑事いらっしゃい――あのっ」
本部まで遺族担当が足を運んだ。船上から証拠品が到着するまで時間がある。咄嗟に最悪の想像をした二人は顔を見合わせるまでもなく彼女のもとへ駆け寄った。
「リュックサックの確認、いつできますか?」
「数時間は必要ですね。何がありました?」
「白河由弦さん、こちらに到着するまであと三十分もかからないそうなのですが、どうしましょう?」
「え、早すぎません? 高速使って数時間、新幹線だって一時間くらいはかかるはずですけど」
「ちょうど熱海のホテルに宿泊しているそうです」
「どこのホテルかわかりますか?」遺族担当の返答を受けて「被害者が宿泊してたとこですね」髙橋が確認するような口調でつぶやいた。
「リュックサックが署に到着しても、指紋や付着物の確認を終えた後になります。それまで対応願います」
「わかりました」
遺族担当の背を見送り、一拍置くと
「なぜだと思います?」
「お前はどう思う?」
「何にしろ自殺されるよりはまだ良いですね。じゃ、俺、車回してきます」
髙橋の言葉にうなづき、本部の人間に軽く指示を出してから鷲見は会議室を出た。
助手席に乗りこみ当該ホテルの駐車場に到着するまで、車内は無言だった。ホテルの人間に手帳を見せて防犯カメラの映像を確認できるよう協力を要請した。
チェックイン時刻周辺から確認していくと
「お。いましたよ、とんでも眼鏡くん」
「変な渾名つけるな」
最初にエントランス防犯カメラに被害者の兄の姿を確認した。赤と白の縞模様の眼鏡フレームは唯一無二、鮮明とは言い切れない画質でも容易に見つけやすかった。
青年が逐一スマートフォンの画面を気にしながらホテル中を歩き回っているのを観察する。
「何してんですかね、彼」
「……時間だ。それぞれどれくらいで歩いて行けるか、時間を見ている」
「ああ、確かに高校生たちが行ったと話してたところ巡ってますね」
鷲見は椅子に背を預けて一息ついた。
「彼は被害者の友人らに話を聞いている。このホテルを宿泊先に選んだのも偶然ではないんだろう」
「……なぜだと思います」
「お前はどう思う?」
「二択ですね。復讐計画か証拠隠滅か……。この映像あれば歩容認証いけますよね?」
鷲見は思わず髙橋の横顔を固い笑みとともに見つめた。
バイクにしろ電車にしろ、被害者の兄には自宅と熱海との往復手段がある。学生は夏季の長期休暇に入った時期である。強い日差しのもと帽子を目深にかぶっていても違和感は少ないし、感染症対策としてマスクをつけて出かけている人々は多い。とくに夏場は海水浴を目的にした熱海への来訪客はかなりの数に上る。それに紛れることは難しくない。関東で望月が兄を判別できたのはひとえにその特徴的な眼鏡のためだった。外して、帽子とマスクを装着していればわかるかどうか定かではない。
専ら、殺人という犯罪は顔見知りの間で実行される。
「そうだな」
一言だけ、掠れた声で答えた。
14
「間違いありません」
横長の机に乗せられた黒いリュックサックを見つめながら、由弦は答えた。鷲見は「ご協力ありがとうございます」静かな声色で返した。
「中身も、すべて白河六花さんのものでしょうか。それか、不足しているものはありますか」
「わからないです、把握してません。リュックサックは私が貸したものですし洋服に見覚えはありますが……他のものについてはあの子が持っていそうだと思いますけど、断言できません。すみません」
「いえ、十分です。ありがとうございます」
「これらは証拠品の扱いですよね? いつか返していただけるんですか?」
「そのつもりです。ただ、事件解決後になりますから」
「正確な時期はわからないんですね」
「ええ、はい」
「今年中は難しいですか?」
「捜査次第です」
「そうですよね」
髙橋は、鷲見と由弦の会話を数歩下がったところから観察し続けていた。妹の遺体と対面したとき含めて、あくまでも取り乱さない由弦だ。本質を見えないよう抑えているようでもあった。
「問題なければ、少々話聞かせてもらえますかね」
ひと段落して髙橋が由弦に問う。眼鏡のレンズが反射して瞳は見えなかったが、青年は緩やかな笑みを口元に浮かべてひとつうなづいた。
それを合図に、事件まもなく集った会議室へ移動することになった。髙橋は鷲見と由弦の背を眺め、後ろ手にジップロックに収められた一式を掴んで部屋を出た。
遺族担当含め、あの日と同じ椅子に腰を下ろした。
「取調室に案内されると思いましたが、違うんですね」
「そちらのほうが話しやすいかな」
鷲見は髙橋に鋭く肘打ちしてから「確認したいことがいくつかあるだけですから」なるべく穏やかな声色で告げた。由弦側に座る遺族担当は、遺族を労われば良いのか髙橋を睨めばいいのか、状況についていけず困惑している様子だった。
「長い時間お待たせしてすみませんでした」
「いえ。私が早かっただけです」
「ちなみに、熱海には何時くらいに到着されたんですか?」
「昼下がりです」
「何か目的がおありでした?」
「いえ。なんとなく思いつきです」
「それだけかい?」
「……隠しても時間の無駄ですね」
由弦は、顔を上げて目の前の刑事らをまっすぐ見つめると
「知りたいだけです、真相を」
明言した。会議室内に沈黙が流れた。やがて鷲見は「そのためにホテル内や市内を歩き回っていたのか?」重々しく質問を返した。
「星は私たちの気を惹きますが、私たちを束縛することはありません。事実として、そこにあるだけです……繋げたり想像を働かせたりするのは私の勝手です。誰も、与り知らぬところでしょう」
「妹さんの友達を疑っているように見えるけれど?」
「仮に六花のことを何も知らない人物による犯行だとして、あまりにも解決が遅いですから。偶然、目の前の人間を襲うなら計画性など無いでしょう。遺された痕跡からまもなく犯人は逮捕される。日本の警察は優秀だと聞いたことがありますから。それが適わないなら、身近な人物による実行だと考えるのが自然です。あの子の着衣などから何か採取できたとしても直前まで行動を共にしていたなら証拠としては不十分だと扱われる。難航しているのはそのあたりも関係しているのだろうと思いますが……?」
「痛いところをついてくるね」
「当たらずも遠からずだと考えていますが、いかがでしょうか」
「あいにく捜査中だから」
「そうですよね」
「ただ、君はすでにあの子たちから話を聞いたんだよね? それならわかるはずだ。二日目の夜、被害者がひとりで部屋を出た二十時四十分前後、ひとりは疲れて寝ていてもうひとりは入れ替わりでシャワーを使い始めた直後だった。二十一時半くらいになるまで、このふたりはずっと室内にいたし、男子たちも自分たちの部屋にいた。知らない土地で三十分以上遅れてどこへ向かったかも知らない妹さんを追いかけるのは困難だろうし、以降は必ず二人以上で行動を共にしている……彼らに犯行は不可能だったんだ」
納得させようと言い聞かせるような若い刑事の主張を聞いて、由弦は言葉を失い、呆然と虚空を見つめている。髙橋は「加えて」落ち着いた声色で続ける。
「幸い回収された所持品の中でも、この袋の中に入っていたハンカチとノートだけは浸水を免れていた。ハンカチから採取された指紋は被害者ものだけだったが、ノートは二人分……被害者と、もうひとりの指紋が残されていた。虚構ではなかった、とまでは言わない。が、兄である君の知らない交友関係は学校内だけには収まっていなかった可能性がある」
髙橋は手袋を装着したままジップロックからノートを取りだし、適当なページを開いた。青インク一色で三色団子を描き分けて紅葉や銀杏の葉を周囲に散らしているイラストだ。端には「ゲンのお気にいり、すっごく褒めてくれた!」はねやはらいが丁寧な文字によって綴られている。
「ゲンと名乗る男を知っているか?」
信じがたい事実に遭遇したかのように、由弦は目を見開いて硬直していた。
「心当たりはないか?」改めて鷲見が労わるように尋ねる。由弦は机に両肘をつき、何も言えないまま組んだ両手に額を押しつける。
「このページ以外にもゲンは登場する。定期的に会っていたんだ。探せば必ず見つかる」
「……そうですね」
「難航しているのは事実だ。それでも、必ず犯人を捕まえる――信じてほしい」
鷲見は真摯に告げた。由弦がゆっくり顔を上げると、三対の視線が彼に集中した。
憂色を帯びた、危うい儚さ……柔和を感じさせつつも、そこにあるまっすぐな芯。兄妹ともにどこか人好きのする雰囲気がある。兄が鷹のように鋭く大切に研いだ爪を隠しているように見える一方、妹も一筋縄ではいかないような美しき花の棘を思い出させる。知れば知るほど、認識が固まっては解けてしまう……静かに席を立つと
「すみません、もう良いですか」
「……ええ。ご協力ありがとうございます」
由弦は警察署を出ると、早足で熱海駅へ向かった。途中の信号で足止めを食らうと、ポケットからスマートフォンを取りだしてまもなく耳に押し当てた。
十分なキョリを取ってその背を見つめる髙橋もまた、ある番号に電話を掛けた。
15
由弦は、電話で妹の友人のひとりを呼び出した。
久藤が作成してくれたグループチャットに登録されたアカウントから目的の人物だけを選んで電話を掛けた。
「聞きいてほしいことがあるんです」
相手は突然そう告げられたわけだが、渋ることなく
「わかりました。どこへ行けば良いですか」
由弦の指定した場所へ向かうと返して電話を切った。
ホテルにある荷物のことなど忘れていた。由弦は熱海駅の改札を通過して、なんとか購入できた新幹線に乗りこむ。通路側の席に体を預けると、目を閉じて睡眠の真似事をする。傍目からは休んでいるように見えるが、嫌でも繰り返し思考を精査してしまっているため、休息どころでは無い。
由弦は、妹の友人を呼びだしたものの、自らの推測について確信は無い。実際、ところどころ論理の飛躍や無理な展開が見つかる。しかし、由弦はそれで構わなかった。
重要なのは、真実にたどり着くことではなく、誰が六花を殺したのか明らかにすることだ。
たった今しがた、刑事との会話で必要なパズルのピースを獲得した。
六花殺害犯の判明さえ適えば、納得いく解答が得られると信じていた。正気は由弦が保持している。目の前にある狂気を測る自信なら持ち合わせている。
一時間もかからないうちに横浜駅に到着して、先を急ぐ――同様に、彼の掛けている特徴的な眼鏡を目印として、神奈川県警の長谷部が無事に尾行を引き継いだ。
由弦は指定した公園にたどりつくと、ベンチに腰かけて夜空を見上げた。電灯の光量に負けて、星はほとんど見えない。時間経過とともに月がゆっくり天上へ向かっていく。
やがて、一人分の影が公園へ加わった。月を眺めている由弦に「お待たせしました」と告げる。
長谷部の位置取りから当該人物の顔は見えなかったが、その声で誰なのか把握した。しかしながら、彼らが何をしようとしているのか正確にはわからなかった。とはいえ、直前の電話にて事件が大詰めである可能性は聞かされていた。下手に動いて彼らに存在を知らせてしまうような真似は避けたかった。引き続き、公園の植物の影に身をひそめたまま息を抑えた。
「いえ。早かったですね。二十三時回ってますから、来ないかと思いました」
「断らないとわかってて呼び出したわけでは無いんですか?」
「……」
「聞いて欲しいことって、何ですか?」
「その前に、少し歩きませんか?」
由弦は質問に答えない代わりに提案した。気障に差し出した手を宙を漂ったが、相手から了承を受けとれた。二人は公園を出て並んで歩く。無言の中、当てもなく歩く。目的地は無いが、一方は高校生だ。補導されるのは避けたかった。人目を気にしているうちに、徐々に周囲を歩く人が減っていく。
他方、長谷部は慎重に、しかし決して捲かれないよう尾行する。思い切って大胆にも距離を詰めると、
「こんな時間になったのは、すみません。なかなか決め手に欠けていたもので」
不意に由弦が足を止めた。相手も距離を保つようにその場に佇む。
「何を聞けば良いんでしょうか」
「私の推測が間違っていないかどうか」
「何に対する推測ですか?」
由弦は引き結ぶように口角を上げて相手に向き直った。
「きっかけは、事件当日の六花の足取りに違和感を覚えたこと。日中ならともかく、なぜ夜に絵を描きに外へ出たのか。絵を描くだけなのになぜリュックサックを持ち出したのか」
質問の答えがはぐらかされても、相手は平然としている。その場のペースを掌握しようと言動を選んでいる由弦からすると幸いな反応とは言い切れないが、主導権を奪われないなら問題ないと判断した。
二人が足を止めたのを確認し、長谷部はメールで鷲見たちに住所を伝えた。何も答えない高校生と緩やかな笑みを浮かべたままの由弦の動向を注意深く観察し続ける。
「兄として六花を分析するとね、夜ひとりで外出することも絵を描きに行ったというのもありえない。小さいころから間接照明が無いと眠れないくらい、暗いところは苦手だったんだ」
由弦が告げると、
「満月に近かったですし、ムーンテラス周辺はライトアップされてましたよ」
暗いから外出しないという前提に対して、夜だったが暗くなかったと主張しているらしい。内心、由弦は反駁に安堵した。まだ全貌が把握できていないから理解も納得もできていないだけだ。今からひとつずつ測れば良い……努めて笑みを浮かべる。
「たしかにこれだけでは根拠が弱いね。じゃあ、本当にあの時間に六花は絵を描くために外出したと思う? さあ、これについて考えてみようか。六花の荷物はリュックサックだけだったけれど、絵を描くために必要なのはジップロックに入れたノートとペンの一式があれば十分だった。わざわざ二泊三日分を詰めなおしたリュックサックを背負って絵を描きに行こうとするのは不自然きわまりない。それに、君らは六花が夜にひとりで絵を描きに行ったと判断するために、二つ――二日目午後の休憩時間に六花が絵を描きに外出したと発言したこと、小さいころ夜遅くまで外で絵を描いていたら怒られた経験があると話していたことを根拠にしているわけだけれど……一旦、少なくとも君は――君だけはこの時点で六花が絵を描くために外出したのではないと把握していたことは置いておこう。まずは、前者について、久藤くんの証言と警察の聞き込みによって覆った。久藤くんと六花で熱海プリンを買ったり近くの店を軽く巡ったりしたらしい。実際、事件発覚の翌日早朝に私は久藤くんから六花が選びそうな栞を受けとったよ」
「……」
得意げに話して見せているものの、無反応ではどこか心許ない自覚があった。あいにく暗がりでは相手の表情はよく見えない。表情に現れた感情を拾い集めてやり取りを進めていくつもりだったが、相手は拒否するように暗がりの中にいる。こうなっては、暴力も逃走も選択しないかぎり話を聞いているのだと認識するしかない。仮に話している内容が事実と異なるならば、さきほどのように反駁すれば良い。
由弦は好戦的な心情とともに言葉を続けた。
「後者は、単純に日本じゃないから成立したことだった。私たちはスイス出身でね。白夜が見られるほどの緯度ではないけれど、サマータイム期間なら二十二時でも昼間のような明るさなんだ。だから祖母があまりにも帰りが遅かった妹に激怒したんだ。妹いわく暗くなったら帰ろうと思っていたらしいけれど、いつまでも日が落ちないから時間を見誤ってしまったらしい。それ以降はあの子、時間制限にはうるさくなったよ。テスト勉強はギリギリのときもあったけどね」
試験当日の数時間前にわからないところを質問しようとしてきた六花を、改めて思い出す。由弦は唇を噛み締め、ひとつ深呼吸をすると話を続ける。
「これで、夜に外出して絵を描いていたという目的が崩れるわけだ――ここまで良いかな?」
すると、
「はい。あの夜、六花さんは絵を描きに行ったわけでは無かったんですね」
「そう。ならば、なぜ夜遅くに外出したのか……初めから明確だったんだ。荷物をまとめて出てきたんだから……単に帰ろうとしただけだ」
静謐。
あいかわらず表情は見えないが、影すらも身じろぎひとつなかった。
「驚かないんだね」
「驚いてますよ」
影の中で上体が右へ傾けられたのがわかる。
六花の仕草が重なって見えて嫌悪を抱いた。
「しかし、お兄さん……彼女が発見されたとき、ルームキーを持っていたんですよ? 部屋に戻ってくるつもりだったからカードを持って行ったのだと思いますけど」
「固有チップで宿泊先のもとだと確認されたらしいね」
「そうですよ。五人とも確認しました」
「どのように?」
「はい?」
「そのままの意味だよ。園田さんと古舘さんは男子の部屋にいるときからそれぞれ一枚ずつ持っていたんだろう?」
今一つ意図が読めていないのか質問の内容がしっくり来ていない相手に説明を重ねる。
「じゃあ、男子は? あの暑さで冷房をつけていなかったわけがない。消していなければならない理由もない。同じ部屋に割り当てられた三枚のルームキーのうち一枚は入り口付近のシステム制御のポケットにセットしていたはずだ」
「っ……」
「ひとり一枚のカードがあるわけだけれど、セットしているかぎり自由にできるのは二枚だけだ。二十二時過ぎまで部屋の外にいた久藤くんは一枚確保していただろうね。締め出されたらたまらないし、カフェに集まってくれたとき、丁寧に話してくれた。あのメンバーの中で自分だけはしっかりしていないといけない矜持のようなものが言動から見えた。……さて。男子は誰がカードを持ってなかった? 持ってきていなかった子のカードはどのように確かめた?」
「……」
「刑事立会いのもと部屋から荷物を引き上げるとき、回収されたんじゃあなかったかな。それからそれぞれ三枚ともその部屋に割り振られたカードで間違いないと確認された。そうだよね?」
直前の表情の遷移から返答が無いのは予想していた。由弦は先を続ける。
「割り振られたカードキーが人数分あるとしても、専用ではなかったんだよね? 基本的に机の上に置いておいて、誰でも手に取れるようにしていたというのは君らがカフェで話してくれたことだ」
由弦はようやく相手が見せた同様に満足して続ける。
「あのホテルではアプリを用いた解錠も対応しているようだけれど、入れてなかったというのも教えてくれたね。だから、鍵のかかった部屋に入るには、どうしてもカードキーは欠かせない。電子機器が用いられているなら記録が残されると予想するのは容易かっただろうね。警察も扉が解錠された時間は知っているようだった。おおよそ私が知っている内容だったけれど、彼らはプロだ。ホテル側へ確認しただろうね」
気だるげな推測を一旦区切ると、相手を観察する。焦っている素振りは無く、おとなしく話を聞いているようだった。
「部屋の外に何人いるとしても、一枚あれば自由に出入りできる。けれど、二十一時三十分ころ、女子の部屋のシステム制御のソケットからカードが抜き取られた。このとき女子の部屋において、ひとり一枚、専用のカードを保持できるようになった」
「片方の部屋に全員が集まっていたんですから。誰もいない部屋にカードが一枚もなくなるのは、それほどおかしいでしょうか?」
「カフェでみんなが見せてくれた写真はいずれも晴天だった。気温の高さはなんとなく予想がつくよ。同じように今日も暑かった。ソケットからカードを抜けば冷房は停止する。すぐに戻るつもりなら抜き取るとは思えない」
「あくまでもお兄さんの想像ですよね。実際はソケットからカードは抜かれました」
「そうだね。まあ、その点に関して特段の疑問は無い。必要なことだったから抜かれたというのも、今ならわかる。もしかして、君から事実を引き出すために呼び出したと思われているのかな。心外だな。最初から、確かめたいから呼んだって言ったのに」
「……」
「言ったとおりだよ。警察が把握しているだろう内容は、おおよそ私が知っている内容だった」
由弦は眼鏡を外してポケットに押し込んだ。目の前にいる相手をまっすぐ見据える。
「警察には二十時四十分ころに六花と入れ替わりでシャワールームを使っていたと話したらしいけれど、私には六花が四十分ころにシャワーを使い始めて二十一時になる前に入れ替わったと話してくれたよね?」
相手を視界にとらえたまま、声色を変えず淡々と続ける。
「曖昧さに足を掬われたね。何もかもが許容されるわけじゃあない。私が電話のことを言わなければ変えなくても、いや、一度偽ったからこそ不安だったのかな。暴かれる可能性をできるだけ低くし続けていたかったなら……普通、一般人と刑事が相互に情報共有することはない。今回は偶然、向こうが私を容疑者に数えていたらしくてね。揺さぶりをかけようと提示した事実が、最後のパズルのピースだった……私に伝えた時間、警察に証言した時間、たった数十分の差異がすべてを崩し得る瑕疵になった」
「……続けても構いませんよ?」
言葉が少ないのは、決して動揺しているからでは無いらしい。高校生とは思えない笑みを前に、由弦は寛ぐように背を壁に預けた。
「お言葉に甘えて――警察は、君らは外に出られないから六花を殺すのは不可能だと話していた。まずはそこを崩そうかな。事実とは異なるなら、反論しても構わない。ただ、私が参考にしているのは君らがカフェで話してくれた内容だ。修正したいなら、相応の理由が欲しいね。勘違いしていました、というのはあまりにもナンセンスだ」
由弦は数秒間だけ件の録音を流した。相手はいくつか目を瞬いたが、
「ええ。不用意に訂正して四人との話が食い違う可能性もありますからね……気をつけます」
落ち着いた声色だった。
由弦は話しを続ける。
「六花は誰にも止められないように部屋を出たつもりだった。同室のふたりのうちひとりは眠っていたしシャワールームから水の音が聞こえていればもうひとりも追いかけてくることは無いと安心しただろうね。けれど、君は服を着たまま水を流していただけ。鍵が閉まらないようルームキーに細工していたのか六花が開けた扉が閉まる前にシャワールームから出て開けたままにしておいたか、いずれにしろほぼ同じタイミングで部屋の外へ出た。しかし、六花はエレベーターホールへ向かったが、君は非常階段を使用して一階を目指した。戻ってきたときに非常階段の扉から宿泊階へ戻れるよう何か物を挟んで閉じないようにしながら」
推測を離しながら、由弦は両手を握りしめる。
「六花が荷物を持って向かう先は熱海駅以外になかったんだから、少し遅れても走って追いかければ追いつけたはずだ。このとき六花がどこかに電話している姿を確認できていれば最初からそれを考慮した証言を警察にもできただろうから、追いついたのはその後だったんだろうね。その後だったとしても……ネットニュースの情報を用いるのは遺憾だけれど……二十一時ころに言い争うのは可能だよ。五分くらいで引き返せば次のフェーズにも間に合う」
「いくつか段階があるんですね」
「スマホのアラームだよ。古舘さんは自由時間にはずっと眠っていたらしいし、経過時間的にもまだ眠りは浅かった。だから、アラームで起きれた。部屋は冷房で乾燥していただろうから喉が渇いただろう。だから、自販機へ飲み物を買いに行くため内側から扉を開けた。そのとき園田さんとすれ違ったと話していたね」
「……」
「このとき、古舘さんはスマートフォンや財布は握っていただろうけれど、カードキーは持っていなかった。そして、渡してもらわなかった。そのまま自販機に向かった。直後、制御ソケットからカードを抜き取り、扉を閉める。そのカードを使って外側から解錠してサイドテーブルに乗せておいたカードとベッド近くのスマートフォンを回収して、部屋の外に出れば良いだけだ」
しだいに相手が口元浮かべている笑みが不快に感じ始めた。夜空を見上げ、視線を戻す。
「カードキーは誰かが財布にいれたりしてキープしていたわけでは無く、サイドテーブルに乗せておいて使う人が持って行くようにしていた。場所がわかっていれば暗がりで手探りでもカードは見つけられる……以降は、なるべくひとりきりにならないようにしておけばほかの四人との記憶の齟齬なく容疑者から外れることができる。これを実行するには古舘さんの記憶の性質を知っている必要がある。古舘さんはヴィジュアルシンカーの気質が強い。順序立てて説明するのは苦手だった。四月からクラスメイトで夏休みの旅行で友人として関係性を憂慮できるくらいには彼女のことを知っていたなら、曖昧さに説得力を持たせれば納得させて記憶を書き換えることすら可能だと予想できたんじゃあないかな」
由弦は一旦咳払いをしてから喉を湿せた。
「高校受験から間もない。上位校に名を連ねる修桜大学付属高校で学びをともにするならわかっただろう。得てしてクラスメイトたちはプライドが高いことに。自分の納得できないことには反発するけれど、反対に納得させてしまえば自分からそうだったと思い込んでくれるということに。プライドの高さとの相関は証明されていないけど、認知に関しては多くの実験が行われてその曖昧さが嘆かれる結果も少なくない。そして、曖昧さに説得力を持たせるためには、素早さが必要だった。でなければ、古舘さんを騙せても警察まで煙に巻けない……運も愛も大胆に振る舞う者の味方をするとは言い得て妙だね」
「話を伺うかぎり、確かに可能ですね。では、なぜこのようなことをしなければならなかったのでしょうね?」
「丁度いいアリバイを獲得するため……鉄壁が過ぎると作為を疑われやすく、瑕疵からすべてが崩されることもある。だからといって曖昧過ぎると意味を成さない。そのためにも、六花を含めて女子はちゃんと一人一枚ずつ持っていた――これを印象付けるためだ。帰るためにひとりで部屋を出た六花がカードキーを持っていないのはわかっていただろう。だから、自分が持っていたカードキーを六花に持たせた。何かの拍子に怪しまれたら、こう言えば良い……私一枚持ってたんだよ。二枚も持つ理由ないでしょう?」
薄暗い中、相手が両手を握りしめたのはわかった。
実際に使った言葉に近かったのだろうか……由弦は容赦なく言葉を続ける。
「この方法を実行するには、そもそも六花が早急に帰る用意を整えて部屋を出る必要がある」
「疲れ切った夜、しかもシャワーを浴びた後ですよ? 二泊三日ですから、それまでに広げていた荷物も片付けなければならないんですよ? あの子が夜に絵を描きに行っていないことはご自身で論証されたばかりですよね?」
今までよりも強い語調だ。揺さぶれている感覚が得られて、なおさらこの曖昧な推測の正しさを信じられる。
由弦は人差し指で天上を指しながら告げた。
「ここで重要なのは――白河六花の恋人の存在だ」
「お兄さんのお知り合いでしたか」
「いいや。あの子に恋人なんていないよ」
「……そう信じたいんですか?」
呆気にとられたように尋ねられ、思わず「違う違う」と否定する。
「あー。これじゃあ保護者面した面倒な兄か。違うよ、本当にいないんだ。ゲンなんて恋人は」
気づいたとき、由弦は何も言えないほど自分に呆れかえってしまった。
あまりにも初歩的で当たり前なことだった。しかし、感覚の相違に気づけなかった自らを恥じた。
今も、自嘲するような口調になってしまうのがわかる。
「友達だったなら知っているかな? あの子のもうひとつの本名を。日本じゃあ白河六花を名乗っているけれど、向こうでも同じ名前を使っていたわけじゃあない。そもそも向こうでは夫婦同姓にしなければならない法は無いし、私たちは都合の良い父方のバルマー姓を用いていた。もうわかるよね? クリステルが六花と名乗っているように、その兄がユヅルのままじゃあないって……ユルゲン・バルマー……ゲンは家族や友人が使っていた、私に対する愛称だよ」
息を飲む声が聞こえた。カフェで話したときに漢字表記まで丁寧に名前を教えれば予想できたかもしれないが、音からは想像しにくかっただろう。
「そう、恋人なんかじゃない。君らはあの子が、お兄ちゃんのことだと誤魔化しているように聞こえたらしいけれどね。学校であの子が友達やクラスメイトをどう呼んでいたか知らないけど、大方、さん付けだったのかな。おかげで警察も踊らされていて馬鹿らしかったよ。下手に秘密主義なのは非効率だ」
「……白河さんに恋人がいないから、何でしょうか?」
「あいにく君ら五人のことは知らない。警察に何を話したのかも、ほんの一握りしかわからない。それでも、六花の兄を十六年してきたから、あの子のことなら少しわかるんだ。どのようなことを考えたのか……恋人はいなかった。だからこそ、どうしようもなく恐ろしかった」
崩れない微笑みから確信した。やはりわかっていたのだと。
「どうしても三日目に唯一行くはずだった来宮神社には行きたくなかった。そのために、三日目が来る前に帰ろうとしたんだよ。縁結びが有名で恋愛成就を祈願できるパワースポットに行かずに済むように…………一度、古舘さんとの関係を揺るがした原因は恋愛関係だった。君とまで同じことを繰り返したくなかったんだ。けれど、あの夜、古舘さんが眠ってしまった後、二人きりになってから日中のことを指摘された……自由時間のとき、絵を描きに外出していたのではなく久藤くんと一緒に過ごすためだったことを……あの子がどのように何を考えるのか予想した上で、君は言ったんだろう? 園田彩結さん」
少女は何も言わず、何も知らないような年相応の無垢な笑みを浮かべた。
由弦は両手を握りしめた。
「咄嗟に六花は否定したかもしれないけれど、その直後、部屋を抜け出したのが答えだ。君にしたって、私に話したそのときのことと警察に証言したそのときとで十分間の齟齬を生じさせる理由は無い。遺族と警察が情報交換する機会なんて普通は無い。それぞれに最大限疑われず五人にも疑われないよう計算したのだろうけれどそれが契機だったよ。実際、私が警察に疑われていなければ一生わからないままだったかもしれない」
「そこまでわかっていらっしゃるなら、もうご自身の罪もわかりますか?」
「罪……?」
「わからないんですか?」
妹の苦悩に寄り添いきれていなかったこと、旅行を許したこと、電話を無視したこと……思考を過ぎったものはいずれも耐え難い後悔だが、罪という表現には引っかかった。
所詮、由弦が六花の死について自らを責める理由付けに過ぎないのだ。他人に責められるような内容ではない。
園田は蔑むように「わからないんですか?」眉を下げて声に困惑と落胆を滲ませる。
「あの子の死は共有されるべきだったのに、怠ったじゃないですか」
「……殺したのは君だろう?」
困惑のまま問い返した。
「そうですよ、けれどお別れができるほどの猶予はありませんでした。だから通夜が行われるのを待ち望んでいたのに」
目を瞬かせるのは、由弦の番だった。
間違いなく日本語は聞き取れている。しかしながら内容が理解できない。早朝の電話も同じような感覚だったと思い出しながら、何をすれば良いのかわからず、祈るように両手を握りしめて微笑む園田を眺めた。
「眠るように目を閉じたままの彼女は、きっと、童話のお姫様そのものごとく美しさだったでしょうに……」
「最初から六花を殺すために追いかけたんだね。手間をかけて警察を欺いたわりには殺人を認めているけれど、捕まることすら理解してなお犯行に踏み切ったのかな?」
園田はその問いを鼻であしらい、しまいにはお腹を抱えて笑い出した。
由弦はそれを眺めながら、全身の力が抜けるのを自覚した。
「違いますよぅ、それなら自分で話してもお兄さんが警察に話しても変わらないじゃないですか! だいだい、なぜこんな時間に公園へ行ったか、わかりませんか?」
後ろ手に取りだしたそれが月下に煌めいた。
「妹さんと似た殺されかた、あるいは、罪の重さに耐えられず自殺……どちらにしますか?」
「急だね」
明確な危機と相対しているのは認識しているが、目の前にある強烈な未知が思考を奪ってしまい、由弦を冷静にさせている。もはや、共通言語が不在だった。
「ふふっ……私、捕まりたくないんです。だって、私が捕まったらリッカが奪われてしまうんですもの」
「奪ったのは君だ」
「仕方ないじゃないですか、彼女の美しさが失われてしまうよりはずっと良いですもの。ええ、そうです。だって私は、世界の損失を防いだ立役者としての栄誉があるなら、いかなる不名誉だって受け入れられます。けれど、いいえ、だからこそ、リッカを盗られるのだけは耐えられません」
「……あの子は誰のものでもないよ。恋人がいないっていうのも話したとおりだ」
「そう、そのはずだったんです! けれど、その均衡を崩そうとする身の程知らずさんがいらしたのは事実です。今はまだ問題無くても、いつか誰かのものになってしまう――それだけは避けなければなりません! お兄さんならわかりますよねっ?」
同意を求められても由弦は何も言えなかった。全く知らない言語で熱弁されても内容を、まして核心など理解できるはずがない。煮え切らない態度の由弦に憤慨したのか、園田は肩掛けバッグの中から小さな紺色の容器を取りだして叫ぶ。
「日本は火葬だからですよ!」
「……は?」
「どうにかしないと六花を保存できないでしょう? すべてを美しいまま保つことができないならせめて一部だけでも残しておかないと! 本当は毛髪が欲しかったのですが、調べられたとき切られた箇所があったら不自然にみえかねません。だから彼女の首を刺しました。彼女のお気に入りのペンだったら痛くても許してもらえるから、ジップロックの中からお借りして……缶の中に溜まっていく彼女の温もりは何よりも尊く、これ以上なく素晴らしかったです」
恍惚とともに両手でボトルを抱える園田を眺めながら、由弦はどうにか思考を試みる。
こんな理由のために殺されたのか。怒りや恨みを抱かれていたのならまだ受け入れられたのに……六花はあの子らしく生きていただけだったのに?
園田の手には、今は刃物が握られていない――行動は早かった。由弦はその手から容器を取りあげた。中身が音を立てて揺れる。取り返そうと手を伸ばす園田を制して、容器を地面に叩きつけた。
ガラスが割れる音とともに液体が飛び跳ねて広がる。
「君の言葉を借りると、生きているときのほうが六花は圧倒的に美しかったんだよ……。ああ、愚かしいね。美しさを保つために殺したのに、そのせいで醜く枯れることになったんだ」
「あ……ああ…………」
ボトルの破片を乱暴に踏みつけて責める。
「純粋に君の愚かな行為によって! 切り取った一部ですらいつかは朽ち果てるのに」
アスファルトの表面をなぞる液体をどうにかその場に留めようとする彼女を見下ろす。
「妄言吐いてないで目を覚ませよ。お前がその手で白河六花を殺したんだ。それ以上でもそれ以下でもない」
冷たく言い捨てながら立ち上ってくる強烈な臭いにむせ返りそうになる。
缶に溜めた血液を、その容器に移動させたのだろうか……ふとカフェで聞いた話を思い出した。男子部屋に集まった後、園田はお手洗いのために女子部屋に戻っている。その際にでも入れ替えられる。持ち物を確認されたとしても中身まで確認されたわけではなかっただろう。
もし確認されていたならごまかしようもない。
すると、地に伏せるように肩を震わせていた園田は、突然立ち上がる。
腹の底から何かを叫びながら由弦に体当たりする。体格は由弦のほうが悠に勝っているが、勢いは往なしきれなかった。倒れた拍子に地面に後頭部を強く打ちつけ、次第に鈍い痛みを知覚する。
銀色が月光を反射する。
視界が揺れる。園田が両目から涙をあふれさせながら両手で握りしめた刃を振り下ろそうとした、次の瞬間――――突然姿を現した髙橋が、園田を取り押さえた。彼女は抵抗しながら何か喚き続ける。
「怪我は?」
手を差し伸べてきた人物――鷲見を見上げた。問いに対して由弦はゆるゆると被りを振った。
「頭ぶつけてただろ」
「すべて聞いてたんですよね、最初から。私の話、どれくらい正確でしたか?」
「想像に任せる」
「任せたからこうなったんですよ」
鷲見は由弦の隣に膝をつくと、質問を変えた。
「知りたいだけというのは、本心だったんだね?」
「……真相がわかれば気が晴れると信じてたんですけどね」
「自棄になるな。止めなかったらどうなっていたか、わかるだろう?」
「メロスが帰って来なかったら、セリヌンティウスだって友を恨むものですよ」
由弦は言ってから自分の言葉に笑った。小さかった笑いが長引き、少しずつ大きくなる。
事件後、初めて心から面白いと感じて笑った。妹を信じていたのに現実に裏切られた。結局、約束は守られず、リュックサックは返してもらっていない。
本人すら三日間の期限は守れなかった。果たして暴君は何をすれば良いのだろう。
由弦は体を起こして立ち上がろうとする。それを遮ったのは、鷲見ではなく髙橋だった。
「安静にしているんだ。救急車は呼んだからここで」
髙橋の手を外そうとしながら「大丈夫です」と立ち去ろうとしたが、「何かあったら寝覚めが悪い」と引きとめられる。
「死なせてすらくれないんですね」
「……遠回しな自殺か」髙橋が言う。
「これからどうしろと?」
「まだ若いんだ。考える時間は長い。きっと何か見つけられる」
鷲見は頭部の打撲を刺激しない程度に由弦の肩を軽く叩いた。すると、
「他に何がありますか」
唐突に理解した。
かつて証言を無視してしまった少女の、あの表情……あれは悲しみや不満などの負の感情が煮詰められたものだったと理解した。怒りに近い何か表層に現れたものだった。
清水のような声色の彼に返せる言葉を見つけられなかった。じんわりと穏やかに、しかし確実に寒気を自覚する。自らの言葉が宙を空回ったのも遅れて理解した。
16
残酷にも日は巡る。後期も必修講義が多いため課題は溜まっていくが、休学届を出せるほどの気力はなかった。どうしても課題を進めなければならない。あまり家にいたくない。特に理由も用事もないが、よくカフェで作業するようにしていた。そうすれば体を起こしておかねばならないし、帰るためには終わらせなければならない。
「ねえっ、起きてよ! 今日は朝から出かけるって約束したでしょ?」
甲高い声で催促する妹の声――わかっている、幻聴だ――由弦は引っ張られるように体を起こした。
自分の準備を完璧に済ませてリビングでのんびり絵を描いていた彼女に「……行こ」あくび交じりに声をかけた。スケッチブックを閉じながら丸くした目を瞬かせながら
「さっきまで寝てたよね?」
駆け足で道具を自室へ片付けに行った。
「本気だせば百十秒で支度できる」
キッチンで利き手の小指側にこびりついた炭素を洗い落として「四十秒は?」手を拭きながら尋ねてきた。端的に「無理」とだけ返す。
「朝ごはんいらないの?」
「そこらへんで珈琲買う」
「うわぁ、不摂生」
「クリスのグリーンスムージーと変わんないって」
「はーい、ゲンは世界中の美容に真面目な人たち敵に回しましたぁ」
「愚か者が。我こそ、この世界を滅ぼさんとする者なるぞ」
「手始めに?」
「カフェイン摂取する」
「じゃあ私のも買って! 今月の新作、抹茶なの!」
「去年もこの時期そうだったと思うけど」
「企業努力は消費者に届いてこそ意味を成すんだよ」
ただ飲みたいだけだな、とは思ったが口には出さなかった。待たせた詫びにもなるだろう。靴を履きながらスマートフォンと財布だけは持っていることを確認して家を出発した。
向かう先は変わらないが、心模様までは似ても似つかない。真上から日光が降っており、澄んだ白い光は眩しかった。寝ぐせ直しのついでにキャップを目深にかぶった。歩道の信号を眺めながら、色が変わるのを待つ。ビル風が吹き抜けて首筋を冷やした。これを心情に重ねて寂しいと表現する人もいれば落ち着くと表現する人もいるだろうか。由弦は帽子が飛ばされないよう片手で押さえた。
秋は深まらず気温が安定しない日々が続いているものの、今日は暑すぎず寒すぎず……不意に数日前に電話で聞かされた証拠品を返却できる旨を思い出した。時間があるときに、とだけ曖昧な返答をしたが、今日なら構わない気がした。トートバッグの中には、ノートパソコン、充電器、イヤフォン、スマートフォン、財布――問題ない。肩紐を掛けなおして背に回す。スニーカーの紐を結びなおした。立ち上がった瞬間、青信号に変わった。
いつものようにホットコーヒーを注文して席に着くなり半分を嚥下した。誰かと目があった気がしたが、イヤフォンを装着して課題を消化しにかかった。一度も途切れなかった集中。最後にカップの中身を呷り、ダストボックスに放ってカフェを出た。
新幹線で向かわねばならない必要性を見いだせず、結局、在来線を乗り継ぐことにした。
到着まで数時間かかる。立ち続けていられるほど体力に自負は無い。開いている席に腰を下ろして一息ついた。最初の数駅は車内アナウンスを聞いていたが、いつの間にか微睡んでいた。
「年号は、もう教えるも何も、覚えるしか無いでしょ」
リビングのテーブルに突っ伏せる妹に言った。
「年号覚えられない」
「数字得意なのに?」
「日本語が好きな人は、アイヌ語も英語もアラビア語も得意だと思うの?」
「無理だね。じゃあ、語呂合わせは?」
「ワンツーツーワン承久の乱」
「……それ語呂合わせじゃない、力技」
「ウグイスおはようキケリキー」
平安京か平城京か、どちらか混乱する云々の訴えかと思ったが「それ、は……何?」考えるまでもなく初めて聞いた。そもそも語呂合わせでは無い。
「もー、私だって家康に育ててもらえるウグイスになりたい!」
さすがに当人もよくわかっているらしく、両足をパタパタさせながら天井を仰ぐ。
「残念ながらホトトギスだなぁ」
「天下人なら何種類だって鳥飼って良いの!」
今はとにかく不満を発散したいのだろう。正論は意味を成さない。
「まあ、昔から文字列覚えるの苦手だよね」
「そうっ、そうなんだよ! 文字列が覚えられないの!」
「だったら……」由弦は近くのルーズリーフを引き寄せて、有名な年号をいくつか列挙した。それを、顔を上げた六花の前に掲げる。「……紙に列挙して、これを覚えるのは?」
「力技?」
「語呂合わせは音感頼りで意味を付随させて記憶する作業。それができないなら真正面から向き合うしかない」
「他に無いの?」
明らかに乗り気ではない。しかし、始める前にどれだけ及び腰だろうと、結局は取りくむ。わかっているからこそ突き放しても問題ない。
「ワンツーツーワン行けるなら行ける」
「うぇええ……」
電車に揺られている間、いくつか記憶が再上映された。しかし、目覚めてしまうと鮮明に覚えていられたのはたったワンシーンだけだった。惜しくなってもう一度目を閉じてみたが、熱海駅に到着してしまった。
季節が異なると印象も異なる。足を踏み出せば車窓から走り去っていた景色はゆっくり隣を進んでくれる。体温と気温のコントラストが心地よくなってくると、自然と歩幅が大きくなるのがわかった。
ようやく記憶が重なる場所に到着したころにはもう陽は暖色を帯び始めていた。
三六〇度を見渡す。もう半周ほどして、視線は北北東へたどりついた。献花台は撤収していたが、花束がいくつか並んでいた。
由弦はトートバッグを膝に乗せるようにしゃがんだ。
「Requiescat in pace.
(死者に安らかな眠りを)」
ここなら、誰もいない。誰も聞いていない。誰も見ていない。
日記帳のような空間だった。
どれほど時間が経過したのか、背中の熱が消えていた。いつの間にか、影が夜に解けようとしている。海のほうを眺めると、黒ではないが深い青……眼鏡を外して見ても色は変わらなかった。
天から零れる月の光は、あらゆるものを蒼く照らし出す。
すべてを浄化し得るだろう清い光を浴びようと、決意は変わらない。いつまでも、白河由弦という人間を作るひとつの要素として肚の底で澱んだままだった。
リュックサックに詰められた返却品を片手に、コンセントがある店を調べて熱海駅併設の商業施設に入った。適当にパンを買って、妹のスマートフォンを充電する。
蛍光灯が狭量はなはだしく窓ガラス越しに見える月光を和らげてしまっている。
この月を最後にこの地を去るのは心なしか癪に障った。
電車に揺られながらやろうと思っていたが、充電が半分を超えたあたりで店を後にした。しかし、とくに行く当てはない。宿泊先も目的地も無い。
なんとなく海岸へ足を運んでみた。この季節の日が落ちた時間に泳いでいる者の姿は無いが、波打ち際で水温の低さを騒いでいたり砂浜の建築を嗜んでいたりする人々は少なくない。ひとまず由弦は離れたところで彼らの仲間に加わった。胡坐で、トートバッグを置いた上に肘を乗せる。満を持して妹のスマートフォンと向き合う。スケッチブックに描いた花の絵が表示される。幾重にも重なる花弁が、恥ずかしそうにはにかむ彼女を思い出させる。筆致をなぞるように画面を撫でた。画面がカメラに遷移して、焦ってホームボタンを押した。元の画面に戻り、もう一度、ホームボタンを押す。
パスコード入力を要求する画面だ。六桁の数字を要求されている。
不意に、 日記の最初のページが脳裏を過ぎった。花のイラストと
「雪……さ、く、は、な……違う…………」
――闇夜に咲き誇れる日を待ち望む
――八、三、四、二、三、九
入力してみると……ホーム画面に遷移した。
簡単なことだった。考えてみれば容易にたどり着ける答えだった。随分前に、刑事に知らないと答えた自分の愚かさに面白さがこみあげてきた。
なんとなく空を見上げる。
月光で安心した。陽光は眩しすぎる。