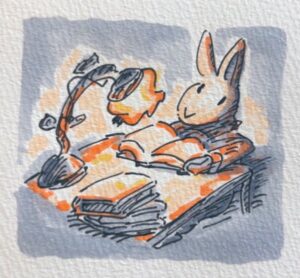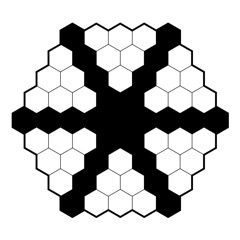本作で語られるものはすべてフィクションです。本作の岩松城のモデルは、会津の若松城です。
第一章 蓄音器泥棒の殺人
1
ひとりの女子学生が、「熊沢館」という民宿を探しながら、人気のない夜道を歩いているところだった。
日はすでに山並みの向こうに没してしまい、押し寄せるような黒雲からは土砂降りの雨。
ボツボツと雨音の鳴る傘片手に、道のところどころにある外灯の光を頼りに歩いていると果たして、山道の先に、汚らしい三階建ての洋風建築があるのが見えてきた。ぼうっと照らし出された看板には、「熊沢館」と、墨でのたくったような汚い文字が見えている。ここで間違いないだろう、と思った瞬間、女子学生はようやくほっとして胸を撫で下ろすことができた。
腕時計を気にしながら、軋んだガラス扉を引き開けて、ひとりでロビーに立ち入った女子学生は、常滑焼やら、民俗人形やら、美しい原石やら、さまざまな骨董品のところ狭しと並んでいる、赤いカーペット敷きの幾分レトロなその空間が物珍しくて、しばし目を奪われてしまった。
「すみません……!」
奥に向かって声をかけても、静寂が張り詰めているばかりであった。刹那、ぽちゃんっという音が響いた。はっとして、右手を向くと、水槽の中の金魚が飛び跳ねて、返事をしたのだった。
「君に話しかけたんじゃないよ……」
金魚は何食わぬ顔で泳いでいる。
女子学生は前日に、旅行サイトで宿泊の予約を済ませていた。今日は、大学の授業終わりに埼玉の自宅に帰宅して、旅行の荷物をまとめてから、上越新幹線で、遥々埼玉のさいたま市からやってきたので、宿への到着がこんなにも遅くなってしまったのだった。
しばらくすると、廊下の奥から白髪混じりに丸眼鏡の、恐ろしげな顔つきの男性がのそのそと歩いてきた。
「いらっしゃい……」
「あの、予約している芦沢柚葉です……」
「ああ、芦沢さんね。ようこそおいでになりました」
その言葉に安心した芦沢柚葉は、瓶のオレンジジュースやコーラが数本入っているガラス張りの冷蔵庫の、鏡のような一面に映っている自分の顔をふと見たのだった。
柚葉は、都内の大学に通う史学科の二年生である。黒髪を首元あたりで綺麗に切り揃えていた。同級生に色白な美人と褒められることもあるので、自信過剰になる日もある。しかし自分の顔が嫌で嫌で仕方なくなる日も多くあった。人間だもの、そう思って誤魔化す日もあったのだが、そもそも美とはそんなに大切なものだろうか、と首を傾げている。勝手に美を定義されて、それに従わなければならないこの社会の不自由さには常日頃から辟易としていた。私たちはもっと自由であっていいのじゃないだろうか。
「芦沢さんね。ちょっと待ってね。今、ここにお名前を書いていただきますから……」
この民宿の主人と見えるその男性は、名前を記入する紙を、薄汚れたカウンターの上にそっと出した。柚葉は、幾分緊張しながらペンを取り、名前を記入してゆく。
「わたしは熊沢館の主人の熊沢大吉です。よろしくお願いします……」
「よろしくお願いします……」
柚葉は、その主人から昔ながらのプラスチックのスティックがぶら下がった鍵を受け取った。そして言われるままに奥の階段をのぼって、三階にある自分の部屋へと向かった。
柚葉が鍵を開けて、電気をつけ、中に足を踏み入れると、畳敷きの部屋は電灯の下、畳の香りのする、澱んだ空気をずっと溜め込んでいたようだった。柚葉は鞄を床に放り出して、畳敷きの部屋の片隅に深く座り込んだ。床の間には、風神の掛け軸がかかっている。それがどんよりした暗いオーラを室内に漂わせていた。墨に汚れたような風神の血走ったまなこは、なにかを訴えているかの如く悲しげな光を放っていた。
柚葉が、窓の外を眺めると、雨に濡れそぼる、この暗い街の陰鬱な光のゆらめきが、イルミネーションのように、かわるがわる、目に飛び込んできて、どきりとさせたのだった。
(今日から知らない土地にひとり。人見知りのわたしには慣れないひとり旅……)
柚葉は畳の上に胡座をかくと、ふと薄暗い天井を見上げた。
天井に黒いシミが渦巻きのように広がっていた。
今は三月であった。ところどころで、梅の花が咲き乱れる季節である。
外を見ると、窓の下に梅の花が見えている。
昼間は美しい梅の花であっても、暗闇の中の外灯のもとでは、白っぽいもやのように浮かび上がっているだけである。
うら若き女子学生が、こんな観光地へとひとり旅をしにやってきたのは、誰の目にも奇妙なことと感じるかもしれない。
これには理由があった。柚葉は史学科の生徒なので、どうしても四月以降のゼミのレポートを仕上げるために、史跡めぐりをしなければならなかったのだ。
史学科のゼミの美しき禿頭の教授は言った。「失われていると思われている歴史の中で、今なお、わたしたちの内側で持続しているものをレポートにまとめて来なさい」。その言葉の意味は、不明確であった。この宿題の提出日は示されていなかったが、この春休み期間に資料を集めておくとよい、というのが先輩たちの助言であった。とりあえず史跡をめぐっておけばよいのだと柚葉は思った。
どうせ史跡をめぐるのなら、旅行を兼ねようと思ったのだったが、仲の良い友人と予定が合わず、このような寂しいひとり旅となってしまった。しかし柚葉はそれもまた楽しい気がした。ひとり旅というのは、自分の内面と向き合える時間である。果てしない過去から持続しているものを自分の内面に発見できるかもしれない、と柚葉は思った。
柚葉の見つめる窓の外、景色の先には、美しくライトアップされている日本の城郭があった。
(あれが……)
柚葉は、その四層の城郭を見つめながら、明日はまず、あの場所へ訪問してみようと思った。なんでも、あの城はかつて小田原北条氏の支城であったそうだ。豊臣秀吉の小田原征伐の際に、猛攻を受けて、落城させられたものだという。江戸時代に入ってからは、現在のような石垣の城となったのだが、戦国時代には迷路のような曲輪をこしらえた土塁の城であったということを、柚葉は事前に調べていた。
「絶好の歴史散策ポイントだな……」
この地は、温泉も湧くというから、歴史あり、温泉もありの優れた観光地スポットといえるのだった。それがどういうわけか、今、観光客も少なく、民宿の経営が苦しいという噂を聞いている。
柚葉は、腹が減ったので、最低限の荷物を持つと、民宿を飛び出した。坂道が続いているところを下ってゆくと、昔ながらのうどん屋があった。そこで天ぷらの盛り合わせと共に一杯、かけうどんを食べる。柚葉はうどん好きであった。民宿を素泊まりにしてしまって、こうした店で腹ごしらえをするのも悪くないと思っていた。うどん屋の店主は愛想よく、柚葉を迎え入れてくれた。
柚葉が、うどんをすすりながら、歴史の名所がありますかと尋ねると、うどん屋の店主は、
「まずは、あの岩松城だね。それとその反対側に、密教寺院があるから、そこも尋ねてみるといいよ。街の真ん中を貫く商店街には、お洒落な喫茶店なんかもあるし……」
と優しくなんでも教えてくれる雰囲気だった。柚葉にはこうした案内人的な存在が嬉しく感じられた。
「ジャズは好きかい?」
「ジャズ?」
柚葉はその言葉に驚いて、思わず聞き返してしまった。柚葉は生粋のジャズファンだったので、あまりの偶然に戸惑ってしまったのだ。
「いや、ジャズ喫茶があって、いつも貴重なレコードを流しているんだよ。ネルドリップで淹れた昔ながらのコーヒーが自慢でね。ジャズに関しては、たまに生演奏なんかもやっているから、もし長く滞在するのなら……」
「楽しそうですね。ジャズの生演奏。わたしは普段、レコード盤で聴いています」
「へえ、若いのに珍しいね」
と、うどん屋の店主は突然、柚葉が遮るように喋り始めたので、面食らったようだった。
「ええ。ハードパップもモードジャズもフリージャズもなんでも聴きます。時代でいえば、ディキシーランドジャズからコンテンポラリーまで……。でも、わたしが一番好きなのはセロニアス・モンクとエリック・ドルフィーなんです。尊敬しているのは、ビリー・ホリデイです」
「な、なるほど……。すごく詳しいんだね」
うどん屋の店主は幾分、反応に困っているようだった。
柚葉は、ジャズと聴くと興奮してしまうのだった。
「セロニアス・モンクのピアノははじめて聴くと、おもちゃ箱をひっくり返したみたいだけど、それでいてとても美しく整っているんです。セザンヌやピカソの絵のように……。またそこから醸し出されるブルージーな悲壮感と美しい幻想は、いつだってわたしの心を癒してくれます……」
本格的に語り始めようとしたところで、柚葉は自分が一方的に喋っていることに気がついて、口を閉じた。そしてわずかな気まずい静寂がその空間を包んだことに、責任を感じた。
「行ってみます。時間があれば……」
変な間合いを埋めるように、柚葉は言葉をまとめた。
「是非」
と、うどん屋の店主は笑って答えた。
2
柚葉は翌朝、城へと向かうために再び民宿を飛び出した。一日で城と寺をめぐることができれば、時間の節約にこそなるが、レポートを仕上げることを考えると、日を分けた方が良い気もした。市内循環バスに飛び乗ると、十分もしないうちに大手門前に到着してしまう。
強い日が差し込む車窓からは、風に揺れる梅の花が無数に咲いているのが見えていた。
柚葉は、タイヤの上の席に座り、煌々としたアスファルトの道を見下ろしていた。冷たい隙間風が吹き込んで、優しい春の訪れを感じさせる。城に近づいてくると、柚葉は鞄を握りしめて、スニーカーを履いた右足をぶらつかせて、スムーズにバスから降りるための準備をした。
(ひとり旅もなかなか楽しいな)
柚葉はそう思った。
柚葉が、小銭を運賃箱に放り込んで、バスから飛び降りると、左手には広い駐車場があり、道の反対側には石垣のお堀が続いていた。そのあたりにも梅の花が絢爛に咲き乱れていて、柚葉はカメラを取り出し、梅の花と城郭を重ね合わせて数枚の写真を撮った。
(実に良い眺めだ)
柚葉は写真を撮りながら、土塁を渡り、枡形(ますがた)虎口(こぐち)に入ってゆく。お城は迷路のようなものである。迷い込んだ先で足止めを食えば、左右から矢の雨が降る。鉄砲の弾を浴びることもあっただろう。柚葉は、石垣と門に囲まれたその空間をまじまじと見つめながら、感慨深く思った。
(一体、この門をどうやって突破したというのだろう……)
分厚い木に鉄板の打ち付けられた頑強な城門は、アメリカの映画の中で、大猿キングコングを防ぐために南国の原住民がこしらえたあの大門を彷彿とさせる。
「でも、石垣の城になったのは江戸時代のことで、北条氏の頃は土塁の城だったはず……」
それならば、当時、この大門ももっと違ったものだったのかもしれない。
そうは思ってみても、柚葉には、人々が石垣を登ろうとして、槍で刺されて転がり落ちる武者や足軽の姿がしきりに目に浮かんでくるのだった。
二の丸を越えて、本丸へと入ると、四層の天守閣が天高くそびえていた。
中へ入ると、黒々とした板敷の間で、急な階段がいくつもあった。梯子を登るようにして、階段を登ってゆくと、間もなく天守の最上階にたどり着いた。小さな正方形の部屋で、四方を高欄に取り込まれていた。柚葉は、景色を眺めようと思って、足を踏み出した。
青天の下の、屏風のような山並みに囲まれた小さな街の中である。寺院の甍のある方向へ向かって、家並みに挟まれた辻が続いているのを見ると、あのあたりが商店街というのだと思った。
冷たい風が前方から吹きつけてきて、柚葉は涼やかな髪が舞い上がった。
ふと隣を見ると、三十歳手前くらいの男性が立って、一緒に景色を眺めていたのだった。
(この御仁は……)
柚葉が驚いたのも無理はなかった。その御仁というのが、絶世の美男子だったのである。四十六億年の地球の歴史において、類例がないほどの美男子であった。黒髪が風に乱れ、瞬くように目を細めていながらも、その男性への異様な確信は、柚葉の胸を駆け巡っていた。
(落ち着きたまえ……)
と柚葉は思った。
(ただの人間だ。神や仏でもなければ、物の怪の類ということもないだろう。こうして床に足つき、風に煽られて、呼吸をしているからには……)
柚葉はそう思いながら、ちらりと見る。男性はしかし、おそらく恋にでも悩んでいるのだろう。憂いが刻まれている、悲壮感のある表情が美しく凛然としている。
「すみません」
とその男性が声を発した。柚葉はどきりとした。
「はい!」
「黒髪で、赤っぽい服を着た女の子を見ませんでしたか?」
「えっ、黒髪……」
「僕の妹なんですけど、入り口ではぐれて、電話で連絡しても出なくて……」
と男性が言うのをみると、どうも「女の子」というのは幼稚園児や小学生などではないらしい。この人の妹というからおそらく二十代の女性だろう。
「さあ、すみません。たぶん見てないと思います……」
「ここにのぼれば見渡せるので、見つけられると思ったんですけどね……」
「確かに高いところから探すというのはひとつの手ですよね」
短絡的な発想だな、と柚葉は思った。馬鹿と煙はなんとやらというけれど。
「ものすごく天然な妹なんです。芸術家だから、なにをするにつけても、自由気ままでマイペースなんですよ」
「ふうん」
話してみると、この男性は気軽で話しやすい人物だということが分かってきた。
「黒髪であることと赤っぽい服以外に特徴はありますか?」
「スケッチブックを手に持っていると思います。だから今もどこかで絵を描いているのかもしれない……」
そういうと男性は、なにか考え込んでいる様子だった。
「見つけたら、お兄さんが探していましたってお伝えします」
「ありがとうございます。妹はひどい方向音痴だから、ひとりで民宿に帰れないかもしれない」
「方向音痴なんですか」
「すごく……。芸術家だから方向という観念を否定しているのかもしれない」
そんなわけないだろう、と柚葉は思った。
「熊沢館という民宿なので、バスですぐなんですけど……」
その名前を聞いて、柚葉は再びどきりとした。自分が泊まっているのと同じ民宿の名前であった。
3
柚葉は、天守閣から降りると、二の丸の広場にある歴史資料館に向かった。
受付に人の姿はなく、硬いガラス扉を引き開けると、蛍光灯の白っぽい光の下、木造の城の模型が飾られていた。その先には、壁伝いに古風な甲冑がずらりと並んでおり、柚葉はそのひとつひとつを観察しながら歩いた。
鈍い光を放った刀身も飾られていた。柚葉はまじまじとそれを見つめながら、少しでもこの刃に指が触れれば、たちまち切断されて宙に飛んでしまうのだろうなどと思って、背筋が冷たくなった。
刀の黒塗りの柄と鞘は上下に分けられて、段を変えて展示されている様は重々しい印象であった。柚葉は興味深くそれらを観察していった。スマートフォンで写真を何枚も撮影した。
(歴史を感じる。わたしは今、歴史を感じている……。過去から押し寄せてくるイメージの大群に飲み込まれてゆこうとしている……)
自分の血の中にこうした戦乱の記憶が宿っているとでもいうのだろうか、柚葉はめらめらと燃えたぎる闘志を自覚していた。ポニーのような小型の木曽馬に乗って、野山を駆け巡り、敵陣に斬り込んでゆきたいとすら妄想した。
ところが、イメージはだんだんと変質していった。燃え上がる城郭、石垣から転がり落ちる人々、泣き叫ぶ声。鮮血が滝のように流れ落ちる。この城を守った人々が無惨に死んでゆく有り様をまるでどこかで見たことがあるみたいだった。
(過去からの持続、わたしの中に眠っているもの……)
しかし我に戻ると、柚葉は、埃をかぶった静寂の展示室にひとり佇んでいるのだった。
(わたしは歴史と関係なく存在しているのか……)
そう思える瞬間もあった。目の前の甲冑や刀剣が単なる「もの」としか思えなくなり、歴史の幻想がどこか遠いものに感じられて仕方がなくなってくるのだった。
(すべては感覚だ。わたしの感覚がすべてを理解し、幻想を打ち破る。そこには何もない。幻想を掴むこともできない。しかしこの「もの」であるということを理解し、幻想を打ち砕くことで、自己と他の境界を突破できるのだ……!)
柚葉はそう思った。確かにそうかもしれないと自覚している。しかし浮かび上がる幻想は異様に生々しかった。
柚葉は、展示室の奥へと進んでゆく。炎上している岩松城の油絵が、壁にかかっていた。豊臣秀吉の小田原征伐の際に、この支城も攻められて、燃え上がった。その時の再現図だということが、柚葉にはすぐに分かった。
(凄惨な……)
そう思わずにはいられない。その絵は柚葉の妄想とはどこか違っていた。
今から四百年あまり昔、豊臣秀吉の二十二万の軍勢は、小田原城を本城とする小田原北条氏を征伐するために、関東に出兵した。北条氏の支城網は、蜘蛛の巣のように関東地方に張り巡らされていたが、この群馬県のこの地にも、支城を構えていたのである。そして、その支城は次々と攻略されていった。そのうちのひとつがこの岩松城なのであった。
(この時に失われた命は今、どうしているのだろう……? 絶えて消えてしまったのか。それとも今もどこかにあるのか……)
死者の霊魂は今、どこを彷徨っているのだろう……?
失われたと思われている歴史の中で、今なお、わたしたちの内側に持続しているもの……。
柚葉はそんなことを考えながら、展示室の奥へ奥へと足を踏み入れていった。
そして柚葉はふと、あるものに気がついて立ち止まったのである。
パンフレットの置かれた机の上に、見たことのない宝石を抱いた、美しい紫色の数珠が落ちていたのだった。
(これは……なんだろう)
展示品という印象もないし、見たところ高価なもののようだから、こんなところに放置してあるのも不自然な気がした。忘れ物だろう、と柚葉は直感した。そして、ほとんど無意識にそれを手に取ると、展示室から飛び出した。外の光が別世界のように眩しかった。この数珠を手にしたところで、事務室や管理人室の場所がわからなくては、届けることができないな、と柚葉は思った。しばらく呆然としていると、決心がついて、それを鞄に入れて、事務室を探して運ぼうと思った。忘れ物だとしても高価なものなら、あの場に放置をしておくのは盗難の危険があると思ったのだった。
(しかし一体これは……)
紫色の数珠を手に、二の丸の真ん中あたりまで歩いてきた柚葉は、砂上でぼんやりと立ち尽くして、雲のない青天を見上げた。世界が丸くなって自分を包み込んでいるようだった。その中で、自分は小さくなり、まるで存在していないかのようにさえ感じられた。紫色の数珠はずしりと重たかった。この重さだけが柚葉にとっての現実だった。
4
民宿「熊沢館」に戻る前に柚葉は、市内循環バスで商店街へと向かった。明治大正を感じさせる洋風な建物の並んでいる中に、ジャズ喫茶があるということだった。地下へと通じる階段を下ってゆくと、午後六時を過ぎて、私語厳禁から解放されて、ジャズ喫茶は、ジャズクラブ状態となっていた。丸いテーブルの席に座ってコーヒーを注文すると、小さなステージで黒人ピアニストが「枯葉」を弾いていた。そこに売れない小説家の男がいた。ウイスキーを飲みながら、帽子を目深にかぶったその男は、田崎慎一という名前であった。
「ジャズが好きと見えるね」
とその男は酔っ払いらしい回らない舌で話しかけてきた。
「はい」
「レコードを聴いているのかね」
「ええ。セロニアス・モンクとエリック・ドルフィーが好きで」
「それなら君は、俺の友達だ。セロニアス・モンクとエリック・ドルフィーが好きなやつで悪いやつはいない。ジャズ研かい?」
「いえ、ただ聴いているだけで……」
そういうと柚葉は、自分が相手の期待から外れてしまったことにわずかに悲しくなった。
「気にするな。レコードは俺たちに過去を追体験させてくれる。いつだって通り過ぎたもののはずなのに、再生される音は現実のものなのだ。俺たちはそうやって過去の本質を知るのさ。過去はどこにもいっちゃいない……。ただ内面化されただけだ。なあ、そうだろう。セロニアス・ヒムセルフを二周もしてると見えてくる世界があるさ」
「はあ、ヒムセルフを……」
深いことを言っているようだが、柚葉にはわからない。
田崎慎一は少し、寂しそうに俯いた。小さな声で「過去」と繰り返している。
「君は小説を少しは読むかね」
「少しは、太宰治とか芥川龍之介とか……」
「太宰や芥川なんて駄目さ」
そう言ってすぐに人の好きなものを否定するところをみると、意地悪な気もしたが、そういいつつ、嬉しそうな顔をしているので、本心はどうかよくわからない。
「谷崎潤一郎も……」
「それも駄目だね。君は時代に取り残されてしまっているよ。まるでこの俺みたいだな……」
そう言うと、田崎は青白い顔で寂しそうに俯いた。
「だから俺の小説は売れないのさ」
柚葉は返事ができなかった。
「君も俺と同じで過去に取り残されている人間なんだ。セロニアス・モンクとエリック・ドルフィーを愛しているところまで同じだ。そして、この観光地のあの悲しい城も俺たちと同じ、過去に縛られているのさ。そして過ぎ去りし思い出ばかりを胸に抱いているのさ」
柚葉はしばらく考えた。
「わたし、過去から持続しているものを探しに来ているんです」
「過去から持続しているもの。そうだな。それは俺たちが吸っているこの空気だ。俺たちが踏み締めているこの土だ。そして掴むことのできないあの青空じゃないか。でも君はそんなもの、どうして探しているんだ。どこにでもあるのに……」
「どこにでもあるはずなのにどうしても見つけられないんです……」
その言葉の意味を、田崎はしんみりと考え込んでいるようだった。
「そうだな。どこにでもあるはずのものでもいざ見つけるとなったら大変だ……」
田崎は、ジャズピアニストが「チュニジアの夜」をゆったりとバラード風に弾き始めたので、不満げに唸ると、柚葉の方を向いた。
「この観光地も、すっかり観光客が減ってしまってね……」
「どうして減ってしまったのですか?」
「なんだ、何も知らないのか。これを見てごらん……」
田崎はスマートフォンで、ある記事を取り出してきた。柚葉はそれを見ると、意味を理解した。
「怨霊騒ぎさ」
「今の時代にそんな……」
「今の時代だからこそ、面白がってユーチューバーだのなんだのが集まってきて、観光資源をめちゃくちゃにしてしまうのだろう。それもひとつの怨霊の仕業かな」
ナンセンスだとも思わなかった。そして柚葉は、この売れない小説家と別れた。
柚葉は熊沢館の自分の部屋へと戻ってきた。柚葉はまず、田崎が教えてくれた記事をスマートフォンで検索し直した。それと同時に、資料館で集めてきた戦国時代の資料を机の上にひろげた。
柚葉は、それらをまじまじと見比べている。
(ふたつの出来事に関連はあるのかな……)
柚葉は、数年前の事件の記事を見つめながら、過去から不断の持続の中にあるふたつの現象の関連を頭の中で探っていた。
田崎が教えてくれたのは五年前のある事件の記事であった。
「地震により、霊妙寺の北条氏家臣の供養塔が横倒しとなった直後、猿渡家心中事件は発生した。そのためにこれは北条氏家臣の呪いなのではないかと世上で囁かれていることとなった。事実、この噂が流れた後に、この観光地の客足は遠のいている」
柚葉は記事の一文を繰り返し読んだ。「猿渡家心中事件」というのが、ひどく気になる内容であった。
「猿渡家心中事件において、もっとも異様な存在として印象的なのが、三体の遺体のそばにあった食べられていないアップルパイである。このアップルパイは東京都内の某有名店のものであったが、このアップルパイをこの家に届けた人物が誰であったのかは、はっきりとしない。もしも猿渡家心中事件が、猿渡庄造による無理心中事件だとしたら、このアップルパイの存在が説明づけられないのである」
柚葉はなるほど、と思いながら早口の小声でボソボソと音読を続けていたが、声は部屋に浸み込むように消えてゆくばかりで、馬鹿らしくなって、黙読に変更した。
(しかしながら当時有力であった被疑者には、完璧なアリバイがあり、捜査陣営はそのアリバイを崩すことができなかった……)
これがミステリ小説ならば、いかにも面白そうな状況である。
しかし柚葉が現在、気にしているのは、実はそんなことではない。
小田原征伐の際、この地の農民含め、多くの人々が城に立て籠もり、無数の死者を出すことになった北条氏の家臣団であったが、その霊魂が今もこの地に眠っているという噂はかつてからこの地の伝承として続いていたものらしい。それらは怨霊として残っていることがゆえに供養塔は最大の供養であった。その供養塔が地震により、横倒しとなった。霊魂は、荒御魂となり、祟り神となり、災いとなって降りかかり、この猿渡家心中事件が発生した……。
それが歴史好きの柚葉にはなんとも真実めいて感じられて、恐ろしくなるのだった。
「北条氏の家臣の、そしてその農民たちの霊魂は今もこの地に彷徨っているのかな……」
城の向こう側には、寺があった。そこでこの時に命を落とした人々の供養塔や墓が立っているのだという。地震の際に横倒しになったという供養塔もそこにあるはずなのだ。
「わたしは、この謎を突き止める必要がある……」
柚葉は、ノートに二つの文章を記入した。
・四百年前の岩松城落城
・五年前の猿渡家心中事件
このふたつの謎とその関係性を解き明かそうと、柚葉は誓った。そしてそれを怨霊論にして、レポートにまとめてゼミの美しい禿頭の教授に提出しようと考えた。
しばらくぼうっとしていると、妙にわくわくしてきた。
居ても立っても居られなくなって、この民宿の中を探検してみようと柚葉は思い立った。部屋から出て、ぼんやりしながら廊下をのそのそ歩いてゆくと、一角に小さなゲームコーナーがあり、ずいぶんと古いカーレースゲームや、スロットが並べられて、チカチカと下品に光り輝いていた。それらが玩具のように子どもっぽく、空虚で美しく感じられた。その隣には古いマッサージ機があった。見ると少女と呼称するのが似合っているような若い女性がひとり、浴衣姿で、マッサージを起動しながら、椅子の上ですやすやと眠っているのだった。一匹の巨大な猫のような印象だった。歳はまだ十代といったところか。しかし柚葉は、人の年齢を見抜く自信があまりないので、もう少し若いかもしれないし、その反対なのかもしれない、とも思った。
「うおっ」
と、その少女は突然叫んだ。
「背中が折れる!」
少女は苦悶し、マッサージ機からどうにか逃れようとしているが、体勢を変えられず背中じゅうを乱打されてもがいている。乱れた浴衣が美しい肢体を露わにして官能的であった。しかしまあ、やっていることはまるで陸に上がった魚だ。
柚葉はその少女を、以前どこかで見たような気がしてならなかった。彼女の中にあるなにかが、今、既視感となって自分の内側に存在しているような気がした。
少女はもがきながら、どうにか立ち上がり、マッサージ機を思い切り蹴ると、その古風な機械はぴたりと動作を止めた。
「なんて暴れん坊なんだ……」
と、少女はマッサージ機を睨みつけると、振り返り、
「あなたは今、わたしを見て、見覚えがあるなと思いましたね」
と言ったので、柚葉はぎょっとして二歩ばかり、引き下がった。
「なぜそれを……」
「そんな顔をしていたから。わたし、人の顔を見ていると、考えていることが大体わかるんです。今度はアジフライが食べたいと思ったでしょう……?」
(そんなこと思っていない……)
どうやらまぐれのようだった。
「わたし、羽黒未空と申します。秩父の山奥に小さなアトリエを構えて、のんびり絵を描いているしがない芸術家です……」
少女がそう名乗ったので、柚葉ははっとした。ハグロ……。確かに耳にしたことがある名前だった。
「するともしかしてお兄さんと一緒にご旅行中の……」
「兄とどこかで会ったのですか」
「天守閣で……」
「そうですか。迷子の兄がお世話になったのですね。今日は兄がわたしからはぐれてしまって、ずいぶんと大変な一日でした……」
そうやって未空はやれやれと呆れた声を出した。
「お兄さんが迷子になったのですか」
「ええ。なんでもわたしがトイレに行っている間に、ひとりで勝手に天守閣の最上階に登って呑気に景色を眺めていたそうです。おかげで、わたしまで、お城の敷地内で長時間、迷うことになりました」
「はあ」
解せない話である。
「それで、兄さんとは無事に再会できましたか?」
「ええ。おかげでこうして民宿に戻ってくることができました。わたしは民宿の名前も知らなかったので兄と再会できないと危ないところでした。先ほど、兄とわたしは温泉に入浴するため、同時に部屋を出たのですが、戻ってみるとまだ部屋の鍵が開いていません。いつまで湯に浸かっているやら。兄が鍵を持っているため、わたしは部屋に入れずにこうしてレトロなマッサージ機と格闘していたというわけです」
「ずいぶんと困った状況ですね」
未空は、もはや起動することのなくなったマッサージ機を触りながら、延々と兄の不満を述べているのだった。
「あなたは面白い方ですね」
と柚葉は言った。
「わたしは絵を描くことを生業としています。どのみち普通と違う生き方をしているのだもの。変であるなら変である方がいいんです」
「変だなんて思いませんよ。一体どんな絵を描いているんですか」
「今描いているのは、インドとアフリカの民俗文化の闇鍋みたいなものです……あと現代の日本が片付かずに、文化が乱れて、とっ散らかっている絵です」
「是非、見てみたいです」
「それなら、一緒にわたしの部屋に行って、もう少しお話しでもしませんか。そろそろ兄も戻ってきている頃でしょうし……」
と未空が言ったので、柚葉はひとり旅とは出会いのためにあるものだと感じて、
「ええ、是非」
と咄嗟に答えた。今まで会ったこともない人たちと会話を交わす。部屋でくつろぐ。考えてもみると恐ろしい気もしたが、ひとり旅は人見知りでは到底できないものだ。
「兄もマイペースで困ったものですよ……」
ふたりは二階の廊下を歩いてゆき、203号室の前について、ドアノブを握った。ガチャガチャまわすと、やはり鍵がかかっているのだった。
「まだ戻ってないのかな……」
その瞬間、ドアがガチャリと音を立てて、開かれた。ところが、その先に立っているものを見て、柚葉はぎょっとして息を呑んだのである。
その先に立っていたのは、黒頭巾の人物であった。目のところだけ、穴が開けられて、こちらを見つめている。ふぅーふぅーと掠れた息が漏れている。
ふたりがしばし凍りついていると、
「なにか?」
と尋ねてきた。
「間違えました」
と未空は小さく答えて、全力でドアを閉めると、廊下を走り始めた。
「えっ、ちょっと!」
柚葉は驚いて、未空の背中を追いかけた。未空は先程のゲームコーナーまで戻ってくると、息を切らして、
「わたしの部屋、三階だったかもしれない……」
と述べたのだった。
一体全体、あの黒頭巾の人物はなんだろうと柚葉は思った。
三階へと向かうと、果たして303号室のドアは開錠されていた。中へ入ると、柚葉の部屋より幾分広い畳の間に、昼間のお兄さんがあぐらをかいていた。
「あっ、君は……」
「この人、柚葉さん。ゲームコーナーで会ったんだよ。お兄ちゃんの知り合いだってね」
と未空は簡略な説明を述べた。
「そうですか。妹がご迷惑をおかけしたみたいで……。昼間はお世話になりました。そうそう。申し遅れました。わたしは羽黒祐介と申します。上池袋二丁目で私立探偵をしているものです……」
「私立探偵……。すると猿渡家心中事件の調査をされているのですか……?」
と柚葉はすぐさま尋ねた。探偵というイメージから、オーギュスト・デュパンやシャーロック・ホームズといった探偵譚を連想してしまったのだった。
「猿渡家心中事件のことをご存知ですか」
と羽黒祐介の目がきらりと光る。
「ついさっきジャズ喫茶の売れない小説家の男性から教えてもらったばかりなんですが……」
「はあ……」
羽黒祐介は、ジャズ喫茶の売れない小説家の男性というパワーワードに頭の処理が追いつかないようであった。
「いえ、まあ、これはまた風変わりな依頼でして……。猿渡家心中事件と北条氏の霊魂が無関係であることを証明してほしいというものでして……。この熊沢館のご主人が依頼主なんです」
そういうと羽黒祐介は、なんとも困った笑い顔を浮かべた。
「それはつまり猿渡家事件の犯人が人間であることを証明するということですか」
「まあ、そうなるでしょうね。この観光地が怨霊騒ぎのせいで客足が遠のいているのは事実でしょう。それを面白がるユーチューバーたち、インフルエンサーたちが面白おかしい内容の情報発信を繰り返し行うことで、陰鬱なイメージが、この地に定着してしまっている感があります。もしも僕がその猿渡家事件の真犯人が人間であることを解き明かしたら、その悪夢のジレンマは終わりを告げることでしょう……」
それでこの探偵は、あの城の天守閣に登っていたのか、と柚葉は思った。
「どうですか、事件、解けそうですか?」
「いえ、現場にアップルパイがあったというのは確かに引っかかる点ではあるのですが、アップルパイを持ち込んだ人物がイコール犯人だとも断定できませんし、なにぶん、五年前の事件ですから、現場にはほとんど手がかりが残されていません。それに四百年前の豊臣秀吉の小田原征伐に関しては、恥ずかしながら自分が歴史について門外漢なこともあり、一向に手がつけられない状況なんですよね」
柚葉は、自分が捜査しようとしていることと、この美貌の私立探偵が捜査しようとしていることが、互いにシンクロしていることに気がついた。ただ異なるのは、柚葉は過去と現在の関係性を見つけ出そうとしていて、この私立探偵は無関係であることを証明しようとしているのだった。
「それでしたら、わたし、史学科の学生なので、ご協力致しましょうか。わたしの場合、犯罪捜査は門外漢ですけど、歴史と民俗学については、わたし、専門ですので……」
すると羽黒祐介の目がきらりと輝いた。まるでその内側にプラネタリウムの天の河を見るようだった。
「それは助かります。是非、わかることがあったら教えていただけると助かります」
柚葉はにんまりと頷いた。
こうして柚葉は想像もしてなかった事件へと巻き込まれてゆくことになったのである。恐ろしきことかな。柚葉は自分の未来を知らない。おぞましき連続不可能犯罪の渦中に自分が巻き込まれることになるなどとは、この時、まるで知らずにいるのだった。
5
ようやくミステリ小説らしい展開になってきたと安堵された方も多いと思われるが、物語はまたしても明後日の方向へと進んでゆく。
柚葉は翌朝、霊妙寺という密教寺院があるという城郭から見て商店街の反対側の地域へと向かった。バスから降りてみると、そこはなだらかな坂道であり、小高い丘の上に、密教寺院といった印象の重厚な檜皮葺きの山門がそびえていた。かつて真言宗の寺院であったこの寺は、今では金剛宗とかいう独立単一宗派となったという。
この寺の金堂へと足を踏み入れると、ここは密教寺院らしく、宇宙の神秘をその内側にひた隠しにしている。大日如来の大仏が本尊であり、その金堂の正面にそびえているのだった。
(ここは密教寺院だ……)
密教というのは、ヒンドゥー教の影響を受けたタントラ仏教であり、呪術的色彩が強いものだというのが、一般的な認識だと思うが、インドの歴史的には前期密教、中期密教、後期密教の三種があり、日本に伝来しているのは、インドにおける中期密教である。神秘主義や呪術性の高いこの密教を、深淵なる哲学によって理論的にまとめ上げたのは、真言宗の開祖、弘法大師空海の偉業であった。
経典の話になると、初期の雑部密教の経典『十一面観世音神呪経』などはともかくとして、中期密教にもなると、いよいよ密教の代名詞『大日経』『理趣経』『金剛頂経』が主要な経典となってくる。
というようなことは、柚葉は史学科の学生なので、当然の如く知っている。
知っているから、金堂のサイケな色彩の堂内に足を踏み入れた時、これぞ宇宙だ、と素直に思えたのである。
金堂の正面には、三躯の大仏級の仏像が横に並んでいる。その中央に、巨大な金色の大日如来(だいにちにょらい)の坐像がそびえているのであった。
宇宙のありとあらゆる現象は、この大日如来の真理の顕現なのだという。
(これはなんと見事な仏像だろう……)
そういうことを考えながら、柚葉は丁寧に礼拝し、堂内を散策した。
自分の内側にある神秘領域である衆生秘密と、宇宙の、つまり森羅万象の真理である如来秘密とは、本来同一なものだという。
柚葉は、人間心理の神秘と森羅万象の神秘が異なるものではないと知ることができれば、自分もまた、真の悟りを得ることができるのでは、と思った。
柚葉は、金堂から出ると、横倒しになったという供養塔がある庭へと歩いていった。そこは墓所の一部であった。
「これか……」
柚葉は、供養塔というより、一面が平らに削られた巨大な岩が立てられているのを見つけた。
「これが五年前、地震で横倒しになったってわけね……」
柚葉はひとりで頷いた。
「その通りでございます」
背後から美しい声が聞こえてきて、柚葉は驚いて振り返った。
若い僧侶がひとり、墓場の見える庭の前に立っている。
「その供養塔が倒れた時、猿渡家心中事件が起こったのであります」
「あなたは?」
「霊妙寺の僧侶、覚如であります」
「覚如さん。あなたはなにを知っているのですか」
「わたしは何も知りません。しかし知らないからこそ、すべてを知っているといえるのであります。この世のありとあらゆるものは人間の思量を超えております。それゆえ、自己の無限小を自覚するもののみが、無限大の真如を悟るのでありまして……」
などと意味深なことをいいながら、覚如は歩み寄ってくる。妖しげな雰囲気こそあるが、凛とした美貌の僧侶である。
「あの城で流された鮮血は……。燃え上がって苦悩する人々の叫びは……。今、どこにあるのでしょうか」
と柚葉が尋ねると、
「霊魂と共にあります」
と覚如は答えた。
「その霊魂はどこに……」
「いずこにも行き渡りましょう。本来、生前の遺恨は長きに渡る供養の末に清められてついには無くなるものです。しかしそうならないこともある。祟り神というものであります」
「しかし神ならば祭る人がいなければなりません。祭ることもない荒御魂は……」
「さあ。わたしにはわからないことばかりです。しかし悲しき因果の末に、あの猿渡家心中事件は発生した。猿渡庄造は、なにかしらの武者の霊魂に憑依されたのであります。そして混乱し、妻と娘を刺し殺した……」
その話は柚葉にとって初耳だった。猿渡家心中事件は、霊魂に憑依されたことによるシャーマニックトランス殺人だったということか……。
「猿渡家心中事件について、お詳しいようですね。もっと教えていただけませんか。わたし、池袋の私立探偵から犯罪捜査の委託を受けている史学科の学生なんです……」
そんなわけのわからない説明で納得してもらえるものか疑問であるが、僧侶は平然としている。
「なにか勘違いをなさっているようですね。私立探偵が捜査したとしても何もわかりません。なぜならば、猿渡家心中事件は、ひたすらに超自然的現象であるからです。霊魂というものを捉えられる人々のみ理解できる領域の話です。ご覧なさい。あそこにそびえる城は四百年前に戦災のために燃え上がりました。どれほどの人々が辛苦の中で息絶えたものか……。そして、そのご遺体の多くが埋葬されることもなく、あの地に野ざらしとなり、また城の崩壊と共に、土砂の下で今も眠っているのであります。さて、死とはすなわち「霊魂と肉体の分離」を意味しています。肉体から抜け出した魂は、荒御魂といって非常に危険な状態にあります。これは丁重に供養して、鎮めなければ、浄化されて祖霊となることもない」
「それはあなたたち、僧侶のつとめでしょう」
「そうおっしゃいますな。たとえば、菅原道真や、平将門の御霊を鎮められる僧侶がこの世におりますか。そもそも、荒御魂は怨霊となり、それはつまり御霊というもので、中間神霊ともいい、浄化されている霊魂よりも強大な力を有するものなのであります。そして、あの城を守った侍大将のひとりの霊魂は今なお、城のあるあの土地にとどまっているのです……」
そういうと覚如は、供養塔に向かってなにかの呪文を唱えると、踵を返してその場から去って行った。
(一体なんだろう、あの風変わりな僧侶は……)
しかし柚葉には、彼の語っていることがデタラメとも思えないのであった。
仏教は二千五百年前にインドにおいて誕生した。しかしその姿と内実は、大きく変容しながら、中国大陸、朝鮮半島へと渡り、最終的に日本列島に渡来したのである。インド仏教の最終形態は密教であった。深淵な宇宙と自己の神秘を抱いた秘密仏教である。それはヒンドゥー教などの民間信仰の影響を多分に受けたタントラ仏教で、日本に伝来しているのは、中期密教であるということは前述の通りだが、日本においてはすでに独自の霊魂信仰がひろまっていて、こうした信仰の混淆の中で、はじめて日本仏教となったのである。
(霊魂の問題……)
死とはなんであるかと問われれば、日本人にとってそれは、肉体と霊魂の分離であった。日本人にとって肉体は入れものにすぎなかった。霊魂は、浮遊するものであり、もっぱら肉体という入れものに憑依するものだったのである。
(しかし、それと猿渡家心中事件がどう関係しているのだろう。やなりシャーマニックトランス殺人だったというのかな……)
6
柚葉が、熊沢館に戻ってくると、一階の奥にある蓄音器室に、宿主の熊沢はいた。蓄音器室は観音扉の中、一面がレコード盤の収納棚になっていて、ソファーの前にはクレデンザ風の木彫の蓄音器がひとつと、CDとLP用のオーディオ機器が並べられている。部屋全体は古風な装飾で統一されていて、ランプ型の照明と、音楽家の彫像、赤いカーペットなどが、じっくりと落ち着いたしつらえで、レトロな名曲喫茶を感じさせる。
熊沢はクラシック音楽愛好家であるらしく、一方の棚にはフルトヴェングラー、トスカニーニ、エーリヒ・クライヴァー、オットー・クレンペラー、ブルーノ・ワルターといった名だたる指揮者のLPが並んでいるのが見えた。それでいて熊沢はバッハ通であり、今彼はバッハの『マタイ受難曲』をかけていて、ソファーの上でひとりうっとりと聴き惚れているのだった。
柚葉は、この蓄音器室のソファーに腰を下ろすと、さまざまな音楽機器が並んでいる中で、とりわけ大きなクレデンザ風の木造りの蓄音器をまじまじと見つめていた。
名曲喫茶にいるみたいだな、と柚葉が思った瞬間、熊沢の奥さんと見える貴婦人が気を利かせ、コーヒーを淹れて持ってきてくれた。サイフォンで淹れたコーヒーらしい。コーヒー通は、ハンドドリップ派もいれば、サイフォン派もいるらしい。またコーヒーであれば、コーヒーメーカーでもインスタントでもなんでも構わないという無頼な愛好家もいると聞いたことがある。柚葉は、サイフォン式のコーヒーをはじめて飲むのだった。すっきりとした中に、膨らむような甘みがあって、苦味は僅かに舌を刺激する程度、柚葉にはハンドドリップとの違いがあまりわからなかった。
「芦沢さんはクラシック音楽はよく聴かれますか?」
とバッハの世界に浸かりながら、熊沢が丸眼鏡をちょいとつまみながら、眉間に皺を寄せて、柚菜に問いかけてきたので、柚葉はぎくりとして背筋が凍りついた。
柚葉は、クラシック音楽というと、一時期フルトベングラーとトスカニーニの音楽の違いを楽しんだことがある程度、ベートーヴェンの第九番や、モーツァルトの第四十番、シューベルトの『グレイト』を神格化している他、バッハとヴィヴァルディといったバロック音楽を好んでいる程度のもので、こうしてクラシック音楽通の人に問いかけられるとどきりとしてしまうのだった。それにジャズマニアが、クラシックを親しむ時の悪いクセで、演奏者や指揮者の表現に視点がいってしまいがちであったので、ジャズのアドリブとクラシックの演奏法の意味の違いこそ理解していても、ドビュッシーの『月の光』一曲を聴くにつけても、コルトーだの、ギーゼ・キングだのサンソン・フランソワだの、ピアノ演奏者の弾き方の違いにばかり夢中になって、作曲家であるドビュッシーその人への関心が薄いのが困ったものなのであった。
「あまり聴きません……」
「そうですか。それならば、誰でもクラシック音楽が好きになれるワーグナーの『トリスタンとイゾルデ』を全曲聴いてみますか?」
それ、三時間くらいかかるやつじゃないのか、と柚葉は思ったが、熊沢には熱気があった。よく見ると、熊沢はオットー・クレンペラーみたいな顔をしているのだった。
「わたしバッハのブランデンブルク協奏曲を聴きたいです」
「それは駄目です」
熊沢がきっぱりと断ったので、柚葉はぎょっとした。熊沢には独特のこだわりがあるらしかった。
「わたしのDJ的信念から、同じ作曲家の曲を連続でかけるわけにはいかないのです」
「はあ」
「それはカレーパンの後にカレーうどんを食べるようなものです。適度に変えてゆくことが大切です。常に我々が求めているのは新鮮さです。きっと味の真価がわからなくなってしまいます」
表現の比較をしようという意識はないのだろうか、と柚葉は思った。柚葉の場合、いつもひとつの曲を演奏者を変えつつ、五回は連続で聴いてしまう。そうじゃなければ、わずかな違いがわからなくなってしまうと思った。ショパンのノクターンの第二番にしても、コルトーやらポリーニやらホロヴィッツやら、多くの演奏家のものを立て続けに聴くのである。
「オットー・クレンペラー指揮、バッハ作曲『マタイ受難曲』はここで終わります。続いては、またオットー・クレンペラー指揮で、ワーグナー作曲『ローエングリン』序曲です」
指揮者は連続していいのか、と柚葉は首を傾げた。熊沢は独特の理論を持っているらしい。熊沢がLPを取りにゆこうとしているのを柚葉は止めて、
「ところで、話は変わりますけど、羽黒さんという探偵さんに猿渡家心中事件の解決を依頼したそうですね?」
と突然、思い切って、熊沢に尋ねてみた。
「何故それを……」
「本人に聞いたんです」
「ずいぶんと口の軽い探偵だな、あの人は……。いえ、その通りです。猿渡家心中事件から怨霊騒ぎが起こって、今ではまともな客は尽きて、ユーチューバーだのインフルエンサーだの、悪意の塊みたいな心霊マニアしか宿泊しなくなってしまいましてね……。あれが怨霊と無関係であることを証明していただきたいと思ったのですよ……」
と熊沢は丸眼鏡をそっといじりながら、低い声で言った。
「猿渡家心中事件は、シャーマニックトランス殺人だのと噂されているのですか……?」
「まあ、都市伝説みたいな話ですよ、それは……。四百年前の小田原征伐の際に、そこの岩松城で戦死した侍大将に、林田五郎兵衛という男がおりましてね、弁慶の立ち往生の如く、数十本の矢を体に受けて、立ちながら死んだという伝説なのですが……。この林田五郎兵衛のイニシャルじゃなしに、姓名の頭の一文字ずつを取ると「林五」。つまり「りんご」というわけです。現場にあった謎のアップルパイは、林田五郎兵衛の暗喩というわけですね。ミステリ小説やパルプなSF雑誌を読んでいる低俗な輩が思いつきそうな戯言ですよ……」
とさもつまらなそうに、熊沢は言うと腕組みをした。
「つまり、その林田五郎兵衛の怨霊が、猿渡庄造に取り憑いて、シャーマニックトランス殺人が起こったと……。奥さんと娘を殺害した後、猿渡庄造は自分をも殺してしまったというわけですね」
「ええ。でも、あなたもまさか、おかしなユーチューバーじゃないでしょうね」
とあまりにもしつこく質問された熊沢が、疑うような目を向けてきたので、柚葉は慌てて、
「いえ、わたしはただの歴史オタクですっ!」
と叫んだ。
7
柚葉は、大浴場で入浴を済ませると、夕食をいただき、部屋ですっかり落ち着いてしまった。しかしいざ寝る時になると、わずかに不気味に感じられてくるのであった。林田五郎兵衛の怨霊というのが本当にこの世にあるのか、供養塔が横倒しになったこと、猿渡家心中事件とそれらがどんな繋がりを持っているのか、天井の渦巻き型のシミを見ているうちに、それらが妙に不気味に感じられて、ゾクゾクと背筋が凍りつくようであった。
瞼を閉じると、天井の渦巻き型のシミが回転を開始したように感じられた。そうして自分がその渦巻きの中に取り込まれてゆくのを感じた。自分の感覚にとらわれている。そしてその感覚は、果てしない過去からやってきているように感じられた。
柚葉は、林田五郎兵衛という侍大将の外見をまるで知らなかったが、瞼の内側には自然と浮かんできている。
四十歳くらいの鯉に似た顔つきの武将であった。戦乱の辛苦に曝されて、その日に焼けた顔は土色に汚れていた。疲労に感情を失いながらも、その瞳の奥には執念が沈んでいるように見えた。
林田五郎兵衛の文字が、陣旗に描かれてはためいている。戦火に燃え上がったと思うと、林と五の字だけが残って、ふたつの文字は引き寄せられていった。「林五」という言葉になって、いつしかそれは「りんご」という文字となり、ついには「アップル」となり、それは巨大なアップルパイとなった。アップルパイは巨大なメリーゴーラウンドのようになって、回転しながら柚葉のもとに迫ってきた。
それと共に、美しい音楽が聴こえてきている……。
いつのまにか不可思議で美しい『金平糖の精の踊り』の音楽がかかっていた。
(アップルパイが……そこにあったのか……)
音は水の中に沈んでいるようだったのに、急にリアルに迫ってきた。
柚葉は、はっと目を覚ました。どこからか(おそらくそれは階下の方から)蓄音器の音色が聴こえてきていた。それはチャイコフスキーの『くるみ割り人形』の一曲、『金平糖の精の踊り』の一節なのであった。
(こんな時刻に……)
柚葉が壁にかかった時計を見ると、深夜十二時を過ぎたところであった。
(熊沢さんは気が狂ったのか……)
そう思いながら、よく聴いてみると、『金平糖の精の踊り』が終わって、『花のワルツ』が始まったところだった。曲順は、シャッフルされてランダムになっているのかもしれないが、もしそうだとしたらCDだろう。また、ボリュームはどうなっているのだろうか、あまりにも騒がしかったので、柚葉は廊下に出ると、暗い階段を降りていった。
蓄音器室からその音楽は聴こえてきているようだった。柚葉が、蓄音器室の扉を開こうとすると、鍵がかかっているのか、まったく開く気配がない。これはどうしたものかと頭を抱えていると、廊下から熊沢がパジャマ姿で現れた。
「一体こんな真夜中に誰が……」
熊沢は不満げに唸りながら、扉の鍵が閉まっていることを確認すると、カウンター奥の引き出しの中から鍵を取り出して、再び蓄音器室の扉へと向かい、開錠したのだった。
柚葉は、その姿をまじまじと見つめていた。扉が開いた瞬間、熊沢は「ぐえっ」と小さな声を漏らして引き下がった。柚葉が室内を覗き込んでみると、部屋の中央に、頭を斧のようなものでかち割られた黒頭巾の男がうつ伏せに倒れていた。醜く血肉が溢れていて、死んでいることは明らかであった。
「これは殺人だ。殺人としか思えない。しかし、おかしなことだ。この部屋は施錠されていた……」
「施錠されていたからってそんなに不思議がることはないでしょう。だって鍵は、カウンターの奥の引き出しにあったんだから……」
柚葉は動転しながらも、どうにか反論する。
「その引き出しにも鍵がかかっていて、部外者が開けることはできません。各部屋の鍵が収まっている引き出しの鍵は、わたしが常に持っているものと、わたしの部屋の金庫の中にあるものの、合計ふたつしかこの世には存在しませんものでね……」
「なるほど。それならば、鍵を取り出すことのできる熊沢さんが犯人ということですね」
「あなたもよほど単純な考えのお方のようだ。わたしが自分の民宿で、人を殺して、自分しか開けられない状況で部屋を施錠し、わざわざ蓄音器で『くるみ割り人形』をかけたというのですか。あまりにも出来すぎているとは思いませんか……」
「おっしゃることはよくわかりますわ。確かに不自然です……」
そう言ったって現状、一番怪しいのはあなたで間違いないのだけど、と柚葉は思った。しかしあまり犯人を刺激してはいけない、と思った。
「SP盤がかけられていたのですな。見てごらん」
熊沢は、蓄音器からSP盤を取り出した。チャイコフスキー作曲『くるみ割り人形』である。
「犯人はここで『くるみ割り人形』をかけておいたのでしょう」
「それで殺されたこの人は誰なんです……」
熊沢は、恐る恐るめくれあがった黒頭巾から見えている顔を覗き込んだ。
「203号室のお客さんですな。確か名前は国原忠さんとか言ったっけか。こうして黒頭巾なんか被っていたところを見ると、なにかよからぬことをしでかそうとして、反対に殺されたか」
「まあ、そんなところでしょうね…….」
「憶測に過ぎませんが……」
そう言いながら、熊沢はめくれあがった黒頭巾からはみ出している顔を見つめている。三十代後半くらいだろうか、坊主狩りに無精髭の情けない顔の男だった。
「ずいぶん情けない顔の被害者ですね」
と柚葉は率直に感想を述べた。
「被害者なのだから、そんなこと言うものではありませんよ……」
熊沢は、そう言いながら、まじまじと見つめている。
「事件とあれば、警察に通報するのがベターですけれど、その前に羽黒祐介さんを呼びましょう。なに、その方が解決が早いかもしれない……」
と常識のない発言をして、ふたりは三階へと向かった。間も無く、羽黒祐介が呼ばれてくることになった。これはまったく困ったものだな、という眠そうな表情のまま、浴衣姿に寝癖をこさえて、羽黒祐介は降りてきた。
羽黒祐介は、現場をみると、大体の状況を察したようだった。
「密室殺人とはよりにもよって……。しかし状況はしごく単純明快なようですね。この男は黒頭巾をかぶっている。手袋までしています。つまり見た目通りの不審者です。黒頭巾をかぶっているのは自分の顔を隠すためで、なにかを盗もうとしていたのだろうという推測はすぐに思いつきます。問題はこの男がなにを盗もうとしていたかです。見てごらんなさい。レコードのある棚が乱れています。他の棚が整理整頓されているというのに、明らかに不自然です。おそらく、この男はレコードを盗もうとしていたのでしょう」
「それで何者かに見つかって殺された……」
「そんなところでしょう。ところで、この部屋の鍵についてですが、深夜ですから、そもそも施錠してあったのではありませんか?」
「それは確かにその通りです。わたしはこの部屋を午後十時ごろには、確かに施錠していったと思います。それなのにどうやってこの男は侵入することができたのだろう……?」
「つまり、これは入ることも出ることもできない密室殺人だったというわけですね。しかし、まあ、これは非常に単純な物理トリックだから手っ取り早く解説してしまいましょう。みて、ご覧なさい。この蓄音器の中身を……」
羽黒祐介が一番大きな蓄音器をトントンと叩くと、中が空洞な音がした。柚葉が、妙だな、と思っていると、羽黒祐介は、パカッと蓄音器の前面の扉を開いた。そして中が空洞になっているのをあきらかにしてしまったのだった。
「これはおかしい……。ここには蓄音器のラッパが腸詰のようになっているはずだ。それにこんな状態なら、さっきまで蓄音器が『くるみ割り人形』のSP盤を鳴らしていたのは説明つかない……」
と熊沢が苦しげな声を上げる。
「それは、つまるところ、この蓄音器ではなく、隣のCDプレーヤーが奏でていた音色だったんです。そもそもSP盤であるならば、一枚、せいぜい三分程度の演奏時間のはずですから、皆さまがおっしゃるような『金平糖の精の踊り』の後に『花のワルツ』が流れるとは考えづらい。犯人がその場にいて、盤を変えていたのならわかりますが、大音量の音色が響いている殺人現場に残ってそんなことはしないでしょう。そもそも曲の順序がおかしいのは、CDをシャッフルで再生されたためにこんなことになったのです。ご覧なさい。CDプレーヤーには今、一枚もCDが入っていない。犯人が隠滅するために持ち去ったのでしょう。
そしてこの空洞の蓄音器。これはまあ、不自然なことなのですが、この蓄音器はきっと本物ではない。ぱっと見、傍目からはわかりませんが、外見ばかり似せて作られたものですよ。本物の蓄音器はとうに盗まれていたわけです。あの黒頭巾の男は、蓄音器泥棒だったというわけです。こういうハリボテみたいな形ばかりの蓄音器を事前に作っておいて、あなたがいない隙をついて、すり替えてしまった。本物の蓄音器は今頃、どこか遠くにあるのでしょう」
「それはよくわかりましたが、どうして施錠したはずのこの部屋の中に、この黒頭巾の男は入ることができたのですか?」
「それも非常にシンプルなトリックですね。この黒頭巾の男は、蓄音器を窃盗後、蓄音器そのものだけでは飽き足らず、貴重なレコードも盗もうとして、午後十時寸前までこの部屋にいたのです。そこに運悪く、あなたが入ってこようとした。この黒頭巾の男は焦って、このハリボテみたいな蓄音器の扉の中に隠れたのです。あなたは室内に人がいないことを確認すると、部屋の扉を施錠してしまった。さあ、黒頭巾の男はハリボテの蓄音器から這い出してきます。それで、レコードの物色をしようとしたのですが、なんということでしょう、もうひとり、この部屋に入ってこようとする人がいたのです。黒頭巾の男が施錠されている扉を開錠したのだから、入ってこようとしたのは、おそらく窃盗の共犯者でありましょう。それを仮にⅩと名付けましょう。Ⅹとこの黒頭巾の男は諍いを起こし、Ⅹはこの黒頭巾の男を殺そうとした。助けを呼ぼうとするも黒頭巾の男は、黒頭巾をかぶっているから声が響かない。黒頭巾がめくれあがっているのは、彼が必死に黒頭巾を外そうとした証拠です。彼はたまらず、そこでCDプレーヤーに入っていた『くるみ割り人形』のつまみをまわして、大音量で再生しました。そこで、彼はⅩに撲殺されてしまう。この後、Ⅹは芦沢柚葉さんがドアを開けようとしたのに、室内で気づいて慌てたはずです。慌てたⅩは、くるみ割り人形のSP盤を偽物の蓄音器の上にセットし、CDを回収すると、その蓄音器の中の空洞の中に身を隠します。扉を開いて、熊沢さんと芦沢柚葉さんが入ってくると、犯人はひとり、蓄音器の中で息をひそめていたというわけです。Ⅹは、あなた方が僕を呼ぶために三階に上がったタイミングで、『くるみ割り人形』のCDを持って、この部屋から出て行ったというわけです」
なんだか江戸川乱歩の小説に出てきそうな非現実的なトリックである。芦沢柚葉は、江戸川乱歩マニアであるため、こんなおかしさ、奇妙さがかえってトリックの味なのよ、と思った。熊沢は、本当の話かいな、という顔で羽黒祐介を見ている。
「なんと言いますか、理解が追いつきませんが、つまりこの男とⅩという犯人は、蓄音器の窃盗団のメンバーだったというわけですか」
「まあ、そんなところでしょうね。単純に、鍵を開閉することのできる熊沢さんが犯人だったという可能性も捨て切れませんが……」
「それは困る。警察が来たら、あなたの考えたトリックを是非、説明してください……」
と熊沢は悲痛な声で言った。
8
蓄音器泥棒の話は、非現実的で奇妙であったが、警察の到着と共にいよいよ、説得力を増してきたのであった。根来という鬼警部が、到着するなり、殺された黒頭巾の男の身元を洗うと、国原忠という人物は存在せず、住所も出鱈目ということだった。
偽物の蓄音器を作っておいたところを見ると、どこかに小規模なものであっても、加工のできる工場を持っている人物という察しはついた。
熊沢が、蓄音器は週三回しかかけないことを知っていて、こんなすり替えを思いついたのかもしれない。
いずれにしても、骨董品専門窃盗団の仲間割れという羽黒祐介の推理は妥当性があるように柚葉は思った。
しかしひとつだけ気になることが、柚葉にはあった。そもそも、何故CDプレーヤーに『くるみ割り人形』のCDが入っていたのだろうか。羽黒祐介の推理では、被害者が助けを求めるために『くるみ割り人形』の入っているCDプレーヤーを大音量で再生したのだということだった。棚からCDを取り出して、入れるぐらいなら黒頭巾を完全に外してしまえばいいので、やはりあらかじめCDプレーヤーには『くるみ割り人形』が入っていたのだろう。そう想像すると、わけがわからなくなってくるのだった。
その後、熊沢は羽黒祐介を呼び出し、あることに気がついたと説明した。熊沢は、貴重な音源を集めているらしい。そのため、猿渡家心中事件の後、猿渡家の遺品のCDを十枚あまり譲り受けたということであった。どうもそれが九枚になっているというのであった。すると犯人はその一枚を盗んだのかしら、と柚葉は話を聞いていて思った。
(まったく不思議なことばかり……)
柚葉は、羽黒祐介が蓄音器殺人事件の捜査にかかりきりになってしまったので、祐介の妹の未空とふたりで、歴史の方の謎を解き明かすべく、四百年前に戦死した林田五郎兵衛の墓があるという霊妙寺へ向かった。
相変わらず、霊妙寺は密教寺院らしく、五色と金色の装飾の美しいサイケな内装である。祀られている多面多臂の異形の神仏の迫力は物凄かった。御本尊の大日如来を拝んだ後、あの横倒しになったという供養塔があるところを越えて、さらに奥へと登ってゆくと山に向かって墓地が続いている。至るところで、溢れんばかりの梅の花が咲き乱れていた。
「わからないことだらけ。それに、蓄音器泥棒の騒ぎがあって、猿渡家心中事件のことはすっかり忘れ去られてしまったみたい……」
と、柚葉は不満を口にした。
未空はあまり気にしていない様子で、呑気に梅の花を眺めている。
「梅干し食べたい……」
「死後、人の霊魂は、山に登ると考えられていた……。だけど、山そのものは立ち入ってはいけない神域だから、山頂ではなくて、人が山を拝むことのできるこんなところに墓地があるんだよ」
と史学科の学生らしく、仏教民俗学の知識を披露する。
「ねえ、死んだら本当に霊魂が肉体から飛び出して、こんなところにとどまると思う?」
と未空が質問してきた。
「さあ。でも霊魂は浄化されてゆくにつれ山に登り、生前の罪業が無くなって、祖霊となる。肉体は不浄なものとして埋葬される……。だから、墓には二種類必要で、サトの近くで霊魂を供養するための墓、そしてサトから離れたところに不浄な肉体を埋葬する墓を作ったというのが両墓制だよね」
と質問に答えずに余計な知識を披露したところ、未空は「ふうん」とあまり関心のない声を出した。
「古来、人が死ぬってことはそれだけ恐れられていたんだよ。縄文時代には、死者の足を折り曲げて、墓から出てこれないようにする屈葬が流行ったみたいだし、そう考えると現在、わたしたちが死者に対して思う追悼の感情よりも、古代においては、もっと原始的な恐怖心が優っていたのかもしれない。それが怨霊信仰の根源的な感情なのかもしれないね……」
と熱く柚葉が語っていると、その林田五郎兵衛の墓というのが見えてきた。とは言っても、小さな供養塔が立っているばかりで、隣には簡単な説明が記された高札が立っている。
柚葉は、まじまじとその説明書きを読んだが、大した情報はなかった。ひとつあるとしたら、林田五郎兵衛は城内で戦死したため、その遺体は雨風の中、野晒しとなり、他の遺体にまぎれて、現在まで見つかっていない。この墓というのも、要は供養塔であって、死体を葬っているわけではないのだと記されているのだった。
「こうしてみるとちゃんと供養されているように思うけど、縁もゆかりもない人に取り憑いて、無理心中事件を巻き起こすなんてことあるかな……」
と柚葉は疑問を口にした。しかし地震があって、あの巨大な岩の供養塔が横倒しになったという話であったから、理屈はあるわけで、そこは疑問視してもしょうがない。
「肉体が埋葬されていないからね」
「だってそれを言ったら、戦争や災害だってあったんだし、もっと多くの人が怨霊になってないとおかしいじゃん」
と柚葉は言いながらも、未空のいう「肉体が埋葬されていない」ということがわずかに気になった。
「でも、この林田五郎兵衛の名前を暗示するためにアップルパイを現場に残したというのは、いかにも不自然なことだよね。怨霊の仕業ならなおさら、アップルパイを置くなんて不自然だし、どう考えても人間のやることだよね」
と未空はさすが、名探偵の妹というだけあって、しっかりとした意見を持っているようだった。
「それは確かにそうだね。林田五郎兵衛とアップルパイは、心霊マニアのこじつけと考えていいと思うよ」
そう言いながら、柚葉はなんともすっきりしない心地なのだった。
第二章 岩松城の首切断殺人
1
霊妙寺の墓地から、ふたりの少女が降りてきたのを見て、覚如はそっと木の影に身を隠した。
(あのふたり、真相を掴んだのだろうか)
覚如は、一昨日、熊沢館に侵入して、黒頭巾の男を殺したばかりであった。覚如は、要するこの事件の犯人であった。彼は訳あって、熊沢館に忍び込み、チャイコフスキー作曲の『くるみ割り人形』の収録されたCDを聴こうとしたのだった。ところが、蓄音器室に入るとそこには見知らぬ黒頭巾の男がいた。覚如は慌てて、男を打撃し、その隙にCDを物色したのであった。覚如は訳あって、その場でCDをプレーヤーにかけた。そうしなければならなかったのである。ところが黒頭巾の男は一撃では死亡しておらず、覚如の目を盗み、助けを呼ぶためにCDプレーヤーの音量を大きくした。響き渡る『くるみ割り人形』に慌てた覚如は、黒頭巾の男の後頭部を、脅かすために持っていた斧でくるみの如くかち割った。さらに覚如は、音楽を聴きつけてやってきた柚葉に動揺し、手当たり次第、扉を開いた挙句、蓄音器の扉を開くと、なぜかそこが空洞になっているので、慌てて隠れたのであった。熊沢と柚葉が、羽黒祐介を呼びに三階に上がっている隙に逃げ出したというのは、羽黒祐介の推理の通りである。
(まさか人を殺すことになろうとは……。拙僧もついに殺生戒を犯してしまったか)
仏敵を調伏するのは、毘沙門天の如くなり、と自分を肯定する。
黒頭巾の男が一体全体何者だったのか、覚如はよく分かっていなかった。覚如にとって大事なのは、チャイコフスキーの『くるみ割り人形』が収録されたあのCDを回収することだけだった。
あのCDの後半には『猿渡家心中事件』の真相が録音されている。
(しかしそのことを知るのはきっと、今ではこのわたしともうひとりだけだ……)
完全なるアリバイのもとに遂行された完全犯罪。しかしあの地震による供養塔横倒しとアップルパイから「りんご」の連想、そして林田五郎兵衛という怨霊騒ぎがなければ、とうに忘れられていたものを。全体、怨霊というものが存在するのか、僧侶として生きてきた覚如としても確信は持てていなかった。しかしあの覚如をして説明のつけられぬアップルパイの存在の偶発性を思うと、林田五郎兵衛が怨霊の祟りではないのかとも思う。
覚如は、休日ともなって、ニット帽を目深にかぶって、商店街へと繰りだすと、その地下にジャズ喫茶があるのだった。
覚如はジャズ坊主である。彼が、はじめにジャズを聴いたのは高校三年生の夏のことで、それはジョン・コルトレーンがジャズクラブの名門ヴィレッジ・ヴァンガードで、エリック・ドルフィーと共演しているライブ盤の名演であった。特にマッコイ・タイナー不在の狂ったような疾走感のある長演奏を、彼は般若心経よりもありがたく聴いたのだった。
彼は貪るようにジャズを聴いた。仏教寺院という封建的な実家への抵抗感から、仏法とは異なる反動的なエネルギーを求めていたのかもしれない。しかしコルトレーンの持つ世界は、反動的なエネルギーというよりも、スピリチュアルで、生活の次元を異にする超俗的なものであった。
彼は自己の精神のよりどころを求めて、ジャズに聴き入っていたのである。
ジャズ喫茶が、午後六時を過ぎて、ジャズクラブになると、バリトンサックスを持った白人プレーヤーが現れて、ドロドロと抉るようなノイズともサウンドともつかない音を出して、周囲を圧倒した。
(自分の心の奥底に、まだ自分の知らない世界があることを教えてくれるのだ……)
覚如はそう思った。
覚如の育った寺は、封建的で保守的な世界であった。仏教の本来の教えはもっと超俗的で、反動的でさえあったのに、覚如はきわめて苦しい形式儀礼の厳格さと僧侶間の上下関係の厳しい生活の中で生きてきた。そうしてみるとジャズの自由の精神は彼が求めていたものだったのである。
それでありながら、覚如は知っていた。仏教の教えも本来もっとも超俗的なものであることを。般若心経の経文を読んだその時から、この世に絶対的な存在や価値観念などありはしないことを、覚如は知っていた。それでありながら、彼は現在の仏教界で生きなければならなかった。
(貴様は迷っておるな。しかしよく知るがよい。貴様のその迷いすら、大日如来さまの一部なのだ)
と祖父に当たる和尚は笑って言った。覚如はそうかもしれないと思った。森羅万象そのものである大日如来は究極の悟りそのものであるけれど、自分のこの迷いも、そのほんの一部に過ぎないのだ。そうしてみれば、迷いと悟りは地続きで、迷い抜けばそれがそのまま悟りの諸相だったなんてことにもなり得るだろう。人は迷い苦しむ。しかしそこから離れたところに悟りがあるのではなくて、迷いそのものがそっくりそのまま悟りになるのだ。
(とは思弁的に捉えても、いざ実際に悟るとなったら大変だ。森羅万象は自分と比べようもなく大きなものだ。また、迷いは醜く暗い。それに比べて悟りは美しき妙光に満ちている。それだというのに、それがそのままひとつであるなどと体感するのは、はなから自分の能力を超えたことだと思う)
覚如は、自分の内側の神秘領域「衆生秘密」と、森羅万象・宇宙の神秘「如来秘密」が、同じものだなどということは、到底悟り得ないところのものだと感じていた。
しかし深層心理を追求するシュールレアリストと、歴史民俗のルーツの根源を辿ろうとする神秘主義者もまた、まさにこのふたつの秘密の相互依存性を悟ることで、自己と歴史をひとつのものとして捉えることができるのではないか、と覚如は思っている。
同じ理屈で、思弁的な経典仏教と、民間信仰的な霊魂信仰の融合も、可能なのではないか、と覚如は思う。
真理を追求すれば、理屈が沢山出てくる。しかし実感そのものは、今、聴いているバリトンサックスの「音色」しかない。そこに絶対的な説得力が秘められている。上滑りする言葉や論理は、現実体験を超越することはない。冷たい水を飲み、息を吸い込めば、それが生きるということで、人間は「思考」が止まっても人間である。生きるということはそういうことで、感情や思考といったものは虚妄の夢のようなものだ。燃え続ける蝋燭の火を見ていると、刹那に生滅している火が、そこにあたかも実体として存在しているように思ってしまう。そもそも自分の心と思っているものは、無限の現象の反応に過ぎない。自分というものがなければ、他人の心を、自分の心と錯覚しているのかもしれない。心もまたあるようでないものだ。なぜならば、対象をもたない意識は無いからである。対象があってはじめて心は起きるのである。はじめに自分があったわけではない。世界があったのである。果てしない過去から、世界があって、少しずつ自分というものを育ててゆく中で、迷いの世界へと陥ってゆくのだった。
それならば、自我意識こそが最大の錯覚なのだ。それを唯識仏教や密教では、これをマナ識という。第九識まであるとされる心の中では、第七識に当たり、自分という虚妄の実体を錯覚させる自我意識であることから、重要である。ちなみに第六識は、概念・観念をつかさどる意識といわれるものである。
(自分はこの宇宙の波風のようなものだ。そう考えてみても、体感することができぬ以上、そこに絶対の説得力はないのだ。思考は無力なのだ。理解することと悟ることは本質的に違う……。体験から遊離した理解は無力だ。人生体験の結晶こそが悟るということなのだ……)
つまり自分には、体験が足りていないのだ、と覚如は思う。仏典など、体験なしには何が書いてあるのかちっともわからない。自己の過去からの体験は、第八識であるアーラヤ識に貯蔵されているというが、DNAのようなものであり、これが反映されて生み出されているのが自分の世界であり、そこから他者を含むさまざまな心の世界が関係し合い、影響し合うことで、複雑な共同幻想の世界が生まれてくる。唯識仏教に関してはこの関係論の追求が脆弱で、自己と他の相互依存関係を看破するためには、華厳経の領域にまで入ってゆく必要があるものと覚如は思っている。
(自分の心と思っているものは、他人の心の一部であったりすることもある。このコップの水の重さの実体は、自分の心のものか、このコップのものか、それすらもわたしにはわからない。自己と他を分別しようとするところから錯覚は始まる。すべてはひとつの巨大な存在なのだ)
大日如来はこの世界そのものであり、マクロコスモスである。そして自己、ミクロコスモスがそれと同体であることを悟ることができれば……。
(だとしても、何も変わらない。知ることで何かが変わることはない。ただ生きるということは、こうして水を飲むことなのだ……)
しかし、バリトンサックスの音色が刹那生滅とは思えない。ずっと自分の心の中に残っている。そうして過去から未来へと存在が残り続けてゆくのを、覚如は知っている。
2
自分のまだ生まれていない果てしない過去から、自分の死んでしまった行く末の未来まで、大河の流れを直感するものは、阿弥陀如来の別名、無量寿如来という名前を覚えておくとよいだろう。それは無限の「時間」を意味する。
自分には到底、捉えきることのできないこの宇宙・森羅万象・世界の拡がりと自己の関係性を直感するものは、これもまた阿弥陀如来の別名、無量光如来という名前を覚えておくとよいだろう。これは無限の「空間」を意味する。
自己の空無なるを悟るものは、巨大な時間と空間の一部にして、自分そのものがその時間であり、空間であるということを悟る。
覚如は、自己を実体化させているのは、生存の不安を根源とする自我意識(マナ識)だけではないと思った。感情は、次々と継起していながら、そのものひとつひとつは別ものの心作用であることから、刹那生滅でありながらも相続しているものと捉えられ、それを不連続の連続というのであるが、覚如はそうは思っていなかった。意識は対象がなければ持続しないため、それが灯火であるなら度々、消えてしまっているものである。それが対象を見つける度に、再び燃え上がるので、自己を実体化させているのは対象を持続させている記憶であり、それはつまり、マナ識よりもアーラヤ識に貯蔵されているものである。つまり自己を錯覚させる心は、アーラヤ識なのである。
(そのアーラヤ識も、第九識のアンマラ識の一部だ……)
そこまで来るともはやすべては清浄で、妙光に輝いている。それぞれの識は、迷妄を清浄にすることで、転識得智し、それぞれ悟りの智慧を得ることができるのだが、アンマラ識は仏性そのものであり、大日如来の悟りの領域が得られるものだといわれる。
しかし覚如のような密教の僧侶は、やはり哲学だけでは悟りに得られないことを知っている。マンダラを前にして、瞑想によってこのような世界に達するのである。
サックスの激しい音色が響きまわる。宙をまわる。天井を伝う。床を這う。それらは根拠なく空間に響き渡る無価値な存在なのだろうか。いや、そうではないと考える。音色が単なる波動ではなく、精神的な内容をもって、伝達されるものは芸術の表現である。
(言葉もまた同じ……)
密教では、真言という呪いの言葉がある。日本においても古来より言葉は呪いの力を持っていた。現代において、言葉は概念を伝えるためのもの、情緒を伝えるためのものばかり残ってしまい、この言霊の世界がすっかり失われてしまった。そのため、文学者は苦悩している。言葉の本領は、言霊の世界にあって、力が秘められたものであって、今日のような単なる概念の記号ではなかった。モールス信号のようになった記号言語ばかり残ってしまい、今人間は概念を超越したものを伝える術がなくて、音楽ばかりがその力を有している。
「あなたは霊妙寺の覚如さんですね。ジャズ坊主ということで有名な……」
と売れない小説家の田崎慎一がウイスキーの入ったコップ片手に歩み寄ってきた。覚如は孤高の瞑想に耽っている最中に、売れない小説家に歩み寄られて、わずかに腹が立った。
(売れない小説家め……。こんなところにいないで家で小説を書け……)
覚如はそう思いながらも、隣に座ってきた田崎と会話をする。
「どうですか。まだ売れませんか」
「変わらずですね。まあ、売れようと思って書いているわけでもありませんからね」
「なるほど。それもひとつの真理でしょうね。歴史的な名作は必ずしも作者の生前に売れていたわけではありませんからね。古来より人は素晴らしい墓を建てることを願うもので、まさに死後、売れればそれですべて人生の苦労は帳消し、万々歳というわけですね」
と皮肉をいうと、田崎は気にせずに赤ら顔でふふふっと笑っている。
「そういうものです。しかしさらに付け加えますと、死後の名誉すら無用なものなのです。こうしてあなたと一杯の酒を飲んでいるのが本当の幸せというものです。だって、我々はみんな死んでしまい、この地球だっていつか死に絶えて、無となるのですから……」
「まあ、この人生がそもそも夢のようなものということもいいますものね」
田崎に変なこだわりを感じなかったので、覚如は先程までの不快感が自然と滅却されてゆくのを感じた。こういうのを悟った人間というのだろう。
「それならばどうして小説を書くのです」
「息を吸って吐くのと同じように」
と田崎は述べると、さらに続けて、
「生きたいように生きたらいいんです。生きたいけれど苦しくて死んでしまう人もいるでしょう。自らこだわりを持つ必要はない。こうして幸せを感じられるのならそれが一番ですよ」
といったので、覚如は自分よりもこの田崎という男の方が、よっぽど悟っている気がした。
「まあ、確かにその通りでしょうね。あなたはいかなる名誉にも欺かれない、生まれ生まれ生まれ生まれ生の始めに暗く、死に死に死に死んで死の終りに冥いこの人間界で唯一、自己が無であることを悟っておられるように思われる……」
「なに、王維の漢詩で「渭城の朝雨、軽塵を浥す、客舎青青、柳色新たなり、君に勧む更に尽くせ、一杯の酒、西のかた陽関を出ずれば、故人無からん」というものがあります。これから陽関を出ることになる王維は、朝雨に潤い、柳の色の美しい宿で、故郷の友人との別れを惜しみ、一杯の酒を勧めるのです。人生は刹那の連続であって、目的があるものではない。すべて消えゆく定めの中で、心と心を通わせることだけが本当に大切なことです。それ以上のことを欲することは、まさに虚空に釘を打つような真似事です」
覚如はその話に聴き入っていた。この売れない小説家の話がいつもより仏教臭かったので、問答を仕掛けてこようとしているのか、とすら思った。しかしにわかに自分のしようとしていることを否定されている気がして、胸がざわついてきたのだった。
(この売れない小説家はただ自己肯定をしたいだけさ。向上心がないのだ。そうでなくても、自分とは関係のない話だ。大日如来の無限大の真理を悟ろうとすること、霊魂信仰の根源を尋ねることは、自己の自我意識を超越している探究心なのだ……)
「ところで、話は変わりますが、二日前に起こった熊沢館の蓄音器泥棒殺人事件をご存知ですか」
覚如はぎょっとした。有名な事件となっているから、こうして話題に上がるのは当然のことであった。しかし自分の反応によっては勘付かれてしまうので、非常に神経を使うのだった。
「ああ、なんでも宿泊していた男が蓄音器泥棒で、夜中に忍び込んで何者かに殺害された……そんな事件でしたっけ」
「そうそう。犯人は、その蓄音器泥棒の共犯者とも、熊沢館のご主人とも言われているらしいですが、どう思いますね」
「さあ。わたしにはなんとも……」
「でも、やはり蓄音器泥棒の共犯者でしょうね」
「なんでですか?」
「あのクレデンザ級の大きな蓄音器をひとりでは持ち出せないでしょうし、盗まれた蓄音器は今も見つかっていませんから、もうひとり共犯者がいないと成り立たない勘定ですから……」
「なるほど……」
そう考えると覚如はぞっとした。あの蓄音器泥棒の共犯者が、どこかにいるとして、息を潜めているのだとしたら、自分は復讐をされないだろうか……?
(あの近辺にもうひとり人間が潜んでいたのだとしたら、熊沢館から逃げだしたわたしの姿を見てやしないだろうか……?)
不安というものは大した根拠もなく発生しながら、なかなか消えてくれないものだ。覚如は気味が悪くなりながら、ジャズ喫茶を出て、商店街をあとにすると、霊妙寺に向かって歩き始めた。霊妙寺の僧坊に自分の部屋があった。部屋に入って、ふとドアの下を見ると、白い紙切れが一枚あった。
「わたしはすべてを知っている。もしも真実を知られたくないなら、今夜、岩松城公園の天守閣の下に来なさい」
覚如はぞっとしてその紙切れを見つめていた。これは間違いなく、二日前のことを知っている蓄音器泥棒の共犯者からの脅迫状だと思った。
(殺すぞ……。蓄音器泥棒を殺してしまう他ない……)
そう思うと、覚如は日本刀を持ち出して、岩松城公園へと駆けていった。
3
柚葉は、朝起きてテレビをつけるとニュースを見て仰天した。
《殺害されたのは、霊妙寺に所属する僧侶で、宮下覚如さん。二十八歳。頭部を切断された状態で、岩松城の天守閣の最上階で見つかったということです》
柚葉は、テレビの画面に映し出されたその僧侶の顔に見覚えがあった。確かに霊妙寺で出会った若い僧侶だった。柚葉は、ザワザワと気味の悪さを感じている。熊沢さんが朝食を用意してくれているだろうが、そんなもの、喉を通らないぐらいの気持ち悪さだった。
(覚如さんが殺された……。何故だろう。蓄音器泥棒が殺害されたことといい……)
柚葉は思い立ったように音を踏み鳴らしながら、階段を一気に駆け降りていった。そして畳敷きの食堂に飛び込むと、長い座卓が並んでいて、すでにそこには羽黒祐介と未空が座っており、焼き鮭、納豆、生卵、豆腐をおかずに白飯を頬張っていた。
「羽黒さん! 今朝のニュース見ましたか!」
羽黒祐介は、米が喉に詰まったらしく、苦しげにもがきながら、どうにか体勢を整えると、柚葉に向き直った。
「ごほっごほっ、今朝のニュースは知っておりますけど、まだ警察の初動捜査の最中ですから、ここでじっとしているより仕方ありません。どうぞ、こちらのお弁当、芦沢さんの分ですよ」
「でも、わたし、殺されたお坊さん、知っているんです……!」
「捜査が落ち着いたら、警察署に行ってみましょう……」
羽黒祐介はそんなことを言うと、呑気に焼き鮭を食べているのだった。妹の未空も納豆に箸を突っ込んで、くるくるまわしている。宿主の熊沢も、呑気にそのあたりをうろついている。
一体これはどういうことだ。自分ばかり焦っている……。この人たちにとっては殺人事件が日常茶飯事なのか。そう、柚葉は思いながら、じっとしていられず、おろおろとあたりを見まわしていた。
柚葉は観念して、自分も畳に座ると、長い座卓に置かれているおひつから、好きな分だけ白米を茶碗によそって、焼き鮭の身を突っつき、一口食べた。塩気がつんとしただけで、ろくに味もわからない。そうしていると、どたどたと廊下から足音が響いてきて、屈強な中年男性が飛び込んできたのはまさに猛虎の如し。
「羽黒。一体何しているんだ。電話に出ないから来てみたら……」
というのは、群馬県警の鬼警部、根来拾三であった。
「根来さん。どうしました?」
「どうしましたじゃない! ここから目と鼻の先だ。岩松城公園で首と胴体が切断された死体が見つかったんだよ。三日前の殺人事件との関連も疑われる。呑気に飯なんか食ってんじゃないっ!」
という根来の怒声は、このオンボロ民宿を揺るがすような勢いであった。
祐介はあまり気乗りがしない様子であったが、岩松城公園へゆくことを約束した。祐介は味噌汁を啜ると、妹と共に立ち上がり、根来警部と共に現場へ向かうというので、柚葉も慌ててついて行った。
自動車だと数分で到着する位置である。岩松城公園の二の丸を越えると、そこは天守閣のある本丸なのであった。
「いいか、あの天守閣の最上階、高欄の中に被害者の切断された頭部はあったのだ。そして胴体が、そこから落ちて、屋根を転がり伝いながら、本丸の地面に落ちるところを三の丸にいた観光客のカップルが目撃している」
「なるほど……」
「しかし奇妙なことがある。天守閣は午後六時以降、完全に施錠されている。ところが覚如はその日、午後七時頃までジャズ喫茶にいたそうだ。彼の死体が発見されたのは午後九時だ。どうやって彼の死体を天守閣の最上階に出現させたのか、まったく説明がつけられない……」
柚葉は、またしても密室殺人だな、と思った。前回はハリボテの蓄音器の中に隠れて逃げたなどという変てこなトリックだったが、今回はどんな凄まじいトリックが使用されたのかと期待が高まる。
「不可能犯罪ですね。どうも今回、不可能犯罪が多いようです。ところでその三の丸にいたという観光客のカップルは疑わしくありませんか?」
「疑わしいといえば疑わしいな。犯人の手口を考えると、このカップルの天守閣から落ちてくる胴体を見たという証言さえなければ、天守閣に首が出現したというだけの話になるからな。それはつまり、天守閣内に胴体を入れるという手間が省けることになる。いや違う。ただ、今確認したところ、防犯カメラの映像に、人のようなものが屋根を転がり落ちるところが映っていたそうだ。また、天守閣の最上階の他、屋根には鮮血こそついていないが、転落物のために瓦が壊れた跡がある。天守閣から何かが落ちたことは間違いないんだ……」
「これは単純に第一発見者が疑わしいか、その第一発見者を巧みに騙した犯罪と考えられますね」
「そうかね。死体が天守閣から落ちてきたところを見たカップルが、警備員に伝えて、警備員が本丸の曲輪に向かうと、そこには果たして鮮血にまみれている、頭の切断された胴体が地面に伏していたのだ。そこで警察を呼び、共に天守閣の最上階へ向かうと、高欄の内側に、覚如の生首があって、鮮血が広がっていたそうだ。騙す方法はないように思うが……」
羽黒祐介は二の丸にある三層の建築物を見つめながら、それが天守閣と向かい合っているのを観察している。しばらくして、その建物にゆきたいと言い出した。一同は二の丸に移動した。それは見張りの櫓のような建築であったと思われる。
「まあ、こうしてこの場から、二の丸にある建物と、天守閣の最上階の高さの違いを見ますと、これくらいならなんとかなりそうですね。非常にシンプルな物理トリックを使用すれば……」
「教えてくれよ……」
「まずは天守閣が施錠される午後六時より前に、胴体を模した人形を作って、高欄の外側にぶら下げておきます。結んだロープは地面まで垂らして下で切断できるようにしておきます。そして二の丸の建物と、天守閣の高欄との間にロープを通して、大きな輪の形にして、ちょっとしたロープウェイのようにしておくんです。午後七時以降に覚如さんを呼び出し、彼を殺害すると、頭部をロープウェイにくくり吊るすか、グロテスクで恐縮なのですが喉と口の中にロープを二周通すなどして、固定しました。犯人はロープをたどり寄せるようにまわして、二の丸の建物から天守閣の高欄へと生首を空中移動させたのでしよう。首は高欄の中へと転がり込みます。そこで犯人はロープを切ってしまう。ロープだけ引き抜いて回収をします。
死体の胴体は、堀にでも落として、転落した痕跡をその胴体に作ると、それを人形が落ちるであろう場所に放置しました。そこで人形をくくりつけているロープを地上から切ると、人形が屋根瓦を破壊しながら転がり落ちてくる。人間とロープを回収すれば、現場には転落した痕跡のある切断された胴体が残る。あとはカップルが城の方向を見た瞬間を狙うだけです。もし目撃者がいなくても、防犯カメラがあるから大丈夫です。まあ、こんな物理トリックが考えられるでしょう……」
「なんというか、ずいぶん手間のかかることをする犯人だな……」
根来警部は、あまり納得がいっていない様子だった。
「大体のことは、物理トリックと心理トリックでできるんです。なにしろ人間が月に行く時代になってから、もう五十年近く経っているんですからね。ただ、不可能犯罪なんてものは要は可能か不可能かの問題ですから、結論を申しますと解決しても、大した情報が得られるわけではありません。犯人推定の最大の手がかりはいつだってホワイダニットなんです。動機を当たった方がいいでしょう。それと三日前の蓄音器泥棒殺人事件と関係があるのかどうか……」
羽黒祐介がそう言うのがひどい茶番劇に感じられるほど、拍子抜けの雰囲気だった。見た目が派手な事件ほど、解決はあっさりとしているものだ。
「まあ、なんというか妙な事件だ。こんな変な事件は他にないと言う気がする」
作者による弁解を挟むと、これはミステリ小説であるから、こんな非現実的なトリックがメインに据えられて売るのではまったく失敗作という他ない。しかしながら、物語の主体はここではないのである。作者が出しゃばって、あまりメタ発言をするのもよくないだろうから、ここらで柚葉の視点に戻るとしよう。
「ただひとつわからないことがあるとしたら、それはカップルが訪れたのは偶然ですし、必ずしも城を見るとは限らないということですよね。男は女を見て、女は男を見る。城が入る余地なんてありませんよ」
と柚葉が持論を展開すると、確かにそうだ、という雰囲気になった。
「いや、カップルは偶然でもなんでもいいんですよ。防犯カメラの映像さえあれば……」
と羽黒祐介は訂正する。まさにその時であった。
「兄が殺されたようですね……」
その声はどこか底冷えする響きを持っていた。柚葉がぎょとして振り返ると、そこには神経質そうな若い僧侶が立っていた。よく見てみると、覚如とよく似ている顔をしているのだった。その僧侶は、静かに歩み寄ってきた。
「あなたは宮下双如さん……。覚如さんの弟の……」
根来警部が震えた声でそう言ったので、柚葉ははっとした。そうか、この人は覚如の弟なのか。
「ええ。兄は何者かに殺害された。わたしは今、兄の宿業の果てをみているように思うのですね。まったく不可思議な連続殺人事件のようですが……。ふたつの事件に関連はあるのでしょうか……?」
根来警部は、意味ありげに引き下がると、羽黒祐介にそっと耳打ちをする。羽黒祐介は静かに頷くと、双如に歩み寄った。
「なるほど。あなたが猿渡家心中事件で被疑者と扱われながら、完全なアリバイを持っていて、容疑を免れたという宮下双如さんですね……」
柚葉はその言葉にぎょっとした。双如は狂ったような笑い声を上げた。
「あれはまったく奇妙な出来事でありました。完全なアリバイを持っているこのわたしが、容疑者扱いというのは……。あの時、担当されたのも根来警部でしたね……」
根来はじろりと双如を睨みつける。しかし言葉にならない様子だった。
「根来警部は、今でもわたしが犯人だと思っているのでしょう。そして今度のことも兄を殺したのはわたしだと思っていることでしょうね。しかしこれは人間が原因の犯罪ではありませんよ」
「それなら、なんだというのです」
と根来は虎の咆哮の如き声で言った。
「林田五郎兵衛の怨霊とやらでしょう。兄の首は切断されていた……。まるで四百年前の戦国武将のようにね」
兄の死をあまりにも平然と語るので、柚葉はぞっと身の毛がよだつ思いがしたのだった。
4
根来警部は、今回も双如を疑っていたため、今回も執拗な事情聴取を実施したが、彼にはまたしても、蓄音器泥棒殺人事件の際に霊妙寺にいたという鉄壁のアリバイがあるのだった。
また初動捜査の中で、天守閣で発見された頭部に、細いロープのようなものが擦れた跡が見つかったことから、羽黒祐介の考えた物理トリックはおおよそ的中していたことが証明されたようである。
岩松城首切断殺人事件は、その後、一向に進展しなくなり、柚葉の方も歴史の探究が暗礁に乗り上げたので、商店街のジャズ喫茶へと向かった。
昼間なので、私語厳禁の状態であった。入った瞬間、レッド・ガーランドのピアノが鮮やかに弾んでいて、最高にグルーヴィーな調子であった。柚葉は、濃厚なチョコレートケーキをフォークで突き刺しながら、レモンスカッシュを飲んで、一時間半ほど、商店街の古本屋で買った水木しげるの「ラバウル戦記」と萩原朔太郎の詩集とマティスの薄い画集をのんびりとめくって過ごした。
(事件なんかどうでもよくなっちゃった……)
そんな時に、もしかしたら、と思ったのは、蓄音器泥棒殺人事件の犯人は、猿渡家心中事件に関する秘密が録音されたCDを回収するために、あの蓄音器室に忍び込み、蓄音器泥棒と鉢合わせになって、証拠隠滅で殺害したのではないか、ということだった。そう考えてみると筋が通る気もする。殺人犯が蓄音器泥棒だとしたら、わざわざ猿渡家にあったCDなんか盗むわけないし、もしかしたら蓄音器泥棒の共犯者は、単に逃亡しているだけで、名乗り出るわけにもいかないで困っているだけかもしれないのだ。
そこまで考えたところ、柚葉が好きな「ゴールデン・サークルのオーネット・コールマン」が流れ始めて、生々しいサックスの迫力のために、事件なんかすっかりどうでもよくなってしまった。
料金を支払って、商店街に出てふらふら歩くと、観光地らしい街並みから外れて、シャッターの数も増えてきた。八百屋には青果が並んでいる。山のように積まれたみかんの一袋を手に取る。一番下の潰れたみかんの裏が白くカビている。ぼんやりと見つめていると、林田五郎兵衛の怨霊もこのカビのように蔓延る得体の知れないものだと思った。
商店街の先を見ると、夕焼けに染まった山並みを背に、未空が苺のアイスクリームを食べながら、ふらふらとこちらへ歩いてくるのだった。長い影が地面を這っている。
「未空ちゃん……」
今朝、知ったことだが、羽黒未空を十代の少女と決めつけていたが、彼女は二十二歳ということで柚葉よりも二歳も年上なのだった。こういう人は十年経っても、二十年経ってもこのままなのだろうな、と柚葉は思った。そうは思ってみても、未来というものは本当にわからないものだとも柚葉は思う。
「柚葉さん。わたし苺アイス食べてるよ」
「よかったですね」
「ううん。本当は梅干し味のアイスを食べたかったんだ……」
「梅干し味……」
そんなアイスあるだろうか、と柚葉は首を傾げた。
「ねえ、お兄ちゃんはまたひとつ真実に気がついたよ。あのCDの音楽さ、柚葉ちゃんが部屋にゆくまで音量が小さくならなかったでしょ?」
「くるみ割り人形のこと? そうだね」
「それって不自然だよね、犯人なら慌てて音量を小さくするはずなのに。犯人がああいう音楽機器を使ったことがなくて、ボリュームの上げ下げができなかったってことだよね。覚如さんはジャズ坊主といわれるくらい音楽好きだったから、当然、彼は犯人ではないってこと……」
「そうか。確かにそうだね」
「ううん。今のは冗談……」
「冗談……?」
なんのための冗談だったんだ……と柚葉は思った。
「犯人はそんなに大きく音楽がかかっていると思っていなかったんだよ。実は現場から無くなったものがもうひとつあって、それはヘッドホンなんだ。犯人はCDの内容を確認するために、ヘッドホンをオーディオにつけて、音楽を再生しているつもりになっていた。ところが、コードは抜けていて、どうも音量が大きくならないと思っていんだ。だから犯人は、音量を小さくしなかったんだよ……」
なるほど、それは確かに筋が通る説である。
「ということは、犯人はやはりCDの内容を確認していたのか……」
それよりも少し前に、覚如が犯人かどうかという話題のあったことに、柚葉は若干引っかかっていた。
(蓄音器泥棒殺人事件の犯人の候補者として覚如さんが上がっているのかな。まさか。だって彼は殺されちゃったんだよ?)
5
岩松城首切断殺人事件から二日後、熊沢館に双如がバイクに乗って、ひとりで訪ねてきた。
宮下双如は二十七歳で、覚如のひとつ年下の弟であった。彼は緻密な思考の持ち主で、仏教問答を繰り広げれば敵なしとまで霊妙寺内で言われてきた男だった。そして五年前の猿渡家心中事件においては、警察は彼を、最有力な容疑者と目していたが、彼は完璧なアリバイを持っていたため、ついに逮捕することができなかったのであった。
柚葉は、双如のそんな細かい事情はほんの少ししか知らなかったが、聡明な中にひどい翳りをもった僧侶だという印象を持った。
「あれから兄の死については、一向に謎が解かれていないようですね」
双如はそういいながら、座敷の上で、萩焼きの茶碗に注がれた民宿の煎茶を熱そうに啜っている。
柚葉は、羽黒祐介や未空と一緒に、羽黒祐介が宿泊している部屋にいるのだった。
「今、兄の法事を終わらせて、魂の供養をしているところです」
双如はそう言いながら、意味ありげに数珠を取り出すとそれは美しい紫色をしている石だった。
「あ、その数珠。わたしが事件の前日……岩松城公園の展示室で拾った……」
と柚葉が瞬間的に声を上げると、双如はぴくりと片眉を上げた。
「これを事務所に届けてくださったのはあなたでしたか。おかげさまで助かりました」
「あの日、岩松城公園に行かれたのですか?」
と羽黒祐介が尋ねてくるのを面倒くさそうに双如は睨んだが、すぐに、
「岩松城で戦死した人々の魂を供養できないものかと思って、赴いたのであります」
と言って、小さな声で呪文を唱えた。それは密教の真言のようなものだったのかもしれない。
双如と共に三人は熊沢館を出て、道なりに歩いた。岩松城が景色の奥へと遠ざかってゆく。あの城の天守台に、覚如の生首は出現したのだと思うと、生々しかった。過去からの断続的なイメージが押し寄せてくる。それはすなわちなにかといえば戦国の殺戮の流血であった。
柚葉も、双如や、羽黒祐介と未空の兄妹とともに、商店街を歩いている。夕暮れ時で赤く染まった商店街には、まばらに人の黒影があった。土産物屋ではどこでも似たような饅頭やバタークッキーを売っている。大好物の塩羊羹が夕暮れ色に染まっているのが綺麗だった。この一角は賑わいがあった。柚葉は、それでも観光地としてはずいぶん人が少ない方だと感じていた。
四人は、街角の料理店に入った。猫のぬいぐるみと共に西洋人形が沢山飾られている西洋料理店で、出された湯呑みには可愛らしい猫の絵が、素朴に筆で描かれている。夕食と称して、それぞれ思い思いの料理を注文した。他の人々はビーフステーキを注文したが、柚葉はオムライスを注文した。ふわふわのオムライスを食べていると、双如と羽黒祐介が、ずっと仏教の話をしているのだった。話題は仏教一般から、次第に密教へと絞られていった。
「インド仏教の最終形態が、密教というのは正確な理解でしょう。つまりそこにはインド仏教の思想の肝要なところがすべて含まれている。般若は勿論、唯識も、華厳も、そして最終的にそれらを統合しているのが密教というわけです」
「しかし浄土教や、禅を含まないところを見ると、完全なものとも思えない気がしますね」
「浄土教や禅というのは、わたしに言わせれば異端の宗教ですね。聖道門の正当なる仏教は、密教ただひとつだと信じております。密教は素晴らしいものです。密教は実践行と加持力を重視します。とりわけ重要なのは、マンダラです。マンダラは宇宙の真理である大日如来とそこから派生する諸現象の象徴である神仏との関係を如実に表しています。マンダラの瞑想を通して、聖から俗へ、俗から聖へ、真理から現象へ、現象から真理へ、修行者は達することができるのです。マンダラには四種類あり、その中でもこの世がそっくりそのまま、真理を体現した巨大なマンダラであるというのが、羯磨曼荼羅です……」
真言宗からも独立して、単一宗派となった霊妙寺であるが、今でも明確にその思想に密教的色彩を残しているのだった。
「アンマラ識というのはなんですか?」
「唯識仏教の八識に、密教独自の第九識を加えたものですね。それぞれ知覚であるところの五感を意味するのが、第五識までです。第六識は意識といって、概念や観念をつかさどるものです。たとえば、あなたを「人間」であるとか「羽黒さん」だとか、概念的に捉える錯覚を起こすのが、この意識なのです。第七識はマナ識といって、自我意識です。この世は因果の関係によって諸現象が刹那生滅を繰り返しているだけですが、自分という固定的な実体があると錯覚させ、好悪などの感情を生み出すのがこのマナ識になります。第八識は、アーラヤ識でありまして、一切貯蔵識と言われるものです。これは過去のすべての体験を貯蔵している識で、この心は、表層心ではなく、深層心であるということが言われています。深層心理のようなものです。過去の自己の行為が、現在の自己の行為に対して、カルマという牽引力を持っているということが言われます」
「悟るというのは、それらの八識をどのようにすればよいのですか?」
「これらの心をそのままに清浄にすることで自ずから真理を悟ることができるのです。これを転識得智といいます。たとえば、意識はすべての存在を概念化して捉える差別認識ですが、これを清浄にすると妙観察智という個別存在を見極める智慧になるのです。この妙観察智を象徴しているのが阿弥陀如来です。自我意識であるマナ識も、これを清浄にすると、平等性智というすべてのものが平等一体であるという智慧になるのです。この智慧を象徴しているのが宝生如来です。このように密教においては、智慧ひとつひとつを象徴するために仏が存在しています。その智慧の関係性はマンダラにおいて表現されております。ところで唯識仏教の論じた八識に第九識アンマラ識を加えたのが密教です。これらの心の根本なるものは、アンマラ識という第九識であり、これこそ自性清浄心たる仏性に他ならないのです」
「双如さんのおっしゃることはわかりました。密教は深淵な教えだということがはっきりと……。しかし我々、日本人の精神文化に根差しているものは、そのような難解なインド哲学ではなく、もっと素朴な霊魂信仰、祖霊信仰のようなものではないですか。怨霊という信仰も、日本的なものだと思います。そのあたりのことをお伺いしたいのですが……」
と羽黒祐介が言うと、双如はふふっと笑った。
「霊魂信仰は確かに素朴なものです。日本人にとって、人が死ぬとは、霊魂が肉体から分離することを意味している。霊魂の抜け出た肉体はすなわち気が枯れておるので、ケガレておりましょう。かつて風葬のあった地域では、特に腐乱する死者は恐れられたものでした。霊魂もまた荒御魂といって、死後しばらくの間は危険な状態にある。これを魂鎮めして、浄化し、いずれは山の神、田の神といった祖霊にしてゆくのであります」
そこで、双如は羽黒祐介に尋ねるのだった。
「ところで羽黒さんは、一体誰が一連の殺人事件を起こしたのだと思いますか? あなたもわたしを犯人だと目しておられるのかな」
と、双如は挑発的なことを言ってくるのだった。
「あなたには、蓄音器泥棒殺人事件の際のアリバイがあるらしいですからね。あなたが犯人でないことは明白ですよ」
と羽黒祐介は、事件自体に、あまり興味を持っていないかのような口ぶりである。そうやって相手の挑発を逸らしているのか、本当に興味がないのかは不明である。柚葉はぼんやりと羽黒祐介の様子を窺っていた。
「しかし、わたしが犯人でないか否かはまだわからないと思いますよ。だって、蓄音器泥棒殺人事件と今回の岩松城首切断殺人事件が必ずしも同一犯の仕業とは限りませんからね」
「あなたも恐ろしいことをおっしゃる。一箇所で連続して殺人事件が発生した場合、確率論的に無関係とは思えませんね」
と羽黒祐介は、双如の挑戦を感じている様子だが、わずかに直接対決をかわしている。
「それは確かにそうです。しかしこう考えてみてはいかがでしょうか。これはいわば不連続の連続というやつですよ。たとえば、蓄音器泥棒殺人事件の犯人が兄で、その兄を殺したのがわたしだったら……」
「覚如さんが蓄音器泥棒殺人事件の犯人……? 一体どこからそんなとっぴな空想が飛び出すのですかな。なるほど。ふたつの事件は関連しながらも、犯人となると別々だったというのですね。しかしそれなら覚如さんはなぜ殺されたのです。蓄音器泥棒の共犯者に報復で殺されたとでもいうのですか。それはあなたではないでしょうに……」
「これはひとつの仮説を申したまでのことです。わたしにも犯行は可能だったということを言っているのですよ。いずれにしても、もとをたどれば、猿渡家心中事件の犯人が兄、覚如だったとして、そこからすべての事件が不連続の連続で発生したのではありませんか」
「これまた面白いことをおっしゃる。蓄音器泥棒殺人事件だけでなく、猿渡家殺人事件までもが覚如さんの犯行だと推理されているのですね。なぜそんなことをお考えになったのです」
「そもそも林田五郎兵衛の怨霊のシャーマニックトランス殺人の下手人が、猿渡庄造ではなく、兄、覚如だったとしたら……。単純な理屈です。怨霊に憑依されたのははじめから兄だったのですよ」
「それは見事な推理です。しかし、それならば、すべての根源は、四百年の昔、岩松城落城、林田五郎兵衛の戦死にまで遡らなくてはなりますまい。そこから怨霊の祟りが始まったのですね。そして猿渡家心中事件も、今回の蓄音器泥棒殺人事件もすべて、林田五郎兵衛のシャーマニックトランス殺人だったと仮定するならば……」
「羽黒さんは名探偵なのに、ずいぶん非科学的なことをおっしゃるのですね」
オムライスを食べていた柚葉は慌てて、強い非難を込めて、そう言った。羽黒祐介が双如の術中にはまっているように恐ろしく感じたのであった。
「その通りです。僕は今、非科学的なことを言おうとしています。それでありながら、僕にはひとつの考えがあります。この世界において非科学と科学は必ずしも矛盾しないように思います。物理と心理とを、憎み合う両極端のように捉えること自体が現代的ではありませんし……。猿渡家心中事件のシャーマニックトランス殺人は、少なくともこの五年間余りは我々にとって支配的な体験的事実であったわけです……」
その時、ぞっとしていたのは柚葉だった。
「羽黒さん。そんな狂ったことを言わないでください。それでは、一連の事件はすべて林田五郎兵衛が怨霊の呪いだったと羽黒さんは本当におっしゃるのですか」
柚葉は、わけのわからない雰囲気になってゆくのが恐ろしくなって叫んだ。
「芦沢さん。こう考えてください。もしも霊魂というものが日本人にとって精神的に根源的なもので、日本文化における人々の共同幻想であって、さらに実際的な影響力を持っているとすれば……」
その言葉に、双如は満足そうに乗り出すと、言葉を繋げた。
「芦沢さん。羽黒さんのおっしゃっていることは非科学なことではありません。こういうことです。たとえば、桜の花は因果の寄せ集めにすぎず、実体としては存在しないけれど、桜の花という概念をもって認識するしかない人間にとっては、やはり桜の花が存在すると思う他ないのです。さらには、その概念が人間の心理間で共有されて、人を突き動かす力を有している以上、それは存在していると捉えるしかないとおっしゃるのと同じことなのです」
柚葉は、ぞっとした。羽黒祐介が双如の言葉に頷いて続けた。
「そうです。その理屈で、やはり怨霊も存在しているし、一連の事件の、すべての根源にもなりうる気がするんです」
「花は花として存在しているわけではない。しかし花は花として確かに存在する。この問題と同じように、神仏は神仏として存在しているわけではないけれど、確かに神仏として存在しているというわけでしょう。まったく般若哲学の論法を逆手にとったのですね」
という双如は不敵に笑っている。羽黒祐介がまたその言葉を引き継ぐ。
「我々の精神的生活においてそれらは実際的な影響力を持っている。実際に共有されている多くの価値観は無力ではなく、有力であるということです。そればかりでなく、問題は、それは我々の内側にいかなる根拠を持つのかという点です」
これを引き継ぎ、双如はさらに語る。
「すべて、共同体において共有されている概念は夢のようなものなのですよ。歴史とはすべて過去の人々が見た夢の走馬灯の如きものです。といって、それらすべてが無根拠だとまでは断言できないでしょう。本当の夢だって無根拠ではなく、深層心理に由来するものです。人々が共に見続けてきた夢にはなにか根拠があるのでしょう。しかしそれらをわたしたちが知ることはない。本当にこの現世は不思議なことばかりです。わたしたちは不思議の中に生まれて、その不思議から一歩も出ないで死んでゆくのですね……」
「僕が言いたいのは、林田五郎兵衛の怨霊は、人々の心を伝って共有されている価値観念で、社会的に実際的な力を有していたということです。僕がいう力とは、物理的な力ではなく、人間を突き動かす精神力動のようなものです。そして、それは深層心理的に無根拠なものではなかったのではないかと思います」
「それは大いに考えられると思います。しかし、羽黒さんの話で曖昧に思えるのが、その根拠とは何を意味しているのか、ということです。その根拠とは単に人間の深層心理にある根源的なもののことをですか、それとも神仏霊魂の実在を意味するのですか」
「僕にはわかりません。ただ、日本文化においては、人が死ねば、その霊魂は山へと昇る。あるいは海の彼方へと向かうものです。僕はそういうことを白緑山寺の円悠という僧侶に学びました(小説家になろう掲載『白緑山寺の殺人』参照)。古代の人間は死ねば、自然の一部になることを直感していたのでしょう。この直感をまったく無根拠なものだとは思いませんね。永遠の過去から続いてきたものが、今こうして自分という存在を作っているのです」
双如は、羽黒祐介の言葉に満足したようだった。双如は、しばらくして用事があるといって席を立つと別れた。双如がいなくなったタイミングで、柚葉は羽黒祐介を批判するように言った。
「羽黒さんはすべての事件が怨霊の祟りだったなんて、本気で思っているんですか」
「あるいはそうかもしれない……。しかし僕はね、あの双如という僧侶の嬉しそうな表情を見たかったのさ。唯識仏教において客観存在の現れ方とは深層心理の共同幻想なんだ。すべての存在が、因果によって仮に生じた夢幻のようなものだと看破したのは般若思想だけれど、そもそも自己そのものが夢幻のようであり、客観存在も夢幻のようなものだと認識された時、神仏のような主観存在も、実在しているものと変わらぬ重みを持ってくる。いうならば、神仏や怨霊のような霊的存在も、アーラヤ識という深層心に貯め込まれたひとつのカルマであり、根拠のあるものと捉えれば、客観存在としても実在していると捉えられる。双如の実現したかったことはまさにこの論理なんだ。僕は彼の求めているこの論理を肯定した。彼の真に喜ぶ顔を見て、直感的に、彼の犯行動機を確信したというわけさ」
柚葉は羽黒祐介の語っていることの意味を理解した。
「それじゃ、双如さんが犯人だというのですね。そしてその犯行動機は、霊魂の実在を、唯識仏教的観点から肯定し、証明することだった……」
「そうだ。彼は僧侶として現代の科学主義と日本文化の霊魂の実在論との対立に苦悩していたのだろう。そして、彼はその対立を超越するために、猿渡家心中事件を起こしたのだ。地震により供養塔が横倒しになったあの日、猿渡家心中事件を起こし、日本人にとってシャーマニズムや怨霊といったものが、今なお、実際的な力を有していることをこの世に知らしめたのだ」
霊魂というひとつのカルマを証明するために、双如は殺人事件を起こしたのだろうか。彼にとって霊魂の実在はそれほどまでに重要なことだったのだろうか、と柚葉は不思議に思った。
「彼は面白いことを言っていたね。蓄音器泥棒殺人事件の犯人は覚如さんだというんだ。だからその時に自分にアリバイがあっても、自分が事件の犯人である可能性が残っているということだった。不連続の連続というわけだね。その覚如さんをなぜ、双如さんは殺害したのか……。それも首と胴体を切断し、首を天守閣の最上階に釣り上げ、胴体を転落したように見せかけている。これもまた怨霊の仕業に見せるためにやったことなんだ」
「すべて林田五郎兵衛の怨霊の仕業に見せるために……。でも、それならどうしてもっと林田五郎兵衛の祟りを演出しなかったの」
「彼は自然発生的に、霊魂の存在が信じられることが、人々の心理間で共有され、自覚されるような状況を生み出したかったのだろう……」
「その最大の説得力が、首が切断された死体だったというわけですね」
「暗示的な点は、首と胴体を切断するということが、戦国時代的というところだね」
「でも、彼が猿渡家心中事件の犯人であるというのなら、アリバイを崩さないといけませんよ」
「その通り。今から根来警部に聞いて、彼のアリバイを崩そうと思う……」
このようにして、双如のアリバイ崩しが始まったのだった。
「双如さんが本当に猿渡家殺人事件の犯人ではあり得なかったのか、そのアリバイ崩しを追体験しするというわけですね」
柚葉は興奮してそう叫んだ。一同が西洋料理店から出ると、外は一面美しい星空に包まれていた。冷たい風が吹きつけてきて、ネオンに輝く商店街はどこか寂しげな影を抱えている。柚葉たちは熊沢館へと歩き出した。足音ばかりがどこか遠くへと消えてゆくように感じられた。
羽黒祐介は、この猿渡家心中事件を担当したという根来警部をその夜、熊沢館に呼びだすと、アリバイについて聴くことになった。屈強なる根来警部は、資料を持って現れて、大きな咳払いをすると事件について語り始めようとしている。
「それでは根来さん、お願いします……」
と羽黒祐介は言った。
柚葉は周囲の人々の姿をじっと見つめた。金剛力士のような根来警部は語り始めた。
「あれは忘れもしない五年前の冬、十二月十日のことだ。前日、地震があって、供養塔が横倒しになった。猿渡庄造が遺書を残して首吊り自殺し、その妻里美、そして娘の詩音が日本刀のようなもので首や腹部を切り裂かれて、殺害された。日本刀は霊妙寺の所蔵品であったことから、俺たちは霊妙寺の関係者の中に犯人があるのではないかと疑うことになったわけだ。俺は現場である猿渡家自宅へと向かった。そこは明治時代に作られたという昔ながらの日本家屋だった。はっきり言って現場は不自然なことばかりだった。まず、第一に押入れの中に血の足跡が残っていた。その血は里美のものだった。そして足跡は、詩音のものだった。詩音の死亡推定時刻は午後六時ごろということで、遅く見積もっても午後六時半ということだった。里美の死体はしばらく見つからなかった。ところが、しばらくして井戸の底に転落している里美が見つかった。水浸しになって、日本刀による二度の切り口で、ひとつは腕に、もうひとつは心臓を貫いていた。死体の状態も悪く、死亡推定時刻は曖昧だったが、里美の血を受けた詩音の足跡が残っていたことから、先に里美が切り殺され、続いて詩音が切り殺されたのだろうということがわかった。庄造は午後八時に、前橋の某所の公衆電話から電話をかけており、その音声が会社の留守電に残っていることから、庄造の死は、午後八時過ぎだということがわかっている。もしも庄造が犯人であるのなら、前橋に行ってからまたこの村の自宅に戻って来たことになる。片道一時間として、庄造の死は午後九時だろうか。庄造には遺書があった。しかしこれはワープロソフトで作られたもので、妻子を切り殺した人物のものとしては不自然だった。それに加えて問題なのは、テーブルの上に東京の名洋菓子店「大宮洋菓子店」の看板商品であるアップルパイが置かれていたことだ。その菓子が作られたのは当日のことだった。アップルパイが入っている店の紙の箱には、製造日と賞味期限が明記された印が押されていた。しかし、その日、事件の関係者で東京からやってきた人物はひとりもいなかった」
「それでどうして、双如さんが犯人ではないかと疑われることになったのですか?」
と、羽黒祐介は身を乗り出すと、気になっている様子で尋ねる。
「双如が持っている紫色の数珠のひとつが現場から見つかったんだ。双如はそれをどこかで無くしたとほざいていた。しかし考えてみても不自然だ。双如が庄造と乱闘になって、数珠の紐が切れて、珠が転がったのじゃないか。俺たちはやつを犯人だと睨んだが、彼には完璧なアリバイがあった」
「どんなアリバイですか」
「夜遅くまで法事のために霊妙寺にいたんだ。やつは午後七時過ぎまでトイレに行く十分程度しか退室しておらず、人に見られていない時間がほとんどなかったというわけさ。また、午後八時からは僧侶仲間と僧坊で会食をしている……。彼の空き時間は実質、午後七時から午後八時までのわずか一時間あまりしかない」
羽黒祐介は、その話を聞きながら、しばらく資料をみていると、だんだんと真相が見えてきたようだった。羽黒祐介は立ち上がるとすぐに霊妙寺へゆくと言い出した。
気がつくと、未空は猫のように眠りこけていた。根来警部が車を出してくれて、羽黒祐介と柚葉のふたりは、空気が澄んでいて、美しい星空の下、霊妙寺へと向かった。
金堂の観音扉は閉じられていて、僧坊もしんと静まり返っていた。まるで死に絶えてしまったような静寂だ。しかし柚葉は、なにかにはっとして、羽黒祐介に囁くと、先導して歩き始めた。
(きっと、そこにいる……)
柚葉は、羽黒祐介を連れて、霊妙寺の崖沿いに例の供養塔がそびえているところへと辿り着いた。そこに、背中を向けて佇んでいる双如の姿があった。
「どうしてここだとわかったんですか?」
「以心伝心です」
と柚葉は言ったものの、説明すると長くなりそうなので、躊躇していると、双如が振り返った。
羽黒祐介は意を決して、双如に歩み寄る。
「双如さん。わたしには真相がわかりましたよ。なるほど。本当に殺人が行われたのはこの霊妙寺だったのですね」
「どういうことですか」
「押し入れの中に里美さんの血のついた、詩音ちゃんの足跡が残っていた……。これをみる限り、里美さんが先に殺され、詩音ちゃんが後に殺されたのだと思ってしまったわけです。しかし、真実はまったく逆だった。詩音ちゃんが先に殺され、里美さんが後に殺されていたのです。里美さんは二度、切りつけられている。一回目は腕だったといいます。押し入れの足跡の血は、この第一回目の時のものに違いありません。里美さんと詩音ちゃんは、霊妙寺にあなたを訪ねに来ていたのです。そしてあなたは詩音ちゃんを切り殺した。里美さんも腕を負傷しながら、追撃を恐れ、詩音ちゃんと共に、霊妙寺の車で自宅へと逃げ帰ってきていたのです。そして詩音ちゃんを助けようとした。あなたはご自身のバイクで追いかけて向かいました。これについては理由があって、まず里美さんがご自宅の車を運転した以上、その車からは血痕または血が付着したことを示すルミノール反応が出るはずです。その報告がない。だから霊妙寺の車を使用したのでしょう。里美さんは襲撃が守るために、詩音ちゃんを押し入れに隠したのです。しかし、この時、詩音ちゃんはすでに息絶えていた。詩音ちゃんの血の足跡が押し入れに残ったのはこの時です。倒れてしまって、足跡がつかないのではという想像もされるでしょうが、押し入れの中でたとえば、段ボールに座らせるようにしていたため、足の裏が床に密着して、その場に立っていた足跡のようなものが残ったのです。あなたは里美さんを殺害すると、井戸の底に投げ落としました。そして詩音ちゃんの死体を押し入れから出したのです。それもおそらく井戸の中に落として隠してしまうつもりだったのでしょう。そこに庄造さんが帰ってきます。あなたは庄造さんの首を絞めて殺害すると、首吊りの形にしました。これがあなたのやったことです。どうですか?」
「すべては憶測に過ぎませんね。しかしあなたのおっしゃる通りであるとすると、確かに里美さんと詩音ちゃん殺しの、わたしのアリバイはなかったことになる。あなたに五年越しにアリバイを崩されたということになりますね。しかし庄造はどうですか。庄造は午後八時まで生きていたのではないのですか…….」
「午後八時に前橋某所の公衆電話から会社に電話がかかってきて、庄造さんの音声が残っているのは、庄造さんが仕掛けた古風なトリックで、あらかじめ録音していたものを受話器ごしに流したのです。会社が営業日でなければ、録音設定にされているはずだから、会話になる危険性はありません。問題は、誰にその前橋某所の公衆電話に行って、録音を流してもらうかですが、これは共犯者がいないのなら、アルバイトを雇ったのでしょう。いわゆる闇バイトです」
「奇妙ですね。それでは、庄造さんがアリバイトリックを仕組んでいるみたいじゃないですか。被害者なんでしょう?」
「庄造さんはあなたを殺そうとしていたのですよ。あなたが、里美さんや詩音ちゃんを殺そうとしていたのを知っていて、先にあなたを殺そうと計った。そのアリバイトリックのひとつが、あのアップルパイです。あのアップルパイがすべての真相なんですよ」
「あれは「りんご」。つまり林田五郎兵衛の隠喩ではないですか……」
「違います。あれは庄造さんがあの名店の洋菓子店のアップルパイの作り方を独学で勉強して自分でそっくりに作ったものだったのです。そして、アップルパイの紙箱は、ずいぶん前のものを回収しておいて、製造日と賞味期限がそっくりの印鑑を拵えて、押したものだったのでしょう。なぜ庄造さんはこんなことをしたのか。それはつまり、彼が東京にいると思わせたかったというわけです。つまり彼は昼間、東京にいて、夕方は前橋にいて、この村にはいなかったというシナリオを作り出そうとしていたのです。あなたがいまだ健在であることから、おそらく、このトリックはまだ本番ではなく、予行練習に過ぎなかったでのでしょう。ということは午後八時の時点で、実際にはその時、すでに彼は殺されていたのです。
まったく奇妙なことながら、それではよくよく考えてみなければならないことがあります。あなたは庄造さんの妻子を殺そうと思っていた。そして庄造さんはあなたを殺そうとしていた。このアリバイ電話用の庄造の音声は、スマートフォンに入れると証拠が闇バイトに取られるから、CDに録音しており、返却する仕組みになっていたのでしょう。そしてそのCDは、表向きの前半部分は「くるみ割り人形」を収録することになって、その正体を隠した状態で返却され、ずっと猿渡家自宅に残り、熊沢館の熊沢さんに寄贈されることになったのです。あなたのお兄さんはそのCDの存在を知り、あなたの犯罪の秘密だと思いこんで、あなたを守るために、回収をしに行った。そこにたまたま蓄音器泥棒が来ていて、お兄さんはその泥棒を殺害した。あなたの秘密だと思っていたから、CDを死守しようとしていたのです。そして、あなたは反対にお兄さんに秘密が握られたと思って、岩松城公園で殺してしまった……。岩松城公園のトリックは何度も練習していたもので、真相に勘づいているお兄さんを殺害する計画は、かなり前からあったのでしょう。
さあ、この状況をあなたはどのように捉えますか。このような偶然の悲劇はまったく常識では考えられぬことです。複数の意識が絡み合いながら、偶発的に悲劇が連続している。しかし現実に起こっていることは間違いありません。このような状況そのものが稀有なことであることは間違いありませんが、実際、日常というのは偶然の集合体であり、それを特別視しているのは我々の意識の方なのです。あなたはこれを怨霊の祟りとか、仕業と捉えることもできると言うでしょう。
さて、すべての発端はあなたもおっしゃっている通り、豊臣秀吉が小田原北条を征伐した四百年前のことに立ち戻ります。この岩松城も燃え上がり、林田五郎兵衛は戦死しました。そして、その遺恨が残り、供養塔が立てられることになった。それから四百年の月日が経ち、あなたは霊魂の実在を証明するために猿渡家心中事件を発生させたのです。あなたの論理はこのようなものだった。「この世のありとあらゆる存在は、縁起と言われるところの因果の作用により仮に生じたものである。したがって、この世のありとあらゆる存在は、有るようで無く、無いようで有る存在であり、夢や幻や泡や影のようなものである。この世の存在は第九識まである心によって投影されているものである。すべての存在はこれらの心によって生みだされた共同幻想である。社会の観念はすべて、事物に対して、このようなあり方をしている。すべての存在・観念が、このような次第であるため、主観と客観の対立はもはや無くなり、神仏や霊魂といった存在も、同様に実在しているものと捉えられる」。
あなたは霊魂の実在を証明するために、猿渡家の人々を殺害したのです。ここにはおそらくこのような理屈が存在するのではないかと推察致します。「霊魂が存在するのであれば、死とは肉体と精神の分離にすぎない。したがって死は喪失ではない」。すべてが自然に帰るということをしただけだということです。その上、あなたは林田五郎兵衛の怨霊が、この現代においても、社会的な影響力を持っていることを知らしめたのです。それでありながら、あなたはお兄さんを殺害した。自己の罪が露呈する恐れが生じた途端に、あなたはその恐れを滅除するため、お兄さんを殺害せざるを得なかった。それが、あなたの中でもっとも自己矛盾している点です」
この動機が理解されたことに満足したのであろうか、ひとりの僧侶が嬉しそうに笑っていた。
「羽黒さん。わたしはそのようなことで兄を殺害したわけではありません。せっかく成し遂げたのです。わたしの理論により、怨霊の力は実在していることが証明されたのです。世界は震撼した。この村が観光地として廃れてゆくのもわたしたちが霊的存在を信じている証拠ではありませんか。わたしは科学万能の世界になって後に、霊魂の実在性を体現することができたのです。もしもあの猿渡家心中事件の謎が解かれたら、この状況も壊れてしまう……。それならば兄を殺害するしかなかった。祟りに思えるような状況でね。それだけの話なのですよ」
「わたしはあなた自身の話をしています。あなたが本当にそうした霊的存在を信じているのならば、そもそもこのような証明自体が不要だったはずです。あなたはただ、葬式仏教の価値を自分で信じられなかっただけ。自己正当化のために殺人を犯しただけではありませんか。なぜ、実在していると信じるものをわざわざ演出する必要があるのですか……」
そういうと双如は、悲しげに笑った。その悲しげな微笑みは終局を象徴していた。
(すべてが終わったんだ……)
柚葉はそう直感した時、過去の人々の営みが、精神文化が、霊魂が、自分の内側に自然と流れ込んでいるような気がした。三人を包み込む世界は広大でありながらどこか小さかった。黒塗りの屏風のような山並みに比べ、夜空は明るく霞んで見えた。そのどこかに、果てしない過去から続いている人々の魂が今も彷徨い、溶け込んでいる気がしたのだった。
「あなたのおっしゃる通りかもしれない。悟れぬ僧侶の苦しみというものです。霊魂を扱うことを生業としながら、霊魂の実在を信じられぬものは、どうやって自己の存在価値を得るのです。まあ、そうやって自己の存在価値なんぞにとらわれていること自体、わたしは僧侶に向いていなかったということかもしれませんな。どこからともなく生じて滅する心作用のありもしない実体にとらわれ、震え慄いている……。兄は、わたしのためを思ってこそ、熊沢館にCDを回収しにゆき、蓄音器泥棒を殺害して、破戒僧に堕落したようですが、あれで一番、僧侶らしい僧侶だったのですよ。そもそも仏典を読めば、そこに霊魂の記載はない。涅槃経に至って、それらしい記述が復活する程度のものです。わたしは自己の存在価値をいかなる論理に求めるべきだったのか……」
「それはしかし、きっと論理ではないのです。果てしない過去から続いている先祖の魂を、その営みを、この自然の中に直感することだけだったのでしょう。あなたは考えすぎたのです」
「おっしゃる通りかもしれない。言語道断の境地というわけですな。月を指差しても、指先を見つめているだけ。月そのものを知ることにはならない。わたしはずっと空虚な論理の世界に埋没して、それを超越した直感の世界を、過去に置き去りにしてきたのでありましょう」
そう語る双如は、いつになく僧侶らしい目をしていた。不安から生じるさまざまな疑念に立ち向かい、殺戮を犯してきた。それも今では、すべてが終わってしまったかのように静かだった。柚葉が双如の視線の先を見ると、欠けるところのない満月が浮かんでいる。
(今、この憐れな僧侶は大悟したんだ……)
柚葉はそう直感した。しかし、その直感には根拠がなかった。
ただ、月の光だけが存在した。
この物語は、論理や必然性よりも、直感と偶然性に満ちている。したがってミステリ小説としては不可解な内容であったが、直感と偶然性が、この世界の課題となって久しいのである。
蛇足ながら、説明を補足すると作中、覚如の心理描写には彼自身の誤解が含まれている。彼は、蓄音器泥棒が音量を上げたのだと思い込んでいるが、覚如は録音を聴くためのヘッドホンのコードが外れていることに気付かず、静かな『金平糖の精の踊り』から激しい『花のワルツ』に移った瞬間に、音量が上げられたものと勘違いをしたのである。