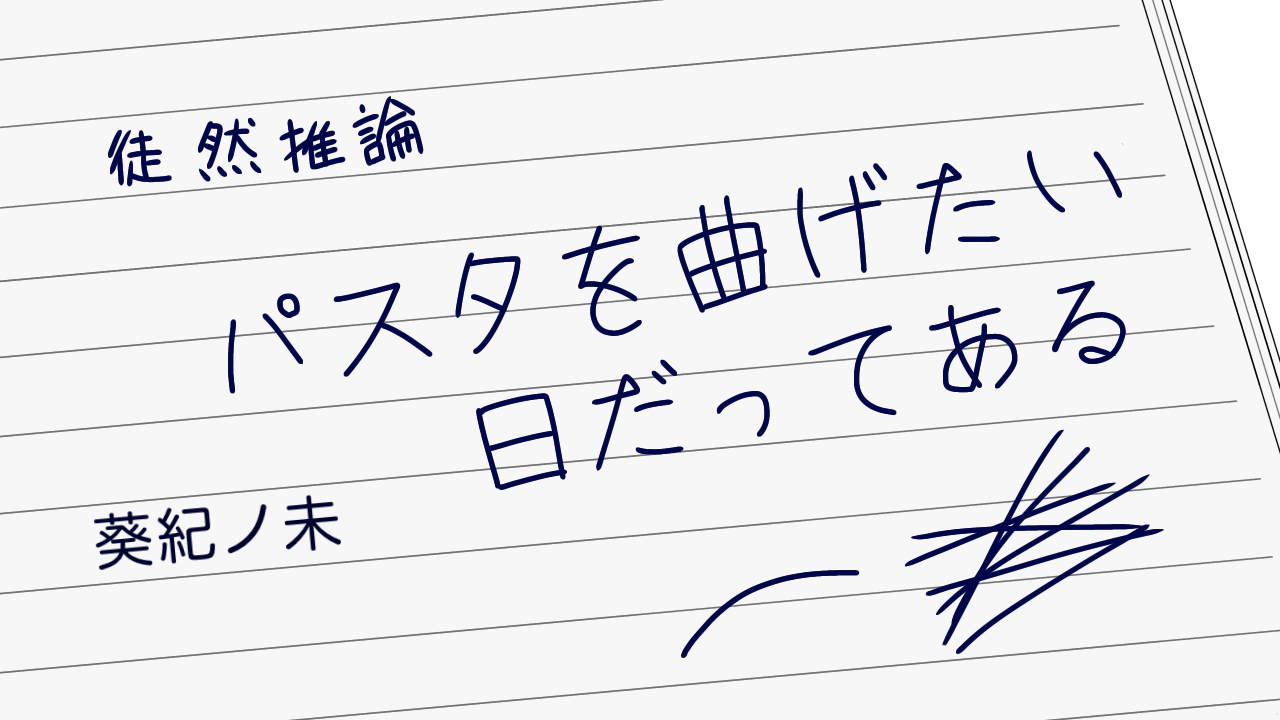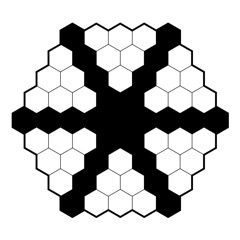パスタを曲げたい日だってある
パスタを曲げると、必ず三つ以上に分裂する。
ある優秀な頭脳を持つ人間がこれを証明したのは、そう昔のことでは無い。しかし、どうしてこれを証明しようと思ったのだろう。端的に言ってしまえば〝くそどーでもいい事実〟のひとつではなかろうか。
……と。
そのような思考にリソースを割きつつ、ひとりキッチンにてパスタを曲げて複数にはじけ飛ぶ様子を眺めて早数十分。
傍目から見たら完全にヤバいやつだと認めざるを得ない。大きめジップロックの中で実行しているので回収に労力は不要だが、自覚によって現れた疲労がため息とともに膝とパスタを曲げさせた。一六本目は五つに分裂した。
手遅れ感否めないこの心をさらに曲げるよりはパスタを曲げてはじけ飛ばすほうが良いだろうと思っていたのだが。
市販の早ゆでパスタなので細かくなりすぎると処理が面倒だからもうそろそろ止めたいとは思っているのだが。
曲げては分裂、曲げては分裂、曲げては分裂、曲げては分裂、曲げては分裂、曲げては……
パスタは想定以上に弾力性があり、半円に近いカーブを描く――そこからスピードを変えたりツイストさせたり、曲げ方にバリエーションを与え始めたころには止め時がわからなくなった次第である。
突然、短い電子音とともに視界が明るくなった。まぶしさに目を瞑ってしまったせいで二二本目の分裂する瞬間を見逃した。
「俺の大切な食料で遊ばないでくれる?」
キッチンの入り口から顔を見せる寺尾さん。彼を一瞥し「茹でればちゃんと食べられますよ」と答えてからパスタ曲げ職人に復職した。
「食べにくくなるでしょ」
「そうですね、多少は」
お。二三本目は七つに分裂した。最高記録だ。ツイストすると細かくなりやすいらしい。
「暗いキッチンから何かやってる音が聞こえてきたら怖いんだって。意味もなくパスタ折る心情も理解の外だし」
「曲げてるだけですから正確には――あっ」
「パスタは曲げたら〝分裂〟もとい〝折れる〟んだから、折ることを目的として曲げているも同然だ。ほら、屁理屈にもなりきらないこと言ってるうちに未成年が補導される時間になっちゃうよ。早く帰んなさい」
ジップロックごとパスタを没収されてプロのパスタ曲げ職人の夢を断念。促されるまま立ち上がり。深く息を吸って、ゆっくりと吐いた。少しは緊張が和らいだ気がする。
それから、わざとらしく聞こえないように気をつけて烽火を上げた。
「そういえば、寺尾さん」
「ん?」
「ここにある食べ物、寺尾さんの食料が多いですよね。この冷蔵庫の中身も含めて」
「そりゃ、オフィス兼住居だからね」
さも当たり前のことのように。ジップロックを棚に放り込み、寺尾さんは答えた。
冷蔵庫から手を離し、疑問を解消しきれていない彼の横を通り過ぎた。リビングへ向かう背後から「日野くーん?」訝しむ呼び声が聞こえてくる。
しかし、もう遅い。準備は整ってしまった。
「いえ、そうですよね。だから来客用のお茶請けや小腹がすいたときの食べ物を、僕も棚や冷蔵庫に入れさせてもらってます。あなたのワトソン役になったとき、許可していただきましたからね。
寺尾さんの食料じゃないものも、冷蔵庫には入ってるんですよ?」
「……なんか、怒ってる?」
「いいえ、まさか! 怒っても責めてもいませんよ」
「オーケー、よくわかんないけど許してくれるわけでは無いことは理解した。それで? なんで不機嫌なの?」
「不機嫌でもありませんよ。疲れただけです」
「いつもより仕事の負荷少なかったと思うけど……」
「そうですね。では、仕事が無くて暇してる寺尾探偵に問題です」
「仕事が無いは余計だよ。これでも本職だ」と憤慨したが「副業利益のほうが圧倒的に多いくせに何を仰ってるんです?」と指摘すると閉口した。
そんな彼に対し、通学カバンを肩にかけながら問いかける。
「ある食べ物……仮に、シュークリームとしましょうか。僕が後日食べようと買ってきていたシュークリームに毒が混入していたとします。どのような人物が毒を入れたと思いますか?」
「わー、いきなり物騒だね」
「仮定の話ですからね。シュークリーム、美味しいですし。シュークリーム、お嫌いでしたっけ?」
「いや。むしろ好き」
ですよね。
彼の答えに満足し、振り返って「さて、寺尾さん」と。
芝居がかった調子で挑戦的に尋ねなおす。
「犯人像について、あなたの推理を聞かせていただきましょう」
得意げな笑みとともに、彼は語り始めた。
「まっさきに挙げられるのは、君へ悪感情を抱いている人物だよね。探偵助手をしている方面から逆恨みをされている可能性が高そうだ。あ、忘れていた。君に熱を上げているファンの可能性も考慮しないといけないよね」
「ご冗談でしょう」売り叩かれた失笑も買う主義なので、お望みの反応を代金にする。寺尾さんの満足そうな笑みを横目に玄関へ歩みを進めた。
「ごめんごめん。ひとまず君への強い感情を抱いている人物と定めるに留めようか。
また、殺害方法として毒殺を選択したならその人物の職業も絞り込めるかもしれない。毒の種類は?」
「そうですね……。では、春ですからスズランから抽出したものにしておきますか」
玄関先に活けられた花々にそっと手を伸ばす。神事や祭りに用いられる鈴のような、蘭に似た白い花。殺風景に見えないようにと飾られているその花。三日目の今日も、生き生きとしている。
「スズランかーぁ。花屋で流通しているから、花を扱う職業って推理は短絡的だよね。今週はここにもメンバー入りしてるし、種類から絞り込むのは難しいか」
「活けていた水に毒素が流れ出ますから、素人でも入手は簡単。毒性も強いですから、少量で十分ですね」
にこやかに告げると、寺尾さんは「うわー……」硬い苦笑を浮かべる。
「日野くんらしい遊び心満載の発想で何よりだよ。じゃあ、犯人像を確定させる前に。ひとつ、明確にしよう」
寺尾さんは伏せていた顔を上げる。わざとらしく「はい?」と首をかしげてやった。
「後日食べようと買ってきていたシュークリームは、食べるまでどこに保管するんだ?」
「オフィスの冷蔵庫ですよ、もちろん」
「そうか。じゃあ、いままでの犯人像を撤回しよう」
「どうぞ」と推理を促した。
「これは復讐だ。募り積もった恨みを、今、こうして発散しようとしている。低質なブラックジョークを用いてね。
……犯人像について。
これまでに数度、冷蔵庫に保管していたスイーツを勝手に食べられた人物と断定する。
実行した理由は、成功する目算が高いと考えたから、かつ、事件後に疑われる可能性が低いと推測したから。自分用に購入した食べ物に毒が混入されていたら、まず被害者は疑われない。食べたら死ぬとわかっているものを食べるわけが無いからだ。
したがって、毒を混入させた犯人像はシュークリーム購入者本人……」
寺尾さんは沈黙を利用して、一拍確保した。
「要するに、日野くん。君のことだ」
名指しされて軽く肩をすくめた。さすが名探偵志望、推理ショーの研究に余念がない。
「仏の顔も三度撫でれば腹立つ、と言うじゃないですか。ほら、いまのところ二度目を経験した人間もいますし? まあ、これはあくまでも仮定の話です。僕だってさすがに毒は入れていません」
「まったく、君ってやつは――」
「きっとお薬です」
「――ん?」
「一口サイズなので、的中させたらお手軽目覚ましにもなりますよ」
「本当、君ってやつは……!」
「お疲れさまでした、おやすみなさーい」
いとまを告げるが早いか否か、寺尾さんはキッチンへ駆け込んでいった。その隙に尋問を物理的に躱すため、帰路についた。
高校生といえど、探偵助手。〝くそどーでもいい事実〟を組み合わせたらどうなるか考えることはあるし、目覚めに良い刺激的な食材を組み合わせて悪戯したい日があれば、企みのためにパスタを曲げたい日だってある。
さて。
冷蔵庫のシュークリームを見たとき、彼はどのような表情をするだろう。五つのシュークリームに紛れた〝目覚まし〟は炸裂するだろうか。
寝ぼけた腹ペコ探偵との第二ラウンド……――結果が待ち遠しいこと、この上ない。
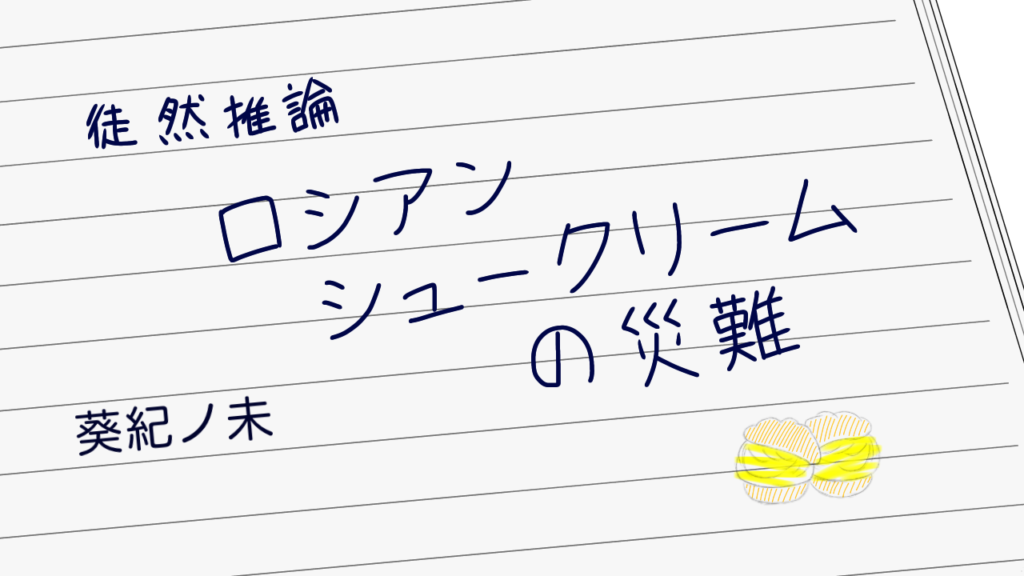
ロシアンシュークリームの災難
昨日の晴天とは切り替わるような、みごとなまでの走り梅雨。おかげさまで多湿にイラつき、髪の毛の気持ち悪さにイラつき。
目覚めてからずっと最悪である。
マンション前で十分に傘の水滴を飛ばし、インターホンの応答を待っている間にケースに入れて通学カバンに押し込んだ。
「こちら寺尾探偵事務所です」
「お疲れ様です、寺尾さん。今来ました」
「日野くんかぁ」つぶやきの直後、電子音とともに自動ドアが開けられた。
体力向上のために階段で駆け上がろうと努力することもあるが、今日は気分ではない。エレベーターの“22”と閉を押してほんのわずかな浮遊感に身を任せた。
現代の空上の計らしく扉は開け放たれたまま。入室してから鍵を掛けて「お疲れ様です、寺尾さん。今到着しました」呼びかけると、反応はすぐに返ってきた。
「んー、お疲れー。冷凍庫に封印したシュークリームあるよー」
「封印?」
「あの容器ごとガムテープでぐるぐるして氷で固めた」
リビングから聞こえる言葉を頼りにして冷凍庫に件のタッパーを発見した。
寝ぼけた腹ペコ探偵は前日の緊急対策を講じた本人によって救われたのだ。彼が夜行性であることを忘れ、犯行を止めてほしい犯人を模倣したからか。氷漬けの十字にガムテープを巻かれた容器、零度の壁越しに凍えている六つのシュークリームを前にして。
正味、悔しい。
事前の物理的対策は想定外だった。ガムテープならまだしも、シュークリーム凍らせる発想は理解の外だし。いや、寝起きでは冷凍庫を開けないからか。そうすれば視界に入らないから封印を解く危険もない。それに万が一の対策を重ねたといったところだろうか。
「マジであの人……」
いや、違うな。
事前の対策として寝起きの頭で容器内の爆弾を手に取らない状況を作り出すのは最適解であり、想定も可能だった。この負けは、同じステージで戦うための条件設定を怠った僕の責任である。
五つの罪なきシュークリームを見捨てるわけにはいかず、謝罪の後、しばらく氷水の中で謹慎してもらうことにした。
ふと小腹がすいて集中が切れる。
時計に意識が吸い寄せられた。夕食時には少し早かったが何か胃に入れるものは無いかとキッチンへ足を運んだ。
タッパーはすでに謹慎を完了していた。手に取るとかなりひんやりしているものの氷片はすっかり融解している。右手で容器を掴んで蓋の突起に左手をひっかけると問題なく開けられた。
蓋を容器と右手の間に滑り込ませる――三列×二行で礼儀正しくしていた。味が落ちていることに予想はついたが、捨ててしまうのはあまりにも惜しい。サイズは長方形のタッパーに準球体六つが無理なく入れられる程度。少々しぼんでいるが、封じられた状態では意図せず中身の配置が動くことはない。例の隣である左列下行を取り上げて口に運んだ。
……食べることは可能。
感想が正直に思い浮かんだ。
リビングに戻って「シュークリーム、食べます?」一息つこうとしているらしい寺尾さんの背中に問いかけた。
「おいしいやつ?」
「残念ながら、あなたが凍らせたものです」
「先にケンカ売ってきたの日野くんじゃん」
「さんざん人のおやつ勝手に食べたのどなたです?」文句を述べながらタッパーごとシュークリームを差し出すと「日野くん、やばいの平気な人……?」若干引いている怯えた声色。
すっと腑に落ちて、ふと思い浮かんだ面白いことを提案した。
「不服ですが、せっかくなので第三ラウンドにしましょうか」
「待って、日野くんが処理したわけでは?」
「ありませんよ。さすがにあれをノーリアクションで通せるほど味蕾死んでいません」
「デスヨネ」
「さて、寺尾さん。二つ連続でセーフだったら爆弾処理は僕が行います。食べ物を無駄にすると批判食らいますからね」
「それ考慮してた? 自分が引き当てる可能性を考慮して自分は耐えられる成分に調整した?」
「いえ。寝起きの寺尾さんのポンコツさに甘えて事前の物理対策を考慮できなかったので。寺尾さんの推理が当たれば、甘んじて己の未熟を受け入れます」
「残りが存在するってことは?」
「はい。〝目覚まし〟はひとつだけです」
「今さら言い直したって質の悪いロシアンルーレットに変わりないよ……」
「これも一興です」
「好奇心、悪魔から買い戻さないの?」
「寺尾さんに言われる筋合いありませんよ。中身を確認して爆弾を事前に処理することもできたでしょうに、そうしなかった。さすが名探偵志望、推理に対してストイックですよね」
ポンコツが滲む「その手があったか……」聞こえないふりしていると、タッパーを蓋とともに受け取りテーブルに静置。両手でひとつに手を伸ばそうとしたので「え、尊敬に値する寺尾さんが今さらそんなダサい真似をなさるんです?」
手を引っ込めて腹を決めたらしい寺尾さんは「君はどうしようもなく無慈悲なサディストだ」小さくつぶやいて腕を組み天井を見上げた。おそらく、聞こえるように。
「違います」
「寝起き状態でタッパーに気がつかなければ勝負はご破算になっていたのに、昨日わざと認識させたじゃないか」
「度重なる前科に対して、いい加減懲りてもらおうとしたんです。
それとも、今までの僕の労力は完全に無駄だったと?」
「……ごめん」
「謝ることは簡単なんですよ」
「はい……」
「さ、どうぞ。どれを選びますか?」
「質問させて、三回だけ!」
両掌を合わせて頭の上に掲げている寺尾さん。サディストではないので「どうぞ」と促した。
「これは当初の予定には無い余興なんだよね?」
「はい。昨日の帰り際のゲームが第一ラウンド、寝ぼけた寺尾さんがシュークリームで自爆するのが第二ラウンドのつもりでした」
「何それ。第二ラウンド、控室で暗殺されるようなもんじゃん」
「寝ぼけた寺尾さんは何も問題なくすべて召し上がる前にさよならするかなって思ってたので」
「つまり、推理の有無以前に君は意図的に俺が手に取りやすい位置に爆弾を配置したわけだ。じゃあ、俺は裏を読んだ君の裏をかく必要がある」
「裏の裏を読んだかもしれませんよ?」
「つまり、寝起きの俺がどれくらい推理できるか推測した君の思考がポイントだね」
「期待してまーす」
「どっちを?」
にっこり微笑んで見せると「うっわ……」苦笑された。そして「ええっと」推理を独り言ち始めた。
「左利きということは、本体を右手で持ちふたを開けて本体の下に滑り込ませるのは左だろう。ということは、今、本体の下にある蓋の突起が右上にある状態……これで左利きの人間が手に取りやすいのは左側の列。実際、二列×三行から左上のものを手に取ったらしい」
残念ですが、虚空を見つめるふりをして出題者の顔色を伺っているのは想定内です。
「特技はポーカーフェイスです」
「まじかよ。話が違うじゃん。数年前の君はどこ行っちゃったの?」
「いつまでもすべて顔に出るガキじゃ無いんで」
「未成年でしょ? まだガキで良いのにぃ」
「ほら、寝起きじゃないんですから。頑張って推理してください」天井に助けを求めている寺尾さんに先を促した。
「日野くんは左利きだけど俺が右利きって知っているから日野くんは俺が右側の列のほうが手に取りやすいと推測することができる。一方、寝起きの俺は基本何も考えていないけど、昨日の君のおかげで警戒することは忘れていない。左側に手を伸ばす……かもしれないけど、結局、右列取るね。実際何も考えてないし、日野くんにバレてるからポンコツ扱いされてんだよな。
……いや、前提に立ち直ろう。
爆弾は一つだけ。
この容器の蓋には突起がついていて開けやすいようになっている。開けて蓋を容器の下に敷いたなら」テーブルの上で蓋と容器を同時に滑らせて、蓋の突起が寺尾さんが正面から見て右上になるように静置した。「おそらく、この向きになる。加えて君は、寝ぼけた寺尾さんは何も問題なくすべて召し上がる前にさよならするかなって思ってたので、と言った。この二列×三行のうち最初に手を取りやすいのは四隅だろう。しかし、君はまっさきに左列の上を食べた。……なんで?」
「配置くらい覚えてます。寺尾さんじゃないんですから」
「んぃぃ……言い返せない。
あれ、ちょっと待った。推理で爆弾を特定できるなら、どうして四つ連続で回避しろって言わなかったのか。推理で完全に特定できないことを防いで公平性を確保するため、二つ目で俺が爆弾処理すると予想できたから……君のことだから、後者の意味合いが強いだろう。
二つ連続――ひとまず、これが必要だったんだ! 俺が二つ連続でセーフだったら爆弾処理は日野くんが行うんだろう? 君は自分の勝率が低い勝負をわざわざ仕掛けてくるような殊勝な心持は一切無いから、一つ目で安心させて二つ目で確実に炸裂させる。つまり、この五つのうち、二つ目で俺が手に取るような場所に爆弾が配置されている!
よおし、ここからだ。
まずは余計な情報を省く必要があるな。
寝起きの俺でも回避できるような推理は当然今の俺にもできるし、それ以上の推理も可能だ。この条件では、君が爆弾処理する可能性が高くなると考えられる。しかし、君がひとつ食べてから予期せぬ第三ラウンドが開幕した。それを許したのは、六つから二つを選択するよりも五つから二つを選択することについて考察事項が増えて俺が混乱すると予想した、から……数が減って考慮事項が増える? そんなことある? やばい、わかんなくなってきた」
そこまで考えていなかったが、まあ、勝手に泥沼にはまっていくのを助ける義理は無い。僕だって爆弾処理したくない気持ちは彼と完全に共有している。
僕と違って彼は内容を知らないにもかかわらず、眼差しや声の切迫具合から本当に〝目覚まし〟を食べたくないのだとわかる。
「隅に爆弾を配置していれば、位置をわかっていても怖くないか? 自分が食べることを考慮せずに作り上げた爆弾だ。怖いに決まってる。いや、君が手に取ったのは左側の列、右側に配置したとわかっていれば左側の四隅は安全だと考えるまでもないのか。だったら、真ん中の行はどちらも安全だ。二つ選ばなければならないのだから、右側に配置している可能性が高い以上、最初に選択するのは左側かつ中央の行が良いだろう。ふたつ目については右列の中央か左列の……いや、俺が安全なものふたつを選択すれば、日野くんは爆弾処理すると明言した。安全なもので優劣をつける必要はないんだ。
お?
これ、俺の勝ちではなかろうか?」
「ご自身の推理を信じて、召し上がっては?」
「なんで崩れないのポーカーフェイス」
「特技なんで。さ、どうぞ」
寺尾さんは左列中央を手に取り、ぎゅっと目を閉じて一息に口へ押し込んだ。
世の中の多くのものは右利き基準で作られているように、開けるときに指をひっかける蓋の突起は利き手と反対側にあることで開けやすくなる。縦向きのまま突起が左側にある右利き・横向きにすれば突起が右側にある左利きでは開け方に限らず、容器本体の下に滑り込ませた蓋の突起の位置も異なる。
第二ラウンドは寝起きの寺尾さんの手によって開幕し、間もなく幕が下ろされると推測したうえで持ち掛けた勝負である。当初の僕の計画に第三ラウンドは存在しなかった。つまり、僕がタッパーを開けるオプションは無かった。
「っ――?!」勢いよく開けた瞳には、涙が滲む。
「自爆オツでーす。飲み込んでくださーい」
何か飲み物を用意しようとキッチンへ向かった。
寺尾さんの頭が回る状態の推理は正確だった。寝起きの彼が結局、右列に手を伸ばすことだけではなく。一つ目で油断させて、二つ目で確実に。それさえも読まれていることには肝を冷やした。
結局、自爆の原因は驕りでも油断でも無い――――〝右利きのエゴ〟である。